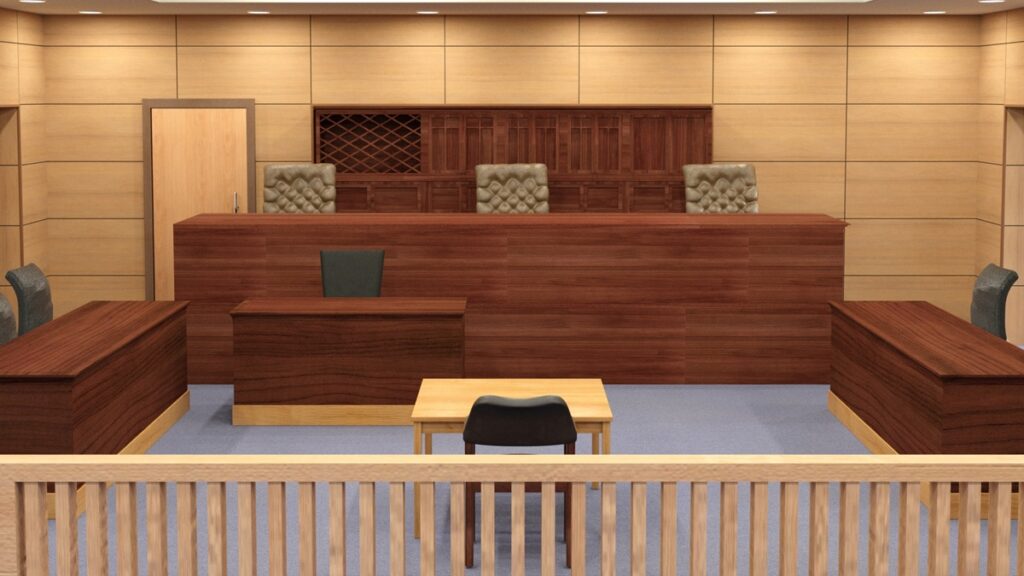記事一覧
-

【判例】最判平7.7.7:国道43号事件
一般国道等の道路の周辺住民がその供用に伴う自動車騒音等により受けた被害が、社会生活上受忍すべき限度を超える場合には、当該道路の設置・管理に瑕疵がある。 👉行政法21:国家賠償法(損害賠償責任の性質) あわせて読みたい -

【判例】最判昭59.11.29:公の営造物の管理者
公の営造物の管理者は、必ずしも当該営造物について法律上の管理権や所有権・賃借権等の権限を有している者に限られるものではなく、事実上の管理をしているにすぎない国または公共団体も含まれる 👉行政法21:国家賠償法(損害賠償責任の性質) あわせて読... -

【判例】最判昭53.7.4・最判平5.3.30:通常の用法に即しない行動の結果生じた損害
国または公共団体は、通常の用法に即しない行動の結果生じた損害については、損害賠償責任を負わない 👉行政法21:国家賠償法(2条の適用要件) あわせて読みたい -

【判例】最判昭30.4.19:公務員個人を相手方とする請求
公務員の職務行為を理由とする国家賠償請求については、国または公共団体が賠償の責任を負うのであて、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また、公務員個人もその責任を負うものではないから、行政機関を相手方とする訴... -

【判例】最判昭57.7.15:政策判断の誤りの違法性
政府が物価の安定等の政策目標を実現するために具体的にいかなる措置をとるべきかは、事の性質上、専ら政府の裁量的な政策判断に委ねられている事柄であって、具体的な措置についての判断を誤ったためその目標を達成できなかったとしても、法律上の義務違... -

【判例】最判昭53.10.20:無罪判決確定後、直ちに拘留が違法となるか
刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに起訴前の逮捕・拘留、公訴の提起、追行、起訴後の拘留が違法となるということはない 👉行政法21:国家賠償法(1条のポイント) あわせて読みたい -

【判例】最判平19.1.25:児童養護施設職員による養育監護行為
国家都道府県の措置に基づき社会福祉法人の設置・運営する児童養護施設に入所した児童に対する当該施設の職員等による養育監護行為は、都道府県の公権力の行使に当たる公務員の職務行為と解するのが相当である。 👉行政法21:国家賠償法(1条のポイント) ... -

【判例】最判昭57.4.1:国家公務員の定期健康診断
国家公務員の定期健康診断における国嘱託の保健所勤務医師による検診は「公権力の行使」に当たらない。 👉行政法21:国家賠償法(1条のポイント) あわせて読みたい -

【判例】最判平17.12.8:拘留されている患者への医療行為
拘留されている患者に対して拘置所職員たる意思が行う医療行為は「公権力の行使」に該当する。 👉行政法21:国家賠償法(1条のポイント) あわせて読みたい -

【判例】最判昭54.7.10:交通犯罪の捜査は公権力の行使にあたるか?
都道府県警察の警察官が警察の責務の範囲に属する交通犯罪の捜査を行うことは、検察官が自ら行う犯罪の捜査の補助に係るものであるときのような例外的な場合を除いて、当該都道府県の公権力の行使にほかならない。 👉行政法21:国家賠償法(1条のポイント)... -

【判例】最決平17.6.24:指定確認検査機関による事務
指定確認検査機関による確認に関する事務は、建築主事による確認に関する事務と同様に、地方公共団体の事務である。 👉行政法21:国家賠償法(1条のポイント) あわせて読みたい -

【判例】最判昭49.7.19:審査請求の棄却裁決の効力
処分を違法と認めて審査請求を棄却する裁決があった場合、当該裁決は処分庁を拘束せず、処分庁は、原処分を取り消したり変更したりすることができる。 👉行政法12-3:審査請求の裁決(効力の種類) あわせて読みたい