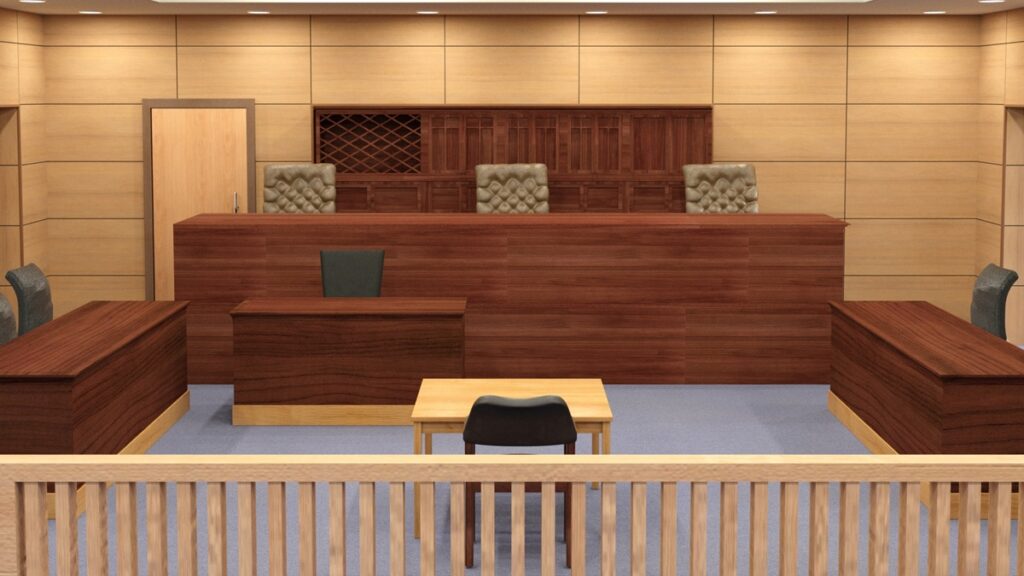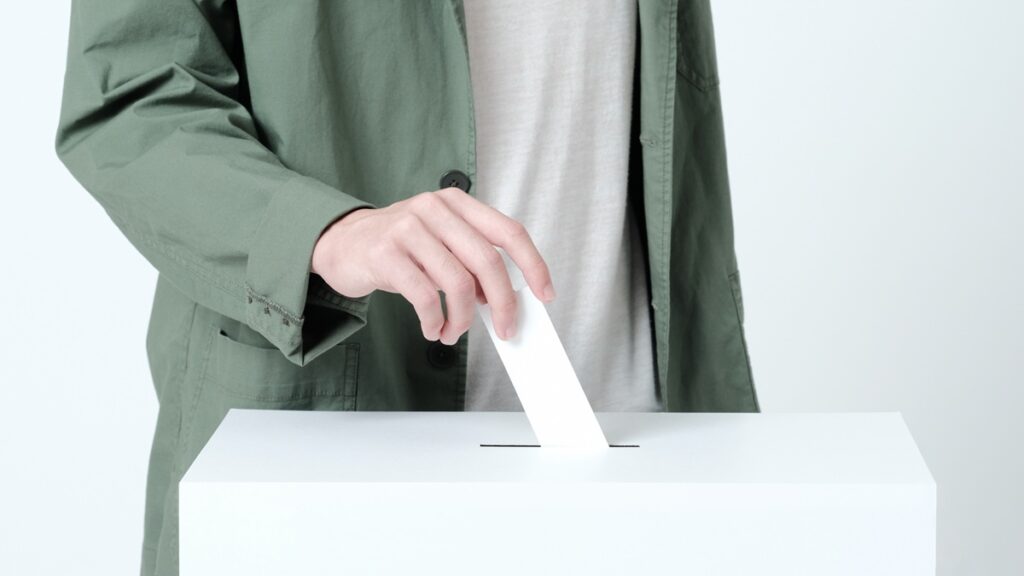記事一覧
-

【判例】最大判令6.7.3:旧優生保護法の規定
特定の疾病や障害を有する者などに対して不妊手術を受けることを強制する旧優生保護法の規定は、憲法13条および14条1項に違反するものである。 👉憲法4:「幸福追求権」とは?憲法13条から読み解く新しい人権と平等原則 あわせて読みたい -

【判例】最判昭61.2.14:オービスによる運転者の写真撮影
自動速度監視装置(オービス)による運転者の容ぼうの写真撮影は、現に犯罪が行われ、かつ緊急に証拠を保全する必要があり、方法も相当である場合には許容される 👉憲法4:「幸福追求権」とは?憲法13条から読み解く新しい人権と平等原則 あわせて読みたい -

【判例】最判平5.2.26:外国人の国政選挙権
外国人には国政選挙権も保障されていない。 👉憲法3:人権総論を完全整理!分類・享有主体・限界をわかりやすく解説 あわせて読みたい -

【判例】最大判昭32.12.25:外国人の出国の自由
憲法上、外国移住の自由が保障されていることから(22条2項)、外国人の出国の自由は保障される 👉憲法3:人権総論を完全整理!分類・享有主体・限界をわかりやすく解説 あわせて読みたい -

【判例】最判平1.6.20:百里基地訴訟
国が行政の主体としてではなく私人と対等の立場に立って、私人との間で個々的に締結する私法上の契約は、当該契約がその成立の経緯および内容において実質的にみて公権力の発動たる行為と何ら変わりがないといえるような特段の事情の無い限り、憲法9条の直... -

【判例】最大決平10.12.1:寺西裁判官事件
裁判官に対し「積極的に政治活動をすること」を禁止することは、その目的が正当であって、その目的と禁止との間に合理的関連性があり、禁止により得られる利益と失われる利益との均衡を失するものではないから、憲法21条1項に違反しない 👉憲法3:人権総論... -

【判例】最判平14.4.25:群馬司法書士会事件
阪神・淡路大震災により被災した兵庫県司法書士会(強制加入団体)に3000蔓延の復興支援拠出金を寄付することは、群馬司法書士会の目的の範囲内の行為であり、そのために登記申請事件1件当たり50円の復興支援特別負担金を徴収する旨の同会の総会決議は有効... -

【判例】最判平1.11.20
天皇は日本国の象徴であるから、天皇には民事裁判権が及ばない 👉憲法2:天皇の役割とは?憲法から読み解く“象徴天皇制”をわかりやすく解説 あわせて読みたい -

【重要判例】最大判平18.3.1:旭川市国民健康保険条例事件
事案 地方税法に基づく保険税の方式ではなく、国民健康保険法に基づく保険料の方式をとっている国民健康保険条例が、市長に対して保険料率の決定などを委任していたため、この条例が84条に違反しないかが争われた。 結論 合憲 判旨 ①租税の意義 国または地... -

【重要判例】最大判令4.5.25:在外国民の国民審査
事案 在外国民に国民審査に係る審査権の行使が認められなかったことにつき、立法不作為の違憲を理由として、国家賠償請求をなした。 結論 違憲。国家賠償請求は認められる。 判旨 ①国民審査権の制限の合憲性 審査権が国民主権の原理に基づき憲法に明記され... -

【重要判例】最大判平17.9.14:在外国民の選挙権
事案 選挙権を行使するには選挙人名簿に登録されていなければならないところ、外国に長期滞在する者は登録されず選挙権を行使し得なかったことから、1998年に公職選挙法の改正を行い、新たに在外選挙人名簿を調整しこれに登録された者には選挙権の行使を認... -

【重要判例】最大昭60.11.21:在宅投票制度廃止事件
事案 重度身障者の在宅投票制度を廃止したままその復活を怠った立法不作為の意見を理由として、国家賠償請求がなされた。 結論 合憲 国家賠償請求は認められない。 判旨 国会議員は、立法に関しては、原則として、国民全体に対する関係で政治的責任を負う...