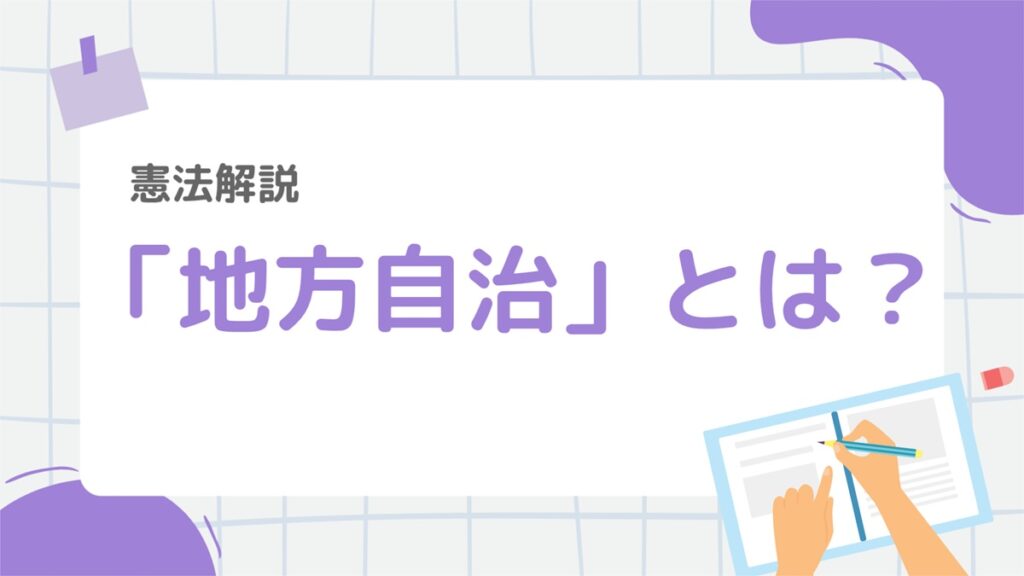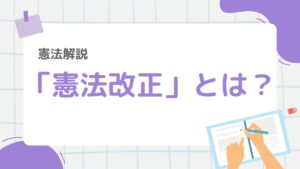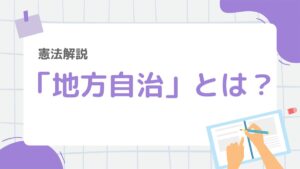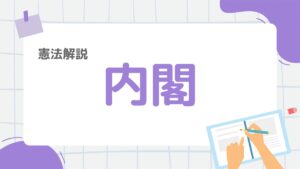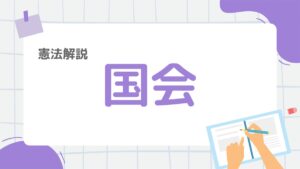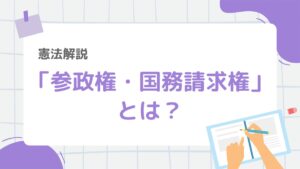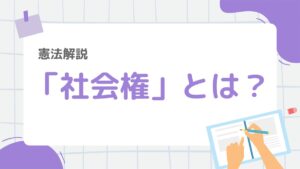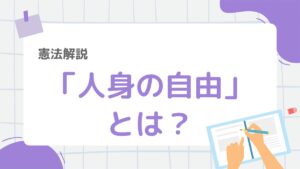- 行政書士試験の「憲法」対策をしている方
- 「財政民主主義」「租税法律主義」などのキーワードがピンとこない方
- 予算や決算の憲法上のルールをわかりやすく学びたい方
🏛財政とは?|財政の基本原則をわかりやすく解説!
国の活動には多くの資金が必要です。そのお金は、最終的には国民が税金という形で負担しています。だからこそ、国のお金の使い方(=財政)は、国民の生活に直結する重要なテーマです。
そこで、日本国憲法では、「財政は民主的に行わなければならない」という財政民主主義の考え方が採用されています。以下、憲法上の財政に関するルールを、わかりやすく整理していきましょう。
✅財政民主主義
財政の運営には国民の意思を反映させる必要があります。
そのため、国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならないと憲法で定められています。これが財政民主主義の原則です(83条)。
✅租税法律主義
税金は国民に直接負担を強いる制度なので、勝手に課すことは許されません。
そのため、税金を新たに課したり、変更したりするには、必ず法律(または法律の定める条件)に基づくことが必要です。
この原則を「租税法律主義」といいます(84条)。
国費の支出と国庫債務負担行為
国が税金を使う(=国費の支出)、あるいはお金を借りる(=国庫債務負担)ときは、必ず国会の議決が必要です(85条)。
- 国費の支出:現金の支払いによって国の活動に必要な費用をまかなうこと(財政法2条1項)。
- 国庫債務負担行為:国が財政上の需要を充たすのに必要な経費を調達するために債務を負うこと。
公金支出の禁止
税金(公金)や公の財産の使い道には制限があります。
拘禁その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、または公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対し、これを支出し、またはその利用に供してはならない(89条)とされています。
【89条前段】宗教団体などへの支出の禁止
宗教団体の活動に対して、税金を使ってはいけないという規定です。これは「政教分離原則」を財政面からも守るためです。
【89条後段】公の支配に属しない事業への支出の禁止
慈善・教育・博愛事業であっても、公的なコントロールが効かないものには、公金を使ってはならないとされています。
この趣旨については、以下のような見解があります:
- 私的な事業への不当な公権力の支配が及ぶことを防止する点にあるとする見解。
- 公金の濫費を防止する点にあるとする見解。
財政監督の方式
✅予算制度
予算とは、国の一年間の「収入と支出の見積もり」のことです。
これにより、国会が国家財政に対してコントロールを持つ仕組みになっています(86条)。
💡予算は法律とは異なり、国民に直接拘束力はありません。
→ 通説では、予算法形式説(予算は法律とは異なるが、国会の議決によって成立する国法の一形式)とされています。
✅予備費
予算では対応できない突発的な支出に備え、予備費が設けられています。
ただし、国会が承諾しなくても支出の法的効力は変わらず、内閣に政治的責任が問われるだけです。
✅皇室財産とその費用
皇室に関する財産や費用も、民主的に管理されるべきです。
- 皇室の財産はすべて国に属する
- 皇室の費用は、予算に計上し、国会の議決が必要
これは「皇室財産の民主化」の考え方に基づいています(88条)。
決算
決算とは、収入と支出の数字を確定する事で、国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければなりません(90条1項)。
「国会に提出」とは、国会が提出された決算をもとに審議し、議決を要するものの、両議院一致の議決は必要ではなく、各議員の議決は決算の効力に影響は及ばすことはありません。
財政状況の報告
内閣は、少なくとも年1回は、国会と国民に対して国の財政状況を報告することが義務づけられています。(91条)。
✅まとめ:財政のルールは国民の生活に直結!
憲法13章で定められている財政のルールは、「税金の使い道を国民がチェックできる仕組み」を作るためのものです。
行政書士試験では、「財政民主主義」「租税法律主義」「予算制度」などの用語の理解と、それに関連する条文・制度のつながりが問われます。
暗記だけに頼らず、制度の意味や目的を理解することが合格への近道です!