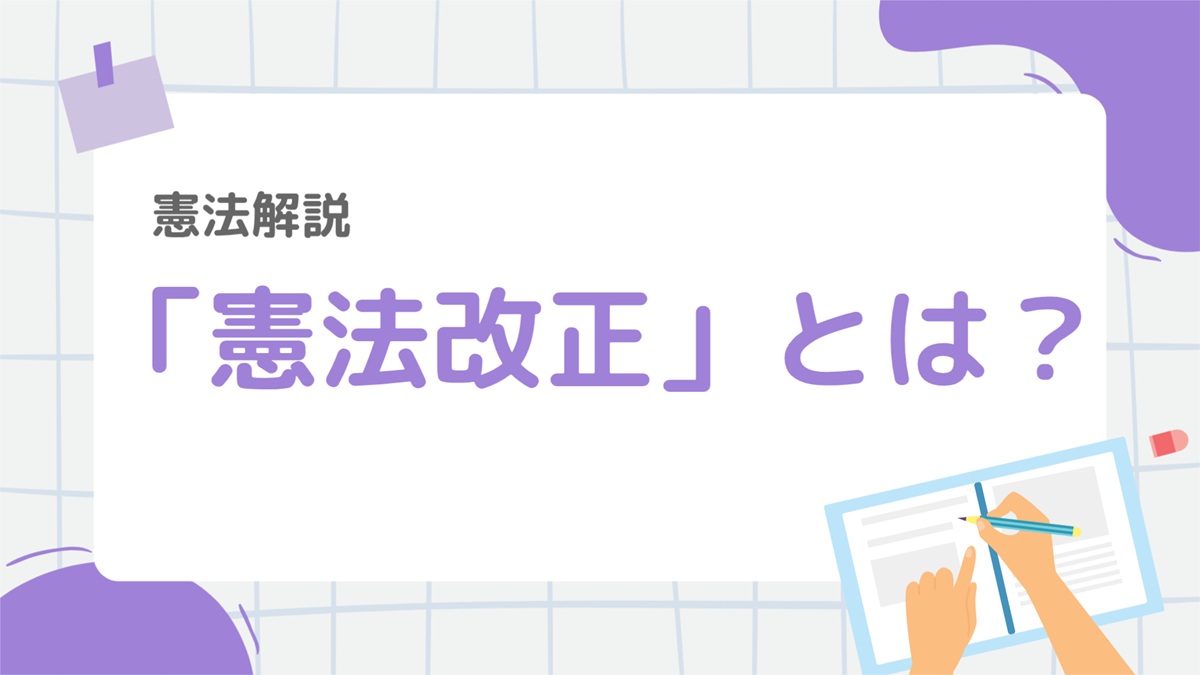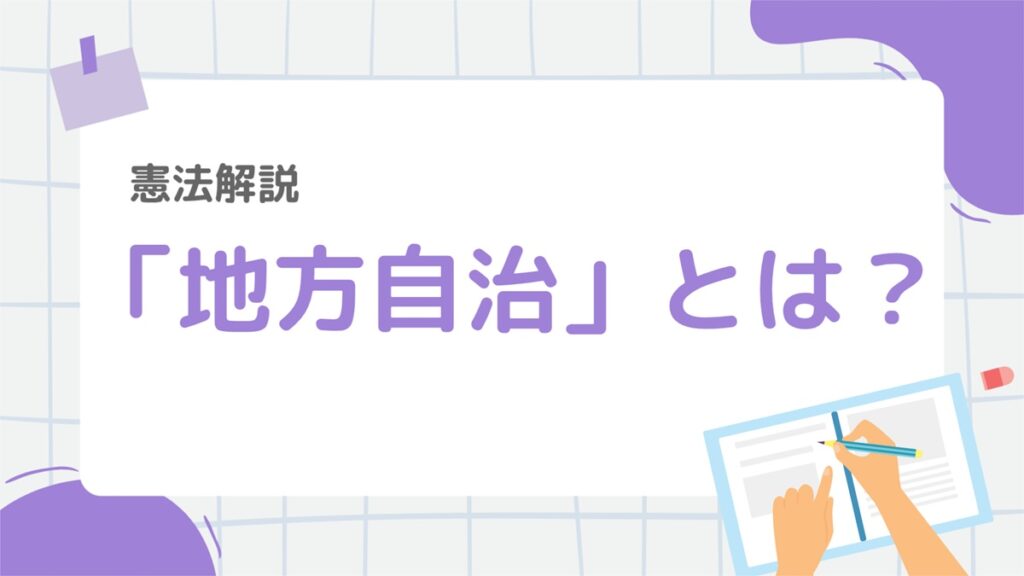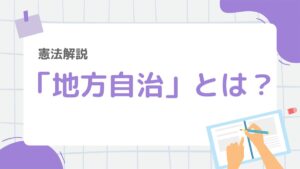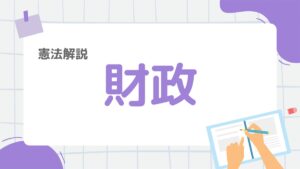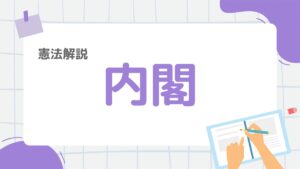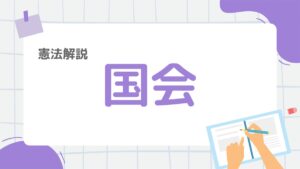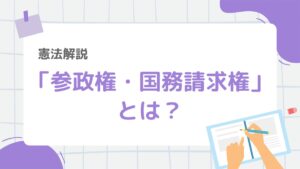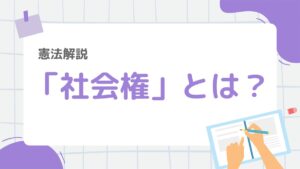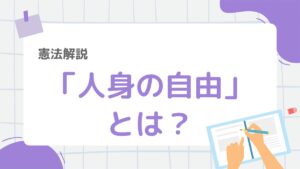憲法改正とは?──「変えることができる」けど、簡単にはできない理由
日本国憲法は、国家の仕組みや国民の権利など、社会の根本を定める最も重要な法(最高法規)です。そのため、簡単に変更できないよう、強い安定性が求められています。
しかし一方で、社会の変化に応じて内容を見直す必要が出てくる場合もあります。そこで憲法には、必要に応じて改正ができるルールが定められています。
このように、改正は可能だけれども、非常に厳しい手続きが必要とされている憲法を「硬性憲法」といいます。日本国憲法もこの硬性憲法にあたります。
憲法改正の流れ|3つのステップで進められる
憲法改正は、❶国会の発議⇒❷国民の承認⇒❸天皇の公布の3つのステップで進められます。
まず、憲法改正を発議(提案)するのは国会です。通常の法律案と違い、憲法改正案は特別なルールに従って審議されます。
憲法改正の発議は、通常の発議(原案の提出)とは異なり、国民に提案する憲法改正案を国会が決定することをいいます。憲法改正の発議は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要とすします(96条1項前段)。
国会で憲法改正案が可決されたら、「国民投票」にかけられます。
この国民投票は、通常の選挙とは異なり、憲法改正専用の「特別の国民投票」または「国会の定める選挙の際行われる投票」で行われます。
憲法改正の承認には、「特別の国民投票」または「国会の定める選挙の際行われる投票」において、その過半数の賛成が必要です(96条1項後段)。
憲法改正に「限界」はあるのか?
「手続きさえクリアすれば、どんな改正もOKなのか?」という疑問が湧いてきますよね。
この点について、日本国憲法には明確な明記はありませんが、改正には一定の「限界」があると考えられています。
特に、次のような憲法の根本原則は、たとえ改正手続きを踏んでも侵してはならないとする見解が有力です。
- 国民主権
- 基本的人権の尊重
- 平和主義
これらを否定するような改正は、「そもそも憲法の枠組みを壊すものであり無効ではないか?」と考えられるのです。
まとめ|憲法改正の手続きは「発議⇒承認⇒公布」の3段階
憲法改正は、以下のような流れで行われます。
| 段階 | 内容 | 要件 |
|---|---|---|
| 国会の発議 | 憲法改正案の提案 | 各議院の総議員の3分の2以上の賛成 |
| 国民の承認 | 特別の国民投票などで承認 | 有効投票の過半数の賛成 |
| 天皇の公布 | 国民の名で公布 | 改正内容が憲法の一部として正式に反映 |
日本国憲法は、改正可能な硬性憲法であるものの、国の基本原則を壊すような改正には慎重であるべきだとされています。行政書士試験では、「憲法96条の要件」「改正の流れ」「限界の考え方」が頻出ポイントですので、しっかり押さえておきましょう。