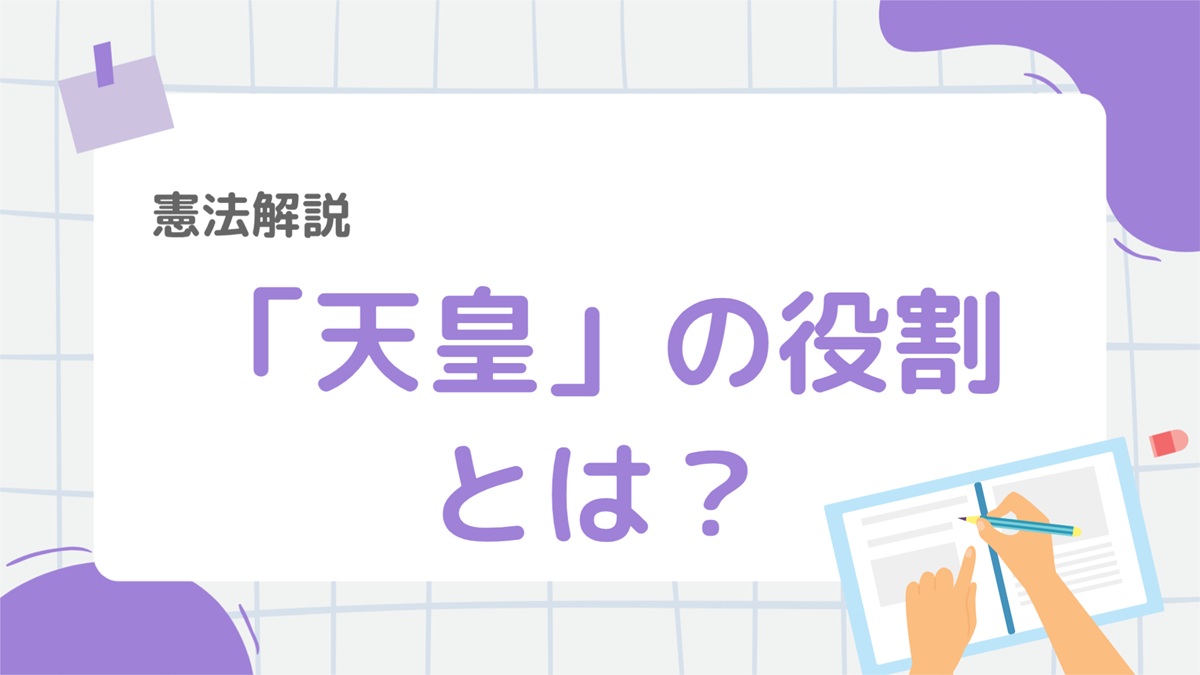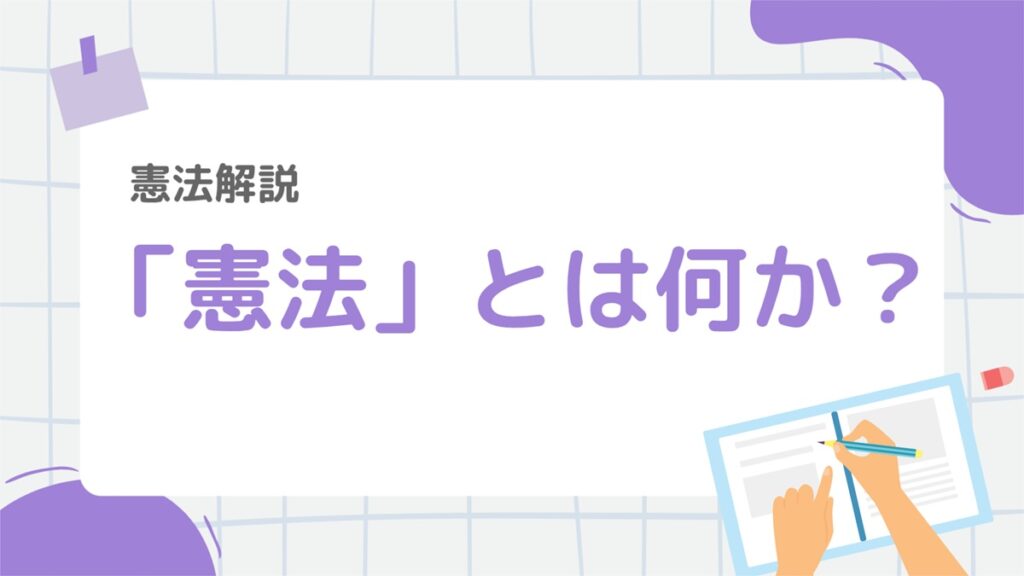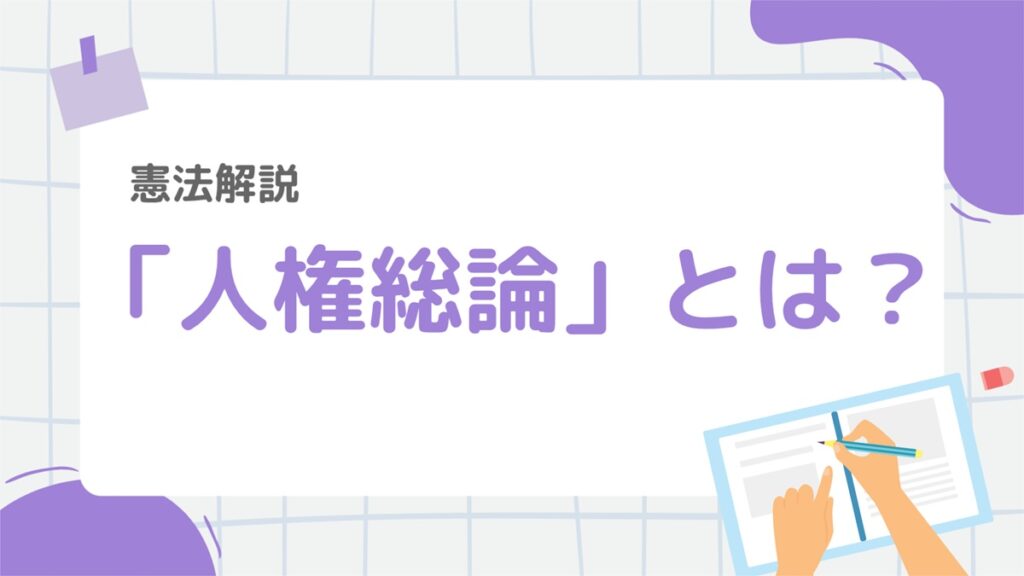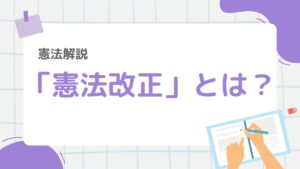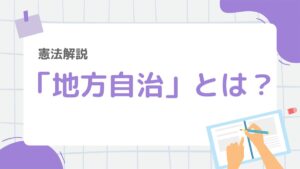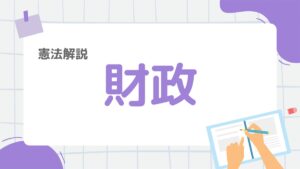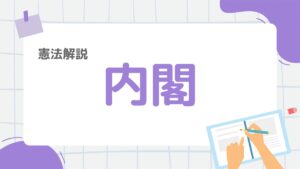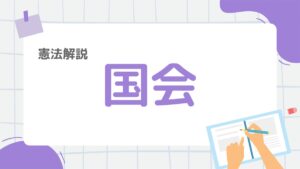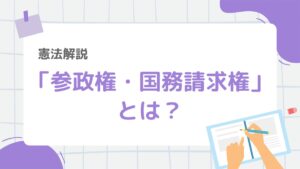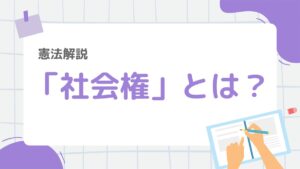- 行政書士試験で「憲法」の理解を深めたい方
- 象徴天皇制の意味や天皇の具体的な役割を押さえたい方
- 天皇の国事行為や権限の仕組みを図解感覚で把握したい方
- 「国民主権」と「天皇制」の関係にモヤモヤしている方
天皇の地位はどうなっているの?
かつての大日本帝国憲法では、天皇が国の最高権力者=主権者でした(いわゆる「天皇主権」)。しかし、現在の日本国憲法では主権は国民にあると定められており、天皇は「日本国および日本国民統合の象徴」という立場に位置づけられています(1条)。
つまり、天皇は国の象徴であり、政治の実権は持っていないのです。

皇位はどうやって継がれるの?
天皇の地位は、代々その血筋を引く者が引き継ぐ「世襲制」です。これは民主主義の平等原則とは相容れない制度ですが、日本国憲法では例外的に容認されています(2条)。
その理由は、天皇制という伝統を維持するためです。
天皇の権能は? ―「国事行為」のみ
日本国憲法のもとで、天皇は「国事行為」のみを行い、政治的な決定権は一切持ちません(4条1項)。国事行為とは、儀礼的・形式的な公務のことで、実質的な政治判断は内閣が行います。
【代表的な国事行為】
具体的な国事行為の例として、内閣総理大臣と最高裁判所の長たる裁判官の任命(6条1項・2項)があります。つまり、行政の長と司法の長といった人たちについては、天皇が任命します。
【国家機関の指名・任命】
| 指名 | 任命 | |
|---|---|---|
| 内閣総理大臣 | 国会(6条1項) | 天皇(6条1項) |
| 国務大臣 | – | 内閣総理大臣(68条1項) |
| 最高裁判所長官 | 内閣(6条2項) | 天皇(6条2項) |
| 最高裁判所裁判官(長官以外) | – | 内閣(79条1項) |
| 下級裁判所裁判官 | 最高裁判所(80条1項前段) | 内閣(80条1項前段) |
また、天皇は、内閣の助言と承認により、以下のような国事行為を行います。
- 憲法改正・法律・政令・条約の公布(1号)
- 国会の召集(2号)
- 衆議院の解散(3号)
- 国会議員の総選挙の施行の公示(4号)
- 国務大臣その他の官吏(国家公務員)の任免の認証(5号)
※任免とは、任命と罷免の略 - 恩赦の認証(6号)
大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除・復権をまてめて恩赦という。 - 栄典の授与(7号)
- 批准書その他の外交文書の認証(8号)
批准書とは、国家が条約の内容を審査し、確定的な同意を与えた書面のこと。 - 外国の大使・公使の接受(9号)
接受とは、外国の大使・公使と儀礼的に面会すること。 - 儀式を行うこと(10号)
国事行為を行うには「内閣の助言と承認」が必要
憲法第3条により、天皇のすべての国事行為は、内閣の助言と承認がなければ行えません。
また、天皇はこの助言を拒否することもできないため、形式的な存在としての性質が強いのです。
天皇の代理人制度 ― 摂政と委任
①摂政
天天皇が未成年や重い病気などで職務を果たせない場合、皇室典範に基づき「摂政」がその役割を代行します(皇室典範16条)。
②国事行為の委任
摂政を置くほどではないものの、一時的に天皇が国事行為をできない場合、一定の行為について他者に委任することも可能です(4条2項)。
皇室の財産管理 ― 国会の関与が必須
皇室と国家の健全な関係を保つため、皇室の財産の授受には国会の議決が必要とされています(8条)。これは、皇室が特定の個人や団体と癒着して、不当な権力を持つことを防ぐためです。
🔸まとめ
日本国憲法のもとで、天皇は「象徴」であり、実際の政治権限は持っていません。ただし、国の儀式や重要な形式的手続きに関わる「国事行為」を担うことで、国の安定や伝統の継承に貢献しています。