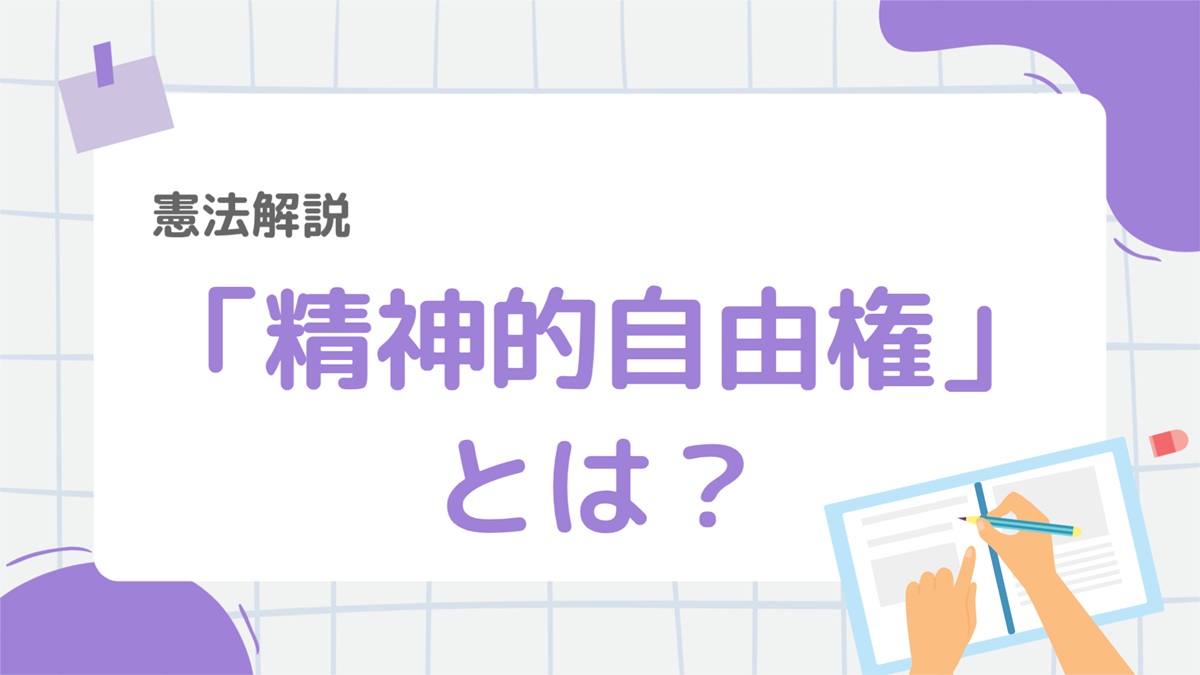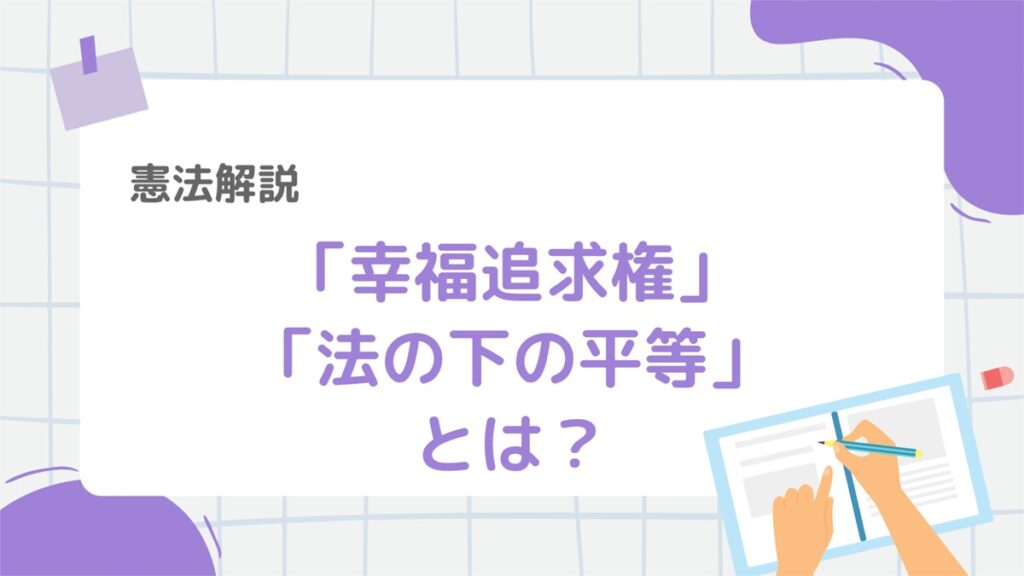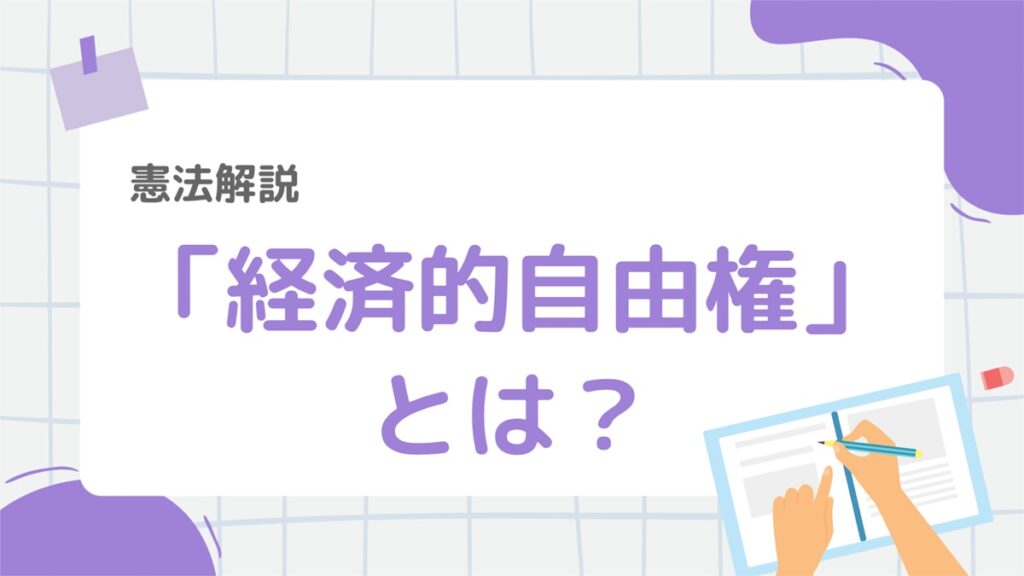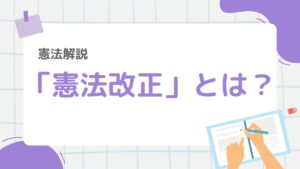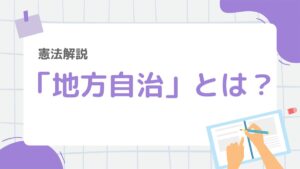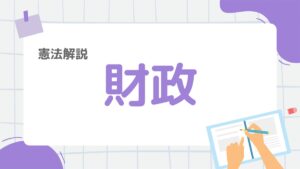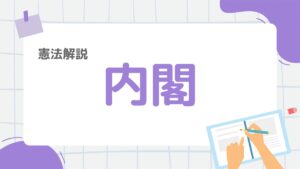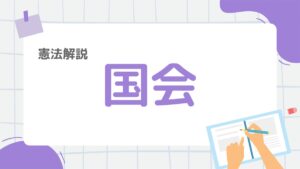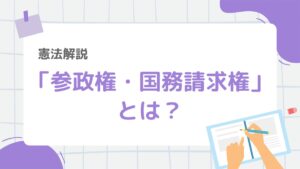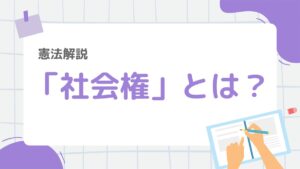- 行政書士試験に向けて「精神的自由」についてしっかり理解したい方
- 憲法における人権の内容と制限について、要点をつかみたい方
- 思想・信教・表現・学問の自由の違いやポイントが曖昧で不安な方
🧠 精神的自由とは?
精神的自由とは、個人が心の中で自由に考え、信じ、表現し、研究する自由のことを指します。憲法では、以下の4つの自由が精神的自由として保障されています。
🧩 思想・良心の自由
概要
思想・良心の自由とは、人がどんな考えを持っていても、それを心の中でとどめておく限り、国家が干渉できないという権利です。日本では戦前、国家が特定の思想を取り締まることがあったため、憲法で明確に保障されるようになりました。(19条)
思想・良心の自由の保障の意味
- 内心の自由の絶対性
国民がどのような世界観・人生観をもっていたとしても、それを心の中で思っている分には絶対的に自由 - 沈黙の自由
国民がどのような思想をもっているかについて、国家権力が申告を求めることは許されない - 思想を理由とする不利益取扱いの禁止
特定の思想をもっていることを理由に不利益な取り扱いをすることは許されない
🔍 主な判例:
- 【重要】謝罪広告強制事件(最大判昭31.7.4)
- 【重要】麹町中学内申書事件(最判昭63.7.15)
- 【重要】国歌起立斉唱行為の拒否(最判平23.5.30)
- 国歌斉唱ピアノ伴奏(最判平19.2.27)
⛪ 信教の自由
信教の自由の内容
憲法は信教の自由を保障していて、以下の3つの側面があります。(20条1項前段)。
- 信仰の自由
宗教を信仰または信仰しないこと、信仰する宗教を選択・変更することについて、個人が自らの意思で決定する自由 - 宗教的行為の自由
宗教上の祝典・儀式・行事その他布教等を行う自由 - 宗教的結社の自由
宗教的行為を行うことを目的とする団体(宗教法人など)を結成する自由
信教の自由の制約
- 信仰の自由:内心の自由なので絶対に保障されます
- 宗教的行為・結社の自由:外部に影響を与えるため、他人の権利や社会秩序を害する場合には制限される可能性があります(公共の福祉による制約)
🔍 主な判例:
政教分離原則
国家が特定の宗教と深く関わることを防ぐため、宗教と政治は分離されるべきとされています(政教分離原則)(20条1項後段・3項、89条前段)。ただし、完全な排除ではなく、宗教団体が他の団体と同様の扱いを受ける場合には支援も可能です。
🔍 主な判例:
- 【重要】津地鎮祭事件(最大判昭52.7.13)
- 【重要】愛媛県玉串料事件(最大判平9.4.2)
- 【重要】空知太神社訴訟(最大判平22.1.20)
- 【重要】孔子廟政教分離訴訟(最大判令3.2.24)
- 最判平5.2.16:宗教上の組織・団体とは
🗣️ 表現の自由
表現の自由の保障根拠
表現の自由(21条1項)とは、自分の意見や考えを他人に伝える自由です。これは単なる「発言の自由」にとどまらず、「知る権利」や「取材・報道の自由」なども含まれます。
表現の自由が重要な理由
- 自己実現の価値:自分を表現することで、人格を成長させることができる
- 自己統治の価値:国民が情報を得て、政治に参加できるようになる
表現の自由の内容と派生する権利
- ①知る権利
-
情報を受け取る自由(例:ニュースを見る自由)
- ②アクセス権
-
一般国民がマスメディアに対して、自分の意見の発表の場を提供することを要求する権利1
🔍 主な判例:
- ③報道・取材の自由
-
報道は、事実を知らせるものであり、特定の思想や意見を表明するものではない。そこで、報道の自由や報道のための取材の自由が、憲法21条によって保障されるかが問題となります。
🔍 主な判例:
👉【重要】博多駅事件(最大決昭44.11.26)2取材に対し情報を提供した人は、自分が情報提供したことを秘密にしてほしいと思うのが普通なので、情報提供者の秘匿が守れなければ、以後の取材に支障が生じます。そこで、取材の自由には、取材源秘匿の自由も含まれると考えられています。
その一方で、裁判における証人は、聞かれたことについて答える義務があります(証言義務)。そこで、裁判における証人が取材源について聞かれた場合に、証言を拒絶することができるかが問題となります。
判例は、取材源秘匿の自由について、刑事裁判と民事裁判で異なる結論となっています。刑事裁判 憲法21条は新聞記者に特殊の保障をあたえたものではないため、医師その他に刑事訴訟法が保障する証言拒絶の権利は、新聞記者に対しては認められない。
(石井記者事件:最大判昭27.8.6)民事裁判 民事事件において証人となった報道関係者は、当該報道が公共の利益にかんするものであって、その取材の手段・方法が一般の刑罰法令に触れるとか、取材源となった者が取材源の秘密の開示を承諾しているなどの事情がなく、しかも、当該民事事件が社会的意義や影響のある重大な民事事件であるため、当該取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお公正な裁判を実現すべき必要性が高く、そのために当該証言を得ることが必要不可欠であるといった事情が認められない場合には、民事訴訟法197条1項3号に基づき、原則として、当該取材源に係る証言を拒絶することができる
(最決平18.10.3)🔍 主な判例:
- 【重要】外務省秘密電文漏洩事件(最決昭53.5.31)■取材の自由と国家機密に関する判例
- 【重要】レペタ事件(最大判平1.3.8)■法廷での取材の自由に関する判例
- 北海タイムス事件:最大判昭33.2.17
- ④性表現と名誉棄損的表現
-
従来、性表現や名誉棄損的表現は、わいせつ文書頒布罪・名誉棄損罪などが刑法に定められているため、憲法で保障されないものとされてきました。しかし、これでは何をもってわいせつ・名誉棄損とするかで本来保証されるべき表現まで保障されなくなる恐れがあります。そこで、判例は、性表現や名誉棄損的表現も表現の自由に含まれるとしながら、その範囲を絞っていくという手段を探っています。(判例:悪徳の栄え事件)
なお、個人の名誉の保護と正当な表現の保障との調和を図るため、以下の3要件を満たした場合には、名誉棄損罪が成立しないものとされています。- 摘示された事実が公共の利害にかんするものであること(事業の公共性)👉判例:「月刊ペン」事件
- 摘示の目的が専ら公益を図るものであること(目的の公益性)
- 事実の真実性を証明できたこと(真実性の証明)👉判例:「夕刊和歌山時事」事件
🔍 主な判例:
- ⑤集会の自由
-
集会とは、多数人が共通の目的をもって一定の場所に集まることをいいます。また、集団行動も「動く集会」といえるため、集会の自由のみならず集団行動の自由も21条1項によって保障されます。
集会や集団行動は、多数人が集合して、特定の場所を独占して使用したり行動を伴う表現活動のため、他社の権利と矛盾・衝突する可能性が高いものといえます。そこで、他社の権利との調整のため、集会の自由や集団行動の自由も公共の福祉による制約を受けます。🔍 主な判例:
表現の自由の規制
表現の自由も公共の福祉などを理由に制限されることがあるが、表現の自由は自己実現の価値・自己統治の価値をもつ重要な権利のため、国家権力の思うままに制限することは許されない。
そこで、表現の自由を規制する立法が合憲か違憲かを判定する基準を明らかにすることが重要となる。この基準として通説が採用しているのが、精神的自由権に対する規制は経済的自由権に対する規制よりも厳格な基準で審査すべきとする二重の基準という考え方。
もっとも、表現の自由の規制の合憲性判定基準は二重の基準から直ちに導かれるものではなく、①事前抑制・②漠然不明確な規制・③表現内容規制・④表現内容中立規制といった規制態様に応じて決定されるべきとされている。
事前抑制
事前抑制とは、表現行為がなされる前に国家権力が表現を規制すること。
この事前抑制は、原則として許されないと考えられている。なぜなら、表現行為がなされる前に表現が規制されると、表現をしようとする者が萎縮し、表現の自由を大きく脅かすことになるため。
そして、事前抑制のうち、行政権が主体となって行う検閲は絶対に禁止され、いかなる例外も認められない(21条2項前段)
🔍 主な判例:
漠然不明確な規制・過度に広汎な規制
漠然不明確な規制・過度に広汎な規制がされると、どこまで表現が許されるかわからず、表現をする人が萎縮する。
そこで、表現の自由を規制する立法は明確でなければならないとされている。これを明確性の理論という。
🔍 主な判例:
表現内容規制
表現内容規制とは、ある表現が伝達しようとするメッセージの内容を理由とした規制。3
この規制については、厳格な合憲性判定基準によることが要求される。4
表現内容中立規制
表現内容中立規制とは、表現が伝達しようとするメッセージの内容には直接関係なく行われる規制(時間・場所・手段に着目して行われる規制)。この規制は、表現内容規制の場合よりも緩やかな合憲性判定基準が用いられるのが一般的。5
🔍 主な判例:
🎓 学問の自由(憲法23条)
外国の憲法においては、学問の自由を独立の条項で保障する例はあまりない。しかし、大日本帝国憲法の下で、滝川事件や天皇機関説事件など、学問の自由が国家権力によって直接侵害されてきた歴史を踏まえ、日本国憲法では、学問の自由が明文で保障されている(23条)
学問の自由の内容としては、①学問研究の自由・②研究結果発表の自由・③教授の自由の3つがある。
- 学問の研究の自由
真理の発見・探求を目的として学問研究を行う自由 - 研究結果発表の自由
研究結果を発表する自由 - 教授の自由
研究結果を教授する自由…旭川学テ事件:最大判昭51.5.21)
なお、先端科学技術をめぐる研究であっても、罰則によって特定の種類の研究活動が規制される場合がある。
例えばヒトに関するクローン技術など
大学の自治
大学の自治とは、大学の内部組織や運営に関しては大学の自主的な決定に任せ、大学内の問題に対する国家権力の干渉を排除しようとすることです。
学問の自由には、大学の自治が含まれます。これは、大学は学問をする典型的な場所であり、大学内の問題に対して国家権力の干渉を許すと、学問の自由が脅かされる恐れがあるとの考えからきています。
🔍 主な判例:
📝 まとめ
精神的自由は、個人の内心の自由や表現の自由、信仰・研究の自由など、民主社会を支える根幹的な権利です。行政書士試験では、各自由の意味や制約、関連する判例などが問われやすいため、体系的に理解しておくことが合格へのカギとなります。
- 具体例:意見広告や反論記事の掲載を請求するなど ↩︎
- 参考:日本テレビが取材したビデオテープを検察官が押収したことの合憲性が争われた、日本テレビ・ビデオテープ押収事件決定(最決平1.1.30)は、博多駅事件の判旨①②を引用している。 ↩︎
- 具体例:政府の転覆を煽動する文書の禁止、国家機密に属する情報の公表の禁止など ↩︎
- 参考:表現の内容を理由とした規制であっても、高い価値の表現でないことを理由に通常の内容規制よりも緩やかに審査され、規制が許されるべきだとされる場合がある。例えば、営利を目的とした表現や、人種的増ををあおる表現(ヘイトスピーチ)など ↩︎
- 具体例:学校近くでの騒音の制限、一定の選挙運動の制限など ↩︎