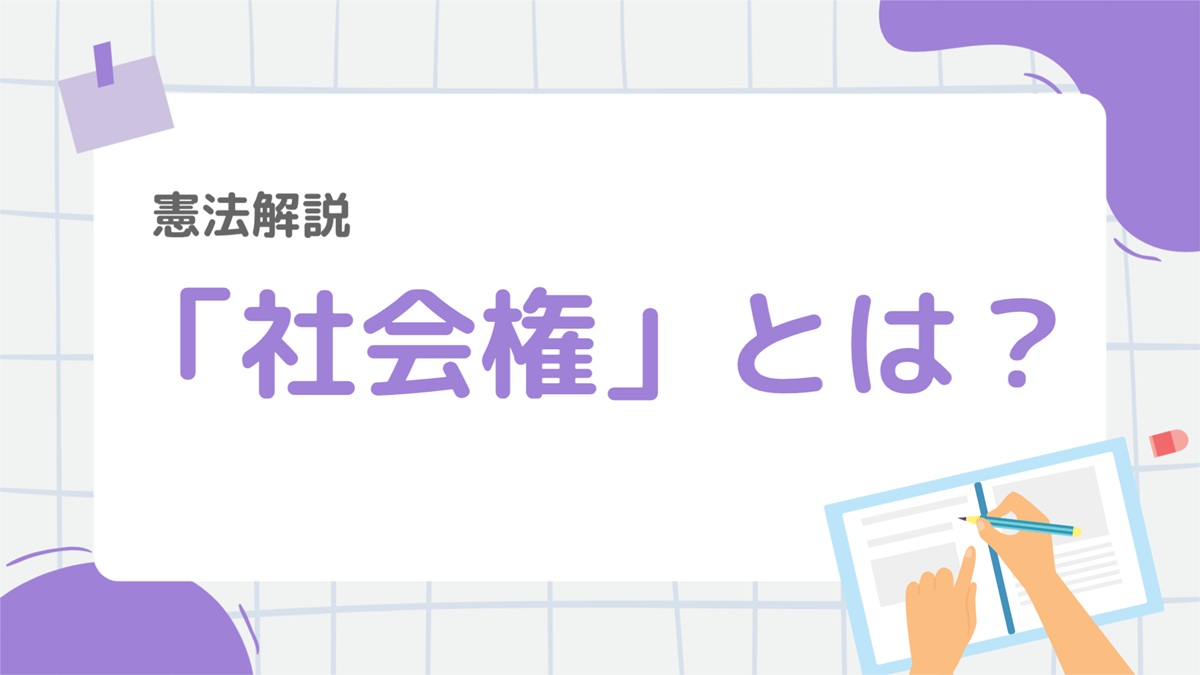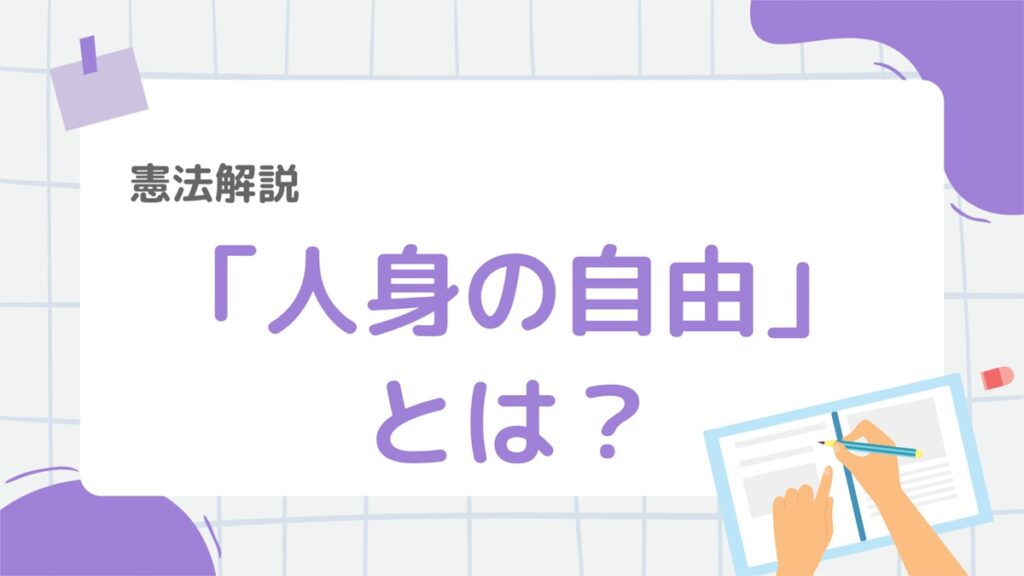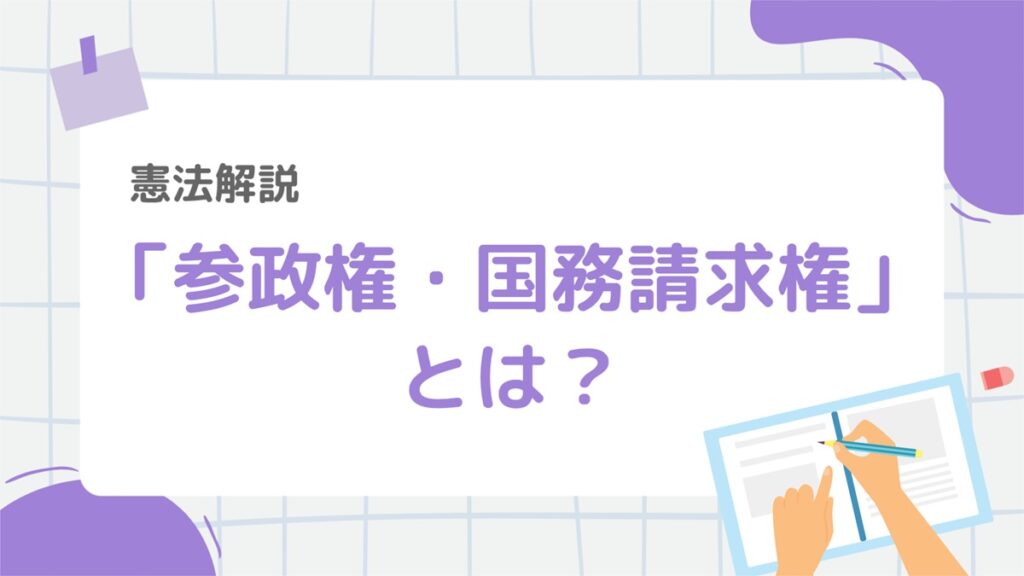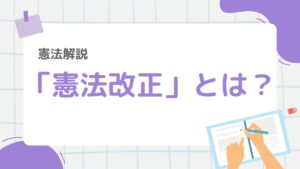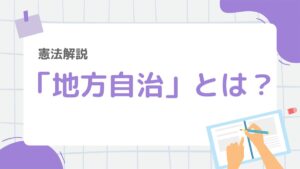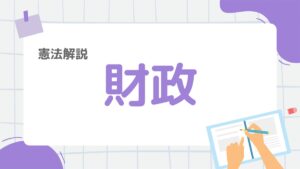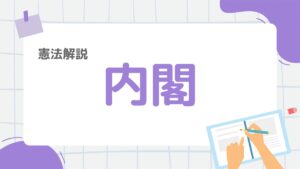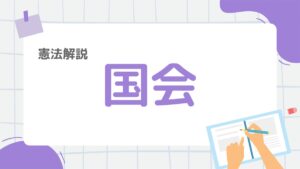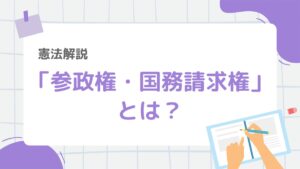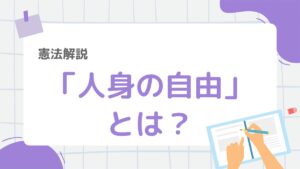- 「社会権ってなんだか抽象的で覚えにくい…」と感じている人
- 行政書士試験の憲法対策で生存権・教育権・労働基本権を重点的に押さえたい人
- 判例や対立説などを整理してインプットしたい人
生存権
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
この規定が「生存権」です。
社会的・経済的に弱い立場の人々も、尊厳ある生活を送るために国家が保障すべき権利であり、いわば「福祉国家」の理念を体現する条文です。
【判例】
🔍【重要】朝日訴訟:最大判昭42.5.24
🔍【重要】堀木訴訟:最大判昭57.7.7
教育を受ける権利
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。」
この規定が「教育を受ける権利」です。人格の形成や社会での自立に不可欠な基本的人権とされています。
(判例:裁決昭32.4.5)
教育内容を決定する権限は誰にある?
この点について、以下2つの対立説があります。
- 国家教育権説
法律は、当然に公教育における教育の内容および方法を包括的に定めることができるとする説。 - 国民教育権説
国の子どもの教育に対する関わり合いは、国民の義務教育の遂行を側面から助成するための諸条件の整備に限られ、教育の内容や方法は教育の実施に当たる教師が教育専門家としての立場から決定すべきとする説。
どちらも一方的な主張とされ、
📌旭川学力テスト事件(最大判昭51.5.21)では、両説を斥けて折衷的な判断を示しました。
義務教育はだれが負う義務か?
「すべて国民は、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」
ここで注意すべき点が2つあります。
✅ 義務を負うのは「親」
「国民が教育を受ける義務がある」と思われがちですが、実際には保護者に子女を普通教育させる義務があります。
✅ 無償の範囲とは?
義務教育は無償とすると規定されている(26条2項後段)ものの、この無償の意義が争われたことがあります。最高裁は、「無償」とは授業料不徴収を意味するものであり、教科書・学用品など全てが無料になるという趣旨ではないと判断しています(最大判昭39.2.26)。
勤労の権利と義務
「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」
国民の生存は、まずは勤労によって支えられるべきという考えに基づいています。
この条文は、❶勤労の権利と❷勤労の義務を同時に定めている点が特徴です。
労働基本権
労働基本権とは?
「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」
労働者が使用者と対等な立場で労働条件を交渉・改善するために、以下3つの権利が認められています。
| 権利 | 内容 |
|---|---|
| 団結権 | 労働者が労働組合などを結成・参加する権利 |
| 団体交渉権 | 労働者の団体が使用者と労働条件を交渉する権利 |
| 団体行動権(争議権) | ストライキなど争議行動を行う権利 |
【判例】
🔍【重要】三井美唄事件:最大判昭43.12.4
🔍【重要】国労広島地本事件:最判昭50.11.28
🔍最大判昭41.10.26(全逓東京中郵事件)
公務員の労働基本権には制限がある?
公務員がストライキなどを行うと、国民生活に深刻な影響を与える恐れがあるため、
📌 公務員には労働基本権に一定の制限がかかります。
その内容や制限の程度は、職種によって異なります。
| 団結権 | 団体交渉権 | 団体行動権 | |
| 警察職員・消防職員・自衛隊員・海上保安庁・刑事施設職員 | × | × | × |
| 非現業の一般の公務員 | 〇 | △ 団体協約締結権は保障されない | × |
| 現業の公務員 | 〇 | 〇 | × |
【判例】
🔍【重要】全農林警職法事件:最大判昭48.4.25
🔍岩手教祖学テ事件判決:最大判昭51.5.21
🔍最判平12.3.17
✅まとめ
社会権は「国が何をすべきか」という視点から理解するのがコツです。
また、条文ごとの具体的内容や判例(特に旭川学テ事件)も重要ポイントなので、行政書士試験の出題頻度が高いテーマとしてしっかり押さえておきましょう!