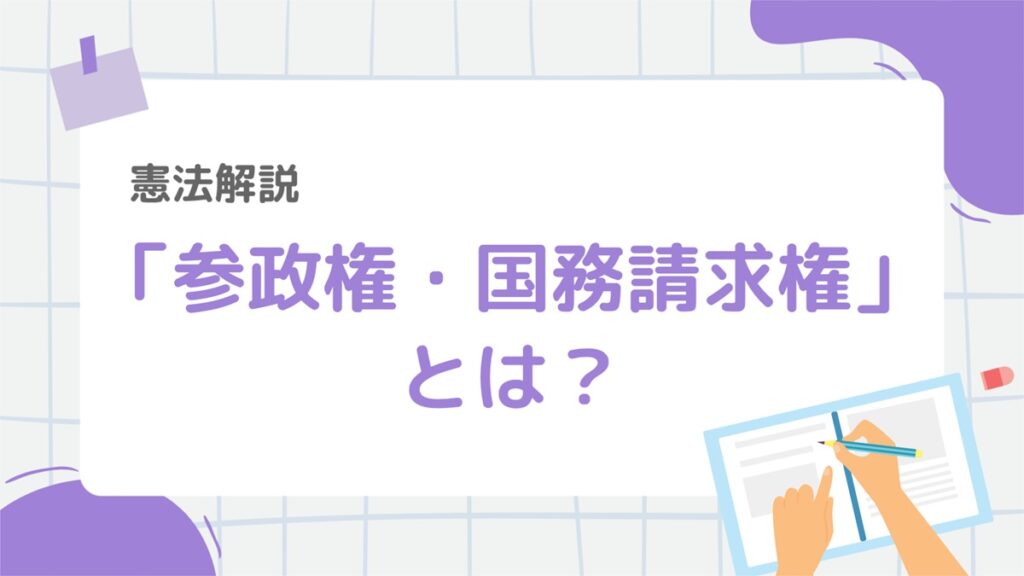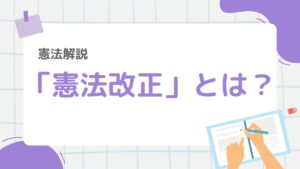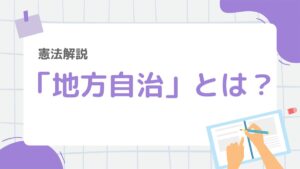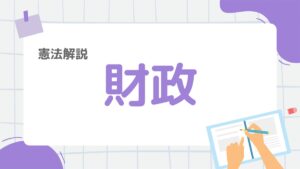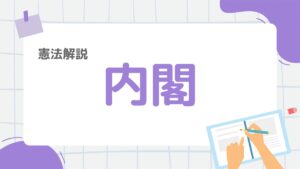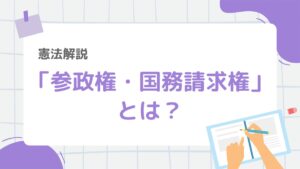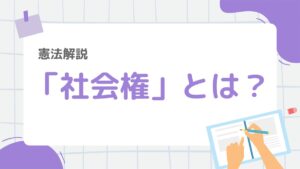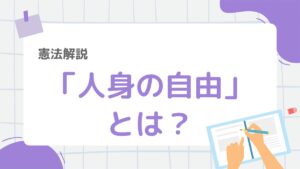- 行政書士試験に向けて、憲法の「国会」に関する知識をしっかり押さえたい
- 「三権分立」や「国会の権限」などを体系的に理解したい
- 衆議院と参議院の違い、衆議院の優越などがよく分からない
権力分立(三権分立)とは?

権力分立とは、国家権力を立法権・行政権・司法権の3つにわけ、それぞれ別の機関が担当し、相互に抑制しあうことでバランスを保つ仕組みのことです。
三権分立とは、国家権力を次の3つに分け、それぞれ別の機関が担う仕組みのことです。
この仕組みによって、国家権力が一極集中するのを防ぎ、国民の権利や自由を守ることが目的です。
.jpg)
🏛 国会の三つの地位とは?
日本国憲法は、国会に次の3つの地位を与えています。
①国民の代表機関
国会は、全国民を代表する選挙された議員で組織されます(43条1項)。そのため、国民の代表機関といえます。
「全国民を代表」とは、国民は代表者である国会議員を通じて行動し、国会議員の行為は、国会議員を選挙で選んだ国民の意思を反映しているものという意味(政治的意味の代表)で、法的に国民と代表者の政治的意思の一致が要求されているわけではありません。
この考え方では、議員は自己の信念に基づいてのみ発言・評決し、選挙区などの訓令には拘束されないという「自由委任の原則」が採用されることになります。
②国権の最高機関
国会は、国権の最高機関とされています(41条)。
「最高機関」とは、国会が他の機関より優先する権力をもつという意味ではなく、国会議員が主権者の国民に直接選挙されることから、国民と直結しているため政治の中心的地位を占める機関とういことを強調したにすぎないと考えられています(政治的美称説)。
③唯一の立法機関
国会は唯一の立法機関とされ、国会が立法権を独占しています(41条)。
- 「立法」の意味
「立法」には、法の一形式である「法律」の定立という「形式的意味の立法」と、「法規」という特定の内容の法規範の定立という「実質的意味の立法」の2つの意味があり、憲法41条の「立法」は、実質的意味の立法を指します。
「法規」とは、民主主義体制の下では、およそ一般的・抽象的規範であれば、すべて法規に含まれると考えられています。 - 「唯一」の意味
「唯一」の立法機関とは、次の2つの意味があります。
🏛 二院制とは? 衆議院と参議院の違い
国会は、次の2つの議院で構成されます(42条)。これを二院制といいます。
| 項目 | 衆議院 | 参議院 |
|---|---|---|
| 任期 | 4年(解散あり) | 6年(3年ごとに半数改選、解散なし) |
| 解散 | あり | なし |
| 設立目的 | 国民の意見を反映しやすい | 衆議院の暴走をチェックする |
※同時に両方の議員にはなれません(48条)。
🥇 衆議院の優越とは?
意見が対立した場合に、決定ができなくなるのを防ぐため、憲法は衆議院に「優越」を認めています(衆議院の優越)。その理由は、衆議院は任期が短く、解散もあるため、国民の意思を反映しやすいからです。
【衆議院の優越が認められる主な場面】
| 項目 | 衆議院の優越の内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 予算の先議権 | 先議権がある | 60条1項 |
| 内閣不信任決議 | 衆議院のみ可能 | 69条 |
| 法律案の議決 | 再可決できる(3分の2以上) | 59条2項~4項 |
| 予算の議決 | 衆議院の議決が優先 | 60条2項 |
| 条約 | 衆議院の議決が優先 | 61条 |
| 総理大臣の指名 | 衆議院の議決が優先 | 67条2項 |
📅 国会の会期と種類
会期
国会は常時開かれているわけではなく、一定の「会期」に限って活動します。国会が1年を通じて活動すると、政党間の争いの激化、立法の過度な増加、議会での討論の長期化、行政能率の低下などの弊害が生じるためこのような制度になっています。
会期中に議決されなかった案件は、後の会期に継続しないのが原則(国会法68条本文)。これを会期不継続の原則といいます。
会期には、❶常会、❷臨時会、❸特別会の3種類がある。
【会期の種類】
| 会期 | 内容 |
|---|---|
| 常会 (通常国会) | 通常国会とも呼ばれる。毎年1回、予算審議などのために開かれる(52条) |
| 臨時会 | 臨時の必要に応じて内閣が招集。または、いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない(53条)。 |
| 特別会 | 衆議院の解散後に行われる総選挙後に召集される国会。 衆議院が解散されたとき、解散の日から40日以内に衆議院の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に国会(特別会)を招集しなければならない(54条1項)。 |
参議院の緊急集会
衆議院が解散されたとき、参議院は同時に閉会となります。内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができます(54条2項)。
参議院の緊急集会とは、衆議院が解散されてから総選挙後の特別会が召集されるまでの間に緊急の事態が生じた場合に、参議院が国会の権能を代行する制度です。
緊急集会で決定されるものとして、自衛隊の防衛出動や、災害緊急措置などがあります。
📜 会議の原則と手続き
定足数と表決数(56条1項)
- 定足数:議事や議決には、総議員の3分の1以上の出席が必要
- 表決数:原則、出席議員の過半数の賛成で決まる。可否同数なら議長が決定権をもつ(56条2項)。
【憲法に特別の定めのある場合】
出席議員の3分の2以上
総議員の3分の2以上必要
- 憲法改正の発議(96条1項前段)
会議の公開(第57条)
- 原則公開。国民の知る権利を保障するため(57条1項本文)。
- ただし、出席議員の3分の2以上の賛成で秘密会にできる。(57条1項但書)。
- なお、出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない(57条3項)。
🛡 国会議員の3つの特権
憲法は両議院の議員(国会議員)に3つの特権、❶歳費受領権・❷不逮捕特権・❸免責特権を付与している。
歳費受領権
両議院の議員は法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費をうけとることができます(49条)。
不逮捕特権
両議院の議員は、法律の定める場合の除いて、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない(50条)。これを不逮捕特権という。
不逮捕特権が認められた理由として、
❶議員の審議権を確保すること
❷国会議員の身体の自由を保障し、政府により国会議員の職務執行が妨げられないようにするため
の2つにある。
免責特権
両議院の議員は、議員で行った演説・討論・表決について、院外で責任を問われない(51条)。
これを免責特権という。目的は、国会議員が責任を問われることを恐れて萎縮することを防ぐため。
⚖ 国会と議院それぞれの権能
国会の権能は、衆参両議院の意見が一致しなければ行使することができないのに対し、議員の権能はどちらか一方の議院だけで行使することができる。
国会の権能
- 法律の制定
法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いて、両議院で可決したときに法律となる(59条1項)。 - 条約の承認
条約の締結は国民の権利義務に重大な影響を及ぼすことから、国民の代表機関である国会の承認が必要(61条、73条3号但書) - 弾劾裁判所の設置
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議院で組織する弾劾裁判所を設けることができる(64条1項)。 - 内閣総理大臣の指名
⇒憲法解説(11):内閣 – 内閣総理大臣の指名 - 憲法改正の発議
議院の権能
議員の権能は以下。❶~❸をまとめて議院の自律権という。
- 議員の資格争訟の裁判権
両議院は各々その議院の資格に関する争訟を裁判する。議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の議決が必要(55条)。 - 役員の選任権
両議院は、各々その議長その他の役員を選任することができる(58条1項)。 - 議員規則制定権・議員懲罰権
両議院は、各々その会議その他の手段および内部の規律に関する規則を定めることができる(58条2項本文)。これを議員規則制定権という。
また、両議院は、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる(58条2項本文)。これを議員懲罰権という。ただし、議員を除名するには出席議員の3分の2以上の議決が必要(58条2項但書)。 - 国政調査権
国政に関して調査を行う議院の権能。
両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して証人の出頭・証言、記録の提出を求めることができる(62条)。国政調査権は、各議院に与えられた権能を実効的に行使するために認められた補助的な権能と考えられている。
✅ まとめ:国会の仕組みを正しく理解しよう
国会は、国民の代表として法律を制定し、政治の中心を担う重要な機関です。
行政書士試験では、国会の地位や権限、衆議院と参議院の違い、衆議院の優越などが頻出です。
三権分立との関係や、各議院の特権・権限の違いなど、やや細かい点まで問われることがあるため、図表や比較を活用してしっかり整理しておきましょう。
特に、「国権の最高機関」や「唯一の立法機関」といった言葉の意味を正確に理解しておくことで、ひっかけ問題にも強くなれます。