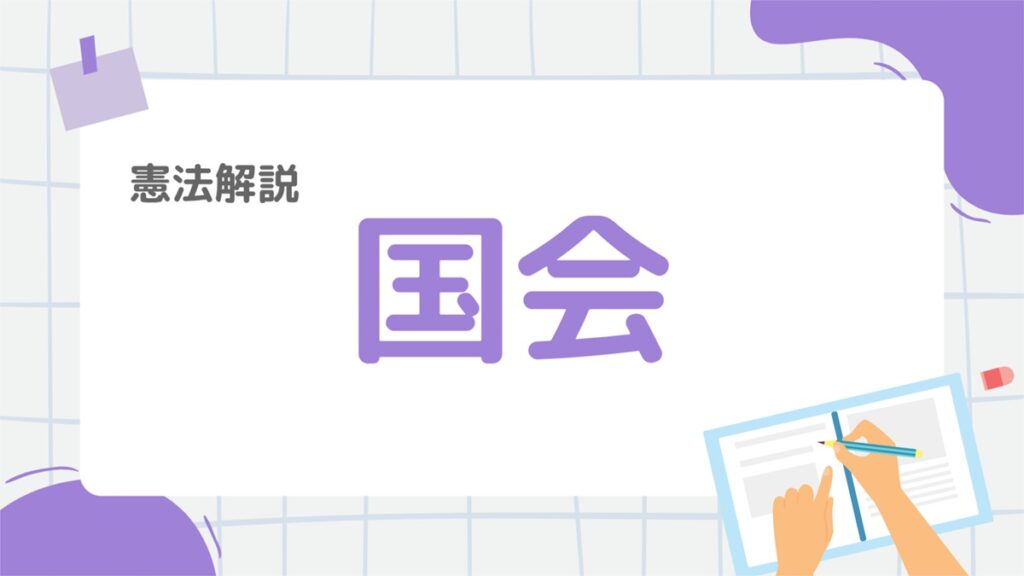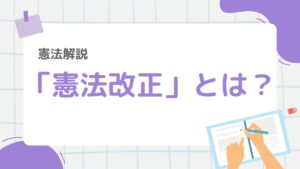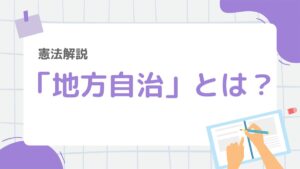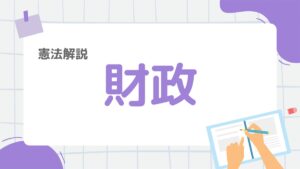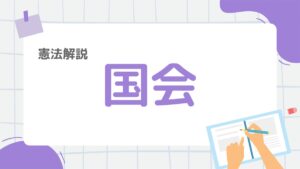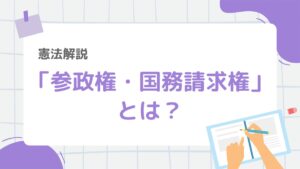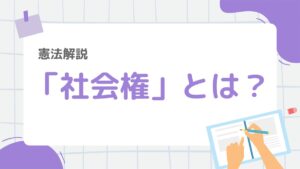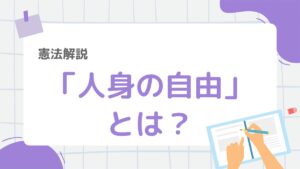- 「内閣」や「行政権」の仕組みをざっくり理解したい
- 議院内閣制のポイントを試験対策として押さえたい
- 内閣総理大臣と内閣の違いがよくわからない
行政権とは?:立法・司法と並ぶ国家の機能
行政権とは、国家権力のうち「立法権」と「司法権」を除いた部分と定義されるのが一般的です(これを「控除説」といいます)。行政の活動は多岐にわたるため、積極的に「これが行政権だ」と明確に定義するのは難しいとされています。
そして、憲法第65条では、この行政権が「内閣に属する」と明記されています。
内閣の組織と構成:だれが内閣をつくるの?
内閣のメンバー構成
内閣は、首長である「内閣総理大臣」と「その他の国務大臣」で組織されます(66条1項)。
なお、内閣総理大臣および国務大臣は すべて「文民※」でなければならない とされています(66条2項)。これは、軍事権を文民がコントロールし、軍の暴走を防ぐための規定です。
※文民:現役の職業軍人および自衛官ではない者

内閣総理大臣と国務大臣の選び方
👉内閣総理大臣の選出方法
👉国務大臣の任命と要件
- 内閣総理大臣が、内閣の一体性を確保するため任命・罷免することができます(68条1項本文・2項)。
- ただし、国務大臣の過半数は国会議員から選ばなければならない(68条1項但書)
内閣の総辞職:いつ、なぜ、どうなる?
総辞職とは?
総辞職とは、内閣総理大臣および国務大臣の全員が同時に辞職すること。
総辞職が必要となる3つのケース
内閣は、自らの意思でいつでも総辞職できるますが、次の場合には、意思にかかわらず総辞職しなければなりません。
総辞職後の内閣の役割
新たな内閣総理大臣が任命されるまで、職務を継続する(71条)。
これは、行政の空白期間をつくらないための仕組みです。
日本の政治体制と議院内閣制の特徴
議院内閣制とは、政府(行政権)と議会(立法権)が原則として分立しつつも、政府が議会に対して責任を負う体制のことです。日本国憲法には明記されていませんが、以下のような規定から、議院内閣制を採用していると理解されています。
- 内閣は国会に対して連帯責任を負う(66条3項)
- 内閣総理大臣は国会議員から国会の議決で指名(67条1項)
- 国務大臣の過半数は国会議員(68条1項但書)
- 内閣不信任決議制度の存在(69条)
- 国務大臣の国会出席・発言権(63条)
内閣の連帯責任
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う(66条3項)。
内閣の連帯責任は、国民からの政治的批判を受けるという政治責任を意味します。
内閣総理大臣の指名
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名する(67条1項)。
国務大臣の任命
国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばなければならない(68条1項但書)
内閣不信任決議権
内閣不信任決議がなされると、内閣は、総辞職するか衆議院を解散するかを選択しなければならない(69条)。
国務大臣の議院出席
議院内閣制の下、行政権の行使について国会に対して連帯責任を負う内閣の構成員である国務大臣には、議員に出席して発言する機会を与える必要があるから、国務大臣の議院出席が認められている(63条)。
内閣と内閣総理大臣の権限の違いとは?
内閣と内閣総理大臣は、それぞれ独自の権限を持っています。
内閣の権能
一般行政事務の他、以下のような権限を行使できる(73条)。
- 法律の誠実な執行・国務の総理
法律の誠実な執行とは、たとえ内閣の賛成できない法律であっても、法律の目的にかなった執行をしなければならないという意味。国務の総理とは、国の政治全体が調和を保って円滑に進行するよう配慮すること。 - 外交関係の処理
外交交渉をしたり、外交文書を作成すること。 - 条約の締結
機動性を有し、専門的な判断力のある内閣に条約締結権が与えられている。
ただし、事前もしくは時宜によっては事後に国会の承認を得ることが必要(73条3号但書) - 官吏に関する事務の掌理
官吏(かんり)とは、国家公務員のことであり、地方公務員は含まれない。 - 予算の作成・国会への提出
予算の作成には専門性・迅速性が必要なことから、内閣に予算の作成権が与えられている。 - 政令の制定
政令とは、内閣が制定するルール。政令は、憲法および法律の規定を実施するために制定される。
ただし、指令には、特に法律の委任がある場合を除いて、罰則を設けることができない(73条6号但書) - 恩赦の決定
内閣が恩赦を決定し、天皇が認証する(7条6号)。
内閣総理大臣の権能
- 国務大臣の任命・罷免
内閣総理大臣は、国務大臣を任命したり罷免したりすることができる(68条1項本文・2項) - 内閣を代表する権限
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務および外交関係について国会に報告し、行政各部を指揮監督する(72条)。
【重要】ロッキード事件:最大判平7.2.22
- 法律・政令の連署
執行責任を明確にするため、内閣総理大臣は、法律・指令について、主任の国務大臣とともの署名(連署)する(74条)。 - 国務大臣の訴追
訴追が慎重に行われるようにするとともに、内閣総理大臣の首長たる地位を確保するため、国務大臣を在任中に訴追するには、内閣総理大臣の同意が必要(75条本文)
ただし、このために訴追の権利は害されないとされている(75条但書)。「訴追の権利は、害されない」とは、訴追のための準備として国務大臣の在任中でも証拠の保全等のために必要な措置を行うことができ、公訴時効も停止するという意味。
👉上記以外に、行政事件訴訟法の執行停止に対し、異議を述べることができる。
おわりに|内閣の仕組みを押さえれば、憲法理解がグッと深まる!
内閣の仕組みは、「誰が何をするのか」「どこに責任を負うのか」を明確にすることで、政治の安定と国民の信頼を支える重要な制度です。
行政書士試験では、内閣の組織・権限・議院内閣制との関連などが頻出ですので、ぜひ本記事で整理しておきましょう!