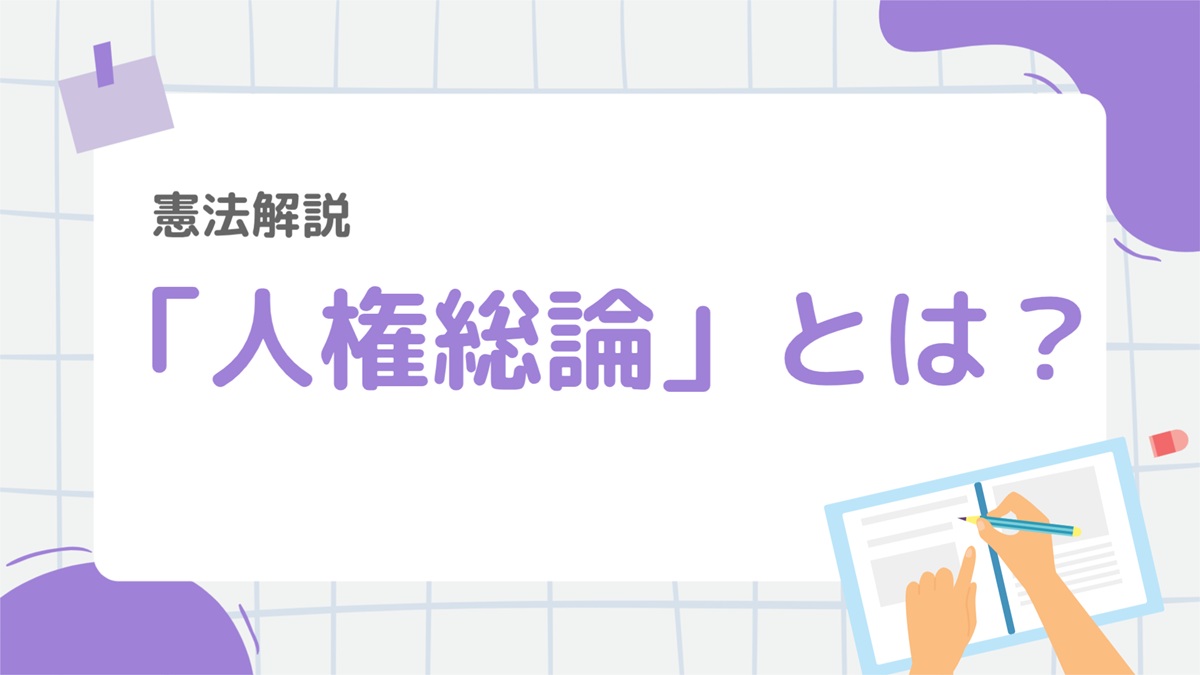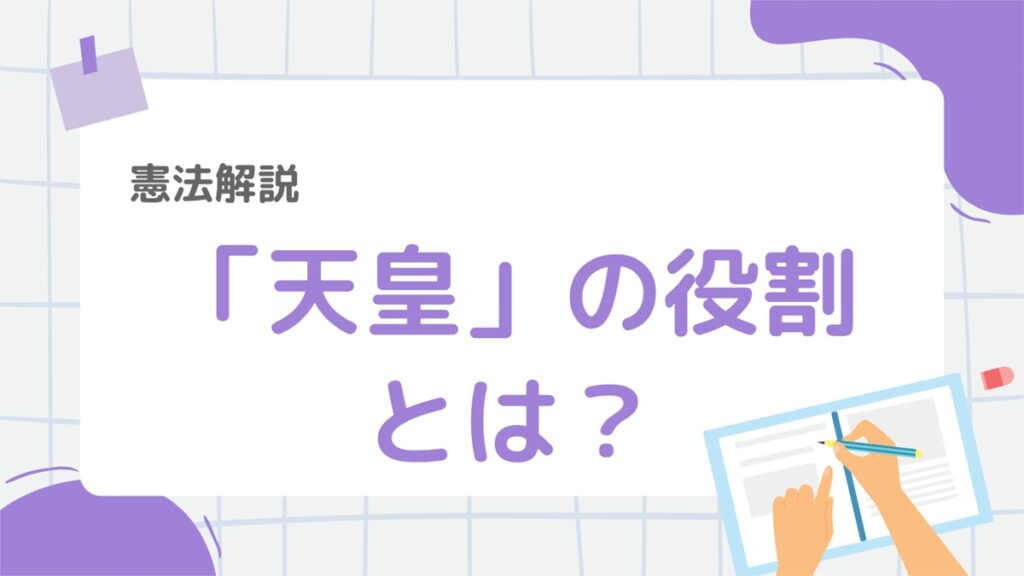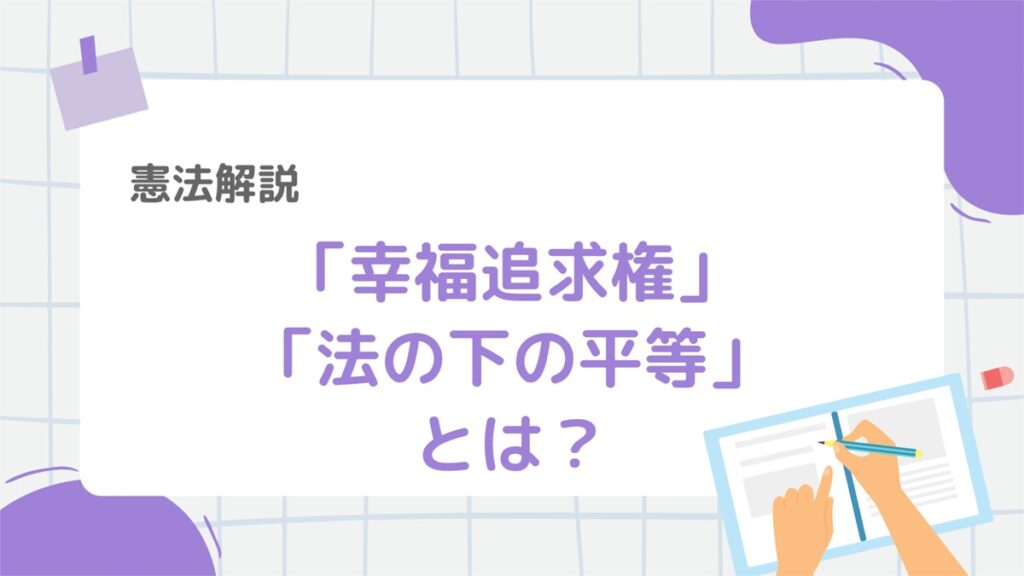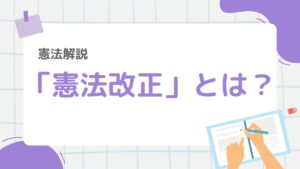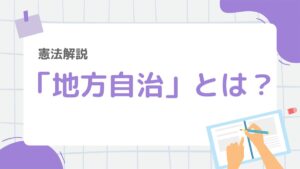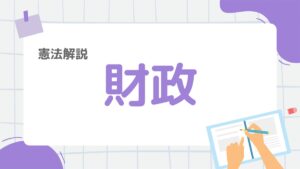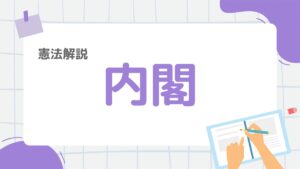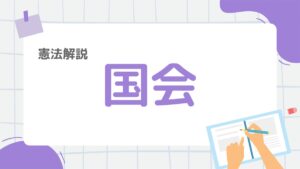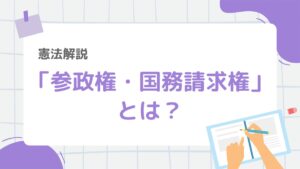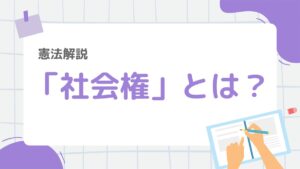- 「人権って結局どんな種類があるの?」とモヤモヤしている人
- 法人や外国人に人権があるかどうかを整理したい人
- 人権の限界や私人間効力といった難しい概念をスッキリ理解したい人
人権とは?基本のキホン
人権とは「人が生まれながらにして当然に持っている権利」のことです。
日本国憲法ではこの人権をとても大切なものとして位置づけており、その保障の仕組みを理解することは、試験でも重要なポイントです。
人権の4つの分類
人権とは、人間が生まれながらにして当然に持っている権利。人権は大きく以下の4種類に分けられます。
■人権の分類
| 自由権 | 国家が国民に対して強制的に介入することを排除して、個人の自由な活動を保障する権利 |
|---|---|
| 社会権 | 社会的弱者が人間に値する生活を送れるように国家に一定の配慮を求める権利 |
| 参政権 | 国民が自己の属する国の政治に参加する権利 |
| 国務請求権 | 人権の保障を確実なものとするため、国に対して一定の行為を求める権利 |
自由権の3つの分類
自由権はさらに次の3つに分けられます。
人権の享有主体:誰が人権を持つのか?
本来、人権は「自然人(=生身の人間)」に保障されるものですが、法人や外国人にも適用されるかが問題となります。
法人の人権
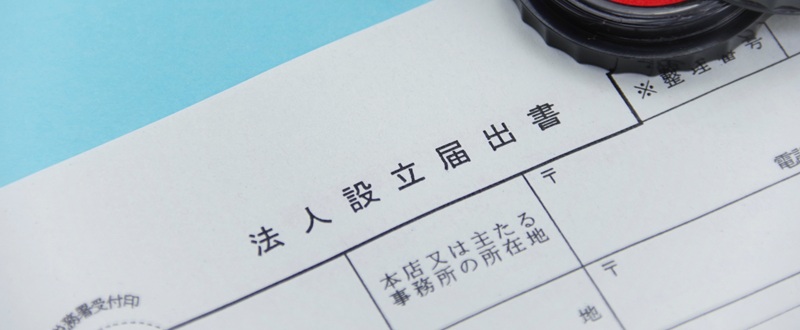
法人も社会的に重要な存在であるため、「権利の性質上可能な限り」人権が保障されるというのが最高裁の立場です(八幡製鉄事件:最大判昭45.6.24)。
🔍 主な判例:
外国人の人権
憲法第3章は「国民の権利および義務」と書かれていますが、外国人にも権利の性質上日本国民のみを対象としている場合を除て保障されるとされています(マクリーン事件:最大判昭53.10.4)
①入国の自由
入国の自由は、外国人には保障されない。(最大判昭32.6.19)
国際法上、国家が自国に危害を及ぼす恐れのある外国人の入国を拒否することは、その国家の権限に属するとされているためです。
🔍 主な判例:
②社会権
社会権は、各人の所属する国が保障する権利につき、外国人には保障されない。
🔍 主な判例:
③参政権
参政権は、国民が自己の属する国の政治に参加する権利につき、外国人には保障されない。
🔍 主な判例:
人権の限界と制限
- ①公共の福祉による人権の制限
-
憲法は、人権を「侵すことのできない永久の権利」(11条)としているから、国家権力は人権を制限することができないのが原則とするものの、人権は絶対無制限ではなく、他人の権利とのバランスを取るために「公共の福祉」によって制限されることがあります(13条)
- ②特別な法律関係に基づく人権制限
-
国家との特別な関係(例:公務員、受刑者など)にある人は、人権が制限されることがあります。
②-1公務員の人権
公務員は、政治的に中立であることが要求され、政治的目的をもって政治的行為を行うことが禁止されている。
🔍 主な判例:
②-2 在監者の人権
在監者については、逃亡や証拠隠滅などを防止するため、刑事施設に強制的に収容するという身体の拘束が認められている。
🔍 主な判例:
人権の私人間効力(しじんかんこうりょく)
①人権の私人間効力とは
もともと憲法の人権は「国家 vs 国民」を想定したものでした。しかし、企業などの私的団体による人権侵害も問題になるようになりました。そこで、憲法の人権規定が私人と私人の間でも適用されるかといった問題を人権の私人間効力の問題といいます。
②間接適用説(判例の立場)
人権の私人間効力の問題について、考え方が分かれています。まず、憲法の人権規定が私人と私人の間でも直接適用されるとする考え方(直接適用説)。しかし、この考え方によると、私人相互の関係に対して憲法が大きく介入することになり、私的自治の原則に反することになります。
そこで、最高裁判所の判例は、憲法の人権規定は、民法などの私法を通して、間接的に適用されるとしています(三菱樹脂事件:最大判昭48.12.12)。(間接適用説)
例えば、女性であることを理由に会社に雇用されなかった場合、憲法14条1項が性別による差別を禁止している以上、このような憲法に反する措置は公の秩序に反するとして、民法90条により無効であると判断しています。(憲法14条1項違反により無効であると判断するわけではない。)
🔍 主な判例:
まとめ
行政書士試験において、「人権総論」は基本であると同時に判例知識も問われる重要分野です。分類・享有主体・制限・私人間効力といったテーマを体系的に理解することが、得点アップへの近道です!