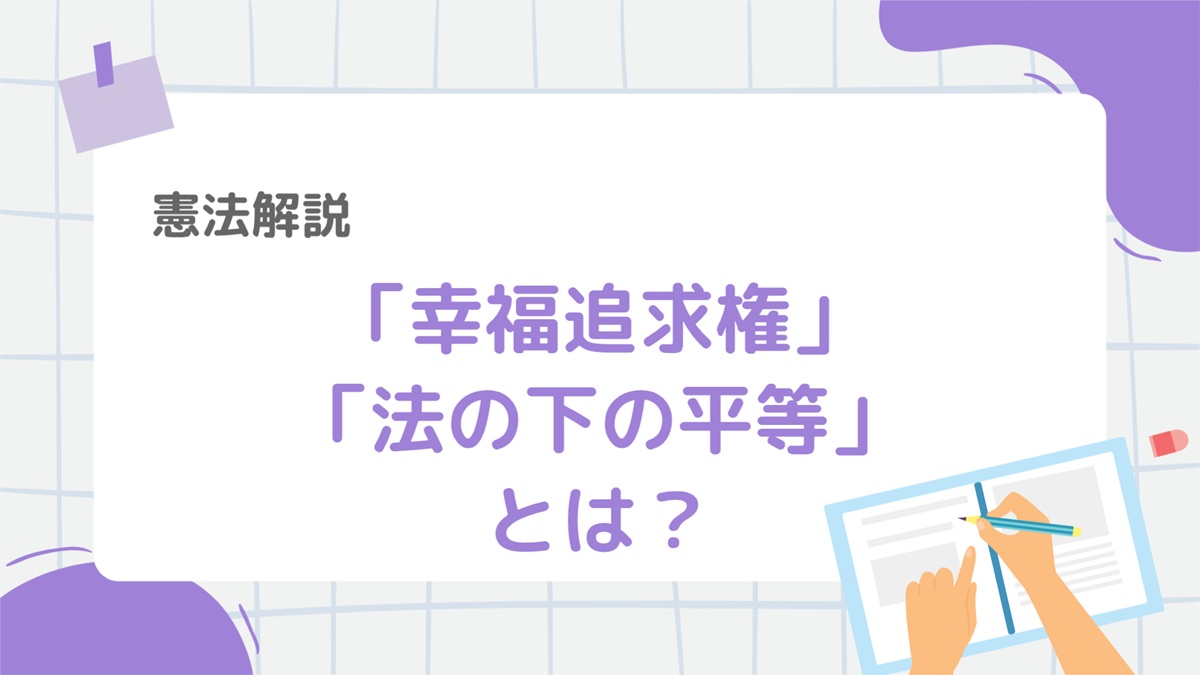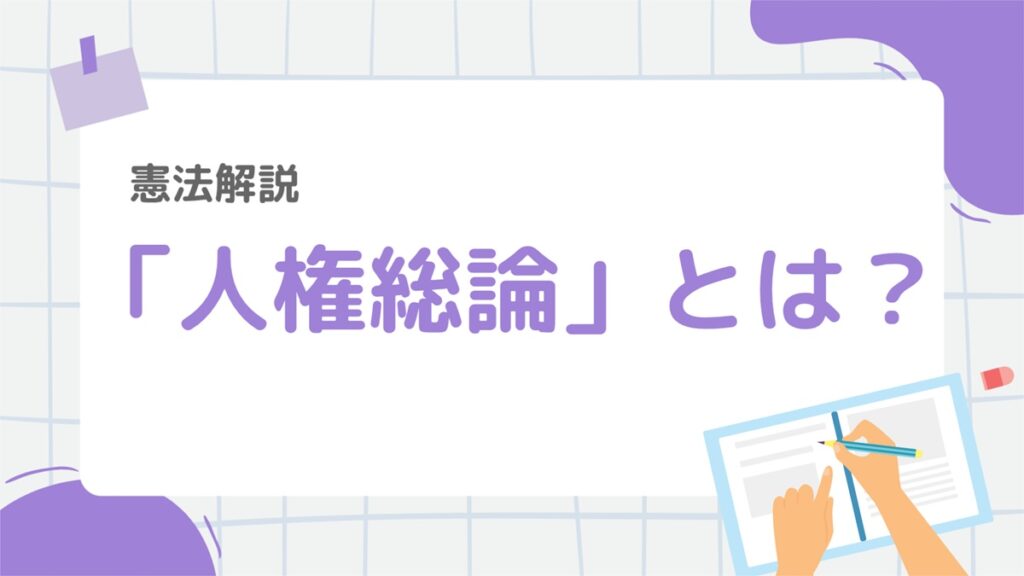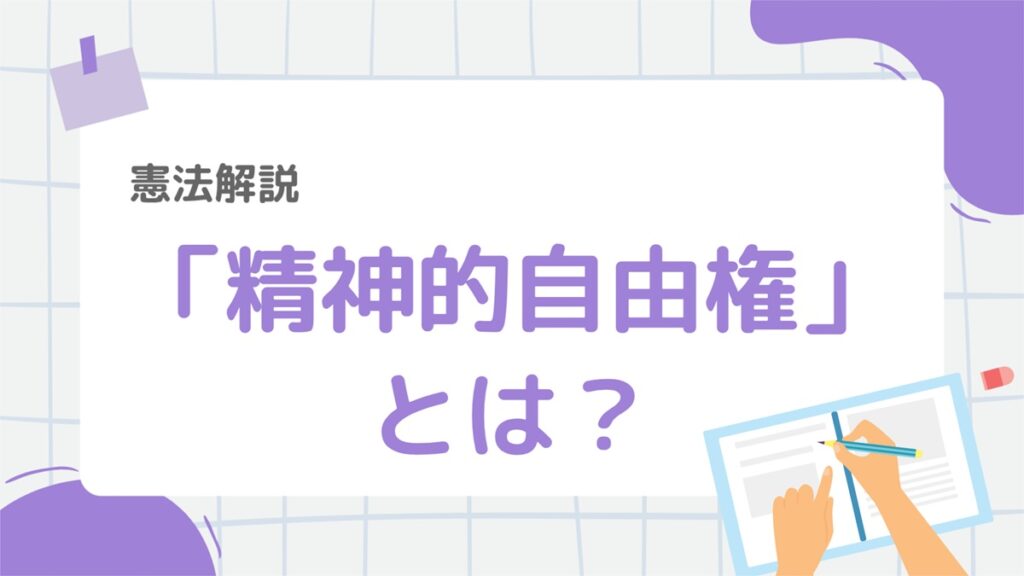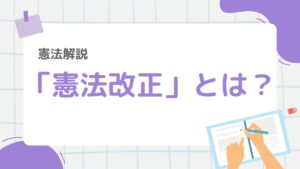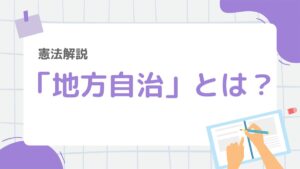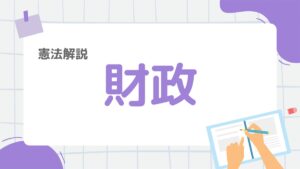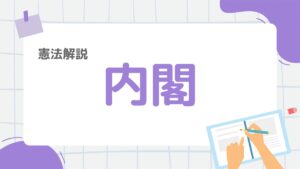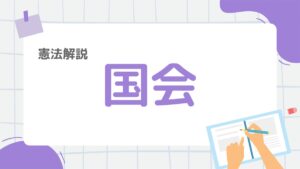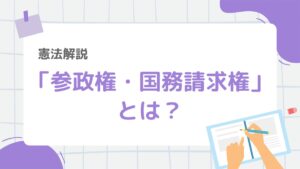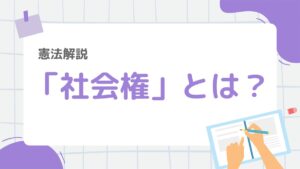- 「幸福追求権って結局どういう権利?」とモヤモヤしている方
- 憲法13条を根拠とした「新しい人権」の判例を押さえたい方
- 「法の下の平等」について、行政書士試験で問われるポイントを整理したい方
「幸福追求権」とは?新しい人権の土台
日本国憲法は第13条で、すべての国民に「個人として尊重される権利」や「生命・自由・幸福追求に対する国民の権利」を保障しています。
ただし、憲法14条~40条に列挙されている人権(自由権・社会権・参政権・国務請求権など)は、歴史的に重要なものに限られており、現代社会で問題となるような新たな人権まで網羅しているわけではありません。
そこで、憲法13条後段の「幸福追求権」は、明文の規定がない権利についても、個人の人格的な生存に不可欠であれば、憲法上保障される根拠となるのです。これを「新しい人権」と呼びます。
新しい人権の具体例と判例
幸福追求権を根拠として認められた「新しい人権」として、肖像権・プライバシー権・自己決定権などがあります。
肖像権
肖像権とは許可なく容貌・姿態を撮影されない権利です。最高裁判所の判例は、憲法13条を根拠に実質的な肖像権を認めています。(※肖像権を認めると名言したわけではない)
📌主な判例:
プライバシー権
プライバシー権とは、従来、「私生活をみだりに公開されない権利」(消極的権利)と定義されてきましたが、情報化社会の進展により、今では「自己に関する情報をコントロールする権利(積極的権利)」としても位置付けられています。
📌主な判例:
- 【重要】前科照会事件(最判昭56.4.14)
- 【重要】ノンフィクション「逆転」事件(最判平6.2.8)
- 【重要】指紋押捺拒否事件(最判7.12.15)
- 【重要】早稲田大学講演会参加者名簿提出事件(最判平15.9.12)
- 【重要】住基ネット訴訟(最判平20.3.6)
- 最判平15.3.14:犯罪を犯した少年を特定できる記事の不法行為成立の有無
自己決定権
自己決定権とは、自分の人生にかかわる重大なこと(例:治療方針など)を、国家や他人に干渉されずに自分で決めることができる権利です。
📌主な判例:
憲法14条「法の下の平等」も重要!
憲法14条1項は、「すべて国民は法の下に平等であって、人種・信条・性別・社会的身分又は門地により差別されない」と規定しています。さらに個別的に、貴族制度の廃止(14条2項)・栄典に伴う特権の禁止(14条3項)といった規定を設けて、平等原則の徹底化を図っています。
ただし、ここでの「平等」とは機械的な絶対的平等ではなく、事柄の性質に応じた合理的な区別は許されるという「相対的平等」が原則です。
📌【判例】尊属殺重罰規定違憲判決(最大判 昭和48年4月4日)
→社会的身分に基づく差別的な刑罰規定が違憲と判断されました。

法の下の平等の意味
「法の下」の意味は、法を平等に適用しなければならないこと(法適用の平等)のみならず、法の内容自体も平等でなければならないこと(法内容の平等)も含まれます。
なぜなら、不平等な内容の法を平等に適用したとしても、不平等は解消されないため。
次に「平等」の意味は、事実上の違いを無視して機械的に平等に取り扱うこと(絶対的平等)ではなく、事実上の違いを前提に結果として平等になるよう取り扱うこと(相対的平等)を意味します。
これは、事実上の違いを無視して機械的に平等に取り扱うと、かえって不平等な結果となる場合があるためです。
このように、憲法14条1項は、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨のため、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取り扱いをすることは、憲法14条1項に違反するものではありません(最大判昭39.5.27)。
法の下の平等が及ぶ範囲
憲法14条1項は人種・信条・性別・社会的身分・門地を列挙しているが、これらの事由は例示的なものであって、これ以外の事由についても法の下の平等の保障は及ぶ(最大判昭39.5.27)。
判例:最大判平11.11.10:選挙制度を政党本位にすることについて
- 人種
人種とは、皮膚・毛髪・目・体型等の身体的特徴によって区別される人類学上の種類 - 信条
信条とは、宗教上の信仰のみならず、思想上・政治上の主義を含む(最判昭30.11.22)。 - 性別
性別による差別が問題となった判例には以下がある
👉【重要】女性の再婚禁止期間(最大判平27.12.16) - 社会的身分
社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位のこと(最大判昭39.5.27)1
■社会的身分による差別が問題となった判例
👉【重要】尊属殺重罰規程違憲判決(最大判昭48.4.4)
👉【重要】婚外子国籍訴訟(最大判平20.6.4)
👉【重要】非嫡出子の相続分(最大決平25.9.4) - 門地
門地とは、家柄のこと
議員定数不均衡
議員定数不均衡とは、選挙において、各選挙区の議員定数の配分に不均衡があり、人口数との比率において、選挙人の投票価値に不平等が生じていること。※一票の重みが違う。
---
config:
theme: neutral
---
flowchart LR
subgraph B選挙区
議員B["議員"]
投票B["↑投票"]
style 投票B fill:none,stroke:none
有権者B["有権者<br>10万人"]
end
subgraph A選挙区
議員A["議員"]
投票A["↑投票"]
style 投票A fill:none,stroke:none
有権者A["有権者<br>20万人"]
end
有権者A <-->|1票の較差<br>不均衡| 有権者B
- 衆議院の場合
【重要】衆議院議員定数不均衡訴訟(最大判昭51.4.14)
【重要】衆議院議員定数不均衡訴訟(最大判昭60.7.17)
【重要】衆議院議員定数不均衡訴訟(最大判平23.3.23) - 参議院の場合
【重要】参議院議員定数不均衡訴訟(最大判平24.10.17) - 地方議会の場合
【重要】地方議会と議員定数不均衡(最判昭59.5.17)
まとめ
✅ 幸福追求権(憲法13条)は、憲法に明文で書かれていない「新しい人権」の根拠となる
✅ 「肖像権」「プライバシー権」「自己決定権」などがその代表例
✅ 「法の下の平等」(憲法14条)は、合理的な理由なき差別を禁じている
✅ 判例を押さえて、試験でも得点源にしよう!
- 具体例:親子関係など ↩︎