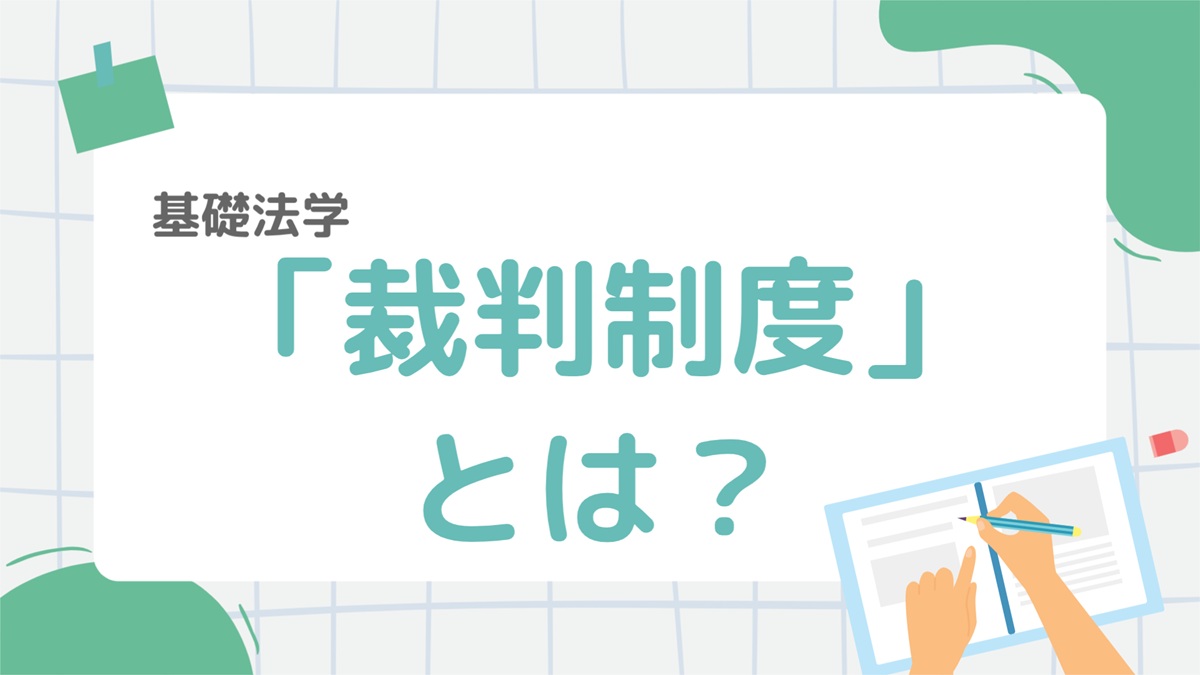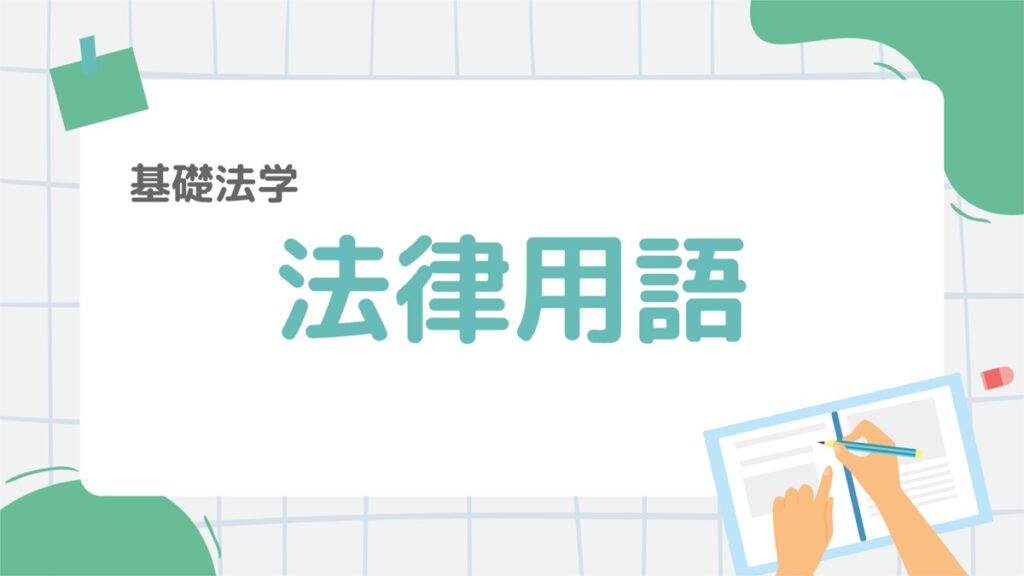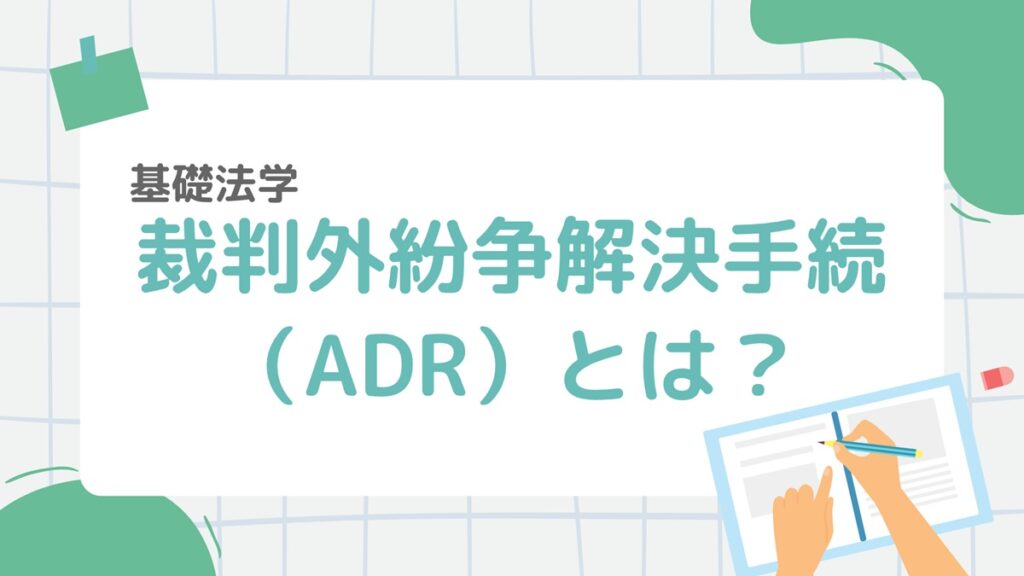- 行政書士試験の憲法対策として「裁判制度」について理解を深めたい人
- 「三審制」や「裁判所の種類」の違いがイマイチわからない人
- 民事・刑事・行政の裁判の違いを簡単に整理したい人
- 憲法の学習初心者で、司法制度の全体像をざっくりと把握したい人
- 「裁判制度とは?」を図や具体例で直感的に理解したい中高生や社会人受験生
裁判とは?
裁判とは、裁判所や裁判官が、現実に起こったトラブルやもめごとを法律に基づいて解決する手続きのことです。これは「司法」の役割のひとつであり、公的な立場から行われる法的な判断といえます。
裁判は大きく分けて2つあります。
1つは、お金の貸し借りや契約トラブルなど、私人間の権利や義務をめぐる争いを解決する「民事裁判」。
もう1つは、殺人や窃盗などの犯罪を犯した人に対して、その責任を問うための「刑事裁判」です。
民事裁判では、裁判を起こす側を「原告」、訴えられる側を「被告」といいます。
一方、刑事裁判では、裁判を起こすのは「検察官」であり、裁かれる人のことを「被告人」と呼びます。
裁判の基本原則
裁判には、適正な手続きと公平な判断を実現するための「基本原則」があります。ここでは、その中でも重要な3つの原則をご紹介します。
当事者主義
当事者主義とは、裁判での主張や証拠の提出(立証)を、当事者同士に任せるという考え方です。裁判官は、そのやりとりを整理・最終的な判断する立場にとどまります。
この原則は、民事裁判と刑事裁判の両方で採用されており、「当事者が主導し、裁判官は裁く」という構図になります。
自由心象主義
自由心象主義とは、裁判所が証拠にもとづいて事実を認定するとき、その判断を裁判官が自由に行えるという原則です。裁判官が自らの良識と経験に基づいて「どの証拠を信用するか」を決められるのが特徴です。
この原則も、民事裁判・刑事裁判の両方で採用されています(民事訴訟法247条、刑事訴訟法318条)。
そのため、同じ事件でも、民事裁判と刑事裁判で異なる事実認定がされることもあります。
証明責任(挙証責任)
裁判では、ある事実が「あったのか・なかったのか」がはっきりしない場合でも、裁判を行わなければなりません。そのとき、どちらか一方の当事者がその不確定な結果による「不利益」を受けることになります。
このとき、不利益を負う側が負担する責任のことを「証明責任(挙証責任))」といいます。
- 民事裁判では、一定の法律効果を主張する側(たとえば原告)が、その効果を発生させるために必要な事実(要件事実)を証明する責任を負います。1
- 一方、刑事裁判では、原則として検察官が挙証責任を負います。これは、「疑わしきは被告人の利益に」という被告人の人権を守る原則があるためです。
裁判所・裁判官
裁判所
裁判所は、最高裁判所と下級裁判所に大別されます。2
- ①最高裁判所
-
最高裁判所は大法廷3または小法廷4のいずれで審理を行うかを自由に決定できるのが原則(裁判所法10条本文)。ただし、以下の場合には、大法廷で裁判を行わなければならない(裁判所法10条但書)。
- 当事者の主張に基づいて、法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かを判断するとき(意見が前に大法手でした合憲判決と同じであるときを除く)(憲法判断)
- 法律・命令・規則・処分が憲法に適合しないと認める時(違憲判断)
- 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき(判例変更)
- ②下級裁判所
-
下級裁判所には、高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所・家庭裁判所の4種類ある(裁判所法2条1項)。
それぞれの権限と担当裁判官の数は以下の通り。
裁判官
- ①種類
-
最高裁判所の長たる裁判官を最高裁判所長官といい、その他の裁判官を最高裁判所判事という(裁判所法5条1項)。また、下級裁判所の裁判官のうち、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官といい、その他の裁判官は判事・判事補・簡易裁判所判事という(裁判所法5条2項)。
- ②任命
-
最高裁判所長官は、内閣に指名に基づいて、天皇が任命し(裁判所法39条1項)、最高裁判所判事は内閣が任命する(裁判所法40条1項)。
- ③定年
-
最高裁判所・簡易裁判所の裁判官の定年は70歳
高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所の裁判官の定年は65歳
これに達した時に退官する(裁判所法50条)。
三審制
三審制(さんしんせい)とは?
日本の裁判制度では、1つの事件について原則として最大3回まで裁判を受けることができる「三審制」が採用されています。
まず、第一審で裁判が行われ、判決が下されます。この判決に不服がある場合は、次の段階の裁判所に対して控訴(こうそ)をすることができます。
さらに、控訴審でも判決に納得できない場合は、もう一段階上の裁判所に対して上告(じょうこく)することが可能です。789
【民事裁判】
graph BT 簡易裁判所--控訴-->地方裁判所 地方裁判所--上告-->高等裁判所 高等裁判所
訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求
graph BT 地方裁判所--控訴-->高等裁判所 高等裁判所--上告-->最高裁判所 style 最高裁判所 fill:#f9f
原則
【刑事裁判】
graph BT 簡易裁判所--控訴-->高等裁判所 高等裁判所--上告-->最高裁判所 style 最高裁判所 fill:#f9f
一定の軽微な犯罪
graph BT 地方裁判所--控訴-->高等裁判所 高等裁判所--上告-->最高裁判所 style 最高裁判所 fill:#f9f
原則
審理の内容(民事・刑事それぞれの特徴)
裁判は、ただ回数を重ねればよいというものではありません。そのため、日本の裁判制度では審級(審理の段階)ごとに審理できる内容が原則として決まっています。
✅民事裁判の場合
民事裁判では、事実の認定(=何が起きたのかという事実関係の確認)については、第二審(控訴審)までで審理が完了します。
そして、第三審(上告審)では、原則として法律の解釈や適用の妥当性といった法律問題のみが審理の対象となります。
つまり、上告審では「法律の使い方に間違いがなかったか」が問われるということです。
✅刑事裁判の場合
刑事事件では、事実問題の審理は第一審のみで行うのが原則です。
控訴審や上告審では、基本的に法律の適用や解釈が適切かどうかといった法律問題のみを扱います。
ただし、例外もあります。たとえば、判決に大きな影響を与える重大な事実の誤認がある場合には、上告審であっても事実問題を再び審理することが認められています(刑事訴訟法411条3号)。
上級審の審理の方式
上級審の審理の方式には3種類あります。
- 続審
第一審の裁判の審理を基礎としながら、上級審においても新たな訴訟資料の提出を認めて審理を続行するもの - 事後審
第一審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの - 覆審
第一審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの
民事訴訟における控訴審の裁判は続審、刑事訴訟における控訴審の裁判は事後審とされている。
司法制度改革
裁判員制度
裁判員制度とは、一定の重大な刑事裁判の第一審において、一般の市民が裁判官と合議体を構成し、審理・評決を行う制度です。
この制度は、司法への国民の理解と信頼を深めることを目的とした司法制度改革の一つとして、平成21年(2009年)に導入されました。
✅裁判員制度の特徴
裁判員制度の対象となる裁判では、裁判員6人、裁判官3人(例外的に裁判員4人、裁判官1人の場合もある)で構成される合議体が、事実の認定・法令の適用・刑の量刑を行います。
この合議体の判断は、裁判官・裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見によることとされています。
つまり、プロと市民が対等に意見を出し合って裁判を進めていく点が、この制度の大きな特徴です。
■裁判員制度の流れ
sequenceDiagram
participant 裁判所
actor 国民
裁判所->>裁判所: 裁判員候補者名簿を調製
裁判所->>裁判所: 裁判員候補者をくじで選定
裁判所->>国民: 呼出状の送達
国民->>裁判所: 出頭
裁判所->>裁判所: 裁判員の選任
裁判所->>裁判所: 裁判を行う日本司法支援センター(法テラス)とは?
「法テラス(日本司法支援センター)」は、司法制度改革の一環として設立された公的な機関です。
正式には「総合法律支援法」に基づき、平成18年4月に設立されました。
このセンターの目的は、すべての人が必要なときに法律サービスを利用できるよう、司法へのアクセスを広げることにあります。
法テラスでは、以下のような支援業務を行っています。
情報提供業務
利用者からの問い合わせに応じて、裁判等の法的紛争を解決するための法制度に関する情報、弁護士や隣接法律専門職の業務および弁護士会や隣接法律専門職者の団体の活動に関する情報を無料で提供する業務
民事法律扶助業務
利用者からの個別の依頼に応じて、法的紛争の解決方法について指導・助言を無料で行い、利用者の資力が十分でない場合には、弁護士や隣接法律専門職の中から適当な者を紹介して、その報酬・費用を立て替える業務
国選弁護等関連業務
刑事事件の被告人・被疑者に国選弁護人を付すべき場合において、裁判所からの求めに応じて国選弁護人の候補を指名して通知を行い、選任された国選弁護人にその事務を取り扱わせて、その報酬・費用を支払う業務
司法過疎対策業務
いわゆる司法過疎地域において、利用者からの個別の依頼に応じ、相当の対価を得て、弁護士や隣接法律専門職に法律事務を取り扱わせる業務
犯罪被害者支援業務
犯罪の被害者やその親族等に対して、刑事手続への適切な関与やその損害・苦痛の回復・軽減を図るための制度その他被害者やその親族等の援助を行う団体等の活動に関する情報を無料で提供する業務
刑事裁判の改革ポイントとは?
刑事裁判においても、迅速かつ公正な裁判を実現するため、さまざまな改革が行われてきました。ここでは、特に重要な2つの制度について紹介します。
- ①強制起訴
-
検察官が公訴を提起しない場合でも、検察審査会が2度にわたって起訴を相当とする議決をしたときには、裁判所が指定した弁護士が公訴を提起ことができるようになりました。
これは、平成16年の検察審査会法改正によって導入された「強制起訴制度」です。
これにより、検察の判断に対するチェック機能が強化されました。 - ②公判前整理手続
-
平成17年の刑事訴訟法改正により導入されたのが、「公判前整理手続」です。
これは、刑事裁判が始まる前に、事件の争点(何が争われているか)や証拠の内容をあらかじめ整理するための制度です。
これにより、実際の裁判(公判)がよりスムーズに、そして効率よく進行できるようになりました。
消費者を守るための制度「消費者団体訴訟制度」とは?
消費者が安心して取引できる社会を実現するため、不当な勧誘や被害に対して団体が立ち向かう仕組みとして、「消費者団体訴訟制度」が整備されています。
ここでは、特に重要な2つの制度「差止め請求」と「損害賠償請求」について解説します。
- ①差止め請求
-
2006年(平成18年)の消費者契約法の改正により、「適格消費者団体」が不当な勧誘や虚偽・誤解を招く広告などの行為に対して、その行為をやめるように求める『差止め請求』ができるようになりました。
この制度のポイントは以下の通りです。
・対象となるのは、事業者による不当な行為(勧誘・表示など)
・請求できるのは、内閣総理大臣に認定された適格消費者団体あわせて読みたい - ②損害賠償請求
-
平成25年に成立した「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」により、一定の集団(クラス)に属する者(例えば、特定の商品によって被害を受けた者)が同一の集団に属する者の全員を代表して原告となり、当該集団に属する者の全員が受けた損害について、一括して損害賠償を請求することができるようになりました。
このように、被害を受けた消費者が個別に裁判を起こす負担を軽減し、救済を受けやすくする仕組みとなっています。
まとめ|裁判制度の基本を押さえて、得点源に!
この記事では、「裁判とは何か」という基本から始まり、裁判の原則や裁判所・裁判官の仕組み、三審制の意義、さらに民事・刑事それぞれの裁判の特徴、そして近年の司法制度改革の流れまでを網羅的に解説しました。
とくに行政書士試験では、単なる知識だけでなく、制度の趣旨や相違点、背景となる考え方まで問われる傾向があります。
- 当事者主義・自由心証主義・挙証責任の関係性
- 裁判員制度や法テラスの役割
- 消費者団体訴訟制度の意義と活用場面
といったポイントは、しっかり整理しておきましょう。
複雑に見える裁判制度も、「なぜこの制度があるのか?」「誰を守るための仕組みか?」といった視点から学ぶことで、理解がぐっと深まります。
- 具体例:売買代金の支払いを請求する者は、売買契約の成立という要件事実を証明する責任を負う ↩︎
- 参考:最高裁判所の裁判では少数意見を付すことができる(裁判所法11条)が、下級裁判所の裁判では少数意見を付すことができない ↩︎
- 大法廷:全員の裁判官の合議体 ↩︎
- 小法廷:最高裁判所の定める員数(3人以上)の裁判官の合議体 ↩︎
- 人事訴訟:離婚訴訟などの家族関係に関する訴訟のこと ↩︎
- 保護事件:飛行に及んだ少年の更生のための処分を決定する事件のこと ↩︎
- 参考:特許庁がなした審決に対する訴えのように、高等裁判所が第一審裁判所になることもある(特許法178条1項) ↩︎
- 参考:刑事訴訟だけでなく民事訴訟においても、再審(確定判決に重大な瑕疵がある場合に、確定判決の取消しと事件の再審理を求めること)の制度が認められている(刑事訴訟法435条、民事訴訟法338条) ↩︎
- 参考:上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について、下級審の裁判所を拘束する ↩︎