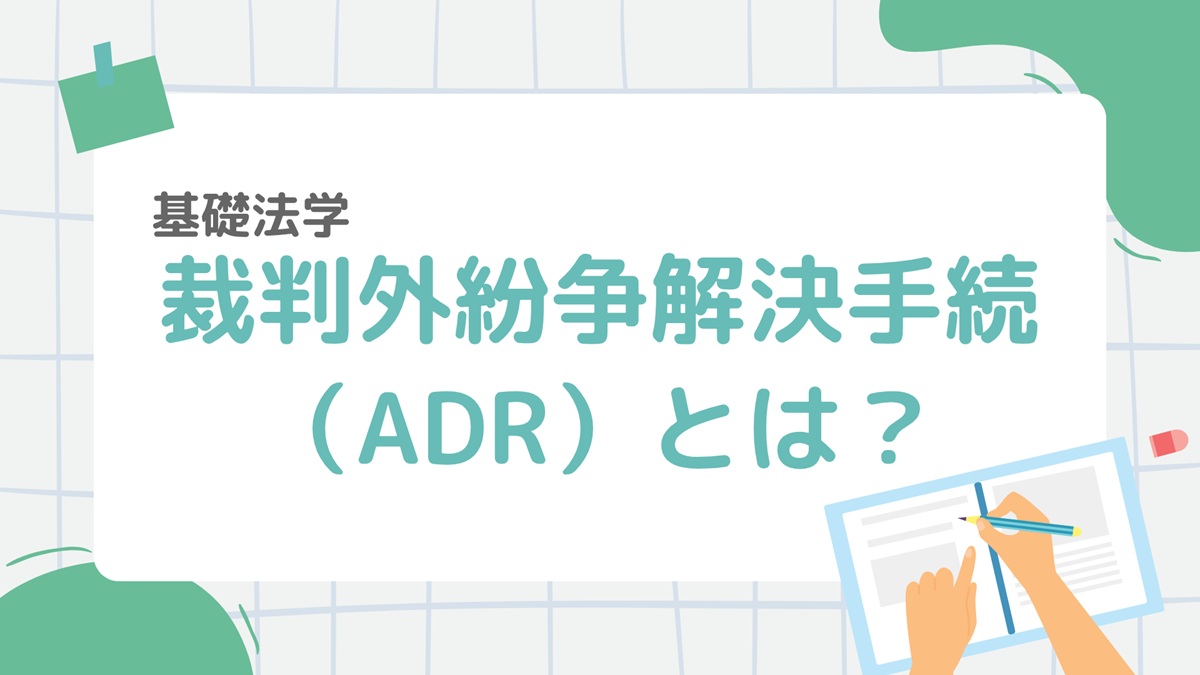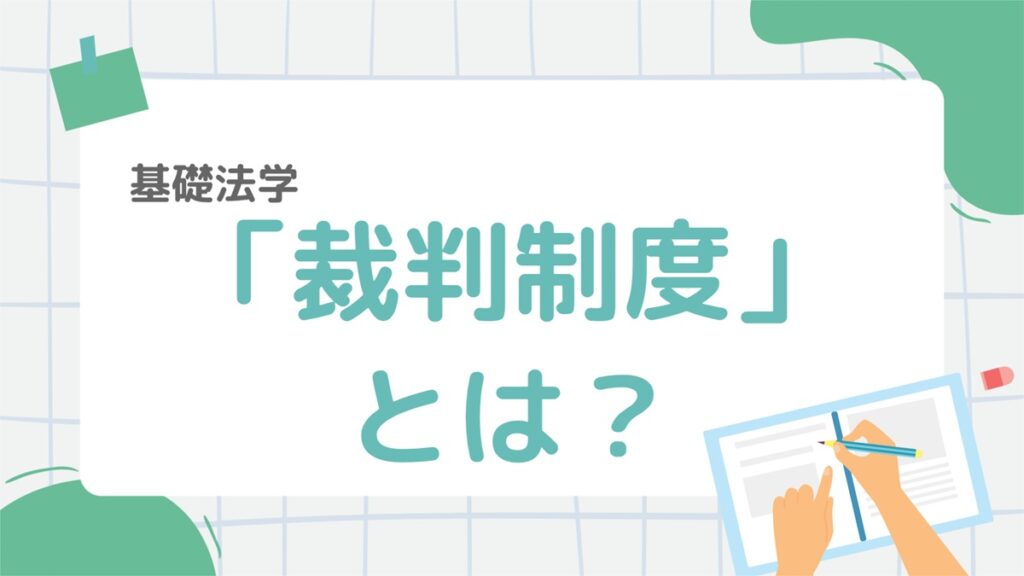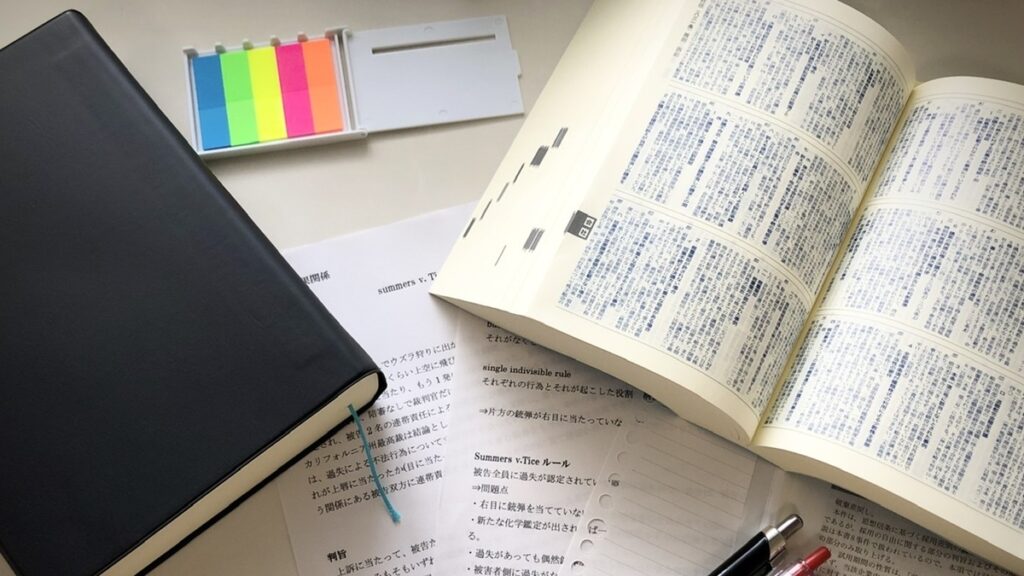- 裁判以外でトラブルを解決する方法を知りたい人
- 「和解」「あっせん」「調停」「仲裁」などの違いがよく分からない人
- 行政書士試験の「民事手続」分野を効率的に学びたい受験生
裁判外紛争解決手続(ADR)とは?
「裁判外紛争解決手続(ADR:Alternative Dispute Resolution)」とは、裁判を行わずに民事トラブルを解決する手続のことです。
代表的なものに、和解・あっせん・調停・仲裁があります。
裁判との違いは?
| 裁判 | 裁判外紛争解決手続 | |
| 長所 | 厳格な手続により、慎重かつ公正な判断を受けることができる | 安い費用で簡易迅速な紛争解決をすることができる |
| 相手方の 合意 | 不要 | 必要 |
| 手続の公開 | 原則として公開 | 通常は非公開 |
| 解決案の 拒否 | 不可 | 朝廷の場合は可能、仲裁の場合は不可 |
和解とは?
和解とは、当事者同士がお互いにの譲歩(互譲)により、争いを解決する手続です。和解によって、新たな法律関係が契約として成立します。
和解の種類
- ①裁判外の和解(和解契約)
-
裁判外の和解とは、裁判所を介さず、当事者間で和解契約を締結することをいいます。
この和解契約が成立すると、たとえ反対の確証がでたとしても、それによって何ら影響を受けない(民法696条)。 - ②裁判上の和解(訴訟上の和解)
-
裁判上の和解とは、訴訟中に行われ、期日において訴訟当事者間で和解することをいいます。
裁判上の和解の場合も、その内容を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する(民事訴訟法267条) - ③特定和解(新制度)
-
特定和解とは、認証紛争解決手続1において紛争の当事者間に成立した和解で、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたもの。
この特定和解は、裁判を起こさなくても強制執行が可能な合意であり、令和5年の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の改正により新設された。
あっせんとは?
あっせんは、中立の第三者(あっせん員)が当事者の間を取り持ち、互いの主張を整理して解決を図る手続です。
労働争議や公害問題などで多く用いられています。
調停とは?
調停は、裁判所の調停委員会(裁判官1名+民間委員2名以上)が当事者を仲介し、話し合いによる解決を促す制度です。
法律の形式にとらわれず、現実的・妥当な解決を目指します。
調停前置主義とは?
家事事件手続法に基づき調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません(家事事件手続法257条1項)。これを調停前置主義といいます。
調停前置主義が採用されたのは、合意による円満解決を促進するための制度です。
仲裁とは?
仲裁は、当事者が合意に基づいて第三者(仲裁人)に判断を委ね、その判断に拘束される形で解決する方法です。
特に商取引の分野で多く利用されており、裁判と同じく強制力がある点が特徴です。
📝まとめ
ADRは、「早く・安く・柔軟に」紛争を解決できる手段として注目されています。
和解やあっせん、調停、仲裁といった手続の特徴をしっかり理解しておくことは、行政書士試験の得点アップにも直結します。
- 認証紛争解決手続:法務大臣の認証を受けた業務として行う民間紛争解決手続 ↩︎