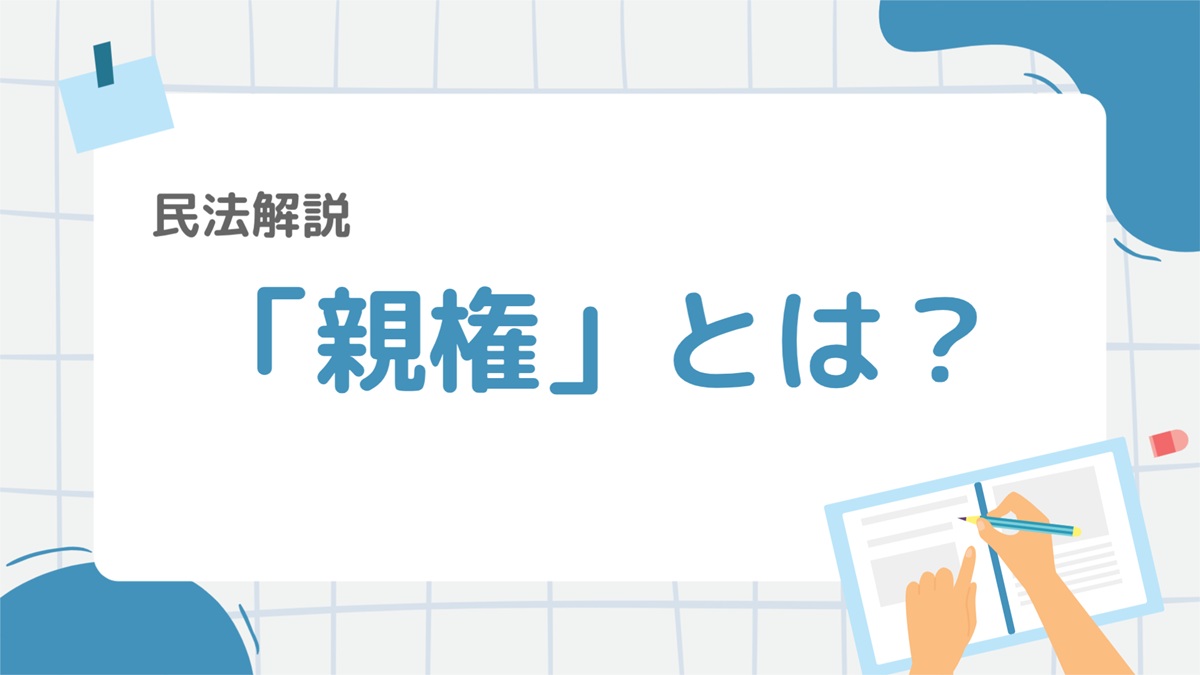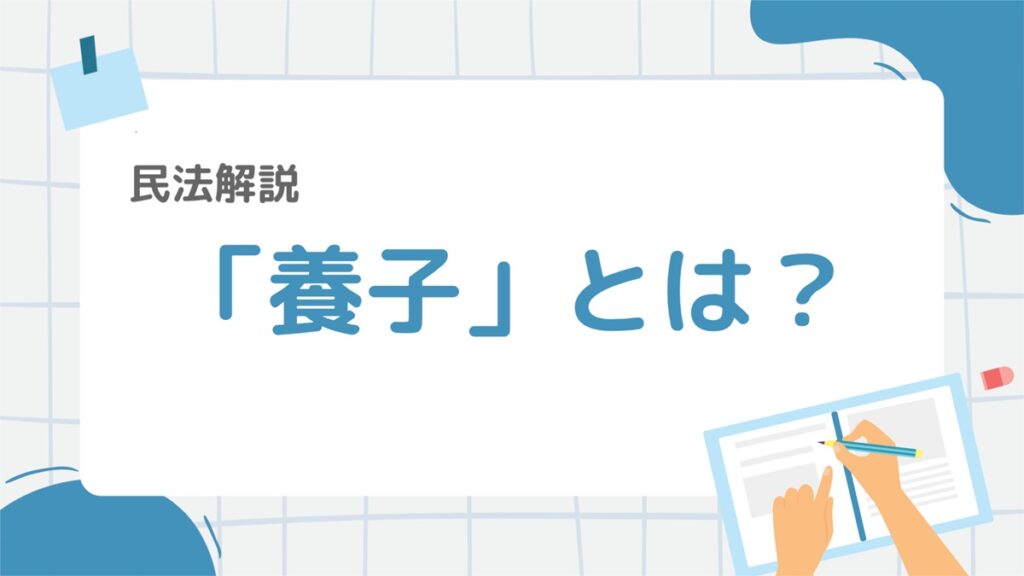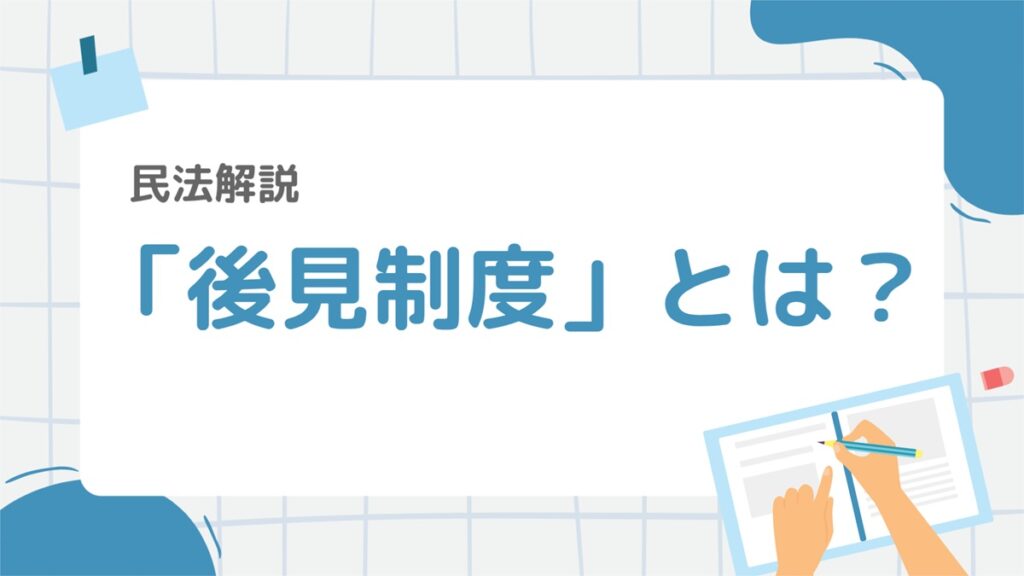- 行政書士試験で「親権」のポイントをしっかり押さえたい方
- 民法の中でも親子関係の法律を整理して覚えたい方
- 親権に関する判例や利益相反の具体例を知っておきたい方
親権とは?
親権とは、未成年の子どもを育て(監護)、教育し、その財産を管理する親の権利・義務のことです(818条1項)。未成年の子は、「父母の親権」に服し、養子の場合は「養親の親権」に服します(818条2項)。
親権は誰が行使する?
親が婚姻中であれば、父母が共同で親権を行使します(818条3項本文)。
ただし、どちらか一方が親権を行使できない事情がある場合には、もう一方が単独で行使します(818条3項但書)。
親権の内容は?
親権には大きく分けて「身上監護」と「財産管理」の2つの側面があります。
身上監護
親権を行う者は、子の利益のために、子を監護1し教育2する権利と義務を負います(820条)。
財産管理
親権を行う者は、子の財産を管理し、さらに、その財産に関する法律行為を子に代わって行うことができます(これを「法定代理権」といいます)(824条本文)。
親と子に利益の対立があるときは?
利益相反行為とは?
親権者が子の代理人として行う行為が、親自身の利益と子の利益が衝突する内容である場合、それを「利益相反行為」といいます。
特別代理人の選任が必要(民法826条1項)
利益相反がある場合は、家庭裁判所に申立てを行い、「特別代理人」を選任してもらう必要があります(826条1項)。
これは、親権者が公正な代理人となれないケースを防ぐための制度です。3
利益相反かどうかの判断基準
- 利益相反にあたるかは、親権者が子を代理して行った「行為の内容」を外形的・客観的に判断します。
- 親権者の主観的な意図や動機は関係ありません。4
【判例で理解】利益相反行為の具体例
- 利益相反行為に当たる例
- 利益相反行為に当たらない例
-
- 親権者が未成年の子を代理して子の所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為(最判昭35.7.15、最判平4.12.10)
利益相反行為の効力は?
親権者が子を代理して行った利益相反行為は、無権代理行為となります(最判昭46.4.20)。
ただし、子が成年に達した後に追認することは可能です(大判昭11.8.7)。
親権を失うことはあるの?
児童虐待の防止し、児童の権利と利益を守るために、民法では「親権喪失の審判」(834条)・「親権停止の審判」(834条の2)の制度を設けています。
親権喪失の審判(民法834条)
以下の要件を満たすと、家庭裁判所は親権の喪失を命じることができます。
- 積極的要件
- 父または母による親権の行使が著しく困難または不適当であることにより子の利益を著しく害すること
- 子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人または検察官の請求があること
- 消極的要件
- 2年以内にその原因が消滅する見込みがないこと
親権停止の審判(民法834条の2)
喪失ほどではないが、一定期間親権を停止すべき場合に利用されます。
- 積極的要件
- 父または母による親権の行使が困難または不適当であることにより子の利益を著しく害すること
- 子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人または検察官の請求があること
まとめ:親権は子どもの利益を守るための制度
親権は、子どもの成長と財産を守るための重要な制度です。
しかし、親の行動が子の利益に反する場合は、法的に制限・停止されることもあります。
行政書士試験では、親権の定義・内容・利益相反・喪失と停止の制度・判例をバランスよく押さえましょう!