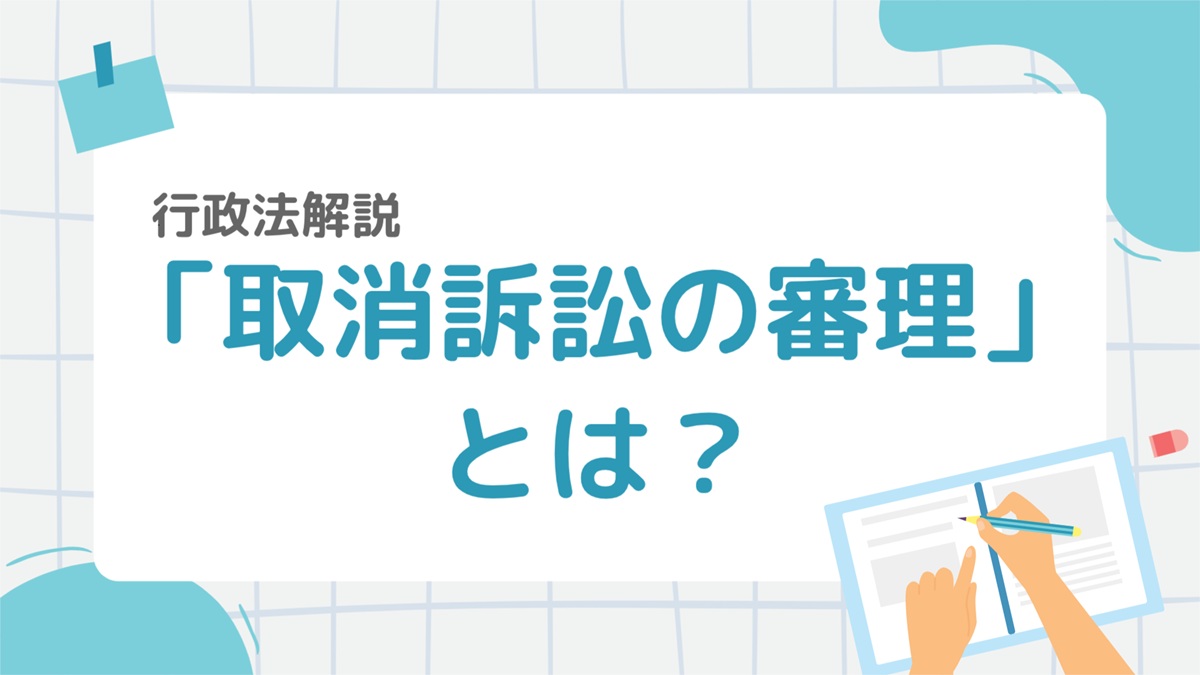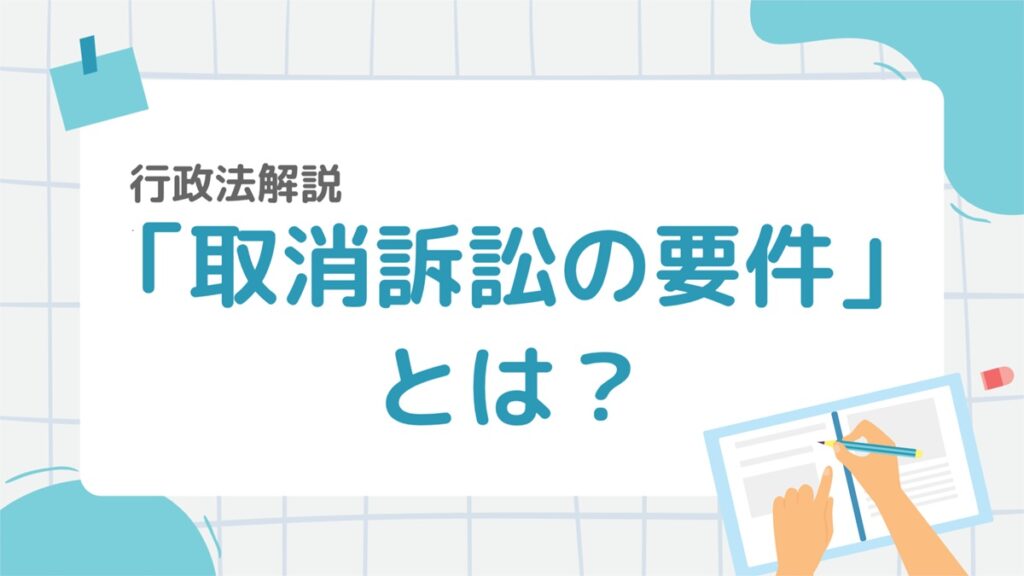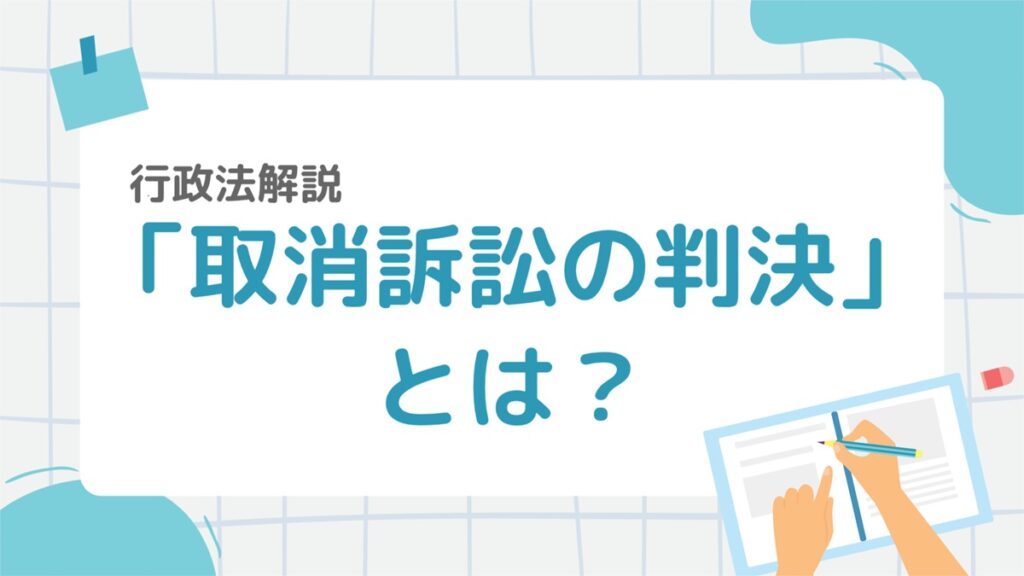🔍取消訴訟の審理とは?全体像をつかもう
取消訴訟は、違法な行政処分を取り消してもらうための訴訟です。
しかし、訴えを起こせば何でも審理してもらえるわけではありません。
この記事では、「何が審理の対象になるのか?」「審理はどのように進むのか?」を中心に、関連請求や訴訟参加などの重要ポイントまで、行政書士試験に出る内容をわかりやすく解説します。
📌1. 審理の対象
取消訴訟では、「処分の違法性のみ」が審理の対象です。
「公益に反するかどうか」といった不当性までは審理されません(これは行政不服申立てでの話です)。
さらに、誰かの違法を指摘すればいいというわけでもなく、自己の法律上の利益に関係のある違法性でなければなりません(10条1項)。
この要件を満たしていない場合、裁判所は訴えを棄却します。
🏛2. 審理の進め方(手続)
行政事件訴訟法では細かい審理手続がすべて定められているわけではないため、多くは民事訴訟のルールに準じて進められます(7条)。
- ①訴訟の提起
-
取消訴訟の提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない(7条、民事訴訟法134条1項)。
- ②訴訟代理人の資格
-
取消訴訟においては、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない(7条、民事訴訟法54条1項本文)。
- ③訴訟の審理
-
原則として、取消訴訟の当事者は、裁判では口頭弁論1をしなければなりません(7条、民事訴訟法87条1項本文)。
- ④事実・証拠の収集・提出
-
取消訴訟においてどんな事実を主張するか、どんな証拠を収集するかは、当事者に任せるべきとされています。これを弁論主義といいます。
ただし、行政事件訴訟の結果は公益に関わる場合が多く、客観的な真実を究明して審理や裁判の適正を図る必要があることから、裁判所が自ら証拠調べを行う(職権証拠調べ)が認められています(24条本文)。
ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見を聞かなえればなりません(24条但書)。
🔗3. 関連請求の併合
取消訴訟と関連する請求を一緒に審理することで、審理の重複や矛盾を防ぐことができます。これが「関連請求の併合」です(13条)。
- 当該処分・裁決に関連する原状回復または損賠賠償の請求
- 当該処分とともに1個の手続を構成する他の処分の取消しの請求
- 当該処分に係る裁決の取消しの請求
- 当該裁決に係る処分の取消の請求
- 当該処分・裁決の取消しを求める他の請求
- その他当該処分・裁決の取消しの請求と関連する請求
具体的には、以下のような併合方法があります。
- ①請求の客観的併合
-
請求の客観的併合とは、当初から1つの訴えで数個の請求をすること。
16条は、取消訴訟に関連請求に係る訴訟を併合して提起することを認めています。2 - ②請求の追加的併合
-
請求の追加的併合とは、1つの訴えが係属している間に他の請求を追加すること。18条は第三者による請求の追加的併合を、19条は原告による請求の追加的併合を認めています。
- ③共同訴訟
-
共同訴訟とは、1つの訴えで複数の原告が数個の請求をし、または、複数の被告に対して数個の請求をする場合のこと。
17条は、取消訴訟と関連請求である場合に、共同訴訟を提起することを認めています。
🔁4. 訴えの変更
裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分・裁決に係る事務の帰属する国または公共団体に損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもって、訴えの変更を許すことができます(21条1項)。
訴訟資料をの再提出などの手間が省け、原告の負担を軽減できます。そのため、訴えの変更が認められている。
🤝5. 訴訟参加
訴訟参加とは、係属中の訴訟に第三者や行政庁が参加することをいいます。
行政事件訴訟法は、第三者の訴訟参加と行政庁の訴訟参加について規定を置いている。
- ①第三者の訴訟参加
-
訴訟の結果により権利を害される第三者に権利を防御する機会(手続保証)を与えるため、裁判所は、当事者・第三者の申立てによりまたは職権で、このような第三者を訴訟に参加させることができる(22条1項)。
- ②行政庁の訴訟参加
-
訴訟資料を豊富にし客観的に公正な事件の解決を図ることができるようにするため、裁判所は、当事者・行政庁の申立てによりまたは職権で、処分・裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることができる(23条1項)。
🧾6. 釈明処分の特則
民事訴訟では、訴訟の当事者が所持している物についてのみ釈明処分3をすることが認められています(民事訴訟法151条)。
しかし、行政事件訴訟においては、行政事件訴訟の審理の充実・促進させるという観点から、裁判所が必要と認めるときは、訴訟の当事者が所持しているものでなくても、被告である国や公共団体に所属する行政庁に対して、その保有する処分の理由を明らかにする資料を提出させることができます(23条の2)。これを釈明処分の特則といいます。
✅まとめ:取消訴訟の審理は「的を絞った」違法性のチェック!
取消訴訟の審理では、対象となるのは「違法性」のみ。
しかも、「自分の法律上の利益」に関係する違法でなければなりません。
審理手続や関連請求の併合など、民事訴訟に似た部分も多いですが、行政訴訟ならではの特則もあります。
これらをしっかり押さえておくことで、行政書士試験でも得点源にできますよ!