🧭この記事はこんな人におすすめ
- 取消訴訟の「判決の種類」や違いがよくわからない
- 事情判決や判決の効力について、試験に出るポイントを押さえたい
- 行政書士試験の行政法を短時間で効率的に復習したい
目次
取消訴訟はどう終わる?
取消訴訟は、原告が途中で訴えを取り下げない限り、裁判所の判決によって終了します。
取消訴訟の3つの判決パターン
取消訴訟で裁判所が出す判決には、次の3つがあります。
| 判決の種類 | 内容 |
|---|---|
| 却下判決 | 訴訟要件を満たしていないとして、審理を行わず拒絶(門前払い)する判決 |
| 棄却判決 | 訴訟要件は満たしているが、請求に理由がない(処分・裁決が違法)として退ける判決 |
| 認容判決 | 原告の請求に理由がある(処分・裁決が違法)として、処分や裁決を取り消す判決 |
なお、棄却判決と認容判決の2つを本案判決(審理の結果を表明する判決)と呼びます。
例外!違法でも取り消さない「事情判決」って?
処分や裁決が違法であっても、取り消すことで著しく公益を害する場合、裁判所はあえて棄却判決を出すことができます。これを事情判決(31条1項前段)といいます。
高速道路の建設のために土地の収用裁決が行われたため、この収用裁決の取消訴訟が提起された場合において、審理の中でこの収用裁決が違法であることが判明したが、その時点で高速道路が完成してしまっていたときなど ↩︎
例えば、高速道路の建設のために土地の収用裁決に対して取消訴訟が提起され、審理の中でこの収用裁決が違法であることが判明したものの、その時点で高速道路が完成してしまっていたとき違法な許認可を取り消すと多くの市民生活に大混乱が生じるというようなケースが該当します。この事情判決は、私人の利益の保護よりも、公共の福祉を実現する制度といえます。
この場合、裁判所は判決の主文で「処分・裁決が違法である」と宣言しなければなりません(31条1項後段)。1
認容判決が確定するとどうなる?3つの法的効力
取消訴訟で認容判決(処分を取り消す判決)が確定すると、次の3つの効力が発生します。
| 効力 | 内容 |
|---|---|
| ①既判力 | 判決が確定した事項について、当事者や裁判所は後に異なる判断ができなくなる効力 |
| ②形成力 | 違法な処分・裁決を、処分時点にさかのぼって消滅させる効力。 しかも当事者だけでなく第三者にも影響(=第三者効)(33条1項) |
| ③拘束力 | 行政庁は、判決の趣旨に従った対応をする義務があるという効力(33条1項)2 |
拘束力には以下の2つの側面があります。
- 消極的効力(反復禁止効)
行政庁は、取り消された行政処分と同一の事情の下で同一の理由に基づいて同一内容の処分をすることができなくなります。 - 積極的効力
申請拒否処分または審査請求の却下・棄却裁決の取消判決が確定した場合、行政庁は、判決の趣旨に沿って改めて処分・裁決をしなければなりません(33条2項)。
処分の違法かどうか、いつの時点で判断する?
違法判断の基準時となるのは、処分がなされた時点(処分時)です(最判昭27.1.25)。
なぜなら取消訴訟は、過去に行われた処分の違法性を後から争う手続きだから。裁判所は事後的な審査にとどまる必要があるのです。3
✅まとめ|判決の種類と効力を整理しよう
- 却下・棄却・認容の3種類を区別できるように!
- 認容判決が出たら「既判力・形成力・拘束力」が発生
- 事情判決は「違法だけど取り消さない」レアな例外
- 違法判断の基準時は「処分時」!
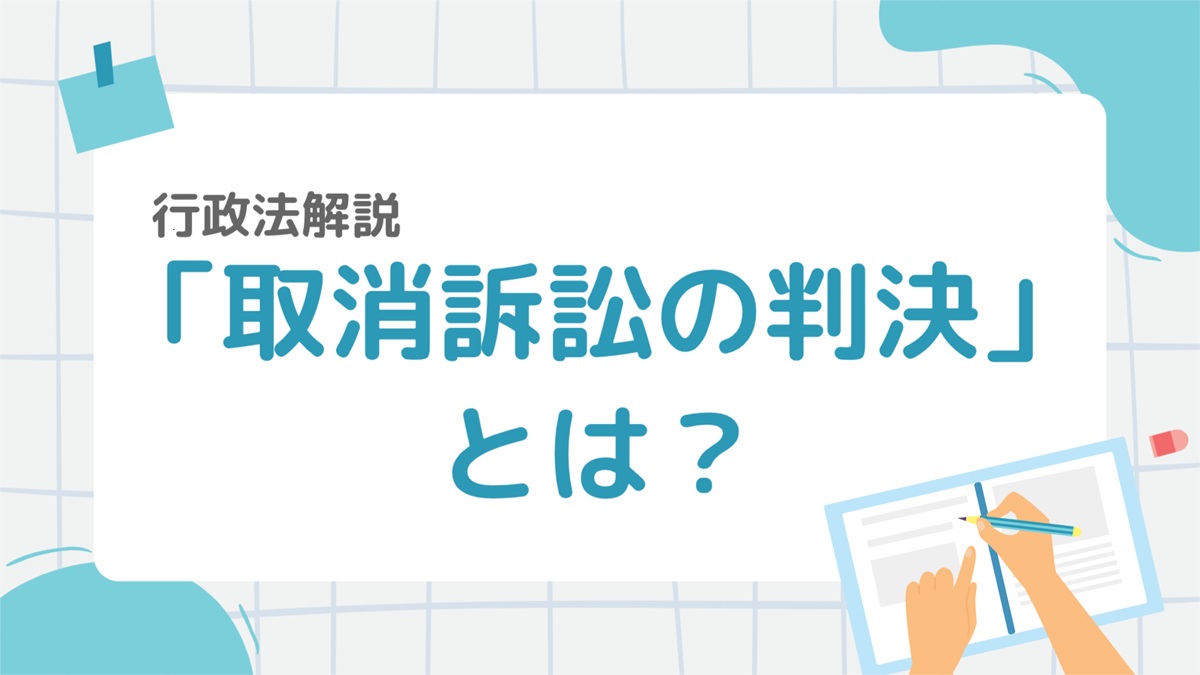
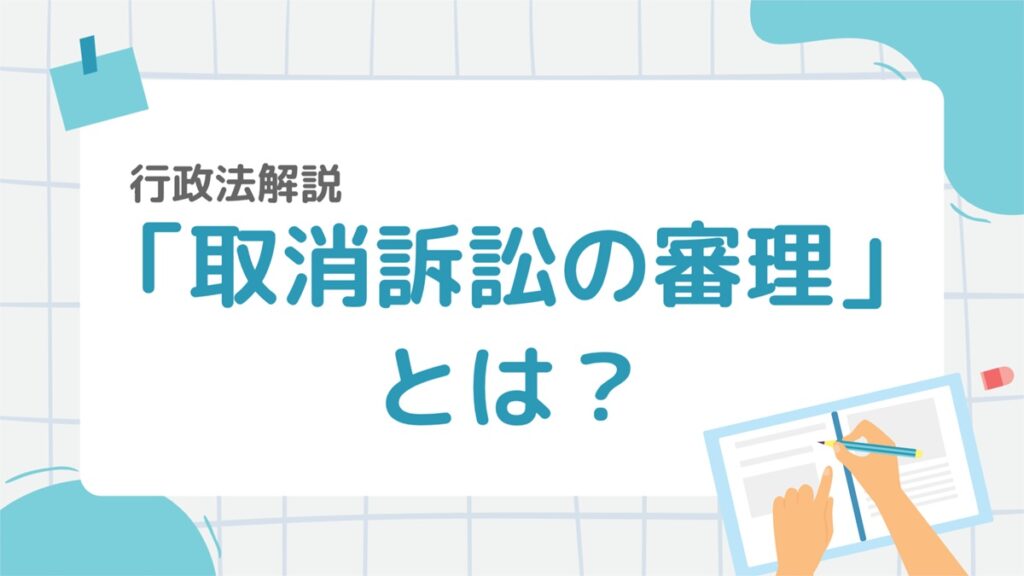
アイキャッチ-1024x576.jpg)







