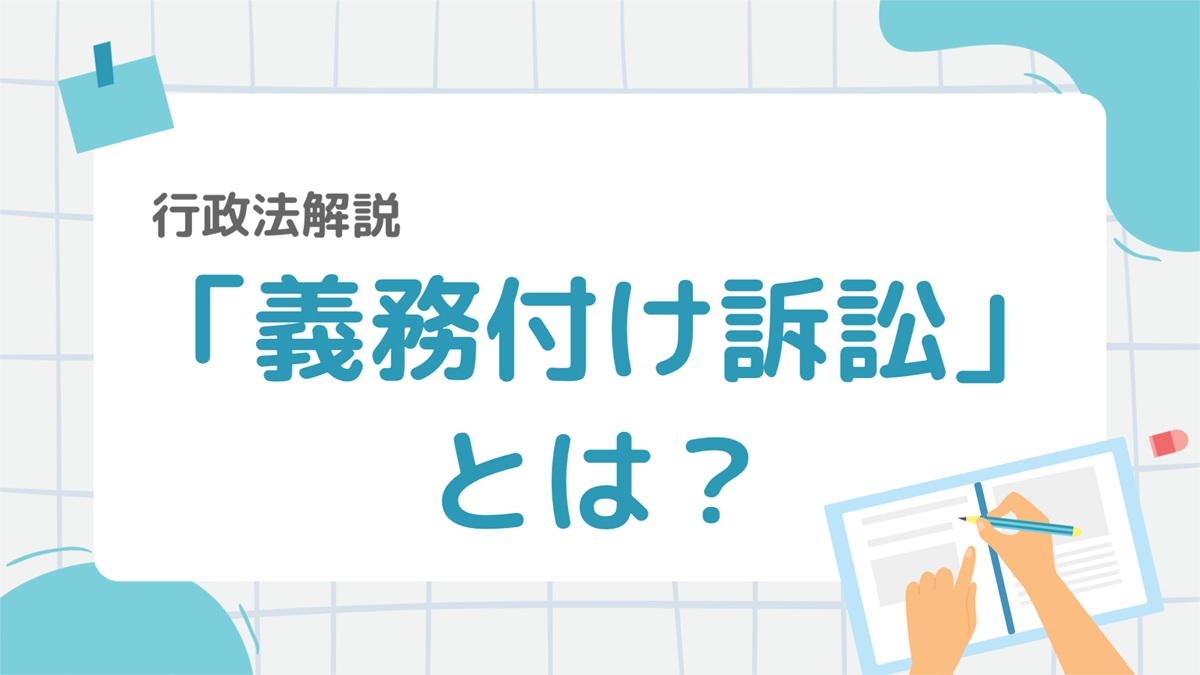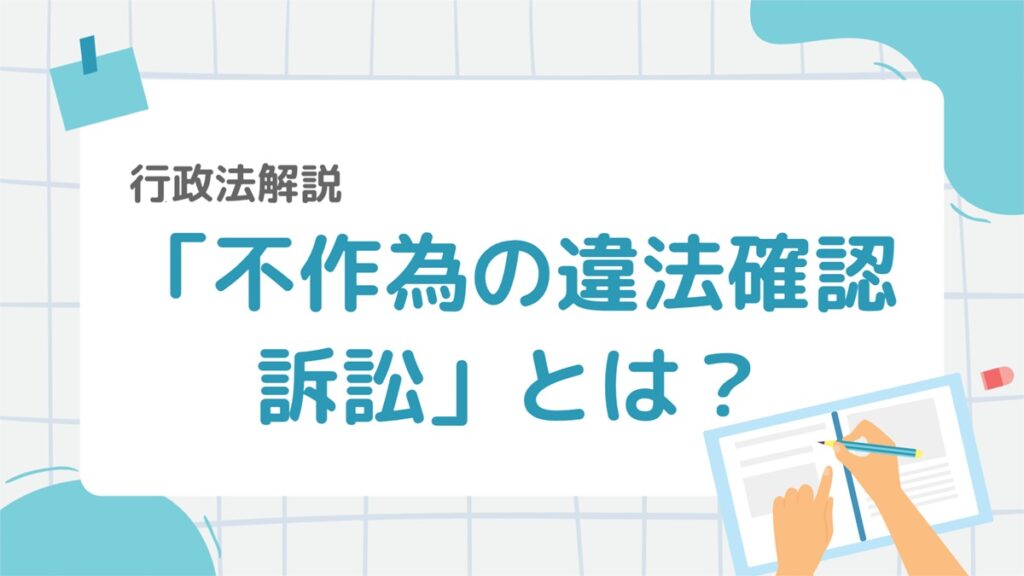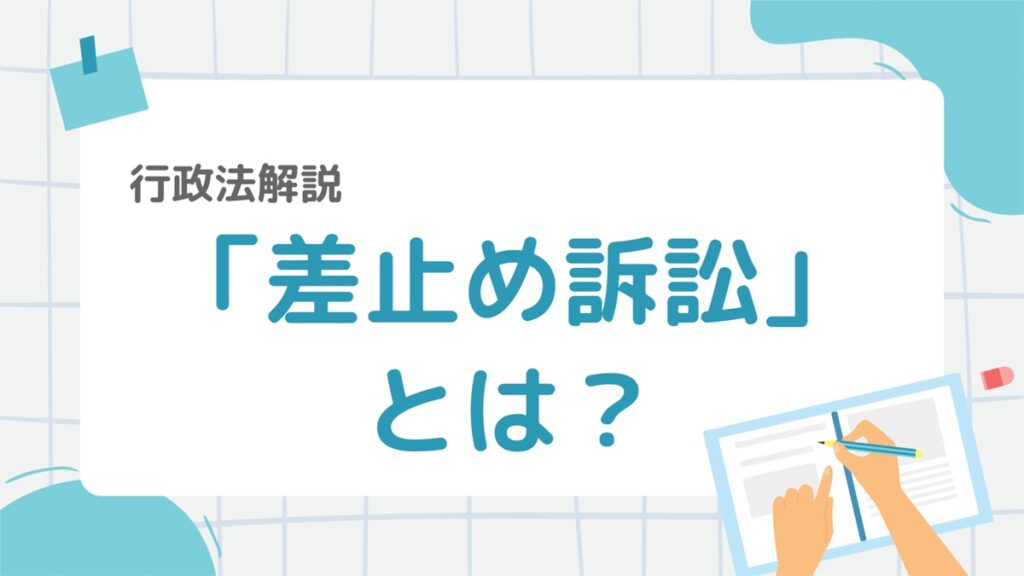この記事はこんな人におすすめ!
- 行政法の「義務付け訴訟」について、基礎から丁寧に理解したい方
- 申請型と非申請型の違いがよくわからない方
- 行政書士試験でよく出題される判決要件について押さえておきたい方
目次
義務付け訴訟とは?基本の考え方
行政庁に申請をしても何の対応もない…。
そんなとき、「不作為の違法確認訴訟」では「何かしら処分をしてくださいね」と間接的に促すしかありません。しかし、それだけでは十分な救済とは言えないことがあります。
そこで、行政庁に対して「この処分・裁決をしなさい」と直接命じることを求める訴訟が「義務付け訴訟」です。
義務付け訴訟は、行政事件訴訟法3条6項で次の2種類に分けられています。
義務付け訴訟の2つのタイプ
- ① 非申請型義務付け訴訟(3条6項1号)
-
非申請型は、法令に基づいた申請が前提ではないタイプです。
行政庁が法律に従って処分をしなければならない状況なのに、それを怠っている場合、「処分をすべきだ」という命令(判決)を求める訴訟を提起できます。
- ② 申請型義務付け訴訟(3条6項2号)1
-
こちらは、法令に基づく申請や審査請求をしたのに、行政庁が何も処分しない場合に提起します。
たとえば、建築許可の申請をしても放置されているようなケースで、「処分をすべき」と命じる判決を求めます。
■行政事件訴訟法の類型
--- config: theme: neutral --- flowchart LR subgraph 取消訴訟以外の抗告訴訟 無効等確認訴訟 不作為の違法確認訴訟 義務付け訴訟 義務付け訴訟 差止め訴訟 仮の義務付け/仮の差止め end subgraph 取消訴訟 処分取消訴訟 裁決取消訴訟 end 行政事件訴訟 --> 主観訴訟["主観訴訟<br>国民の個人的な<br>権利の保護"] 主観訴訟 --> 抗告訴訟 抗告訴訟 --> 法定抗告訴訟 法定抗告訴訟 --> 処分取消訴訟 法定抗告訴訟 --> 裁決取消訴訟 法定抗告訴訟 --> 無効等確認訴訟 法定抗告訴訟 --> 不作為の違法確認訴訟 法定抗告訴訟 --> 義務付け訴訟 法定抗告訴訟 --> 差止め訴訟 抗告訴訟 --> 無名抗告訴訟 主観訴訟 --> 当事者訴訟 当事者訴訟 --> 形式的当事者訴訟 当事者訴訟 --> 実質的当事者訴訟 行政事件訴訟 --> 客観訴訟["客観訴訟<br>客観的な法秩序<br>の適正"] 客観訴訟 --> 民衆訴訟 客観訴訟 --> 機関訴訟 click 処分取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh16-1/" style 処分取消訴訟 color:#1176d4 click 裁決取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh16-1/" style 裁決取消訴訟 color:#1176d4 click 裁決取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh17-1/" style 無効等確認訴訟 color:#1176d4 click 裁決取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh17-2/" style 不作為の違法確認訴訟 color:#1176d4 click 裁決取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh17-3/" style 義務付け訴訟 color:#1176d4,fill:#ffb6c1 click 裁決取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh17-4/" style 差止め訴訟 color:#1176d4 click 仮の義務付け/仮の差止め "https://gs.kabudata-dll.com/gh17-5/" style 仮の義務付け/仮の差止め color:#1176d4 click 当事者訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh18-1/" style 当事者訴訟 color:#1176d4 click 形式的当事者訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh18-2/" style 形式的当事者訴訟 color:#1176d4 click 実質的当事者訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh18-3/" style 実質的当事者訴訟 color:#1176d4 click 民衆訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh19-1/" style 民衆訴訟 color:#1176d4 click 機関訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh19-1/" style 機関訴訟 color:#1176d4
義務付け訴訟の訴訟要件
義務付け訴訟の訴訟要件は、非申請型と申請型で以下のように異なります。
| 非申請型 | 申請型 | |
| 要 件 | 一定の処分がされないことにより重大な損害を証するおそれがあり、その損害を避けるため他に適当な方法がないこと(37条の2第1項)2 | 法令に基づく申請・審査請求に対し、相当の期間内に何らの処分・裁決がなされないこと(不作為型)(37条の3第1項1号) 法令に基づく申請・審査請求を却下・棄却する旨の処分・裁決が取り消されるべきものであり、または無効・不存在であること(拒否処分型)(37条の3第1項2号) |
| 原 告 適 格 | 行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者(37条の2第3項) | 法令に基づく申請・審査請求をした者(37条の3第2項) |
| 併 合 提 起 | 不要 | 不作為型の場合:不作為の違法確認訴訟 拒否処分型の場合:取消訴訟or無効等確認訴訟 (37条の3第3項)34 |
なお、被告適格(11条)、裁判管轄(12条)については、取消訴訟の規定が準用されます(38条1項)。
これに対して、出訴期間(14条)については取消訴訟の規定が準用されません(取消訴訟を併合提起した場合は、その取消訴訟が出訴期間の制限を受ける)。
義務付け判決が出るための条件とは?
行政庁に対して処分を命じる「義務付け判決」を得るには、次のような条件を満たす必要があります(行政事件訴訟法37条の2第5項、37条の3第5項)。
【共通の条件】下のいずれか一つに当てはまる
- 行政庁が処分をするべきことが処分の根拠法令から明らかであると認められるとき(=行政裁量がない)
- または、行政庁の対応が裁量権の逸脱・濫用にあたる(=裁量があるが著しく不合理)
【申請型特有の条件】
- 併合提起された関連訴訟に理由があること(37条の3第5項)。
つまり、申請型では単独では足りず、「他の訴訟の請求が認められる見込み」があることも必要になります。
まとめ
| 分類 | 前提 | 求める内容 |
|---|---|---|
| 非申請型 | 法令による申請なし | 処分・裁決を命じる |
| 申請型 | 法令に基づく申請あり | 処分・裁決を命じる+関連訴訟の判決 |
義務付け訴訟は、行政庁に行動を促す強い救済手段であり、申請型と非申請型で要件が異なる点がよく問われます。しっかり理解しておきましょう!
- 具体例:非申請型の例としては、違法建築物の除却を命ずる権限の行使を求めて周辺住民が義務付け訴訟を提起する場合が、申請型の例としては、年金給付を求める申請が拒否されたため申請者が給付決定を求めて義務付け訴訟を提起する場合がある。 ↩︎
- 「他に適当な方法」とは、①特別の権利救済手段が法律で設けられている場合、②不利益処分について取消訴訟による救済が可能な場合、③申請型義務付け訴訟の提起が可能な場合など ↩︎
- 参考:申請型義務付け訴訟のみを単独で提起することはできないが、取消訴訟のみを単独で提起することはできる。 ↩︎
- 参考:仮の義務付けを申し立てる場合に、執行停止の申立てを併合しなければならないとする規定はない ↩︎