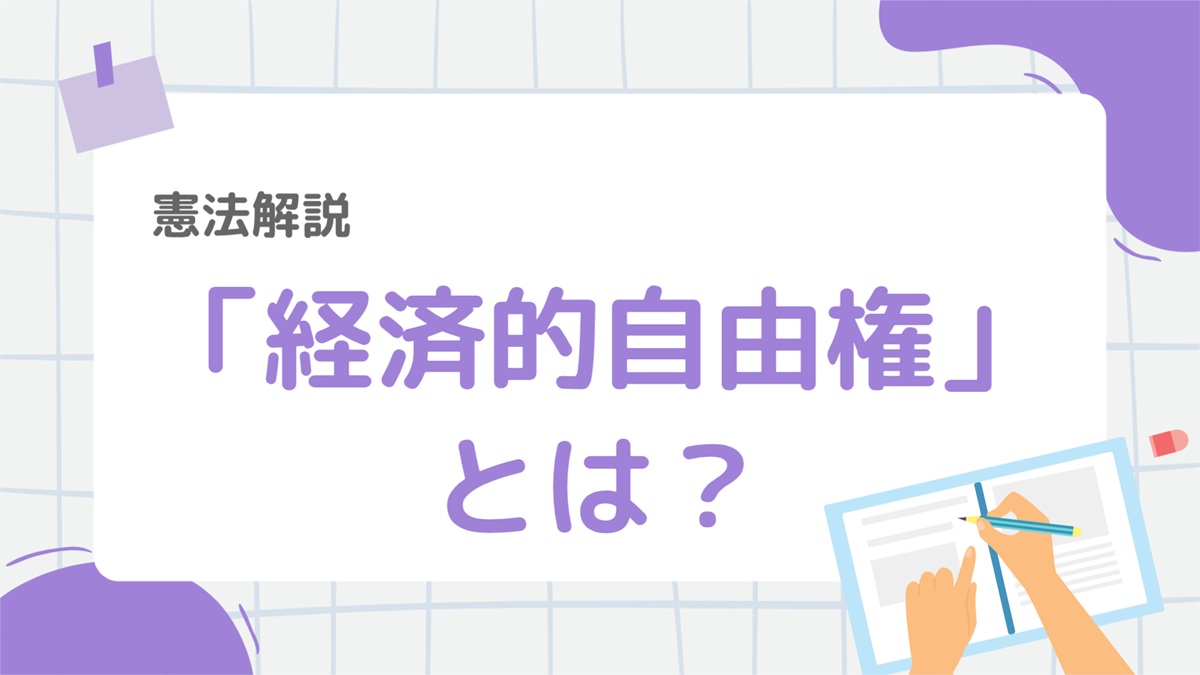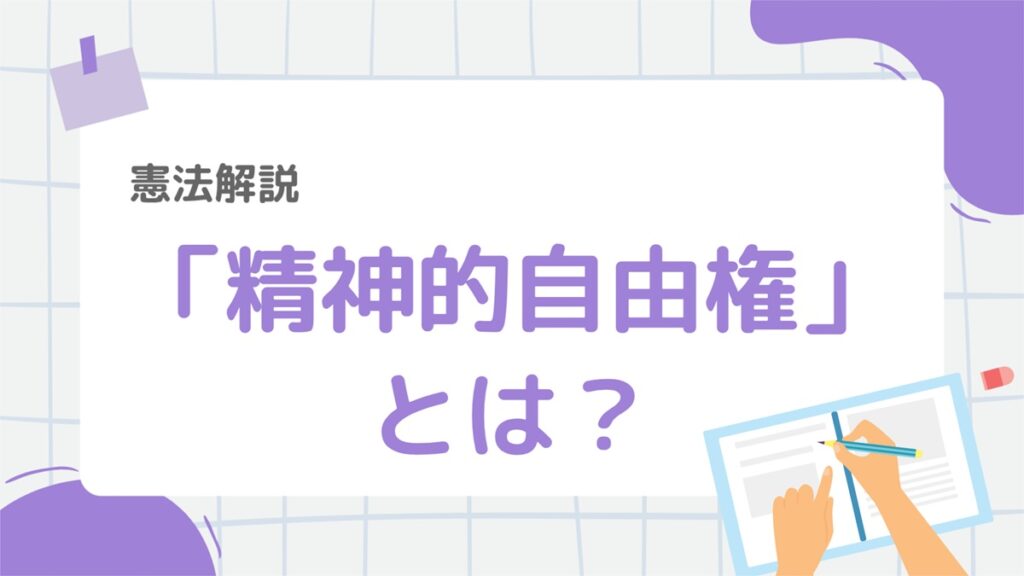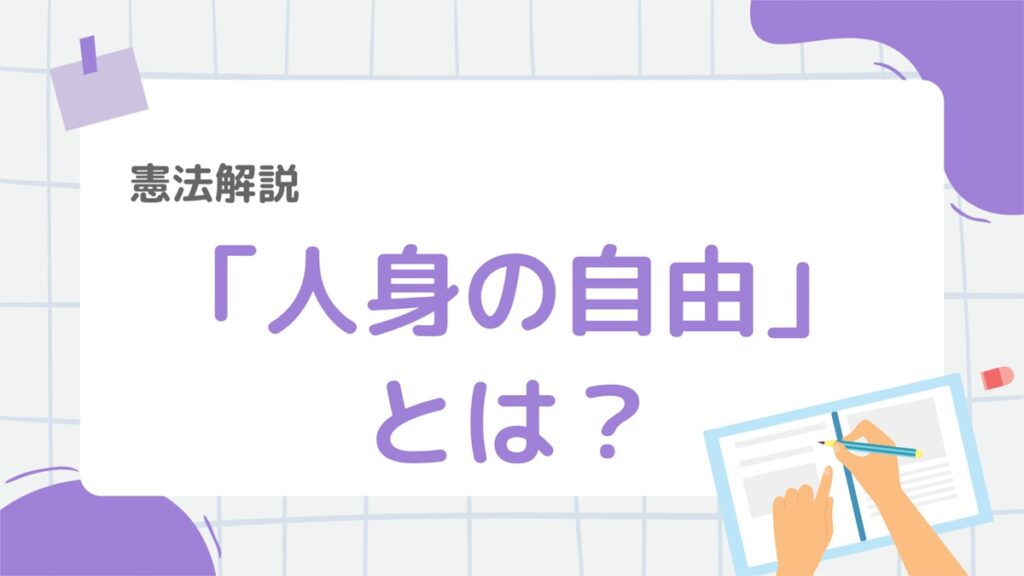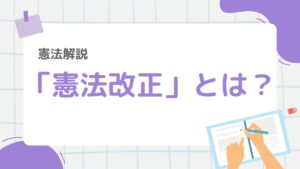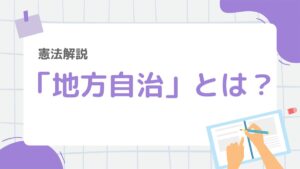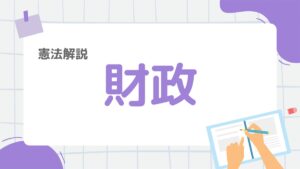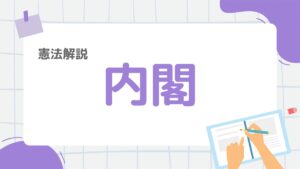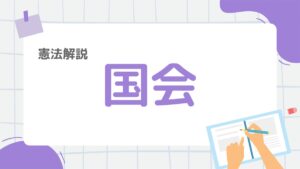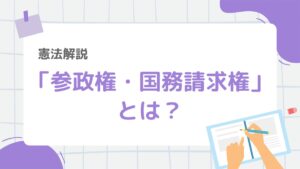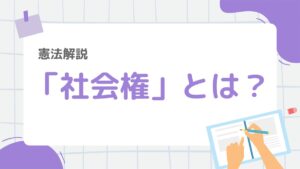- 行政書士試験で「経済的自由権」の出題に備えたい方
- 職業選択の自由や財産権について、条文レベルから深く理解したい方
- 憲法の条文と判例の関係をスッキリ整理したい方
- 自由権の種類と具体的な規制のパターンを確認したい方
職業選択の自由とは?
憲法22条1項に規定されている「職業選択の自由」とは、どんな仕事に就くかを自分の意思で自由に決めることができる権利です。この権利は「経済的自由権」の一つとされ、現代社会の基盤となっています。
ただし、全く無制限ではなく、必要に応じて制限される場合もあります。制限の種類には次の2つがあります。
- 警察的(消極的)規制
👉人の命や健康を守るための制限。たとえば、医師や弁護士などに資格が必要な理由がこれです。 - 政策的(積極的)規制1
👉経済のバランスを整えたり、社会的弱者を守るための制限。福祉国家の理念に基づく規制です。
🔍【重要】小売市場事件(最大判昭47.11.22)
🔍【重要】薬局距離制限事件(最大判昭50.4.30)
🔍【重要】公衆浴場距離制限事件(最判平1.1.20)
🔍【重要】酒類販売免許制事件(最判平4.12.15)
🔍最判平12.2.8:司法書士の業務独占
居住・移転の自由とは?
同じく憲法22条1項に規定されている「居住・移転の自由」とは、どこに住むかを自由に決めたり、国内で自由に移動できる権利です。
この自由が保障されたことにより、人々は自由に移動して職を得たり、商売を始めたりすることが可能になりました。こうした背景から、「居住・移転の自由」も職業選択と同様に経済的自由権の一部とされています。
外国移住の自由と国籍離脱の自由とは?

憲法22条2項では、さらに次の2つの自由が保障されています。
- 外国移住の自由:外国に移り住む自由、すなわち海外に定住する目的で渡航する自由。(判例:帆足計事件)
- 国籍離脱の自由を:自分の意思で日本国籍を離脱する自由。大日本帝国憲法時代には認められていませんでしたが、現在は憲法により保障されています。
これらは「個人の意思を最大限に尊重する自由」として、国際的な人権観にもとづいた重要な権利です。
財産権とは?
憲法29条1項において、「財産権は、これを侵してはならない」と規定されています。これは、単に私有財産制度を保障するだけでなく、個々の国民の財産権を基本的人権の一つとして位置づけたものです。
🔍判例にも注目:「森林法共有林事件(最大判昭62.4.22)」
この判例では、共有林の利用制限が財産権の侵害に当たるかが争われ、財産権の保障の範囲が議論されました。試験でも狙われやすい重要判例です。
財産権に対する制限と損失補償
法律による制限
財産権の内容は、「公共の福祉」に適合するように法律で定めることとされています。つまり、財産権は絶対的なものではなく、社会全体の利益のために法律で制限されることがあります。
条例による制限は可能?
ここで問題になるのが、条例によって財産権を制限できるのか?という点です。憲法上は「法律」による制限とされており、条例による制限には慎重な検討が必要です。
損失補償
適法な行政行為によって生じた損失については、損失補償が行われるべきとされています。これは、例えば公共事業で土地を提供した場合などに、金銭で補填される制度です(29条3項)。
※損失補償の詳細については、行政法の分野でも学ぶ必要があります。
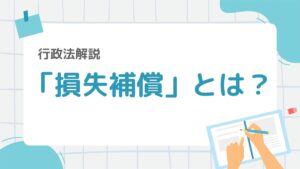
✅まとめ
経済的自由権である「職業選択の自由」「居住・移転の自由」「外国移住・国籍離脱の自由」、そして「財産権」は、行政書士試験でも頻出のテーマです。
それぞれの権利が何を保障しているのか、どのように制限されるのか、そして条文・判例とのつながりを意識して学習しましょう!
- 具体例:消極的・警察的規制の例としては各種の営業許可制が、積極的・政策的規制の例としては大型スーパーなどの巨大資本から中小企業を保護するための競争制限が挙げられる。 ↩︎