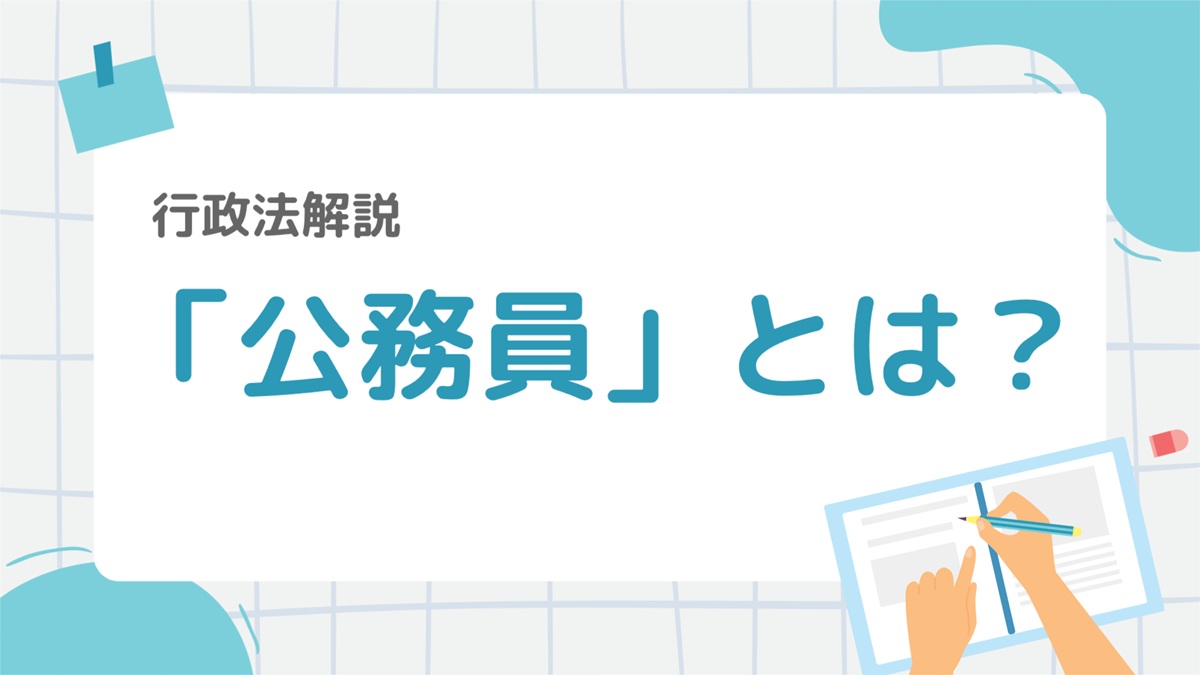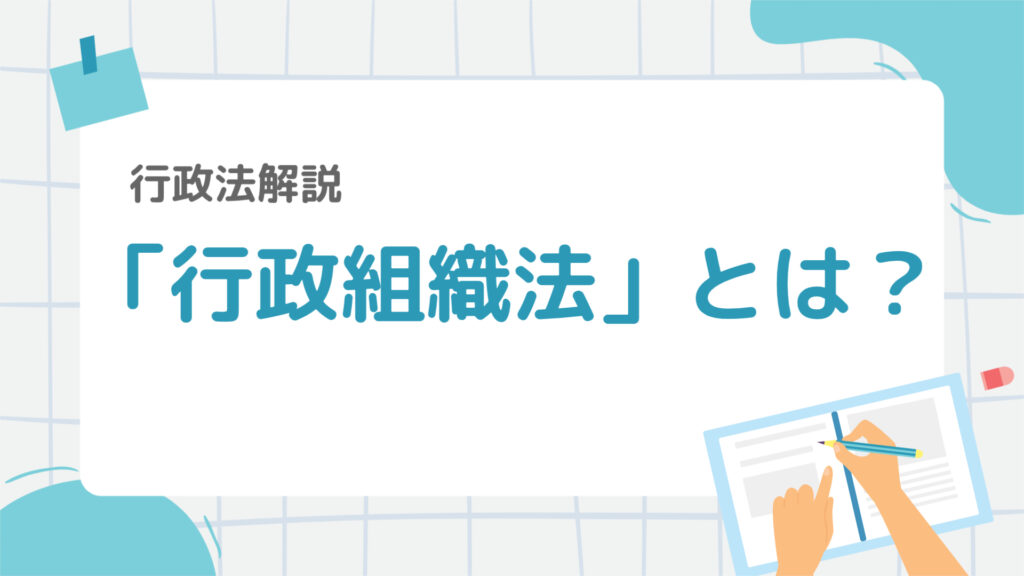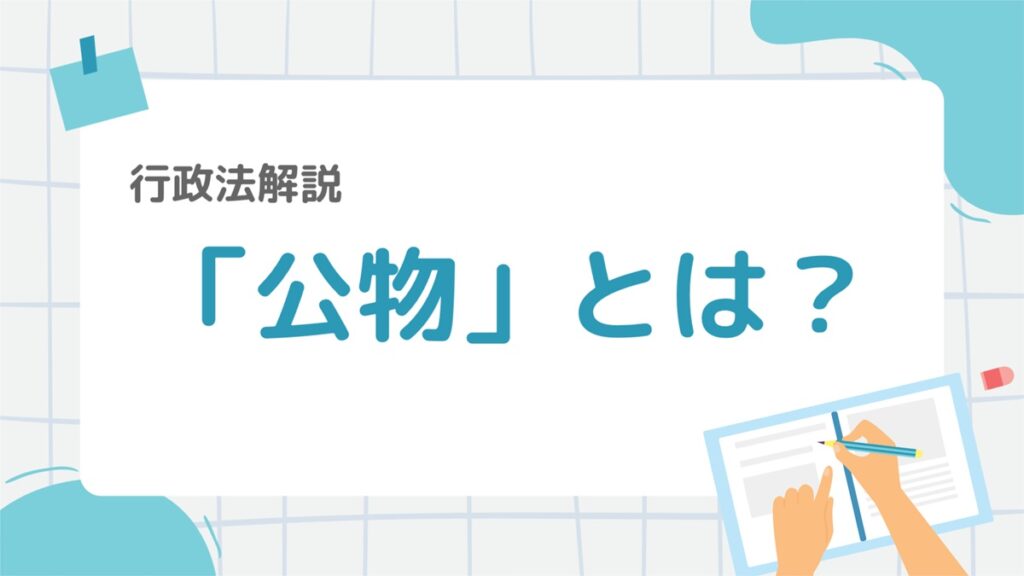✅この記事はこんな人におすすめ
- 行政書士試験の「憲法・行政法」の学習をしている方
- 公務員の種類や制度について体系的に理解したい方
- 分限処分や懲戒処分の違いがよくわからない方
- 「公務員の人事行政」や給与制度のポイントを押さえておきたい方
目次
公務員とは?種類と役割をわかりやすく解説
公務員とは、国や地方公共団体の業務(=公務)を担う人のことを指します。
大きく分けて、国の業務を行う「国家公務員」と、地方公共団体で働く「地方公務員」に分類されます。1
さらに、公務員は次の2つに分けられます。
特別職公務員の具体例
以下のような職種が特別職公務員に該当します。
- 国家公務員の場合
- 選挙で選ばれた者(国会議員など)
- 議会の同意が必要な者(人事院の人事官など)
- 政治的に任命された者(大臣など)
- 立法府・司法府で仕事をする者(裁判官・裁判所職員など)
- 地方公務員の場合
- 選挙で選ばれた者(市長・市議会議員など)
- 議会の同意が必要な者(副市長など)
公務員の身分保障とは?
公務員は、法律に定めがある場合を除き、本人の意思に反して辞めさせられたり、休職させられたりすることはありません。
そのため、公務員に対して行う処分は法律に基づいて厳格に分類され、①分限処分と②懲戒処分の2種類があります。これらの処分は、行政処分と解されており、審査請求の対象となります。
- ①分限処分とは?【職務を果たせない場合】
-
分限処分とは、公務員が職責を十分に果たせない場合に、その身分に関して行われる処分です。3
分限処分には、以下の4種類があります。- 免職:公務員の身分を失わせること
- 降任:現在より下位の職を命じること
- 休職:公務員の身分を維持したまま、職務に就かせないこと
- 降給:給与を減額すること
- ②懲戒処分とは?【義務違反への制裁】
-
懲戒処分とは、公務員が義務違反を犯した場合に、制裁としてその身分に関して行われる処分です。45
懲戒処分には、以下の4種類があります。- 免職:公務員の身分を失わせること
- 停職:公務員の身分を維持したまま、職務に就かせないこと
- 減給:給与を減額すること
- 戒告:行為を戒め反省を促すこと
公務員の人事行政
公務員の人事行政に関する事務を担当するため、国では人事院が、地方公共団体では、その規模に応じて人事委員会または公平委員会6が設置されています。7
これらの機関は、公務員の勤務条件の改善や、懲戒処分などに関する行政不服審査法による審査請求の審査を担当する。
公務員の給与・勤務条件
国家公務員の場合
- 給与は法律によって定められています(国家公務員法63条)
- 勤務条件について必要な事項は、人事院規則によって定められます(同法106条1項)
地方公務員の場合
- 給与や勤務条件は、各自治体の条例によって定められます
まとめ|行政書士試験で頻出!公務員制度の理解は必須
公務員制度は、行政法・憲法いずれの分野でもよく出題されるテーマです。
特に「特別職と一般職の違い」「分限処分と懲戒処分の内容と違い」「人事行政機関の役割」は頻出ですので、しっかり整理しておきましょう。
- 独立行政法人の職員は、一般的には公務員に当たらないが、行政執行法人の職員は、国家公務員の身分が与えられている(独立行政法人通則法51条) ↩︎
- 具体例:一般的な公務員法には政治的行為の禁止が定められているが、国会議員が政治的行為をすることができなかったらもはや国会議員とはいえなくなってしまうので、国会議員は特別職の公務員とされている ↩︎
- 具体例:心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合や、定員の改廃等によって廃員や過員が生じた場合など ↩︎
- 具体例:法令や職務上の義務に違反した場合や、全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合など ↩︎
- 参考:懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院または人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続きを進めることができる(国家公務員法85条前段) ↩︎
- 公平委員会:規模の小さい地方公共団体に設置される人事委員会を簡略化した組織 ↩︎
- 参考:人事院は、内閣の所轄の下に設置される(国家公務員法3条1項) ↩︎