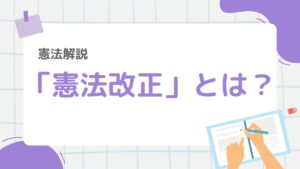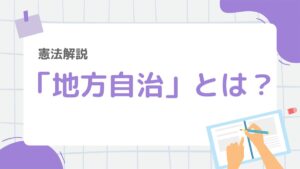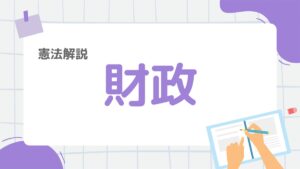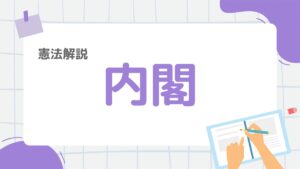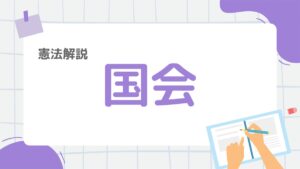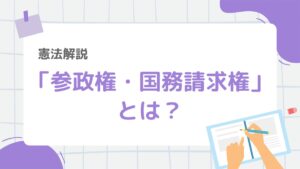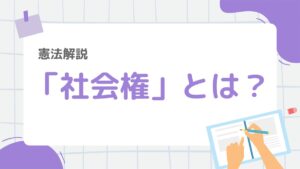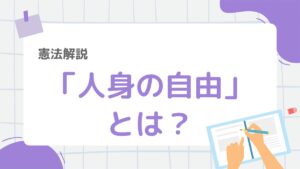- 「司法権」や「裁判所のしくみ」について理解を深めたい方
- 「違憲審査権」や「裁判の公開」について判例も含めて確認したい方
- 暗記だけでなく、仕組みから理解したい方
司法権の意味とは?
司法権とは、「具体的な争いごと(争訟)」について、法を適用し宣言することによって解決する権限のことです。
この司法権は、最高裁判所および法律で定める下級裁判所に属します(76条1項)。
判例によれば、「具体的な争訟」とは、裁判所法3条1項の「法律上の争訟」と同じ意味とされ、法令によって解決できる権利義務に関する当事者間の争いを指します(最判昭41.2.8)。
したがって、以下のようなケースは「法律上の争訟」に当たらず、裁判で争うことができません。
- 国家資格の合格・不合格のように、試験実施機関の最終的判断に委ねられ法令の適用によって解決できないもの。
- 具体的な事件から離れ、抽象的に法律の解釈を争うもの。
司法権の限界とは?
司法権が原則として裁判所に属するとしても、次のような例外や限界があります。
① 憲法に基づく例外
以下のように、裁判所以外の機関が司法的判断を行う場合があります。
② 裁判に適さない性質の行為
- ❶自立権に属する行為
-
自立権に属する行為とは、国会または各議院の内部事項に関する行為で、国会や各議院の自主的な判断を尊重するべきであり、司法権を行使できない。
- ❷統治行為
-
統治行為とは、直接国家統治に関する高度に政治性のある国家行為。
統治行為は、政府・国会等の判断に委ねるべきであり、裁判所は司法権を行使することができない。 - ❸団体の内部事項に関する行為
-
大学や政党など、自主的な団体の内部紛争については、内部規律の問題にとどまる限り、自治的措置に任せるべきであるため裁判所の司法審査が及ばないとされている。(部分社会の法理)
尚、従来の最高裁判所の判例では、地方議会の議員に対する出席停止の懲罰についても、司法審査が及ばないとされていたが、最高裁判所の判例が変更され、司法審査が及ぶこととされた。
司法権の帰属
- ❶特別裁判所の禁止
-
特別裁判所とは、特別の人間・事件について裁判するため、通常裁判所から独立して設けられる裁判機関。
法解釈の統一を図る必要があることから、特別裁判所の設置は禁止されています(76条2項前段)。
👉判例:最大判昭31.5.30(家庭裁判所は特別裁判所に当たるのか?) - ❷行政機関による終審裁判の禁止
-
行政機関は、終審として裁判を行うことができない(76条2項後段)。
反対解釈として、前審であれば、行政機関による裁判も認められます。
裁判所の組織と権能
裁判所は、最高裁判所と下級裁判所に別けられる。
最高裁判所
- ❶構成
-
最高裁判所は、長たる裁判官(長官)および法律の定める員数のその他の裁判官で構成される(79条1項)。
最高裁判所の長たる裁判官は、内閣の指名に基づき、天皇が任命する(6条2項)。
これに対し、長たる裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する(79条1項)。 - ❷国民審査
-
裁判官の選任に対し民主的コントロールを行うため、最高裁判所裁判官の国民審査の制度があります。
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民の審査に付し、その後10年を経過した後に行われる衆議院議員総選挙の際に審査に付し、その後も同様です(79条2項)。
投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は罷免されます(79条3項)。 - ❸定年
-
最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達したときに退官する(79条5項)。
👇あわせてチェック
下級裁判所
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する(80条1項前段)。
下級裁判所の裁判官の任期は10年(再任あり)。法律の定める年齢に達したときに退官する(80条1項後段)。
| 最高裁判所の裁判官 | 下級裁判所の裁判官 | |
| 指名 | 長たる裁判官のみ⇒内閣 | |
| 任命 | 長たる裁判官⇒天皇 その他の裁判官⇒内閣 | 内閣 |
| 任期 | なし | 10年(再任あり) |
| 定年 | あり | |
| 罷免 | 裁判により心身の故障ために職務を執ることができないと決定された場合、または公の弾劾による場合(78条前段) | |
| 国民審査 | ||
下級裁判所には、高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所・家庭裁判所の4種類あります。それぞれの権限等の詳細はコチラをチェック👇
司法権の独立とは?
裁判が公平に行われ、基本的人権が守られるために、裁判官が外部から圧力や干渉を受けずに、公正な立場で職務を行うことが求められる。「司法権の独立」は憲法上で強く保障されています。
▶司法の独立の2つの側面
- 司法府の独立:立法権・行政権からの独立(制度としての独立)
- 裁判官の職権の独立:個々の裁判官が、命令されず自由な判断で職務を行うこと
👉裁判官の職権の独立を確保するため、憲法上、裁判官の身分保障が認められています。
司法府の独立
- 規則制定権
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事務について、規則を定める権限を有する(77条1項)。
裁判所の自主性を確保し最高裁判所の統制権と監督権を強化すること、実務に通じた裁判所の専門的判断を尊重することから、最高裁判所に規則制定権が認められている。 - 行政機関による裁判官の懲戒処分の禁止
裁判官に対する行政権の不当な干渉を防止し、裁判所の自主的な処理に委ねるため、行政機関による裁判官の懲戒処分は禁止されている(78条後段)。
裁判官の職権の独立(身分保障)
すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法および法律にのみ拘束される(76条3項)。
👉判例:最大判昭23.11.17:「良心に従い」とは?
- 罷免事由の限定
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない(78条前段)。
これ以外の事由による裁判官の罷免を認めず、裁判官が裁判に専念できるようにすることによって、職権の独立を確保している。 - 報酬の保障
経済的観点から裁判官を保障することにより、職権の独立を確保するため、裁判官はすべて定期に相当額の報酬を受けることができ、この報酬は在任中減額することができない(76条6項、80条2項)。
違憲審査権とは?
違憲審査権とは、法律・命令・規則・処分が憲法に適合するかどうかを決定する権限です。
最高裁判所は、一切の法律・命令・規則または処分が憲法に適合するかどうかを決定する権限を有する終審裁判所とされています(81条)。
👉判例:最大判昭25.2.1(下級裁判所にも違憲審査権が認められる)
裁判所に違憲審査権が認められている理由として、憲法の最高法規性は、国家行為の合憲性を審査・決定する機関があってはじめて確保されることと、憲法の保障する基本的人権が立法権・行政権によって侵害された場合に、救済する必要があるためです。
違憲審査の方法
裁判所による違憲審査の方法には、2つありますが、日本は「❶付随的違憲審査制」が採用されていると考えられています。これは裁判の過程で必要な場合に限って違憲審査を行う制度です。
※「抽象的違憲審査制」は、ドイツなどで採用されているもので、特別な憲法裁判所が審査を行います。
- 付随的違憲審査制
通常の裁判所が、具体的な争訟を裁判する際に、その争訟において問題となった点についてのみ違憲審査を行う。 - 抽象的違憲審査制
特別に設けられた憲法裁判所が、具体的な争訟と関係なく、抽象的に違憲審査を行う。
違憲審査の対象
- ❶条約
-
条約は81条に列挙されていないが、最高裁判所の判例は、条約を違憲審査の対象とする余地を認めている。
- ❷立法不作為
-
立法不作為の違憲審査の判例として、以下3つ。
- ❸裁判
-
司法行為(裁判)も、最高裁判所の違憲審査権に服する(最大判昭23.7.7)。
裁判の公開
裁判の対審および判決は、自由に傍聴できる公開法定で行うのが原則です(82条1項)。
これは、裁判の公正を確保するために対審や判決のような重要部分が公開される必要があるためです。
👉判例:最判平17.4.14(遮へい措置について)
そして、公開が要求される「裁判」とは、当事者の意思にかかわらず終局的に事実を確定し当事者の主張する権利義務の存否を確定するような純然たる争訟事件の裁判に限られる(最大決昭35.7.6)。
「裁判」に当たるかどうかについては、以下の通り。
- 「裁判」に当たる
金銭債務臨時調停法の調停に代わる裁判(最大決昭35.7.6) - 「裁判」に当たらない
- 家事審査法(現家事事件手続法)による夫婦同居の審判(最大決昭40.6.30)
- 民事上の秩序罰としての過料を科する作用(最大決昭41.12.27)
- 裁判官の懲戒の裁判(寺西裁判官事件:最大決平10.12.1)
- 家事審査法(現家事事件手続法)による夫婦同居の審判(最大決昭40.6.30)
なお、裁判所が、裁判官の全員の一致で、公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあると決した場合には、例外的に、対審は、公開しないで行うことができます(82条2項本文)。
ただし、❶政治犯罪、❷出版に関する犯罪、❸憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常に公開しなければなりません(82条2項但書)。
✅まとめ|司法権と裁判所の本質を押さえよう
司法権は、具体的な争訟について法を適用し、法的な判断を下す国家権力の一つです。
日本国憲法では、この司法権を裁判所に属させ、立法・行政からの独立性を保障することで、公正な裁判と基本的人権の保護を図っています。
また、裁判所には「違憲審査権」が与えられ、法律や命令が憲法に反していないかをチェックする役割も担っています。これは、法の支配を支える重要な制度です。
行政書士試験では、裁判所の構成や任命方法、司法の独立、違憲審査制など、条文と判例の理解が問われます。
しっかりと仕組みから学び、単なる暗記ではなく「なぜそのような制度になっているのか」まで押さえておくことが、合格への近道です。