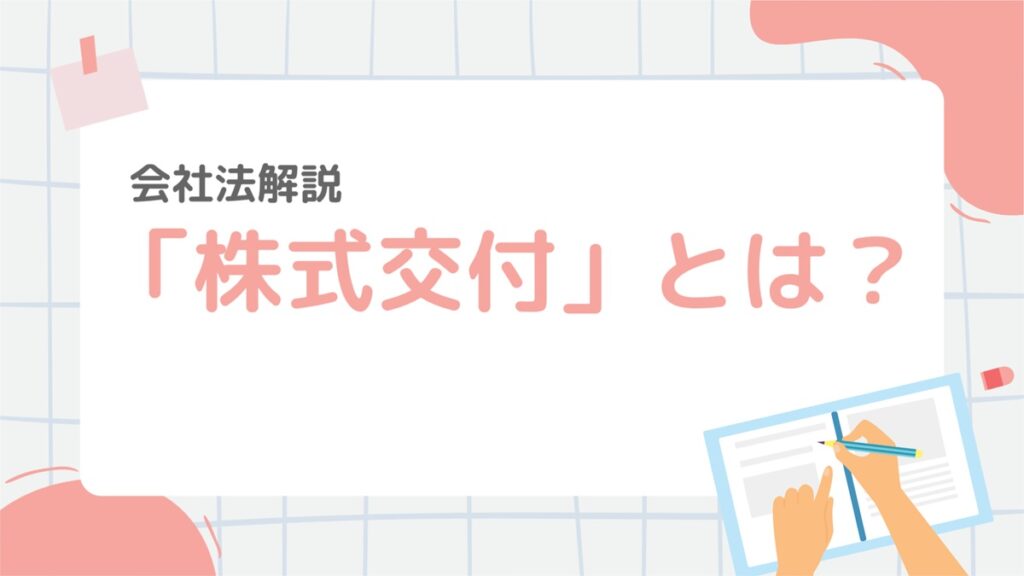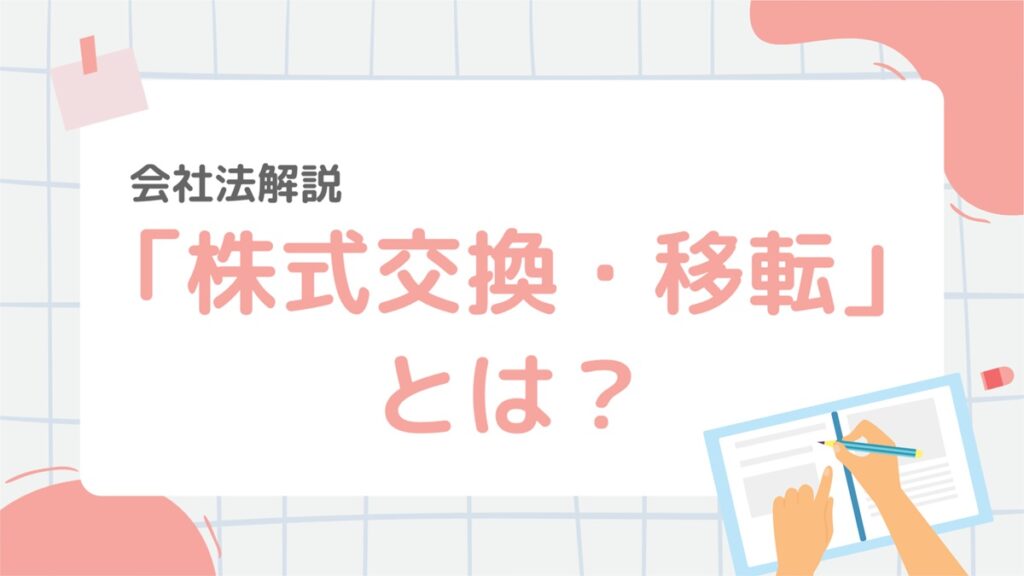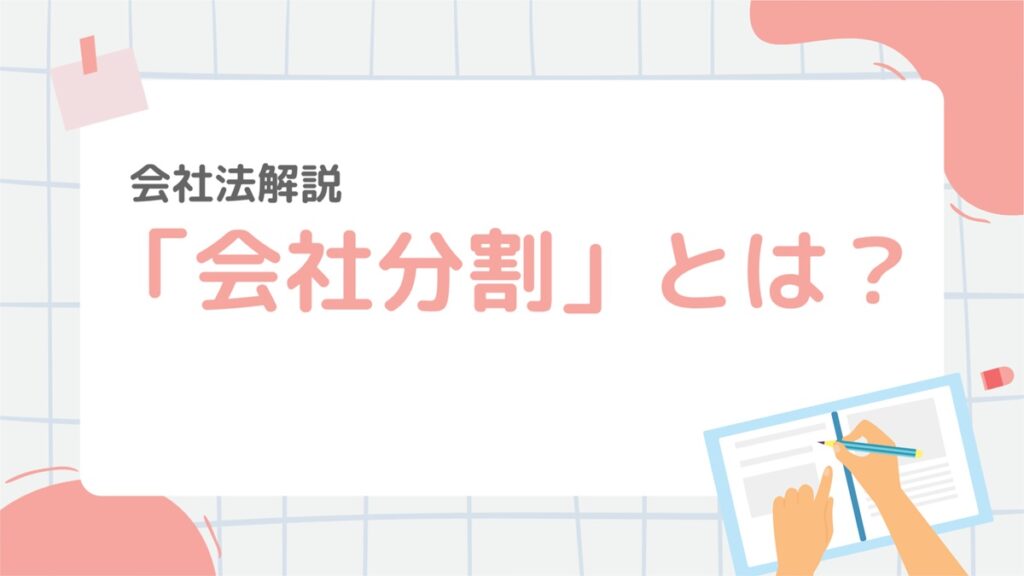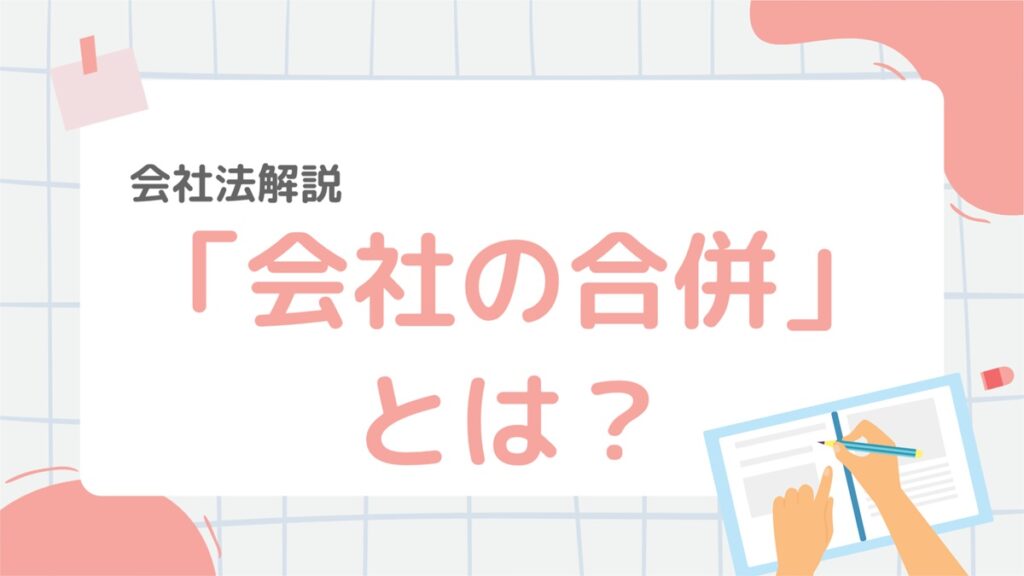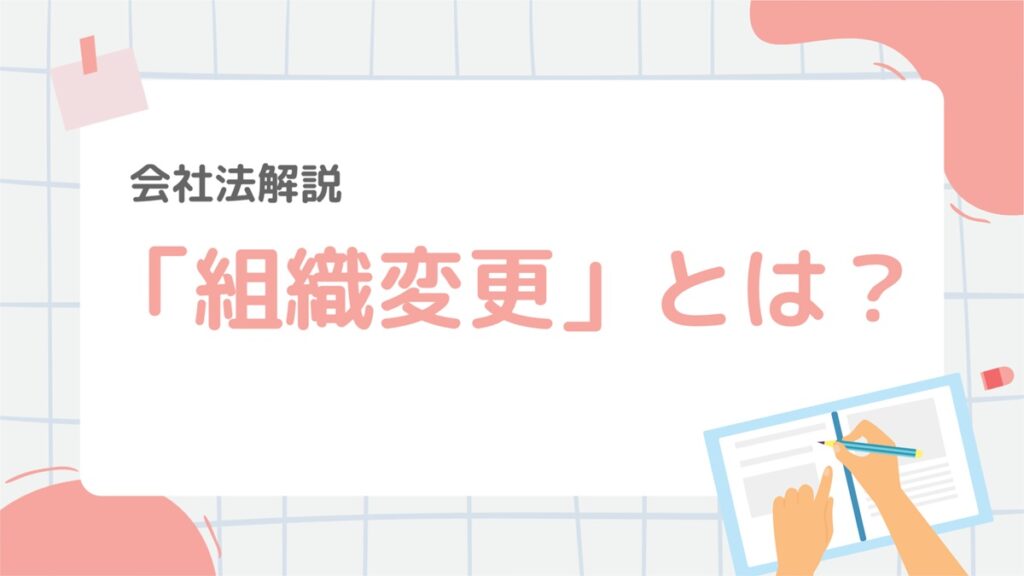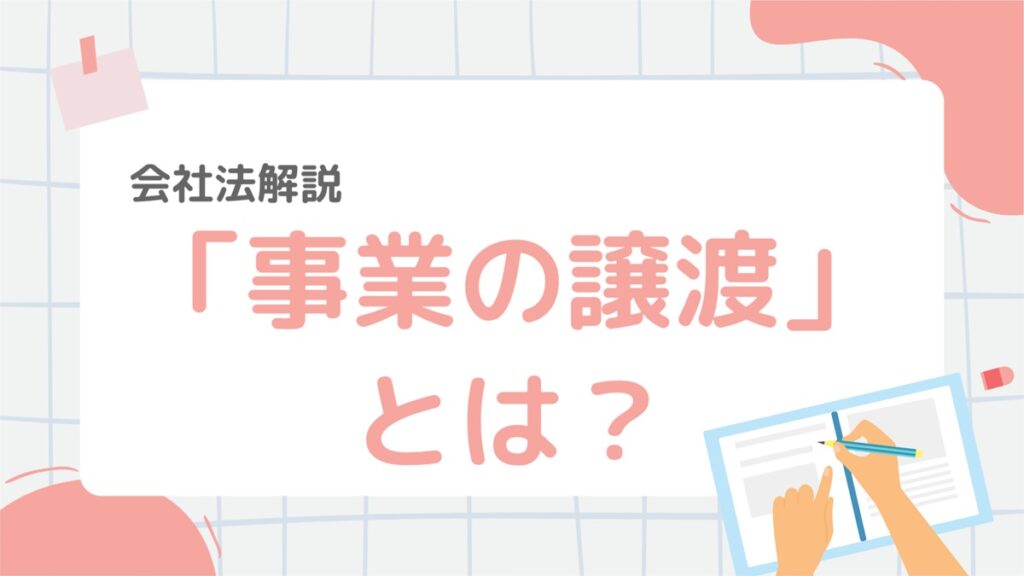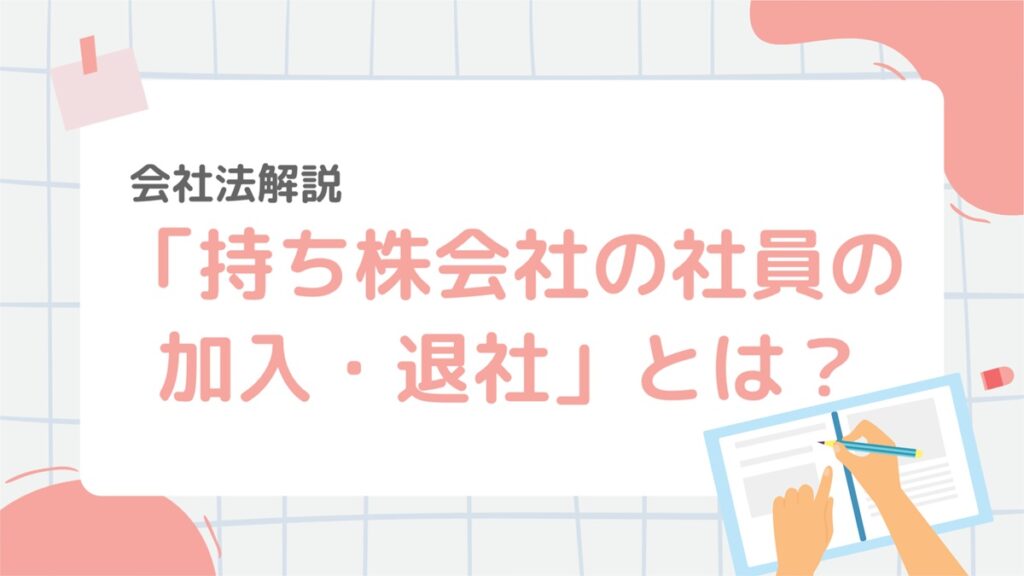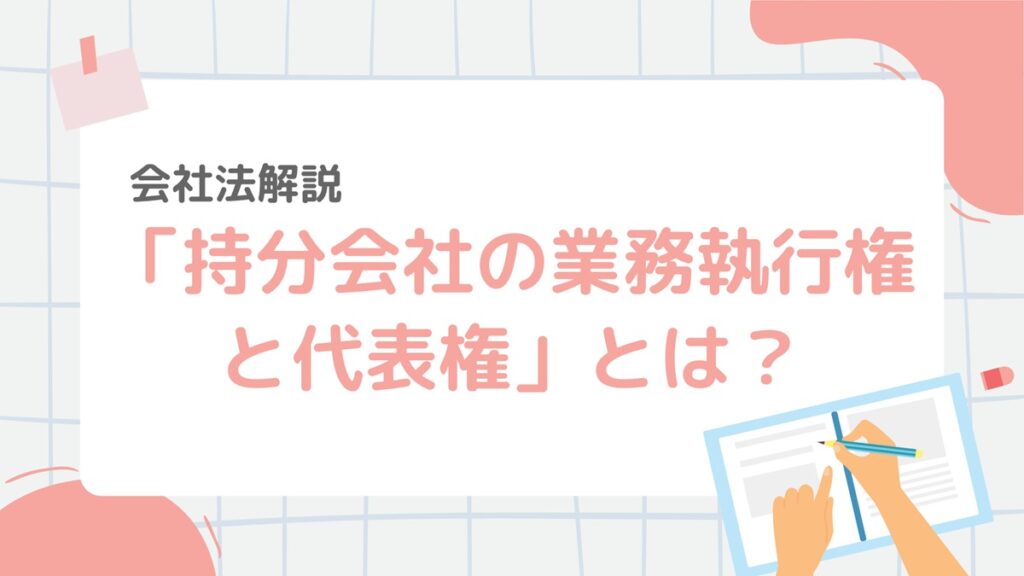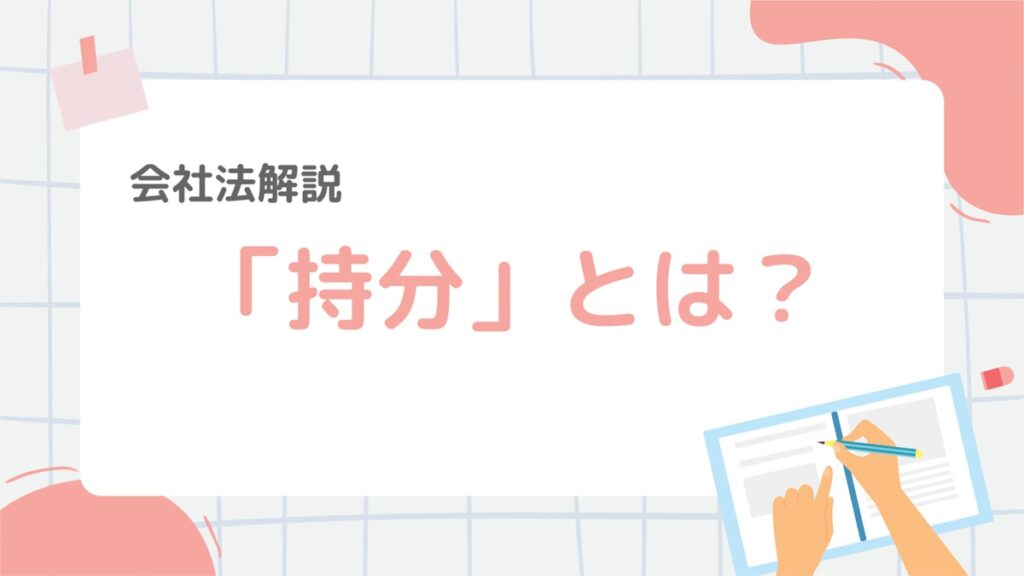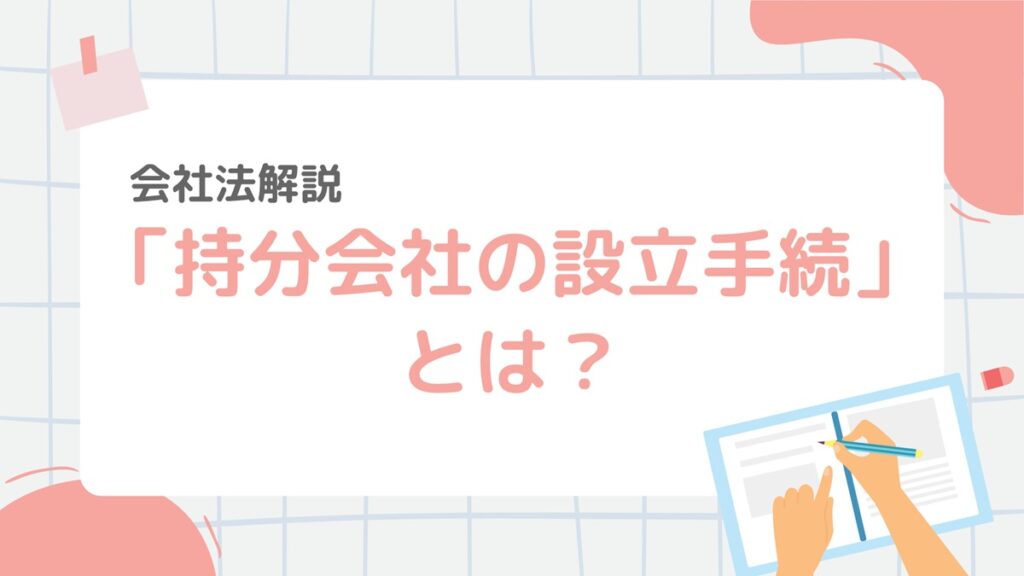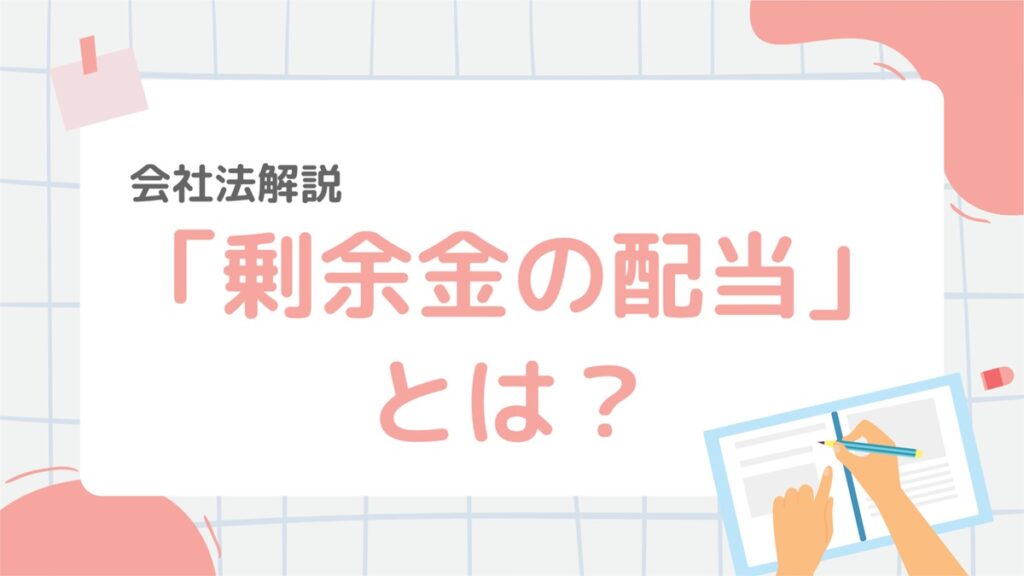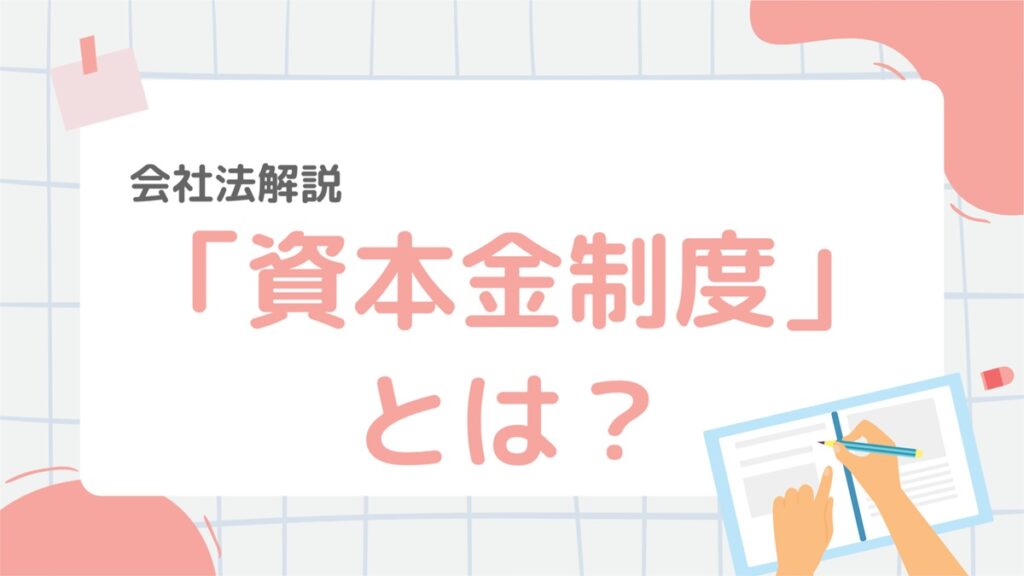法令– category –
-

会社法7-6:「株式交付」とは?仕組み・手続・無効の訴えまでやさしく解説!
この記事はこんな人におすすめ 「株式交付って株式交換とどう違うの?」と疑問を持っている方 会社法の改正ポイントをしっかり押さえておきたい方 行政書士試験の会社法分野で得点源を増やしたい方 株式交付とは?かんたんに言うと… 株式交付とは、ある株... -

会社法7-5:株式交換・株式移転とは?図解でわかる完全親子会社のしくみ
✅この記事はこんな人におすすめ 「株式交換」と「株式移転」の違いをわかりやすく理解したい方 完全親子会社の仕組みを行政書士試験の対策として学びたい方 難しい条文の表現をやさしく整理して覚えたい方 株式交換・株式移転とは?~完全親子会社を作る手... -

会社法7-4:「会社分割」とは?吸収分割と新設分割の違い・手続・効力までやさしく解説
この記事はこんな人におすすめ 「会社分割ってなに?」と基本から学びたい方 行政書士試験で会社法を勉強している方 吸収分割と新設分割の違いがよくわからない方 分割の手続きや効力発生日を整理したい方 会社分割とは?意味と目的をやさしく解説 会社分... -

会社法7-3:「会社の合併」とは?吸収合併と新設合併の違い・手続き・効力をやさしく解説!
🎯この記事はこんな人におすすめ 会社法の「合併」について基礎から理解したい方 行政書士試験で出題される合併の種類・流れを押さえたい受験生 「吸収合併」「新設合併」の違いがよくわからない方 合併手続の具体的なステップやスケジュールを整理したい方... -

会社法7-2:「組織変更」とは?株式会社⇔持分会社の違いと手続をやさしく解説!
この記事はこんな人におすすめ 「組織変更って何?」という初学者の方 株式会社と持分会社の違いを理解したい方 行政書士試験で会社法を勉強中の方 組織変更の手続きや要件を整理して覚えたい方 組織変更とは?株式会社と持分会社の切り替え制度 「組織変... -

会社法7-1:「事業の譲渡」とは?意味・手続・株主総会の承認が必要なケースをわかりやすく解説!
📝この記事はこんな人におすすめ 「事業の譲渡」って何かよくわからない…… 会社法の「株主総会の特別決議」が必要な場面を整理したい 行政書士試験で出題される「会社の組織再編」の知識をきちんとおさえておきたい→ そんな方に向けて、事業の譲渡に関する... -

会社法6-4:持分会社の「社員の加入・退社」のポイントをわかりやすく解説!
この記事はこんな人におすすめ 「持分会社の社員の加入・退社」のルールがイマイチよくわからない方 合同会社・合名会社・合資会社の違いを整理して覚えたい方 行政書士試験の会社法の問題で得点を伸ばしたい方 持分会社の社員の加入・退社とは? 持分会社... -

会社法6-3:持分会社の業務執行権と代表権をわかりやすく解説|所有と経営が一致する会社の仕組みとは?
この記事はこんな人におすすめ 持分会社と株式会社の違いを知りたい方 合名会社・合資会社・合同会社の「管理の仕組み」がよくわからない方 業務執行権や代表権の条文がイメージしにくい方 行政書士試験で「持分会社」が出たときに、迷わず解けるようにし... -

会社法6-2:「持分」とは?株式との違いや譲渡のルールもやさしく解説!
この記事はこんな人におすすめ 「持分って何?」と基本から知りたい方 持分会社と株式会社の違いを知りたい方 行政書士試験で会社法を勉強している方 持分の譲渡に関するルールを押さえたい方 持分とは?持分会社の「社員としての立場」のこと 「持分(も... -

会社法6-1:「持分会社の設立手続」とは?合同会社・合資会社・合名会社の違いもやさしく解説
📝この記事はこんな人におすすめ 持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)の設立手続を基本から学びたい方 株式会社との違いや、出資の種類について理解を深めたい方 行政書士試験に向けて会社法の設立部分を整理したい方 🔍持分会社の設立手続をやさしく... -

会社法5-3:「剰余金の配当」とは?手続・ルール・違法配当のリスクまでわかりやすく解説!会社法5-3:剰余金の配当
この記事はこんな人におすすめ! 「剰余金の配当」って何?とにかく基本から知りたい方 株主総会や取締役会の役割との関係を理解したい方 違法配当とは何か、実際にどんなリスクがあるのか知りたい方 行政書士試験の会社法対策を進めている受験生の方 剰余... -

会社法5-2:「資本金制度」とは?わかりやすく解説|仕組み・原則・減少手続きまでやさしく学ぼう
🎯この記事はこんな人におすすめ 「資本金ってそもそも何?」と疑問を感じている方 行政書士試験で会社法の理解を深めたい方 資本金のルールや減少の手続きについて基礎から知りたい方 株式会社の仕組みに興味のあるビジネスパーソンや起業家の方 資本金と...