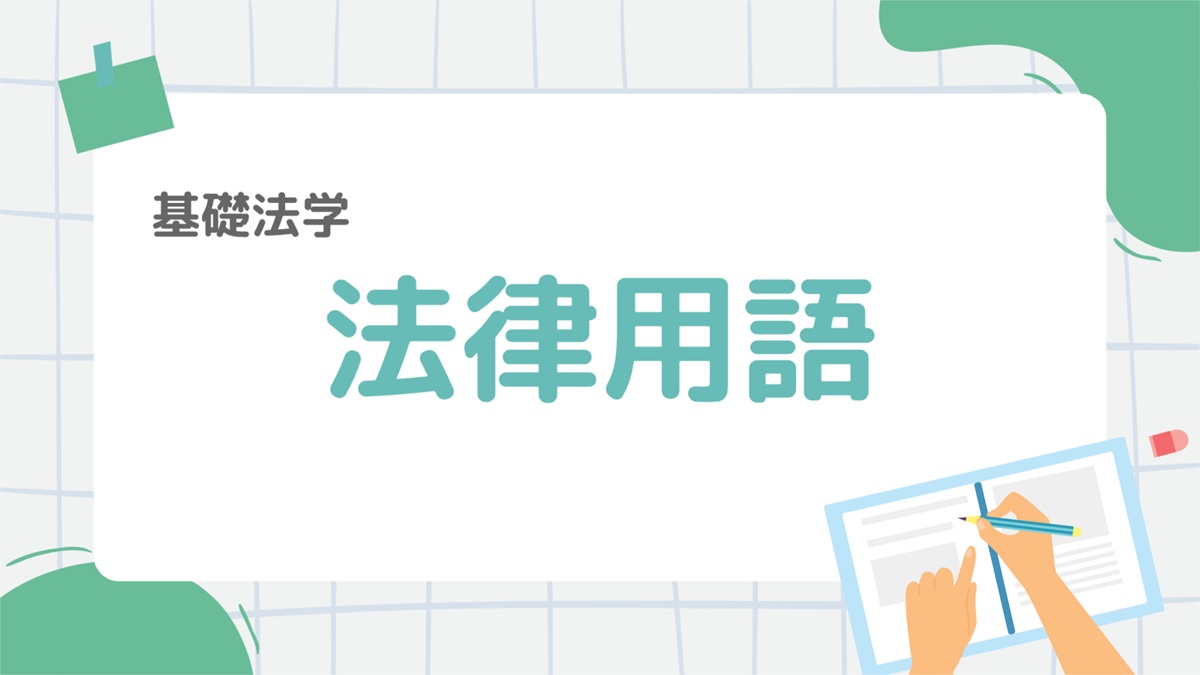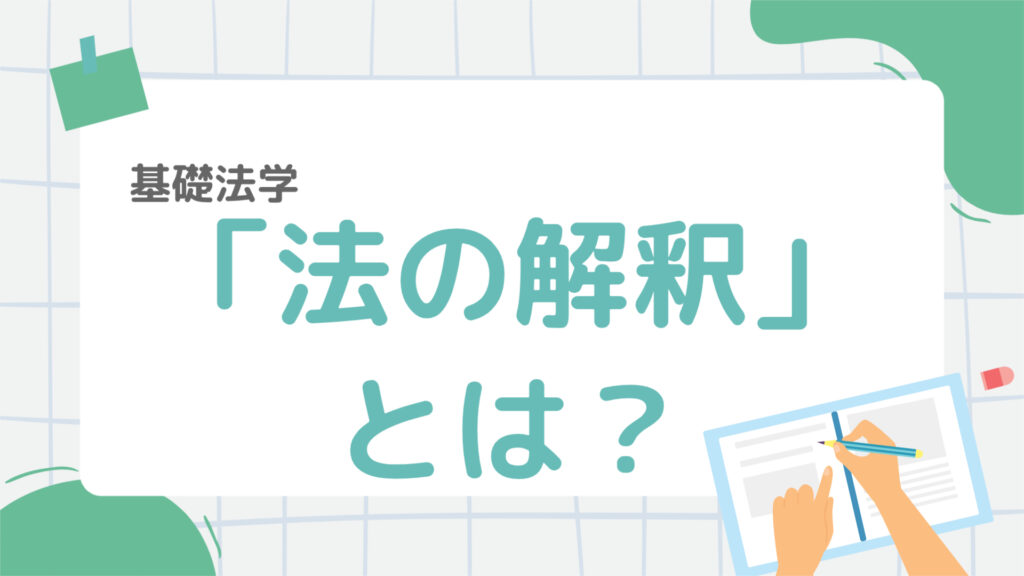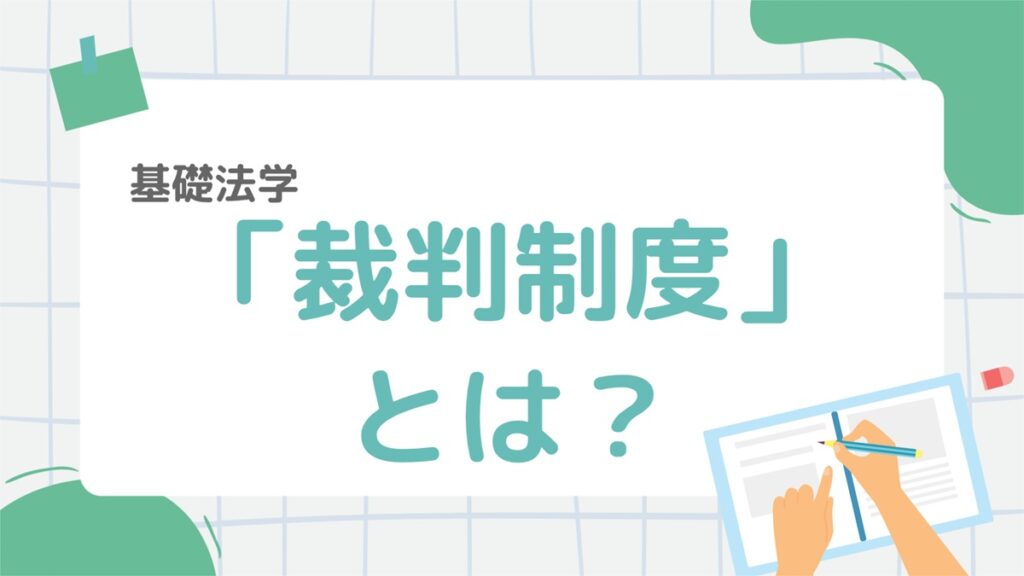基礎法学4:「法律用語」を一気に整理!〜「みなす」「準用」「又は」とは?〜
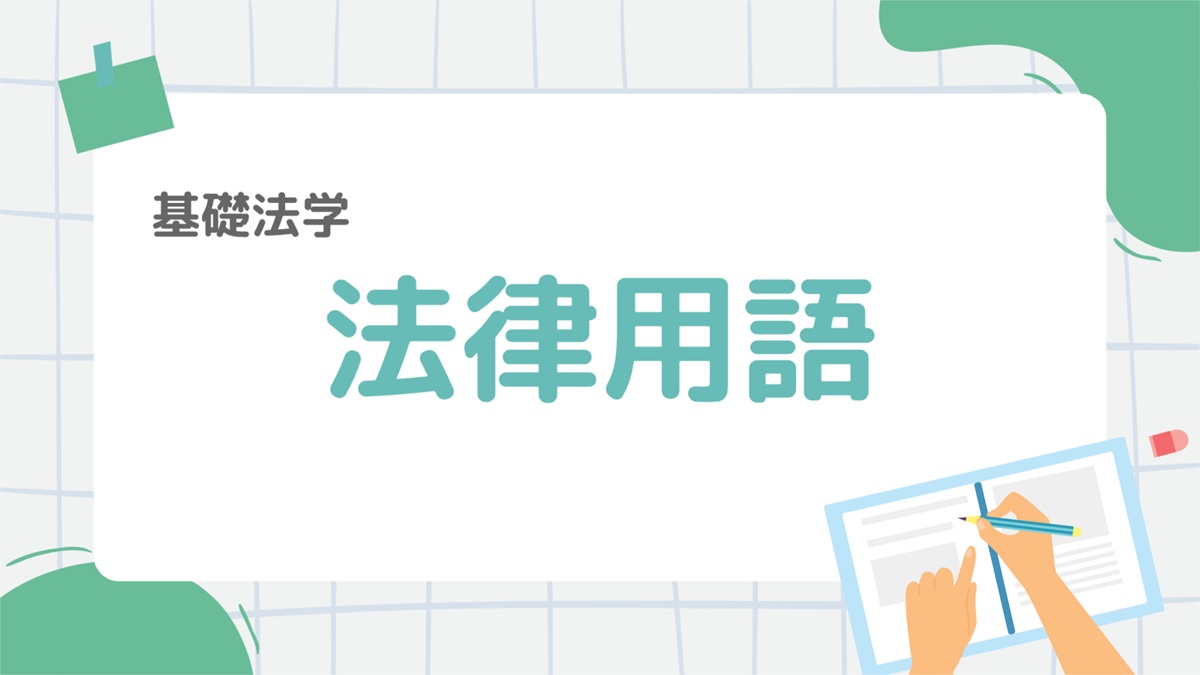
この記事はこんな人におすすめ!
- 行政書士試験に出る「法律用語」の意味や使い分けがよくわからない
- 似たような言葉の違いを明確にして、得点源にしたい
- 「みなす」「推定する」「準用する」など、判別に迷う言葉が多くて困っている
目次
段階的な使い方がされる法律用語
法律には、使い方に段階的なルールがある用語がいくつかあります。具体的には以下のようなものです。
又は・若しくは
選択される語句に段階がある場合、段階がいくつあっても一番大きな選択的接続に「又は」を用い、その他の小さな選択的接続には「若しくは」を用いる。
及び・並びに
並列される語句に段階がある場合、一番小さな並列的接続に「及び」を用い、その他の大きな並列的接続には「並びに」を用いる
意味の紛らわしい法律用語
みなす・推定する
| みなす | 本来性質が違うものを同一のものとして法律が認め、同一の効果を生じさせる |
|---|
| 推定する | ある事実について、当事者間に取り決めがない場合や、反対の証拠が挙がらない場合に、法律が一応こうであろうという判断を下し、そのような取り扱いをすること。 |
|---|
「みなす」⇒反対の証拠が挙がっても覆らない。
「推定する」⇒反対の証拠が挙がれば覆る。
適用する・準用する・例による
| 適用する | その規定が本来の目的としている対象に対して、当該規定をあてはめること。 |
|---|
| 準用する | 他の事象に関する規定を、それに類似する事象について必要な修正を加えてあてはめること。 |
|---|
| 例による | 1つの法令のまとまりのある制度全体を包括的に他の事項にあてはめること。 |
|---|
違法・不当
| 違法 | 法律に違反すること |
|---|
| 不当 | 行為や状態が妥当性を欠くこと(必ずしも違法ではない) |
|---|
権限・権原
| 権限 | ある法律行為・事実行為をすることができる能力 |
|---|
| 権原 | ある法律行為・事実行為をすることを正当であるとする法律上の原因 |
|---|
侵す・犯す
| 侵す | 権利や自由を害すること |
|---|
| 犯す | 刑罰法規で罪とされる行為をすること |
|---|
規定・規程
| 規定 | 法令における個々の条項の定めのこと |
|---|
| 規程 | 法令における一連の条項の総体のこと |
|---|
遅滞なく・速やかに・直ちに
| 直ちに | 一切の遅延が許されない |
|---|
| 速やかに | 「直ちに」と「遅滞なく」の中間 |
|---|
| 遅滞なく | 正当または合理的な理由による遅延は許される |
|---|
期限・期間
| 期限 | 始期以降・終期以前といった不定の時間的を広がりをもつ |
|---|
| 期間 | 始期と終期の間の一定の時間的長さ |
|---|
以上・以下、超える・未満
| 以上・以下 | 基準となる数を含む |
|---|
| 超える・未満 | 基準となる数を含まない |
|---|
その他・その他の
| その他 | 前後の語句を並列に並べる。
例:「A、Bその他C」とある場合、A、B、Cは並列の関係 |
|---|
| その他の | 後の語句が前の語句を含むより広い意味をもつ場合。
例:「A、Bその他のC」とある場合、A、B、Cの例示として、Cに内包される |
|---|
法律要件・法律効果
| 法律要件 | 法律効果を生じさせる原因となる事実のこと |
|---|
| 法律効果 | 法律上の権利義務関係の変動のことを言う |
|---|
立法事実・司法事実
| 立法事実 | 法律を制定する場合、立法の合理性を根拠づける社会的、経済的、政治的、科学的事実のことをいう |
|---|
| 司法事実 | 個別の裁判において、裁判判断の前提として認定される事実 |
|---|
過料・科料
- 過料:行政上の秩序罰
- 「秩序罰としての過料」:秩序罰としての過料は、法令上の義務に違反した場合に科すもの
- 「執行罰としての過料」:行政上の義務を義務者が怠っているときに、行政庁が一定の期限を示し予告して、義務の履行を促すこと ※砂防法のみ
- 「懲戒罰としての過料」:公務員など、公法上特別の法律関係にある場合に、その規律維持のため、義務違反があった場合に科される制裁のこと
- 科料:刑事罰
まとめ
行政書士試験では、法律用語の「正確な理解」が得点に直結します。
特に似た意味に見えて実は大きな違いがある用語は、繰り返し復習しておくと安心です。
こうした用語の使い分けは、実務でも問われるスキルです。試験対策と並行して、実践的な理解も深めておきましょう!