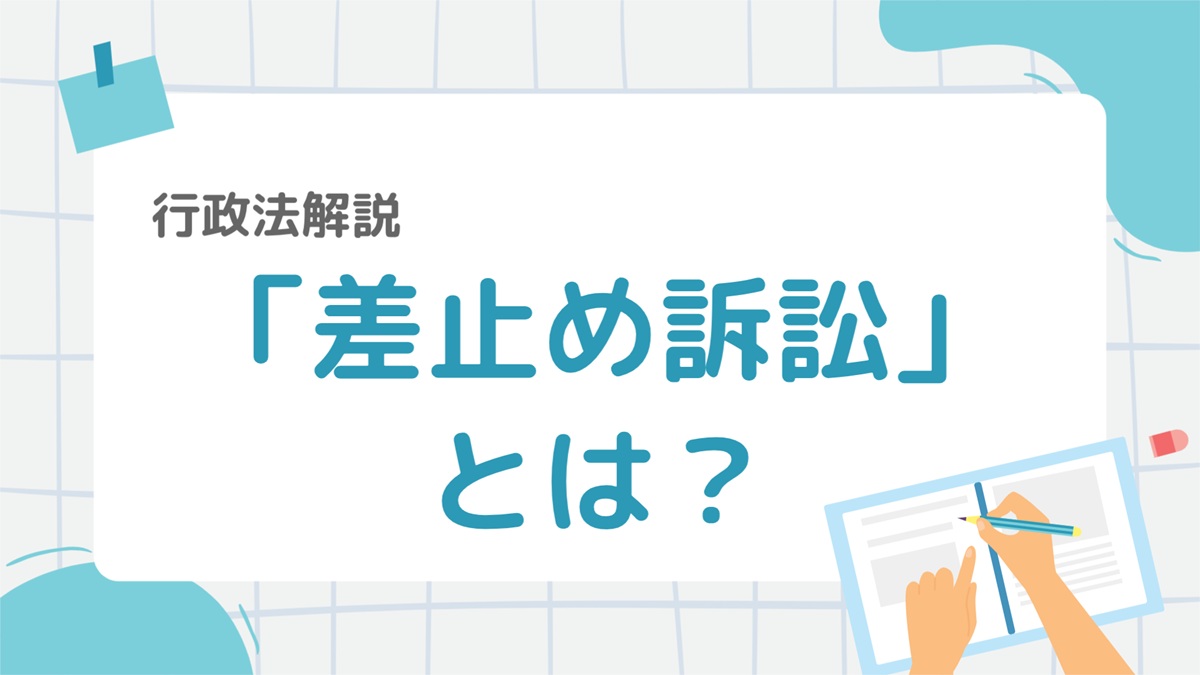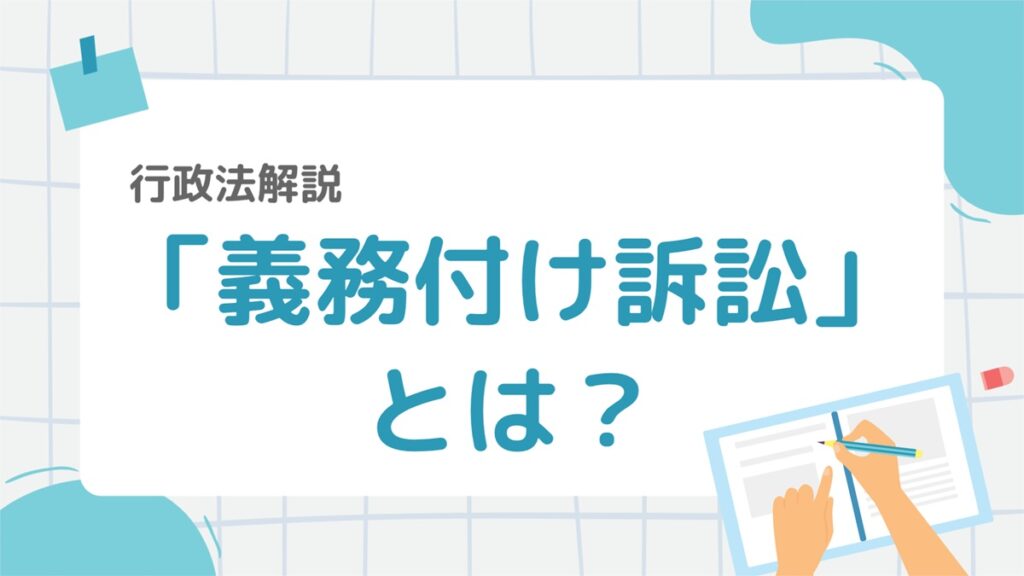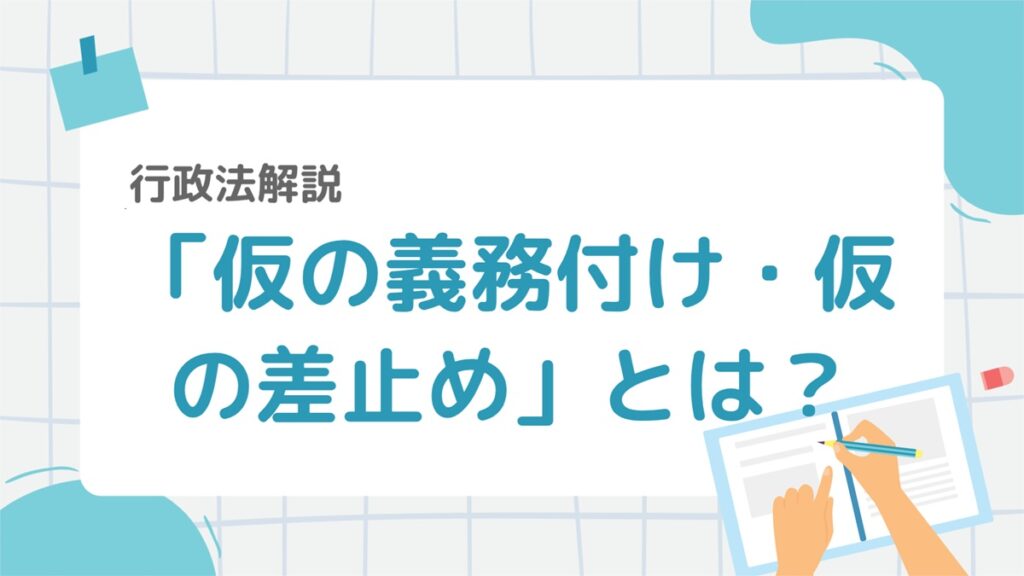この記事はこんな人におすすめ
- 「差止め訴訟」の基本的な仕組みや要件を知りたい方
- 行政書士試験で行政事件訴訟法の得点力をアップさせたい方
目次
差止め訴訟とは?
差止め訴訟とは、行政庁が本来すべきでない処分や裁決をしようとしている場合に、その行政庁に対して「それをやってはいけない」と命じる判決を求める訴訟のことです(3条7項)。
これは、行政機関による処分などによって国民の権利・利益が侵害されるのを未然に防ぐために設けられた制度です。つまり、「起きてからでは遅い」ケースに備えるための法的手段です。1
■行政事件訴訟法の類型
--- config: theme: neutral --- flowchart LR subgraph 取消訴訟以外の抗告訴訟 無効等確認訴訟 不作為の違法確認訴訟 義務付け訴訟 義務付け訴訟 差止め訴訟 仮の義務付け/仮の差止め end subgraph 取消訴訟 処分取消訴訟 裁決取消訴訟 end 行政事件訴訟 --> 主観訴訟["主観訴訟<br>国民の個人的な<br>権利の保護"] 主観訴訟 --> 抗告訴訟 抗告訴訟 --> 法定抗告訴訟 法定抗告訴訟 --> 処分取消訴訟 法定抗告訴訟 --> 裁決取消訴訟 法定抗告訴訟 --> 無効等確認訴訟 法定抗告訴訟 --> 不作為の違法確認訴訟 法定抗告訴訟 --> 義務付け訴訟 法定抗告訴訟 --> 差止め訴訟 抗告訴訟 --> 無名抗告訴訟 主観訴訟 --> 当事者訴訟 当事者訴訟 --> 形式的当事者訴訟 当事者訴訟 --> 実質的当事者訴訟 行政事件訴訟 --> 客観訴訟["客観訴訟<br>客観的な法秩序<br>の適正"] 客観訴訟 --> 民衆訴訟 客観訴訟 --> 機関訴訟 click 処分取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh16-1/" style 処分取消訴訟 color:#1176d4 click 裁決取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh16-1/" style 裁決取消訴訟 color:#1176d4 click 裁決取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh17-1/" style 無効等確認訴訟 color:#1176d4 click 裁決取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh17-2/" style 不作為の違法確認訴訟 color:#1176d4 click 裁決取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh17-3/" style 義務付け訴訟 color:#1176d4 click 裁決取消訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh17-4/" style 差止め訴訟 color:#1176d4,fill:#ffb6c1 click 仮の義務付け/仮の差止め "https://gs.kabudata-dll.com/gh17-5/" style 仮の義務付け/仮の差止め color:#1176d4 click 当事者訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh18-1/" style 当事者訴訟 color:#1176d4 click 形式的当事者訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh18-2/" style 形式的当事者訴訟 color:#1176d4 click 実質的当事者訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh18-3/" style 実質的当事者訴訟 color:#1176d4 click 民衆訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh19-1/" style 民衆訴訟 color:#1176d4 click 機関訴訟 "https://gs.kabudata-dll.com/gh19-1/" style 機関訴訟 color:#1176d4
差止め訴訟を提起するための要件とは?
差止め訴訟を起こすには、以下の条件を満たしている必要があります。
- ① 重大な損害の発生が予想されること(37条の4第1項本文)。
-
処分や裁決がされることで、重大な損害が生じるおそれがある場合は、原則として、差止め訴訟を提起できます。
- ② 他に適切な救済手段がないこと(37条の4第1項但書)。
-
仮にその損害を防ぐために他に適当な方法がある場合は、差止め訴訟を起こすことはできません。
- ③ 法律上の利益を有する者であること(37条の4第3項)。
-
差止めを求める対象について、法律上の利益(法的保護に値する利益)を持っている人だけが訴訟を起こせます。2
なお、被告適格(11条)、裁判管轄(12条)については、取消訴訟の規定が準用されます(38条1項)。
これに対して、出訴期間(14条)については取消訴訟の規定が準用されていないことから、差止め訴訟は機関の制限なく提起することができます。
👉最重要判例:懲戒処分差止訴訟と義務不存在確認訴訟(最判平24.2.9)
👉最重要判例:差止め訴訟の要件(最判平28.12.8)
差止め判決が認められる場合とは?
裁判所が「行政庁はその処分や裁決をしてはならない」と命じる差止め判決を出すには、次のいずれかに該当する必要があります(37条の4第5項)。
- 処分をすべきでないことが処分の根拠法令の規定から明らかであるとき
→ たとえば、法令により処分が絶対に許されない場合などです(行政裁量がないケース)。 - 行政庁の裁量権の逸脱・濫用されていると認められるとき
→ 裁量がある処分であっても、その判断が合理性を欠くときには差止めが認められることがあります。
まとめ:差止め訴訟は「事前に止める」ための重要な救済手段!
差止め訴訟は、行政による不適法な処分や裁決を未然にブロックすることができる、非常に重要な制度です。試験でもポイントとなる「要件」や「判決が認められる場面」はしっかり押さえておきましょう!