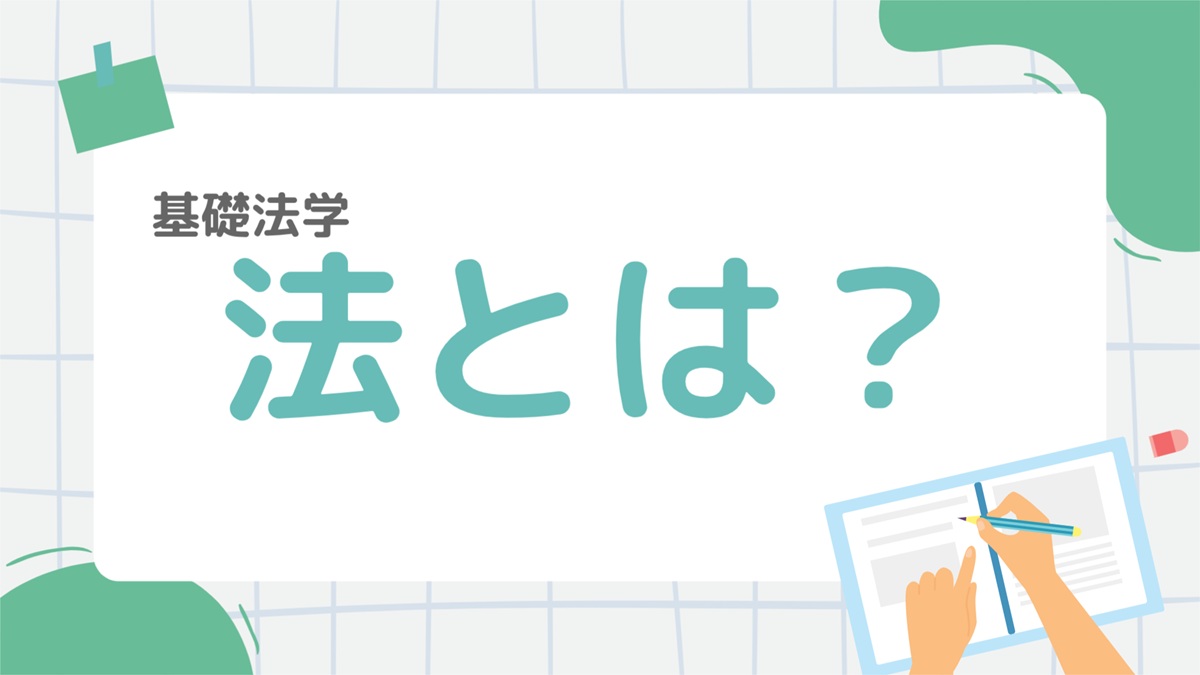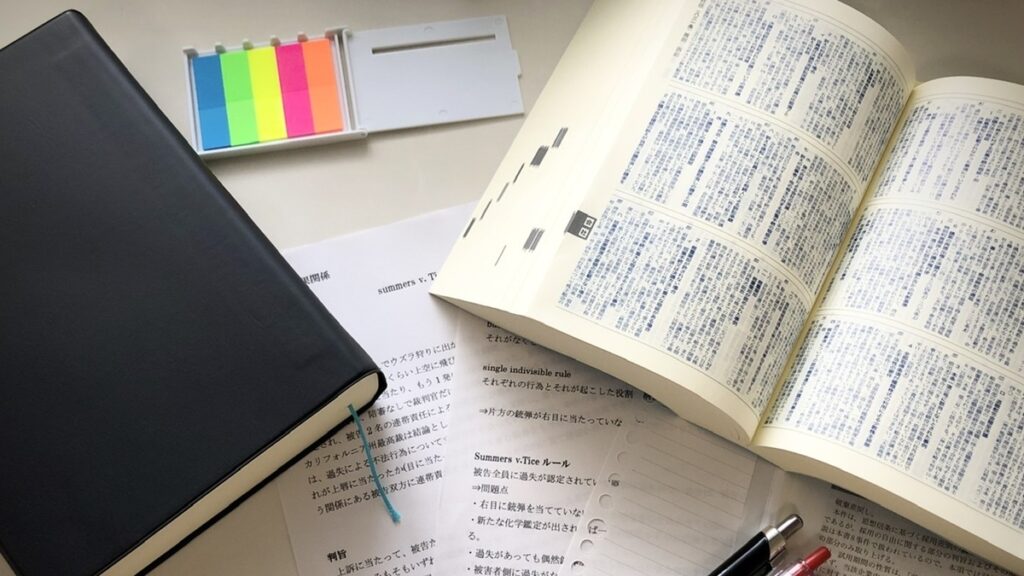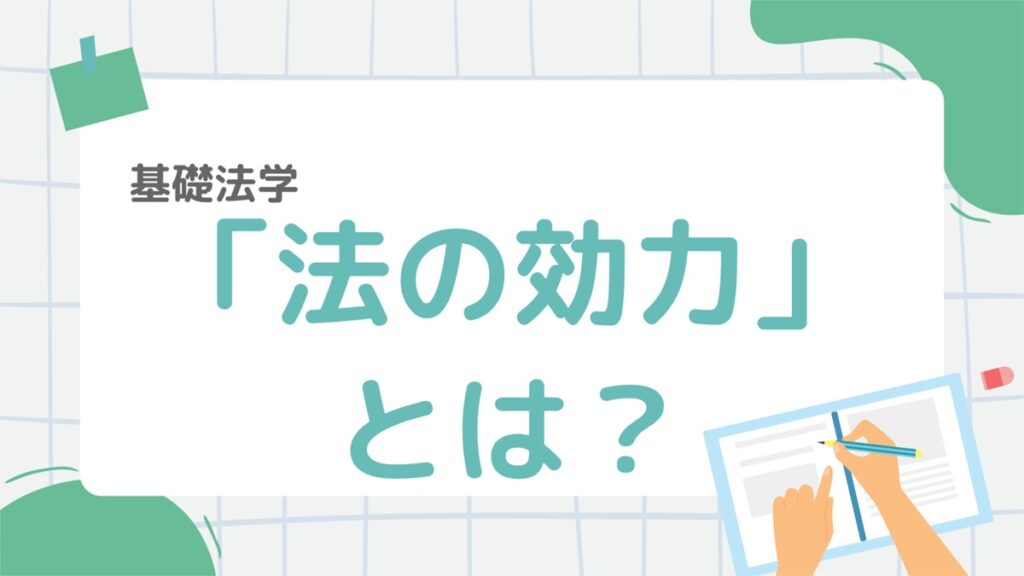- 「法」と「道徳」の違いがいまいちわからない…
- 成文法と不文法の違いをスッキリ整理したい!
- 行政書士試験の基礎法学で得点を取りたい!
- 判例や慣習法などの「不文法」って何なの?と思っている方
法と道徳の違いとは?|社会を支える2つのルール
私たちの生活には、日々無数の「守るべきルール」が存在します。中でも代表的なのが「法」と「道徳」です。これらは社会規範と呼ばれ、社会秩序を保ち、円滑な人間関係を築くために必要な基盤です。
法は社会の秩序を保つために必要なルール(社会規範)であり、個人の自由と社会の安定を両立させる役割を持っています。行政書士試験においても、基礎法学の知識は重要な土台となります。本記事では、法の基本的な概念を詳しく解説します。
✅法と道徳の違い
| 法 | 道徳 | |
|---|---|---|
| 意味 | 国家という政治社会において政治的権力作用を背景に強制される社会規範 | 善を理念として誠実・仁義等の多元的な価値判断をなす社会規範1 |
| 特徴 | ①国家による制裁(サンクション)を伴うものである ②人間の外面的な行為に関係する規範 ③法的義務には原則として相手方が存在する ④法的義務は他の動機に基づいて行われることを許容する | ①国家による制裁(サンクション)を伴うものではない ②人間の内心に関係する規範 ③道徳上の義務には相手方が存在しない ④道徳上の義務はそれが自らの意思により行われることを要求する |
✅ 覚えておこう!
法律は「外からの強制力」、道徳は「内からの自発的な心」が基本。
成文法(制定法)とは?|日本の法体系の中心
法は、文章で表現され、所定の手続きに従って定立される成文法(制定法)と、社会における実践的慣行を基礎として成立する不文法とに分類されます。行政書士試験では、この成文法が基本知識として問われます。
成文法主義とは?
日本は「成文法主義」を採用しており、原則として成文法が最も優先される法源1です。
成文法主義には以下のようなメリットとデメリットがある。
メリット
- 明確な行動基準を示せる。
- 裁判官にとって明確な判断基準となる。
デメリット
- 時代の変化に即応しにくい。
- すべての状況をカバーしきれない。
成文法の分類
①公法・私法・社会法
| 意味 | 具体例 | |
|---|---|---|
| 公法 | 国家の統治権の発動に関する法 | 憲法・行政法・刑法・訴訟法 |
| 私法 | 私人間の法律関係を規律する法 | 民法・商法 |
| 社会法 | 生存権理念に基づき、私的自治に対する国家権力または集団的自治による制限を定める法 | 労働法・社会法 |
②実体法と手続法
| 意味 | 具体例 | |
|---|---|---|
| 実体法 | 権利・義務の種類・変動・効果を規律する法 | 民法・刑法・商法 |
| 手続法 | 実体法を具体的事件に適用する手続に関する法 | 訴訟法・不動産登記法・戸籍法 |
成文法相互の関係
①上位法と下位法
成文法には、上下関係があります。以下の表は、上位法から下位法へと並べています。
成文法の上下関係
| 憲法 | 国の根本について定めた法 | |
| 法律 | 国会が制定した法 | |
| 命令 | 政令 | 内閣が制定した法 |
| 内閣府令 | 内閣総理大臣が制定した法 | |
| 省令 | 各省大臣が制定した法 | |
| 規則 | 委員会や庁の長官が制定した法 | |
| 条例 | 地方公共団体の議会が制定した法 | |
| 規則 | 地方公共団体の長が制定した法 | |
その他
| 通達・訓令 | 上級行政機関が下級行政機関に出す命令や指示 |
| 要綱 | 行政内部のマニュアル |
| ガイドライン | 法律や条例に、「指針を策定する」や「指導及び助言その他の措置を講ずる」などの規定がある場合に、こうした規定を受けて定められる |
②一般法と特別法
一般法とは、ある事項について一般的に規定した法令のことであり、特別法とは、同じ事項について特定の場合または特定の人・地域に限って適用される法令のこと。
一般法と特別法の間では、特別法が一般法に優先して適用され、一般法は特別法に規定のない事項についてのみ補充的に適用される。
③前法と後法
時間的に後に制定された法(後法)は、先に制定された法(前法)に優先して適用される。
④基本法
教育基本法・環境基本法など「基本法」という名称を持つ法律であっても、各議院の通常の多数決を経て制定される。また、通常の法律をもって基本法の規定を改廃することもできる。
不文法とは?|文章化されていないけど法的に意味を持つルール
不文法とは、文章として制定されていないが、法的効力を持つルールです。以下のような種類があります。
- 判例
- 判例とは何か
判例とは、先例として機能する裁判例・判決例のこと。
判例は、一般的見解によれば、英米法系の国では後の事件に対して法的な拘束力を有する法源とされてきたが、大陸法系の国では法源とされてこなかった。
しかし、日本では、大陸法系の国と同様に成文法主義をとっているにもかかわらず、先例としての判例に従うことが裁判実務上の慣行となっており、判例も法源とされている。 - 判決理由の効力
英米法系の国では、判決理由のうち結論を導く上で必要な部分をレイシオ・デシデンダイ、それ以外の部分を傍論(オビタ・ディクタム)と呼び、前者には判例法としての拘束力を認めているが、後者にはこれを認めていない。
- 判例とは何か
- 慣習法
- 慣習法とは何か
慣習法とは、社会において一定の行動様式が繰り返し継続的に行われることによって定着し、かつ、社会の構成品がそのような慣習を自分たちの行動の正当化理由として用いることによって法として確信するようになった場合に成立するもののこと - 慣習法の要件
公の秩序または善良な風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたものまたは法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。(法の適用に関する通則法3条) - 任意規定と異なる慣習
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。(民法92条)
民法は強行規定ではなく、任意規定(公の秩序に関しない規定)に関して、慣習が法律行為の基準として実質的に法源となることを認めている。 - 商習慣
商事に関しては、商法に定めがない事項については商習慣に従い、商習慣がない時は、民法の定めるところによるとされている。(商法1条2項) - 慣習刑法の禁止
犯罪と刑罰の内容は、あらかじめ法律によって制定されたものでなければならないから(これを罪刑法定主義という)、慣習法は刑法の直接の法源とはならない。
- 慣習法とは何か
- 条理
条理とは、社会生活において相当多数の人々が一般的に承認している道理・筋道のこと。
日本では、1875年(明治8年)の太政官布告103号裁判事務心得3条が条理の法源性を認めた根拠とみられている。
まとめ|法は社会を支える見えないインフラ
法律や道徳は、私たちの生活を支える根幹的なルールです。成文法・不文法を含む多様な法体系を理解することは、行政書士試験においても必須です。基礎法学の最初の一歩として、ここで学んだ内容をしっかり押さえておきましょう。