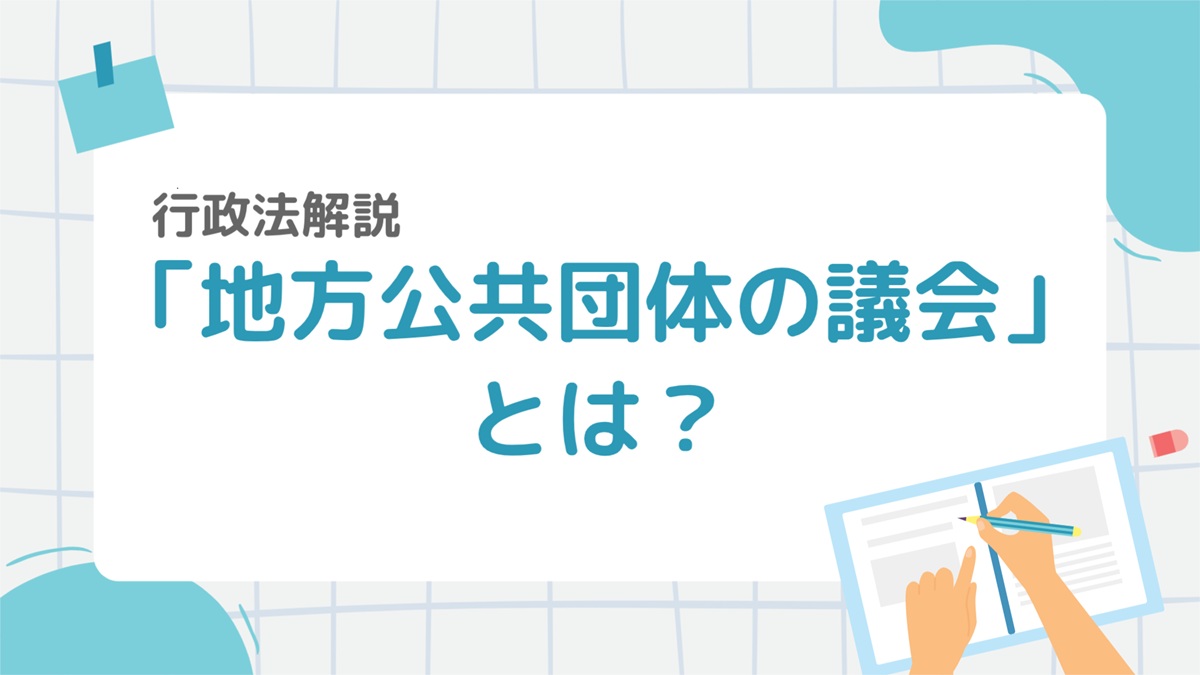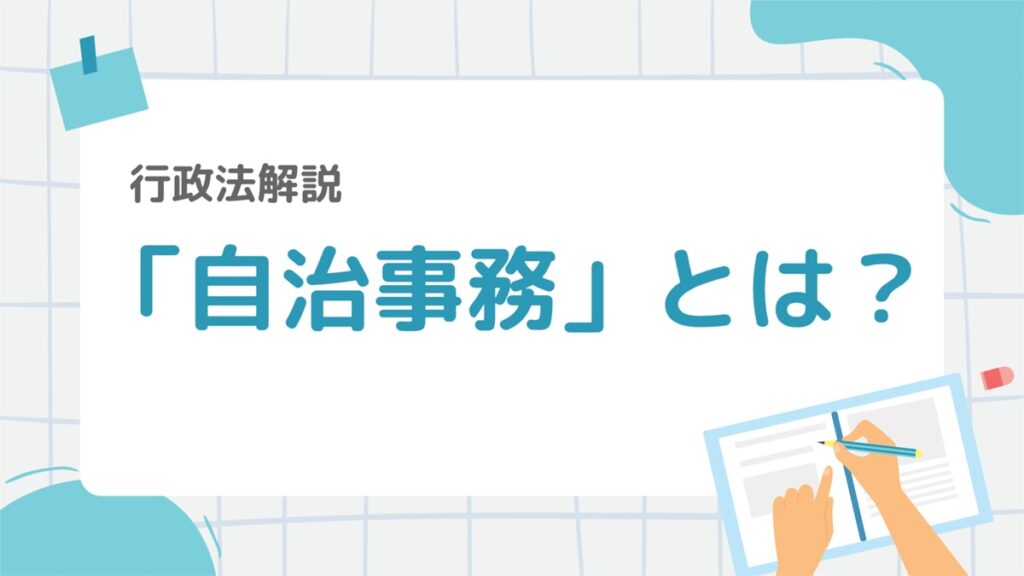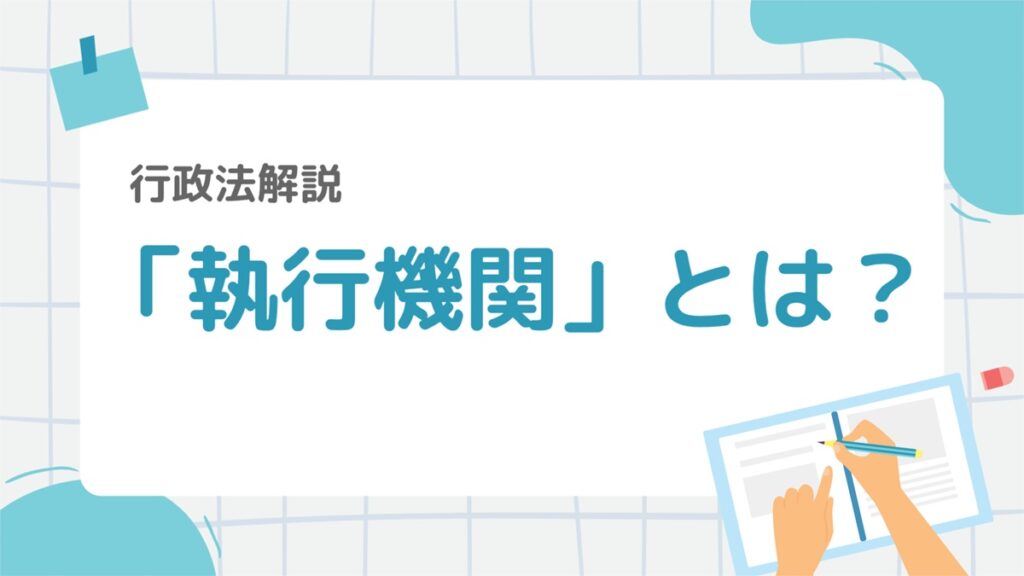- 「地方自治法」に出てくる議会の仕組みを簡単に理解したい方
- 行政書士試験で問われる「地方公共団体の議会」のポイントを効率よく押さえたい方
- 憲法・地方自治法の横断整理をしたい方
地方公共団体の議会とは?基本的な立ち位置
地方公共団体には、憲法93条1項と地方自治法89条1項に基づき、議事機関として「議会」が設置されます。議会は、住民によって直接選ばれた議員によって構成され、条例の制定や予算の議決など、地域の運営における重要な役割を担っています。1
ここでポイントなのが、「長(知事や市町村長)」と「議会」は対等な関係にあるということ。国政における「国会と内閣」の関係とは違い、どちらも住民の直接選挙で選ばれるため(憲法93条2項)、権限上の上下関係はありません。
議会の構成:議員とリーダー役
議会は、議員とその中から選挙される議長・副議長で構成されます。
議員の基礎知識
- 任期:4年(地方自治法93条1項)
- 兼職禁止:衆議院議員・参議院議員(92条1項)や他の自治体の議員・常勤の職員・短時間勤務職員との兼職はNG(92条)
- 議案提出権:議員定数の12分の1以上の賛成があれば可能(ただし予算案は不可)(112条1項本文・2項)。
議長と副議長
- 議会の中から1名ずつ選ばれる(103条1項)。
- 議長:議会の運営責任者。議場の秩序維持・議事進行・議会の代表役を担う(104条)。
また、委員会に出席し、発言することができる(105条)。 - 副議長:議長が不在(事故があるとき)のときに代理を務める(106条1項)。
議会の活動:会議の流れを知ろう
召集
議会の招集は、基本は「長」、必要に応じて議員の請求で臨時会も(101条1項・2項・3項)。
臨時会の場合、議長は議会運営委員会の議決を経て、議員定数の4分の1以上の者はこの議決を経ずに、長に対して会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができます(101条2項・3項)。
※参考:議会の招集請求があったときは、長は、請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければならない(101条4項)。
さらに、議長等の臨時会の招集請求に対して長が召集しないときは、議長が臨時会を招集することができます(101条5項)。
会期
地方公共団体の議会も、国会と同様に、1年を通じて常に活動しているわけではなく、活動するのは一定の期間(会期)に限られています。
会期には、定例会と臨時会の2種類がある(102条1項)。
もっとも、条例により、定例会・臨時会の区分を設けず、通年の会期(条例で定める日から翌年の当該日の前日まで)とすることもできる(102条の2第1項)。
議事・議決のルール
・定足数:議員定数の半数以上(113条本文)
・表決方法:過半数で決定、同数の場合は議長が決定(116条1項)
議会は、議員定数の半数以上が出席しなければ、議事を開き議決をすることができません(113条本文)。国会の定足数は3分の1以上でしたが、地方公共団体の議会の定足数は、これよりも厳しく設定されています。2
また、議会の議事は、出席議員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長が決定権をもちます(116条1項)。このように、表決数については、国会と同様です。3
会議の公開
・原則公開(115条1項本文)
・特例:出席議員の3分の2以上の同意があれば「秘密会」も可能(115条1項但書)
議会の会議は、国会の場合と同様、公開が原則(115条1項本文)。ただし、議長または議員3人以上の発議により出席議員の3分の2以上の多数で議決した場合は秘密会とすることができます(115条1項但書)。
議会のもつ権限とは?
議会は、地方自治法96条1項に列挙された事項に対する議決権を持ちます。主なものは以下のとおりです。4
- 条例の制定・改廃
- 予算の議決・決算の認定
- 契約の締結
- 財産の取得・処分
また、列挙された事項以外であっても、法定受託事務に係るものであって国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除き、条例で議決事項を追加することができる(96条2項)。
これらに加え、次のようなチェック機能もあります。
| 検査権・監査請求権(98条1項) | 調査権(100条1項) | |
|---|---|---|
| 意味 | 地方公共団体の事務に関する書類・計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長や行政委員会の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査する権限 | 地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭および証言ならびに記録の提出を請求する言々 |
| 除外理由 | 自治事務にあっては、労働委員会・収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるもの、法定受託事務にあっては、国の安全を害するおそれがあることその他の事由により対象とすることが適当でないものとして政令で定めるもの | |
委員会制度:本会議だけじゃない!
議会の意思決定は本会議で行いますが、実務は委員会に分かれて一定の分野を集中的に審議されます。
- 常任委員会5
その部門に関する調査や議案・陳情の審査などを行う常設の委員会(109条2項) - 議会運営委員会
議会の運営・会議規則に関する事項や議長の諮問に関する事項などを調査する常設の委員会(109条3項) - 特別委員会6
議会の議決により付議された事件を審査する特別の必要がある場合に設置される委員会(109条4項)
※いずれも議会の判断で設置可(109条1項)。
請願
普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない(124条)。
解散
議会が解散するのは、次のような場合。
- 住民による議会の解散請求があり(76条)、解散の投票において過半数の同意があった場合(78条)。
- 長の不信任議決があり、長が議会を解散した場合(178条1項)。
- 議員数の4分の3以上の者が出席し、その5分の4以上の者が同意した場合(地方公共団体の議会の解散に関する特例法2条)。
まとめ:地方公共団体の議会は、住民自治の根幹!
地方自治体の議会は、地域の意思を反映し、長と対等な立場で地域運営に関わる重要な存在です。行政書士試験では、憲法・地方自治法の横断的な理解が求められるため、議会の構成・機能・手続きの流れをしっかり整理しておきましょう!