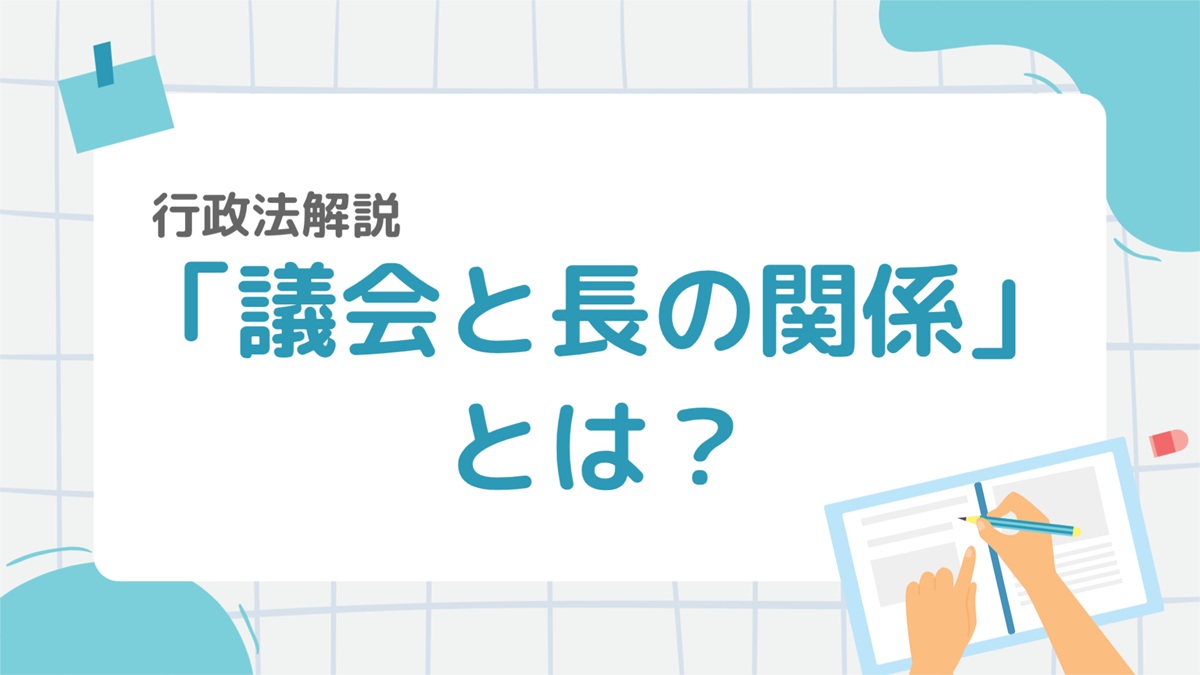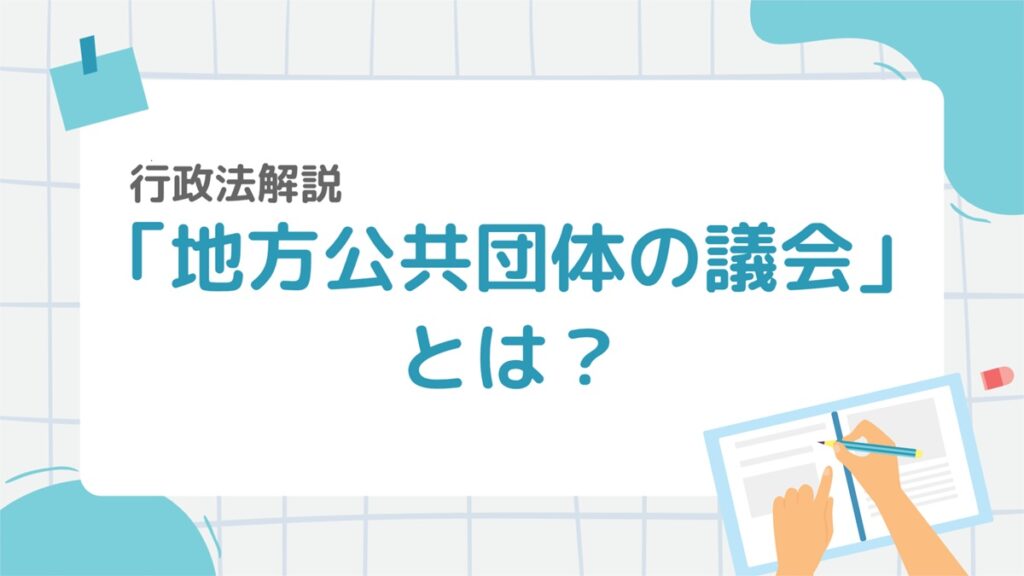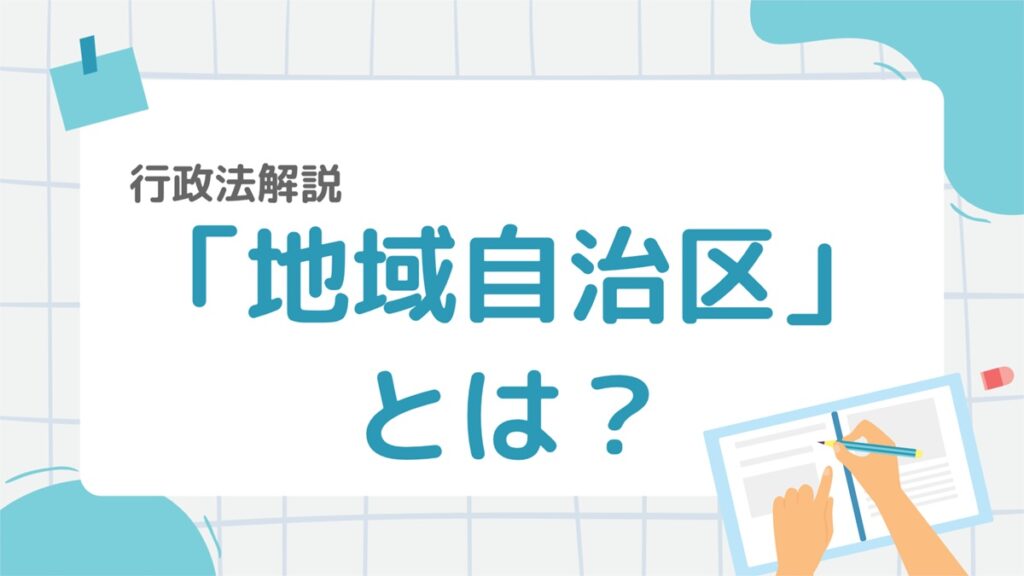- 行政書士試験で地方自治法のポイントを押さえたい方
- 「議会と長の関係」「専決処分」などの用語が曖昧で困っている方
- 首長主義の基本と実務的な運用の仕組みを一度で理解したい方
首長主義とは?議会と長の関係性
地方公共団体では、議会の議員も、長(市長や町長など)も住民による直接選挙で選ばれます(憲法93条2項)。このような制度のもとでは、「首長主義」という考え方が採られており、議会と長は互いにけん制し合いながら職務を行うことが前提です。
たとえば、議会と長の間で意見が食い違ったとき、長は議会の議決に再考を求めること(再議要求)ができます。これがいわゆる「長の拒否権」です。
逆に、議会が長に対して不信任(不信任議決)を突きつけることも可能であり、長はそれに対抗して議会を解散することもできます。これは国政における「議院内閣制」に似た構造ですね。
--- config: theme: neutral --- flowchart LR 議会 ---->|不信任議決| 長 長 ---->|拒否権・解散| 議会
長の拒否権:一般的拒否権と特別拒否権
長の拒否権には2種類あります。
- 一般的拒否権:議会の議決に異議がある場合に、任意で再議を求めることができるもの。
- 特別拒否権:一定の要件があるときに、長が必ず拒否権を行使しなければならないもの。
いずれの場合も、長が再議を求めるときには、その理由を議会に示す必要があります(176条1項、177条)。
拒否権の詳細は次の通りです。
| 要件 | 行使 | 再度同じ議決がされた場合 | |
| 一般的 拒否権 | 議会の議決について異議があるとき(176条1項) | 任意 | 条例・予算について異議があるときは、出席議員の3分の2以上の者の同意により、それ以外のときは、過半数の同意により、同じ議決がされた場合、その議決が確定する(176条2項・3項) |
| 特別 拒否権 | 議会の議決・選挙がその権限を超えまたは法令・会議規則に違反すると認めるとき(176条4項) | 義務 | 審査の申立てができる(176条5項)1 |
| 普通地方公共団体の義務に属する経費を削除し、または減額する議決をしたとき(177条1項1号) | 義務 | その経費およびこれに伴う収入を予算に計上して支出できる(177条2項) | |
| 非常の災害による応急・復旧の施設または感染症予防のために必要な経費を削除し、または減額する議決をしたとき(177条1項2号) | 義務 | その議決を不信任の議決とみなすことができる(177条3項) |
議会の不信任議決と長の対応
議会が長に対して不信任を突きつけた場合、その後の流れは以下の通りです。
初回の不信任議決
議会が長の不信任議決をするためには、議員数の3分の2以上の者が出席し、4分の3以上の者の同意がなければならない(178条3項)。
議長から不信任議決をした旨の通知を受けた長は、その通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができる(178条1項)。
そして、長が議会を解散しなかった場合、長は、通知を受けた日から10日を経過した日に失職する(178条2項)。
再度の不信任議決
長が議会を解散し、解散後初めて招集された議会において再び不信任議決をするには、議員数の3分の2以上の者が出席し、その過半数の者の同意がなければならない(178条3項)。
また、長は、議長から再び不信任議決をした旨の通知があった日に失職する(178条2項)。
■長の不信任と議会の解散フロー図
--- config: theme: neutral --- flowchart LR 初回の不信任議決["初回の不信任議決<br>・2/3以上出席<br>・3/4以上同意"] 再度の不信任議決["再度の不信任議決<br>・2/3以上出席<br>・過半数同意"] 初回の不信任議決 -->|10日以内| 議会の解散 議会の解散 -->|招集| 再度の不信任議決 再度の不信任議決 -->|通知| 長が失職 初回の不信任議決 -->|解散せずに<br>10日経過| 長が失職
緊急時の対応:専決処分とは?
長は、特定の状況下で議会の議決を経ずに単独で決定を下すことができます。これを「専決処分(せんけつしょぶん)」といいます(179条1項本文)。23
【専決処分が認められる場合】
- 議会が成立しないとき
- 所定の理由により会議が定足数に達せず開催できないとき
- 緊急で議会を招集する時間がないことが明らかであるとき
- 議会が議決すべき事件の議決をしないとき
長はこのような場合、議会の議決事項を自ら処理することができます。
【専決処分後の対応】
長の議場出席義務
議会での審議に関して、議長が長に出席を求めた場合、原則として出席義務があります(121条1項本文)。
ただし、正当な理由で出席できない場合は、その旨を議長に届け出れば免除されます(121条1項但書)。
📝まとめ
地方自治体における「議会と長の関係」は、首長主義という制度のもと、互いにけん制し合いながら職務を遂行する仕組みとなっています。
長の拒否権や議会による不信任議決、さらには専決処分といった制度は、バランスの取れた地方行政の運営を実現するために重要な役割を果たしています。
とくに、拒否権の種類(一般的・特別)や不信任議決の手続き要件、専決処分の条件と流れは頻出テーマなので、正確に押さえておくことが合格への近道です。
- 参考:創部大臣または都道留県知事は、審査の結果、議会の議決・選挙がその権限を超えまたは法令・会議規則に違反すると認めるときは、その議決・選挙を取り消す旨の裁定をすることができ(176条6項)、その裁定に不服があるときは、議会または長は、最低のあった日から60日以内に裁判所に出訴することができる(176条7項)。 ↩︎
- 参考:専決処分をすることができるのは長のみであり、行政委員会(行政委員)は、専決処分をすることができない。 ↩︎
- 参考:副知事・副市町村長、指定都市の総合区長の選任は、専決処分の対象から除外されている(179条1項但書)。 ↩︎
- 参考:条例・予算の専決処分について議会が不承認としたときは、長は、必要と認める措置を講じ、議会に報告しなければならない(179条4項)。 ↩︎