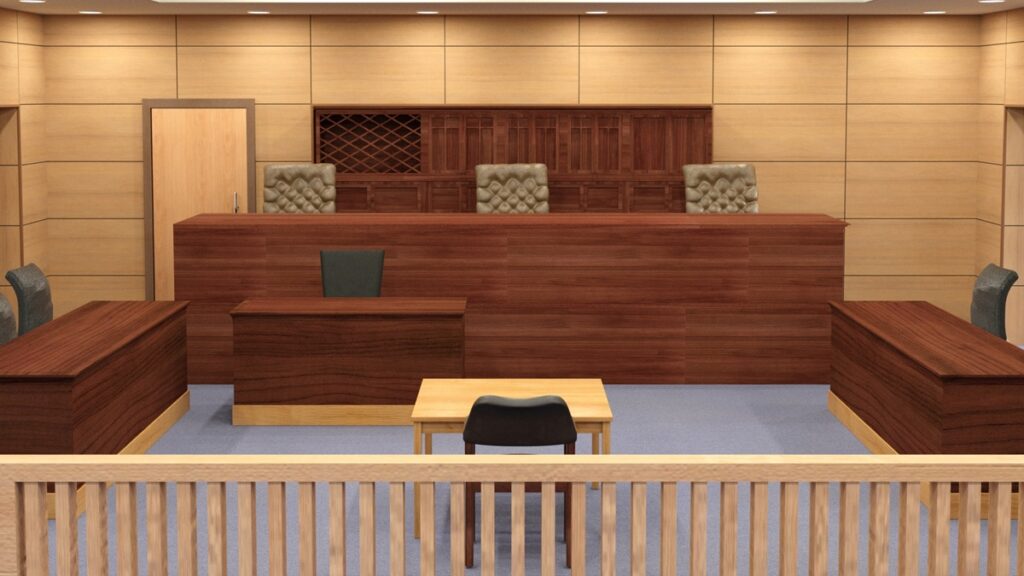事案
女性について6カ月の再婚禁止期間を設けていた当時の民法733条1項の規定が憲法14条1項に違反しないかが争われた。
結論

民法733条1項の規定のうち、100日の再婚禁止期間を設ける部分は合憲、100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は違憲。
判旨
- ①100日の再婚禁止期間を設ける部分について
-
民法733条1項の立法目的は、父性の推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解されるところ、女性の再婚後に生まれる子については、計算上100日の再婚禁止期間を設けることによって、父性の推定の重複が回避されることになる。
夫婦間の子が嫡出子となることは婚姻による重要な効果であるあるところ、嫡出子について出産の時期を起点とする明確で画一的な基準から父性を推定し、父子関係を早期に定めて子の身分関係の法的安定を図る仕組みが設けられた趣旨に鑑みれば、父性の推定の重複をさけるため100日について一律に女性の再婚を制約することは、婚姻及び家族に関する事項について国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えるものではなく、立法目的との関連において合理性を有する。
- ②100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分について
-
婚姻をするについての自由が憲法24条1項の規定の趣旨に照らし十分尊重されるべきものであることや妻が婚姻前から懐胎していた子を産むことは再婚の場合に限られないことを考慮すれば、再婚の場合に限って、前夫の子が生まれる可能性をできるだけ少なくして家庭の不和を避けるという観点や、婚姻後に生まれる子の父子関係が争われる事態を減らすことによって、父性の判定を誤り血統に混乱が生ずることを避けるという観点から、厳密に父性の推定が重複することを避けるための機関を超えて婚姻を禁止する期間を設けることを正当化することは困難である。
他にこれを正当化し得る根拠を見出すこともできないことからすれば、民法733条1項のうち100日超過部分は、合理性を欠いた過剰な制約を課すものとなっている。
👉憲法4:「幸福追求権」とは?憲法13条から読み解く新しい人権と平等原則