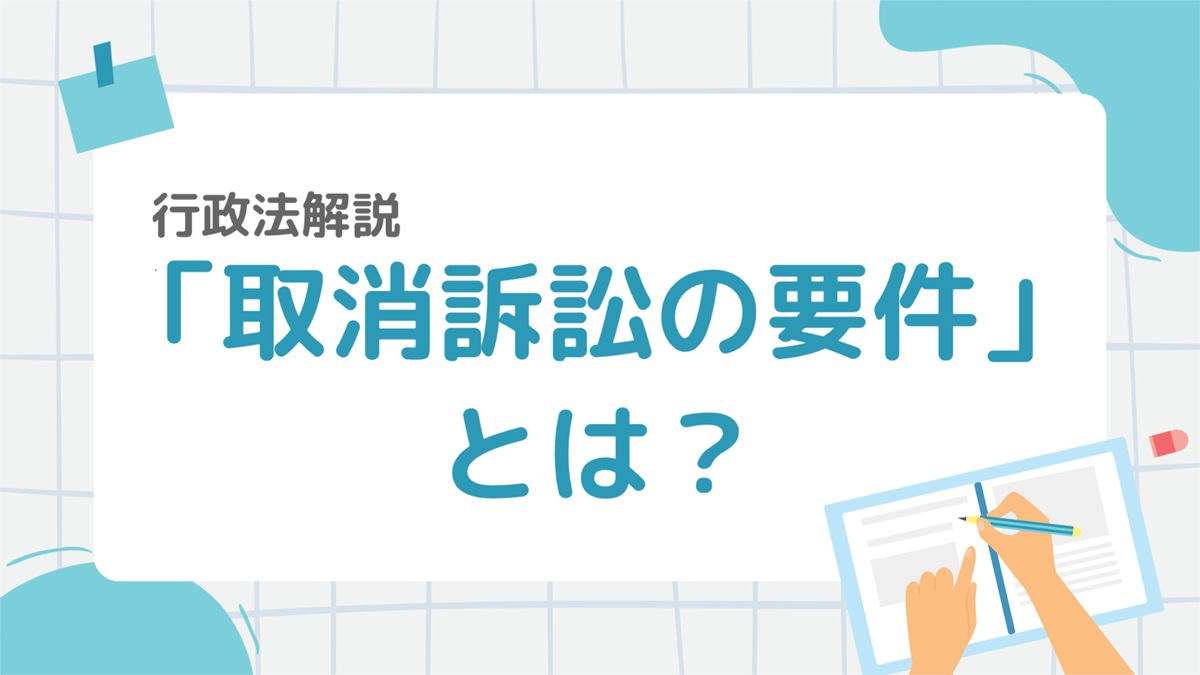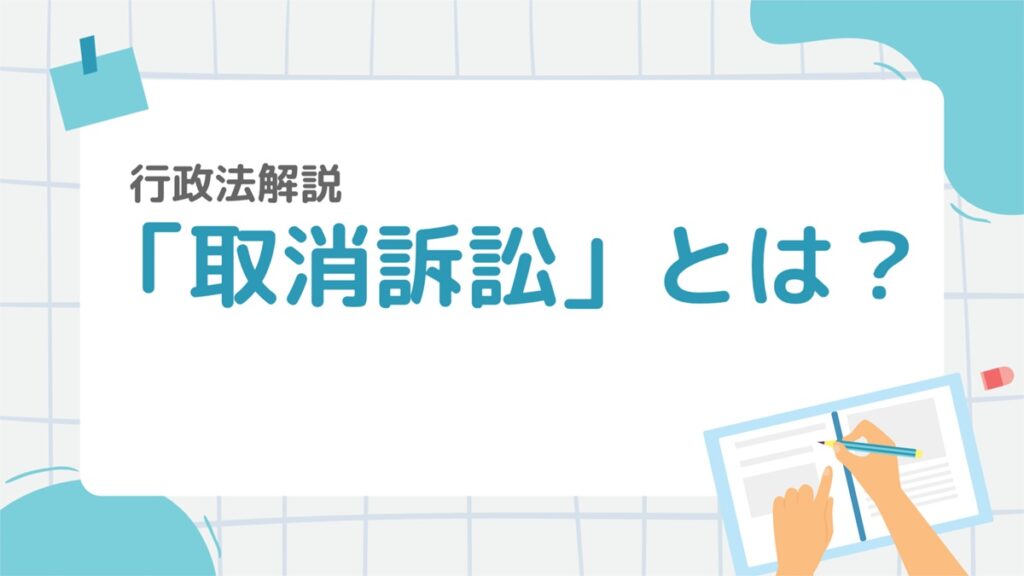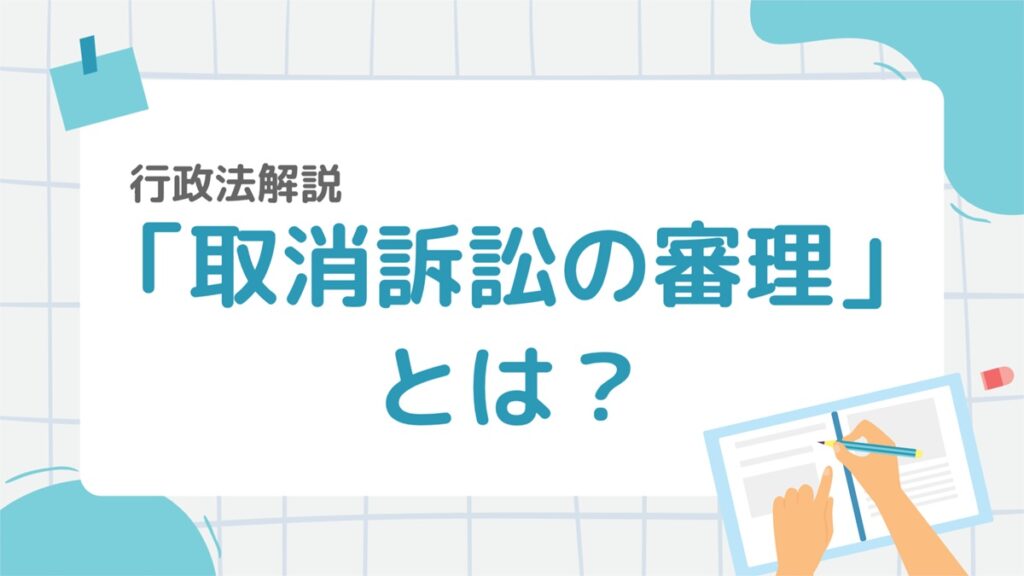- 行政書士試験の「行政事件訴訟法」の出題対策をしたい方
- 「取消訴訟」がどんなときに提起できるのか理解したい方
- 訴訟要件の「処分性」や「原告適格」など、難解な用語を噛み砕いて覚えたい方
✅ はじめに:取消訴訟の「訴訟要件」とは?
取消訴訟の流れは次の通りです。
--- config: theme: neutral --- flowchart LR 訴えの提起 --> 訴訟要件の調査 訴訟要件の調査 --"要件あり"--> 審理 審理 --> 判決 訴訟要件の調査 --"要件なし"--> 却下
行政処分に不満があるからといって、誰でもすぐに取消訴訟を起こせるわけではありません。
訴えが適法かどうかを判断する「訴訟要件」を満たしていないと、裁判そのものが受け付けられないのです。これは、違法な訴訟を排除することにで、裁判を開いたり相手方の裁判所に出頭させたりする時間と労力の無駄を省くためです。
取消訴訟の訴訟要件は全部で 7つ。1つでも欠ければ、訴訟は原則「却下」されてしまいます。
このページでは、それぞれの訴訟要件についてわかりやすく解説します。
✅ 取消訴訟の7つの訴訟要件とは?
| 要件名 | 内容のポイント |
|---|---|
| 処分性 | 行政庁の処分または裁決が存在すること |
| 原告適格 | 訴訟を提起する資格をゆうしていること |
| 訴えの利益 | 訴訟を提起する実益があること |
| 被告適格 | 相手方を間違えずに訴訟を提起していること |
| 裁判管轄 | 管轄する裁判所に対して訴訟を提起していること |
| 出訴期間 | 法定の期間内に訴訟を提起していること |
| 審査請求前置 | 法律によって審査請求に対する裁決を経た後でなければ訴訟を提起することができないとされている場合に、これを経ること |
① 処分性:争う対象は「処分」か?
処分性とは、争われる対象が「処分」であることを意味します。
ここでいう「処分」とは、国や公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものです(最判昭39.10.29)。
また、国または公共団体が行う行為であっても次の行為は原則「処分性」が否定されます。
✋処分性が否定される代表例
- 行政機関内部の事務連絡や命令(内部行為)
- 手続の途中での決定(中間的行為)
- 単なる意見や見解(事実行為)
- 条例や規則の制定(規範定立行為)
ただし、判例ではこれらの例外的に処分性を認めたケース(判例)もあるため、柔軟な判断が必要です。
👉最重要判例:土地区画整理事業の事業計画決定の処分性(最大判平20.9.10)
👉最重要判例:特定の保育所を廃止する条例の制定の処分性(最判平21.11.26)
■その他の処分性に関する判例
| 認められる | 認められない | |
| 私法上の行為 | 供託金取戻請求に対する供託官の却下(最大判昭45.7.15) 労働基準監督署長による労災就学援護費の支給決定(最判平15.9.4) | 国有財産法上の普通財産の払い下げ(最判昭35.7.12) 農地法に基づく農地の売払い(最大判昭46.1.20) |
| 内部的行為 | – | 建築許可に対する消防長の同意(最判昭34.1.29) 通達(最判昭43.12.24) |
| 中間的行為 | 第二種市街地再開発事業計画の決定(最判平4.11.26) 土地区画整理事業の事業計画の決定(最大判平20.9.10) | 都市計画決定としてなされる用途地域の指定(最判昭57.4.22) |
| 事実行為 | 輸入禁制品該当の通知(最判昭54.12.25) 病院開設中止勧告(最判平17.7.15) 登録免許税の還付請求に対する拒否通知(最判平17.4.14) | 反則金の納付通知(最判昭57.7.15) 開発許可に係る公共施設管理官の同意(最判平7.3.23) 市町村長が住民票に世帯主との続柄を記載する行為(最判平11.1.21) |
| 規範定立行為 | 建築基準法42条2項の道路指定が告示による一括指定の方法でされた場合(最判平14.1.17) 特定の保育所を廃止する条例の制定(最判平21.11.26) | 簡易水道事業の水道料金を改定する条例の制定(最判平18.7.14) |
② 原告適格:「法律上の利益」を持つ者だけが原告になれる
- ①原告適格とは?
-
原告適格とは、個別の事件において訴訟を提起する資格のことをいいます。
取消訴訟の原告適格は、処分・裁決の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」に限り認められます(9条1項)。1
そして、「法律上の利益を有する者」とは、その処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害されまたは必然的に侵害されるおそれのある者をいいます(最判平1.2.17)。
- ②✅ 処分の相手方でない人もOK?
-
たとえば、近隣住民が建築許可処分に異議を唱えるケースのように、処分の相手方以外でも「法律上の利益」があれば原告になれます。
9条2項では、処分の相手方以外の者について「法律上の利益」を有するか否かを判断する際の考慮事項が明示されています。これは、「法律上の利益」の有無を判断する際の考慮事項を法定することで、取消訴訟の原告適格を拡大しようとしたものです。
- 当該処分・裁決の根拠法令の趣旨・目的
根拠法令の趣旨・目的を考慮するにあたっては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときは、その趣旨・目的をも参酌する。 - 当該処分において考慮されるべき利益の内容・性質
当該利益の内容・性質を考慮するにあたっては、当該処分・裁決が根拠法令に違反してなされた場合に害される利益の内容。性質、これが害される態様・程度をも勘案する。
- 当該処分・裁決の根拠法令の趣旨・目的
- ③判例の判断
-
判例は、原告適格について、以下のように判断しています。
👉最重要判例:小田急高架訴訟(最大判平17.12.7)
👉最重要判例:場外車券発売施設設置許可と原告適格(最大判平21.10.15)
■原告適格に関する判例まとめ
| 対象 | 原告 | 原告適格の判断 | |
| 営業上 の利益 | 質屋の営業許可処分 | 既存の質屋営業者 | × (最判昭34.8.18) |
| 公衆浴場の営業許可処分 | 既存の公衆浴場業者 | 〇 (最判昭37.1.19) | |
| 文化的 利益 | 史跡指定解除の処分 | 学術研究者 | × (最判平1.6.20) |
| 消費者 の利益 | ジュースの表示規約の認定 | 一般消費者 | × (最判昭53.3.14) |
| 特急料金認可 | 特別急行旅客列車の利用者 | × (最判平1.4.13) | |
| 生命・ 身体の 安全や 健康上 の利益 | 林地開発許可 | 生命・身体等に直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者 | 〇 (最判平13.3.13) |
| 総合設計許可 | 建築物の倒壊・炎上等により直接的な被害を受けることが予想される範囲の建築物の居住者 | 〇 (最判平14.1.22) | |
| 建築物により日照を阻害される周辺の他の建築物の居住者 | 〇 (最判平14.3.28) | ||
| 定期航空運送事業免許 | 航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けることとなる飛行場の周辺住民 | 〇 (最判平1.2.17) | |
| 都市計画事業認可 | 健康・生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある事業地の周辺住民 | 〇 (最大判平17.12.7) | |
| 善良な 風俗等 の居住 環境上 の利益 | 風俗営業許可 | 風俗営業制限地域に居住する者 | × (最判平10.12.17) |
| 場外車券発売施設設置許可 | 当該施設の設置、運営により保健衛生上著しい支障を来すおそれがあると位置的に認められる区域内の医療施設開設者 | 〇 (最判平21.10.15) | |
| 当該施設の周辺住民 | × (最判平21.10.15) |
③ 訴えの利益:今、訴える必要があるか?
「訴えの利益」とは、訴訟をすることで具体的に何かを回復できる、実益があるかどうかです。
❌ 訴えの利益がなくなる場合
- 期間の経過や処分の効果がすでに終了している
- 原告が死亡した
- 他の手段で問題が解決している
- 新たな事情の発生して処分の効果がなくなった
ただし、9条1項かっこ書きでは、処分の効果が失われた後でも、法律上の利益があれば訴えの利益が認められるとしています。
👉最重要判例:運転免許更新処分と訴えの利益(最判平21.2.27)
■訴えの利益に関する判例まとめ
| 対象 | 処分後の事情 | 訴えの利益 | |
| 期間の経過 | 皇居外苑使用不許可処分 | 使用期日の経過 | × (最大判昭28.12.23) |
| 運転免許取消処分 | 免許証の有効期限の経過 | 〇 (最判昭40.8.2) | |
| 運転免許停止処分 | 無違反・無処分で停止処分の日から1年を経過 | × (最判昭55.11.25) | |
| 処分の効果の完了 | 建築確認2 | 建築工事の完了 | × (最判昭59.10.26) |
| 土地改良事業3施行認可処分 | 工事が完了して原状回復が不可能 | 〇 (最判平4.1.24) | |
| 市街化区域内の開発許可 | 工事が完了して検査済証が交付 | × (最判平5.9.10) | |
| 市街化調整区域内の開発許可 | 〇 (最判平27.12.14) | ||
| 原告の死亡 | 生活保護変更決定 | 保護受給者たる原告の死亡 | × (最大判昭42.5.24) |
| 公務員免職処分 | 原告公務員の死亡 | 〇 (最判昭49.12.10) | |
| 代替的措置 | 保安林指定解除処分 | 代替施設の設置 | × (最判昭57.9.9) |
| 新たな事情の発生 | 再入国不許可処分 | 原告たる在留外国人が日本を出国 | × (最判平10.4.10) |
| 公文書非公開決定 | 公文書が書証として提出 | 〇 (最判平14.2.28) | |
| 9条1項かっこ書きの適用 | 公務員免職処分 | 原告公務員が公職へ立候補 | 〇 (最大判昭40.4.28) |
| 運転免許更新処分 | 優良運転者である旨の記載のない免許証を交付 | 〇 (最判平21.2.27) |
④ 被告適格:誰を相手に訴えるか?
取消訴訟の被告は、処分を行った行政庁がどこに属しているかで決まります。取消訴訟の被告とするべきものは、次の通りです。4
⑤ 裁判管轄:どこの裁判所に訴えるか?
取消訴訟は、以下の裁判所に提起するのが原則です(12条1項)
- 被告の被告の普通裁判籍6の所在を管轄する裁判所
- 処分・裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所
✨ 特別なケースもある!
たとえば…
- 土地の収用・鉱業権の設定その他不動産または特定の場所に係る処分・裁決についての取消訴訟
⇒その不動産または場所の所在地の裁判所(12条2項) - すべての取消訴訟
⇒処分・裁決に関し事案の処理に当たった下級行政機関の所在地の裁判所(12条3項) - 国または独立行政法人通則法2条1項に規定する独立行政法人もしくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟
⇒原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(特定管轄裁判所)(12条4項)
⑥ 出訴期間:いつまでに訴えを起こすか?
行政処分に対する争いは、早期に解決されるべきという考えから、期限が法律で定められています(14条)。この期間を経過すると、不可争力が生じて、取消訴訟を提起することができなります。
(行訴法14条)。
✅ 例外が認められる場合
- 正当な理由がある場合
👉出訴期間を過ぎても取消訴訟を提起できる(14条1項但書・2項但書)。 - 処分・裁決について審査請求できる場合 or 行政庁が誤って審査請求できる旨を教示した場合で、審査請求中のとき
👉これに対する裁決があったことを知った日(主観的)または裁決の日(客観的)が起算点となる(14条3項)
⑦ 審査請求前置:まず審査請求が必要なケースとは?
取消訴訟は、いきなり裁判を起こせるケースと、まず審査請求を経る必要があるケースがあります。
取消訴訟は、いきなり裁判を起こせるケースと、まず審査請求を経る必要があるケースがあります。
| パターン | 内容 |
|---|---|
| 原則 (自由選択主義) | 行政不服審査法その他の法令により審査請求をすることができる場合、審査請求をすることも、取消訴訟を提起することもできる(8条1項本文)。 |
| 例外 (審査請求前置主義) | 法律で審査請求の裁決後でなければ取消訴訟を提起することができないとされている場合(8条1項但書)。78 |
✅ 審査請求なしでOKになるケース(8条2項)。
- 3か月たっても裁決がない
- 著しい損害を避けるため緊急の必要がある
- 裁決を経ない正当な理由がある
✍️まとめ
取消訴訟を提起するには、次の7つの訴訟要件をすべて満たす必要があります。
行政書士試験でもよく出題される重要ポイントですので、それぞれの要件の意味と判例をセットで押さえておきましょう!
- 具体例:申請拒否処分を受けた申請者や、不利益処分を受けた名あて人など ↩︎
- 参考:建築確認は、それを受けなければ建築等の工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎない ↩︎
- 土地改良事業:農業生産の基盤の整備・開発を図り、農業の生産性の向上・農協構造の改善等に資することを目的として行われる農用地の改良・開発・保全・集団化に関する事業(土地改良法1条1項) ↩︎
- 参考:原告が故意または重大な過失によらないで被告とすべき者を誤ったときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、被告を変更することを許すことができる(15条1項) ↩︎
- 具体例:弁護士に対して懲戒処分をした弁護士会など ↩︎
- 普通裁判籍:事件の内容や種類を問わずに認められる裁判籍(そこを管轄区域に含む裁判所に管轄を発生させるもの)のこと ↩︎
- 具体例:国税通則法115条1項本文は、「国税に関する法律に基づく処分…で不服申立てをすることができるものの取消しを求める訴えは、審査請求についての裁決を経た後でなければ、定期することができない」と規定している ↩︎
- 参考:審査請求が不適法として却下された場合には、審査請求前置主義の要件を満たさない。もっとも、審査庁が誤って適法な審査請求を不適法として却下した場合は、審査請求前置の要件を満たす(最判昭36.7.21) ↩︎