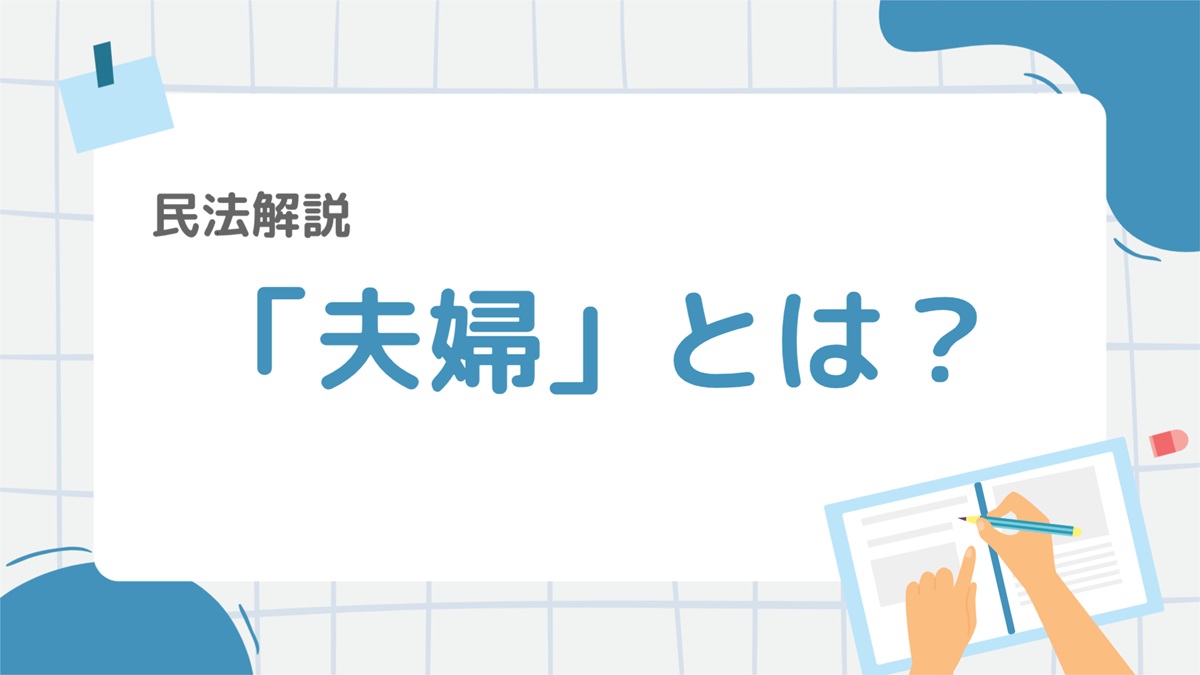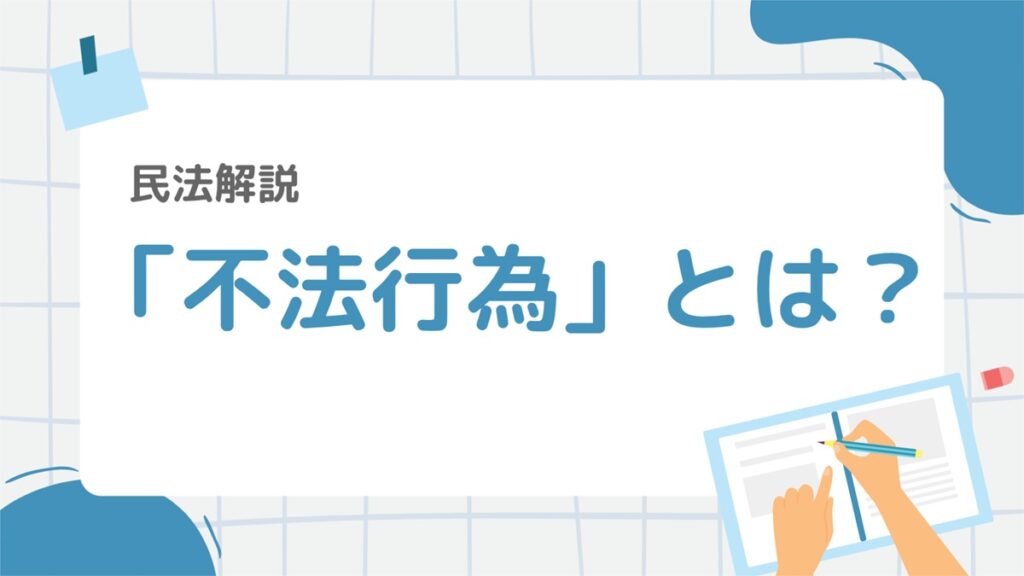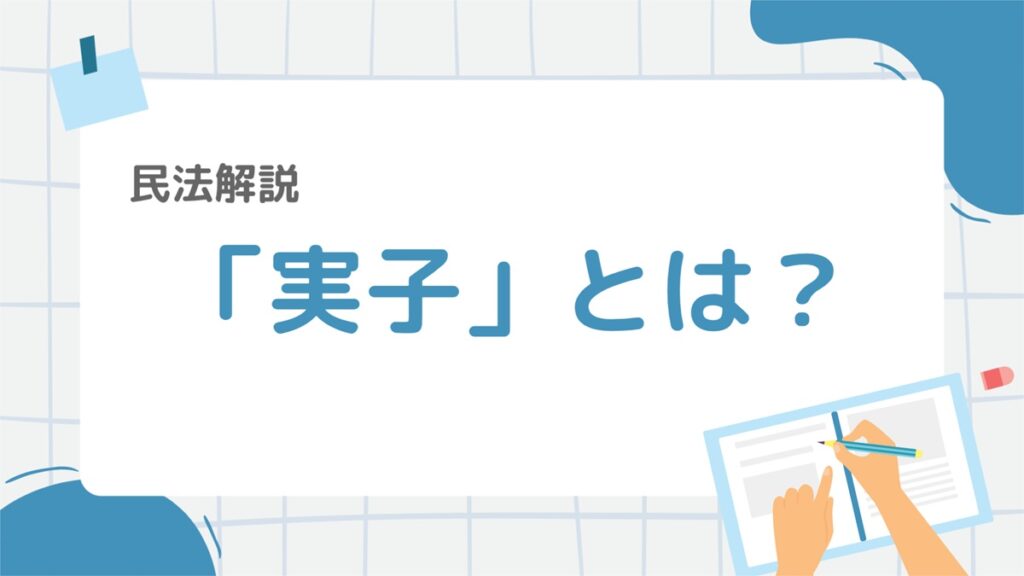- 行政書士試験の民法(親族)を学習している方
- 婚姻や離婚に関する条文や判例を体系的に理解したい方
- 婚姻の効果や離婚後の法的処理について具体的に知りたい方
- 実務でも知っておきたい婚姻・離婚の法的知識を押さえたい方
✅婚姻の成立と無効・取消し
婚姻の成立要件
民法では、婚姻が法的に有効になるためには、次の2つの要件が必要です(民法742条)。
- 当事者に婚姻をする意思があること
- 婚姻の届出がなされていること
このどちらかが欠けていれば、そもそも婚姻は「無効」となります(742条)。1
婚姻の取消しが認められる場合
婚姻の無効・取消し
以下のような場合には、婚姻の取消し可能とされます。
- 18歳に達していないこと(731条)
- 重婚であること(732条)
- 近親者(直系血族・3親等内の傍系血族)間の婚姻であること(734条)
- 直系姻族間の婚姻であること(姻族関係終了後も同様)(735条)
- 養親子間の婚姻であること(親族関係終了後も同様)(736条)
- 詐欺・強迫による婚姻であること(741条1項)
取消しを求めるには、家庭裁判所への請求が必要です(744条1項本文)。また、取消しの効力は将来に向かってのみ有効となります(748条1項)。

✅婚姻の法的効果
① 身分上の効果
- 夫婦同氏の原則(750条)
→ 夫婦は、婚姻時に定めた一方の氏を名乗ります。 - 同居・協力・扶助の義務(752条)
→ 夫婦は同居し、互いに支え合う義務があります。 - 夫婦間の契約取消権(754条本文)2
→ 夫婦間の契約は、婚姻中ならいつでも取り消し可能です。
② 財産に関する効果
■ 法定財産制
婚姻時に特別な財産契約をしていない場合、自動的に法定財産制が適用されます(755条)。
もし異なる契約を結んでいても、婚姻届までに登記していなければ、その内容を夫婦の承継人や第三者には対抗できません(756条)。
■ 婚姻費用の分担義務
生活費や住居費など、婚姻に関する費用は夫婦で分担する義務があります(760条)。
■ 特有財産と共有財産
■ 日常家事債務の連帯責任(761条)
日常の家事に関して夫婦の一方が第三者と契約等(法律行為)をした場合、他方も連帯責任を負うことになります(761条本文)。
ただし、責任を負わないことをあらかじめ第三者に予告していれば連帯責任は負いません(761条但書)。この規定は、夫婦が相互に日常家事に関する法律行為について代理する権限を有することをも規定していると考えられています。4
✅離婚の種類と効果
① 協議離婚
夫婦が話し合い(協議)のうえで離婚の意思が合致し、離婚届を届出することで成立します(763条)。5
② 裁判離婚
以下のいずれかの事由があるとき、一方から裁判所に離婚の訴えを請求できます(770条1項)。
- 不貞行為、
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- 婚姻を継続し難い重大な事由
裁判離婚は、判決が確定することで成立します。
これらに該当しても、裁判所が「婚姻継続が相当」と判断すれば、離婚請求は棄却されます(770条2項)。
✅離婚の主な効果
■ 氏の変更(復氏)
婚姻によって氏を変更した者は、離婚によって婚姻前の氏に復することになります(767条1項、771条)。
■ 親権者の決定
父母が協議離婚をする場合は、どちらか一方を親権者と定める必要があります(819条1項)。裁判離婚の場合は、裁判所が父母の一方を親権者と定めます(819条2項)。
これは、離婚後に両親が共同で親権を行使することが困難であることを考慮したものです。
■ 財産分与(768条)
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます(768条1項、771条)。
家庭裁判所は、当事者双方が協力によって得た財産の額や、その他一切の事情を考慮して、財産分与の要否、分与の額および方法を定めることになります(768条3項)。67
✅離婚と死別の違い
離婚と夫婦の一方の死亡との違いは次の通りです。
- 姻族関係
- 復氏
まとめ
本記事では、夫婦関係に関する民法の規定として、「婚姻の成立要件」「婚姻の無効・取消し」「婚姻による効果」、さらに「離婚の種類と効果」について解説しました。
婚姻が有効に成立するには意思と届出が必要であり、条件を欠く場合は無効または取消しの対象となります。また、婚姻には氏の変更や扶助義務、財産の帰属・管理、債務の連帯責任などの法律効果が発生します。
離婚には協議離婚と裁判離婚があり、親権や財産分与などの重要な法的効果も伴います。さらに、離婚と死別では姻族関係や氏の扱いに違いがある点も押さえておく必要があります。
行政書士試験では、これらの民法の基本原則や条文番号、要件・効果を正確に理解し、区別できることが求められます。条文の趣旨とセットで整理しておくと、応用問題にも対応しやすくなるでしょう。
- 重要判例:婚姻の届出自体については、当事者間に意思の合致があったとしても、それが単に他の目的を達するための弁法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力を生じない(最判昭44.10.31)
※【参考】生活保護の需給を受給を継続するための方便としてなされた離婚も有効(最判昭57.3.26) ↩︎ - 重要判例:婚姻が実質的に破綻していた場合、夫婦間の契約取消権は認められない(最判昭42.2.2) ↩︎
- 特有財産:夫婦の一方が単独で有する財産 ↩︎
- 重要判例:夫婦の一方が日常の家事に関する代理権の範囲を超えて、第三者と法律行為をした場合、その代理権を基礎として一般的に110条所定の表見代理の成立を工程すべきではなく、その越権行為の相手方である第三者において、その行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当な理由のあるときに限り、同条の趣旨を類推して第三者の保護を図るべきである(最判昭44.12.18) ↩︎
- 重要判例:離婚意思は法律上の婚姻関係を解消する意思で足りるため、生活保護の需給を受給を継続するための方便としてなされた離婚も有効である(最判昭57.3.26) ↩︎
- 重要判例:当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の生産のための給付を含めて財産分与の額および方法を定めることができる(最判昭53.11.14) ↩︎
- 重要判例:財産分与がなされても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解せられないか、その額および方法において、請求者の精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められるときは、別個に不法行為を理由として離婚による慰謝料を請求することができる(最判昭46.7.23) ↩︎