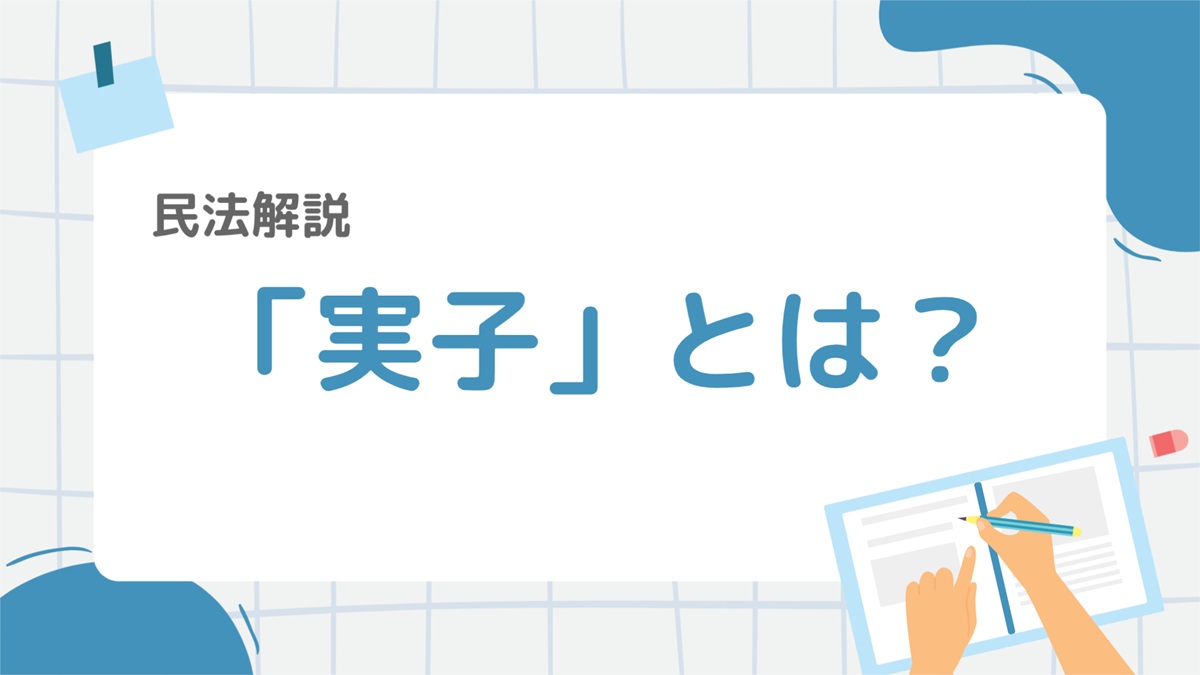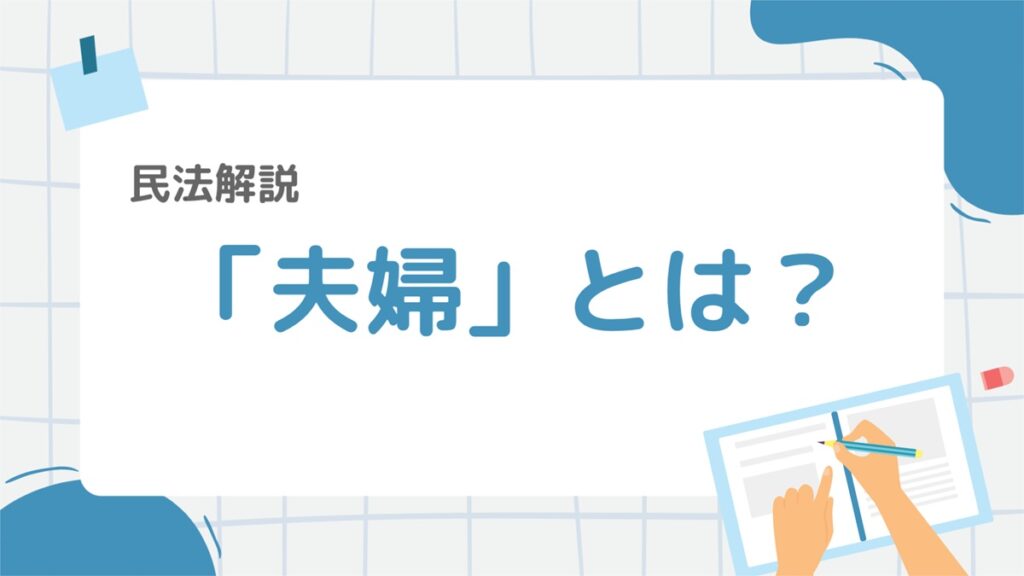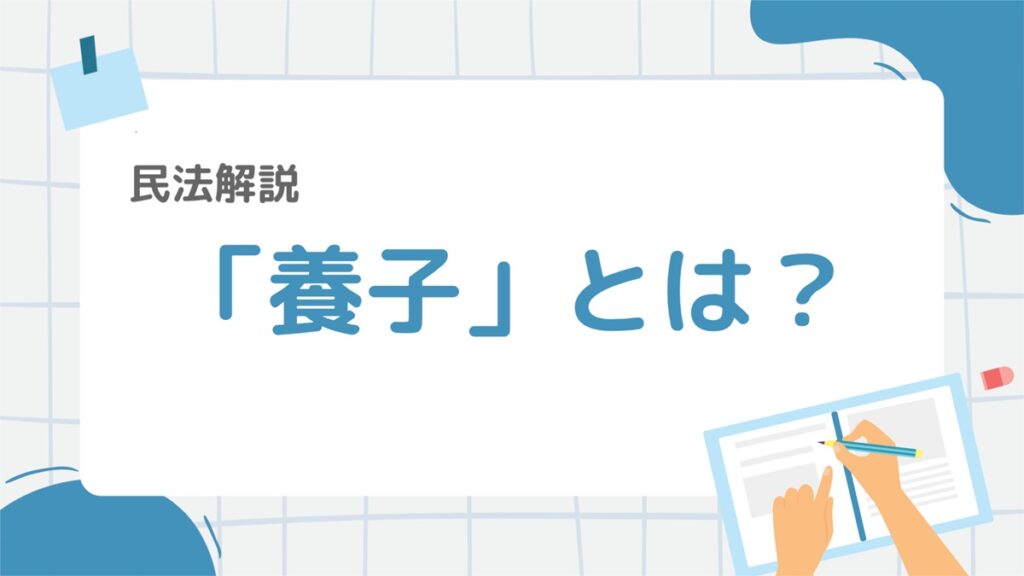- 民法の「親子関係」についてしっかり理解したい受験生
- 「実子とは?」「嫡出子と非嫡出子の違いってなに?」と疑問に感じている方
- 認知や準正の制度について、出題ポイントを押さえておきたい方
👶実子とは?その種類と分類
民法では、子どもは大きく「実子」と「養子」に分類されます。このうち「実子」とは、血のつながりがある親子関係にある子のことをいいます。
さらに、実子は2種類に分けられます。
行政書士試験では、「嫡出の推定」や「認知」など、実子の区分に応じたルールがよく問われます。
🧾嫡出の推定とは?(民法772条)
嫡出子であると法律上みなされる基準のことを「嫡出の推定」といいます。特に重要なのは、出生した時期と婚姻のタイミングです。
① 妻が再婚していない場合
以下のような場合には、現在の夫の子である(=嫡出子)と推定されます(772条1項・2項)。
- 女性が婚姻前に懐胎し、婚姻が成立した後に生まれた子
👉婚姻の成立から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定されます。 - 妻が婚姻中に懐胎し、その後に生まれた子
👉婚姻の成立から200日を経過後、または婚姻の解消・取消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したと推定されます。
② 妻が再婚した場合
次のように判断されます。
女が子を懐胎したときから子の出生の時までの間に2以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定される(772条3項)。
③ 「推定の及ばない子」とは?
上記の期間内に生まれても、例えば夫婦間に明らかに性的関係がなかった場合などは、嫡出の推定は働きません。これを「推定の及ばない子」といいます。1
🚫嫡出の否認(774条)
嫡出の推定を受ける子であっても、夫は「嫡出否認の訴え」を家庭裁判所に提起することで、法律上の父子関係を否定できます(774条)。2
一方、非嫡出子や推定の及ばない子の場合には、「親子関係不存在確認の訴え」が用いられます。
| 嫡出否認の訴え | 親子関係不存在確認の訴え | |
| 提訴権者 | 父、子、母(774条1項・2項) | 利害関係人 |
| 提訴期間 | 父が提起:父が子の出生を知った時から3年以内(777条1号) 子、母が提起:子の出生の時から3年以内(777条2号・3号) 前夫が提起:前夫が子の出生を知った時から3年以内(777条4号) | 制限なし |
| 相手方 | 父が提起:子、親権を行う母(775条1項1号) 子、母が提起:父(775条1項2号・3号) 前夫が提起:父、子、親権を行う母(775条1項4号) ※親権を行う母がいないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない(775条2項) | 親子関係の存在を主張する者 |
実子の種類と嫡出を否認する方法についてまとめると、次の通りになります。
--- config: theme: neutral --- flowchart LR 実子 --> 嫡出子 嫡出子 --> 嫡出の推定を受ける子 嫡出子 --> 推定の及ばない子 実子 --> 非嫡出子 subgraph 嫡出否認の訴え 嫡出の推定を受ける子 end subgraph 親子関係不存在確認の訴え 推定の及ばない子 非嫡出子 end
📜認知とは?(779条〜)
認知とは、非嫡出子について父または母が親子関係を法的に認める手続きのことです(779条)。3
任意認知(本人の意思で行う)
任意認知は、父または母が行う意思表示によって成立します。未成年者や成年被後見人であっても、認知をする際に法定代理人の同意は必要ありません(780条)。
任意認知は、戸籍法に基づく届出によって行うか(781条1項)、遺言によって行うこともできます(781条2項)。4
なお、以下の場合には、認知される側の承諾が必要となります。
- 成年の子:その子の承諾が必要(782条)
- 胎児:母の承諾が必要(783条1項)
- 死亡した子:直系卑属があるときに限り認知することができ、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾が必要(783条3項)
🔄 認知は、出生時にさかのぼって効力を持ちますが、第三者の権利を侵害してはなりません(784条)。
⚖認知の訴え(787条)
任意認知がされない場合、子やその直系卑属、これらの者の法定代理人は「認知の訴え」を提起できます(787条本文)。5
- 父が生存中であればいつでも提起可能
- 父(または母)が死亡した後は、3年以内に提起しなければなりません(787条但書)。
🏛準正とは?(789条)
準正とは、嫡出でない子に嫡出子としての地位を与える制度です。
具体例:
✅まとめ
- 実子には「嫡出子」と「非嫡出子」があり、法的地位が異なります
- 婚姻のタイミングにより「嫡出の推定」が働くかどうかが決まります
- 非嫡出子であっても、認知や準正によって法的な親子関係を築くことができます
- 重要判例:懐胎時に、夫婦が事実上の離婚状態であった場合(最判昭44.5.29)、夫が出征中であった場合(最判平10.8.31)、夫が刑務所に収容されていた場合は、嫡出の推定は及ばない。 ↩︎
- 参考:令和2年に生殖補助医療法が制定され、妻が夫の同意を得て、夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫、子、妻は、その子が嫡出であることを否認できないとされた(10条)。 ↩︎
- 法改正:令和4年の民法改正により、認知について反対の事実を主張する場合には、認知の無効の訴えを提起することとされ、提訴権者と出訴期間が制限されることとなった。 ↩︎
- 重要判例:妻以外の女性との間にもうけた子につき、妻との間の嫡出子として出生の届出をし、受理されたときは、その届出は認知届としての効力を有する(最判昭53.2.24) ↩︎
- 重要判例:認知請求権は放棄することができない(最判昭37.4.10) ↩︎