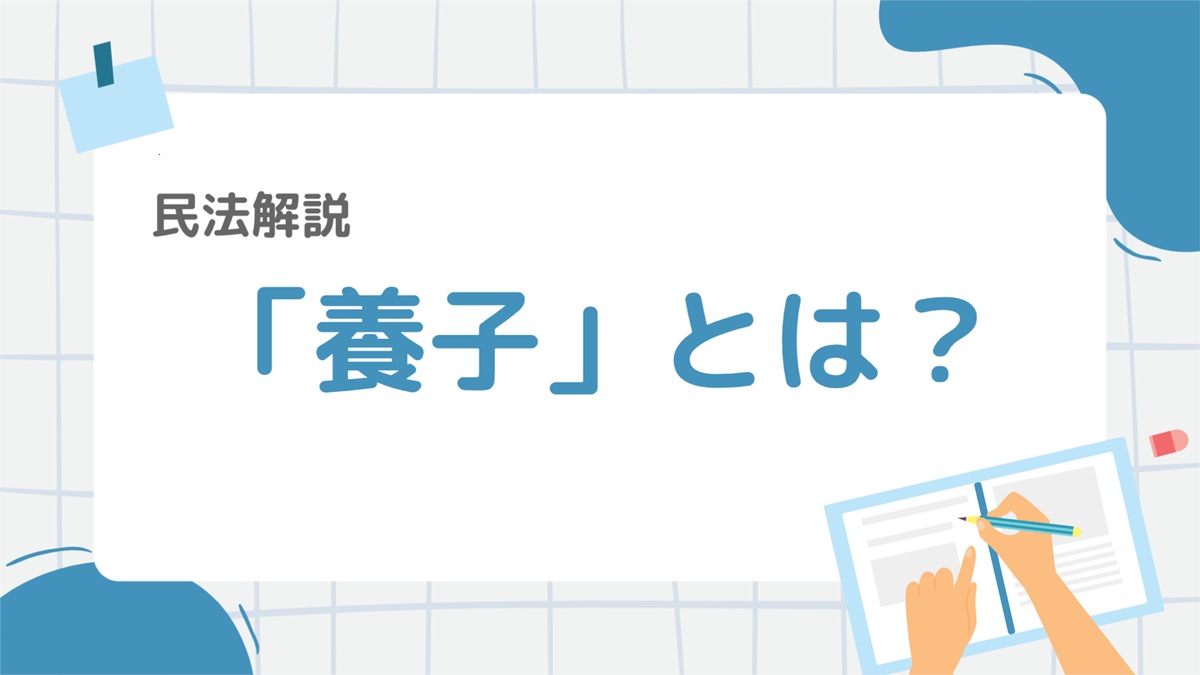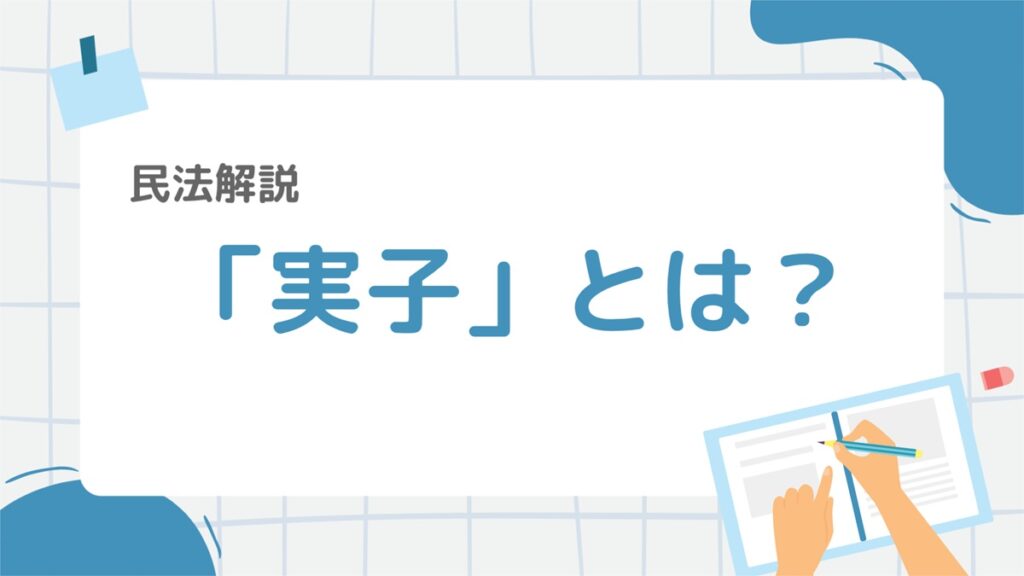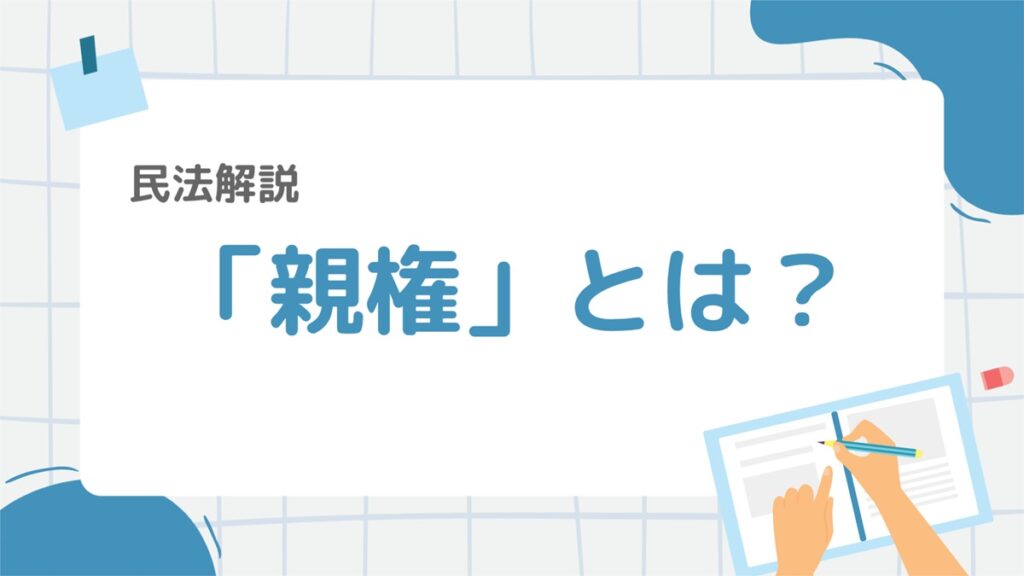この記事はこんな人におすすめ
- 行政書士試験の民法(親族)で「養子」の論点をしっかり理解したい人
- 「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の違いが曖昧なままになっている人
- 養子縁組の要件・効果・取消しや代諾縁組など、試験頻出のポイントを短時間で整理したい人
目次
養子とは?──2つの類型の違いを押さえよう
養子とは、血縁関係のない者同士が法律上の親子関係を結ぶ制度です。
民法上、養子には次の2種類があります。
| 類型 | 実の親族との関係 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 普通養子縁組 | 続く | 親族関係の形成 |
| 特別養子縁組 | 消滅する | 子の福祉の確保 |
それぞれの養子縁組の成立要件や効果は大きく異なりますので、確実に区別しておきましょう。
普通養子縁組とは?──成立・要件・取消しのポイント
普通養子縁組では、実の親との親族関係はそのまま残ります。法的な親子関係が増える形になります。
■ 普通養子縁組の成立要件と無効・取消し
普通養子縁組が成立するには、以下の2点が必要です。
- 当事者双方に養子縁組の意思があること
- 市区町村への縁組の届出がなされること
いずれかが欠けていると、縁組は無効となります(802条)。1
また、以下の条件を満たしていない縁組は、取消しの対象となります(804~808条)。
✅普通養子縁組の要件
- 養親が20歳に達していること(792条)
- 尊属または年長者を養子としないこと(793条)
- 後見人が被後見人を養子とするには家庭裁判所の許可を得ること(794条)
- 配偶者のある者が成年者と縁組をするには、その配偶者の同意を得ること(配偶者とともに縁組をする場合または配偶者が意思表示できない場合を除く(796条)2
- 未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可を得ること(自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合除く)(798条)
▼ 詐欺・強迫による縁組の取消し
詐欺や強迫によって縁組がされた場合、当事者はその縁組を取り消すことができます(808条1項、747条1項)。
■ 代諾縁組とは?(797条)
養子となる者が15歳未満の場合、その法定代理人が代わりに承諾することで縁組が成立します。これを「代諾縁組」といいます(797条1項)。3
特別養子縁組とは?──子の福祉を重視した制度
普通養子縁組では、実の親との関係は続きますが、子の最善の利益のためには、実親との法的な関係を断ち切る方が望ましい場合があります。
このようなケースのために設けられているのが、特別養子縁組です(817条の2第1項)。
この特別養子縁組については、その成立要件・法的効果・離縁について、普通養子縁組とは異なる特別な規定が設けられています。
■ 特別養子縁組の特徴
- 養親となる者の請求と家庭裁判所の審判によって成立します
- 一度成立すれば、実親との親族関係は完全に終了します
- 養親と養子は、実の親子と同じ法律効果が認められます
- 離縁についても、普通養子とは異なる厳格な要件が課されます
この制度は、子の福祉を最優先に考えた、現代的な養子制度です。
まとめ:普通養子と特別養子の違いをしっかり理解しよう
普通養子縁組と特別養子縁組の比較は次の通りです。
| 比較 項目 | 普通養子縁組 | 特別養子縁組 |
| 成立 要件 | 当事者間の合意(802条1号) 届出(802条2号) | 養親となる者の請求(817条の2第1項) 家庭裁判所の審判(817条の2第1項) 子の利益のため特に必要があると認めるとき(817条の7) |
| 養親の資格 | 20歳に達していること(792条) 養子が未成年者である場合、原則、夫婦共同縁組が必要(795条) | 原則、夫婦共同縁組(817条の3第1項・2項) 夫婦いずれも20歳以上で、かつ、そのいずれかは25歳以上(817条の4) |
| 養子の資格 | 養親の年長者・尊属でないこと(793条) | 原則、審判請求時に15歳未満(817条の5第1項) |
| 父母の同意 | 不要 | 原則、必要(817条の6) |
| 試験養育期間 | 不要 | 6カ月以上(817条の8) |
| 効果 | 養子と実方の父母およびその血族との親族関係は終了しない | 原則、養子と実方の父母およびその血族との親族関係は終了する(817条の9) |
| 離縁 | 原則、自由になしうる | 原則、なし得ない(817条の10) |
- 重要判例:真実の親子関係がない親から嫡出子として出生の届出がされている場合でも、その届出を養子縁組の届出とみなすことはできない(最判昭25.12.28) ↩︎
- 参考:配偶者のある者が未成年者と縁組をするには、配偶者と共に縁組をしなければならず(配偶者の嫡出子を養子とする場合または配偶者が意思表示できない場合を除く)(795条)、これに違反した縁組は、届出が受理されないことになる。 ↩︎
- 重要判例:真実の親子関係がない戸籍上の親が15歳未満の子について代諾による養子縁組をした場合には、その代諾による縁組は一種の無権代理によるものであるから、その子は、15歳に達した後はその縁組を追認することができる(最判昭27.10.3) ↩︎