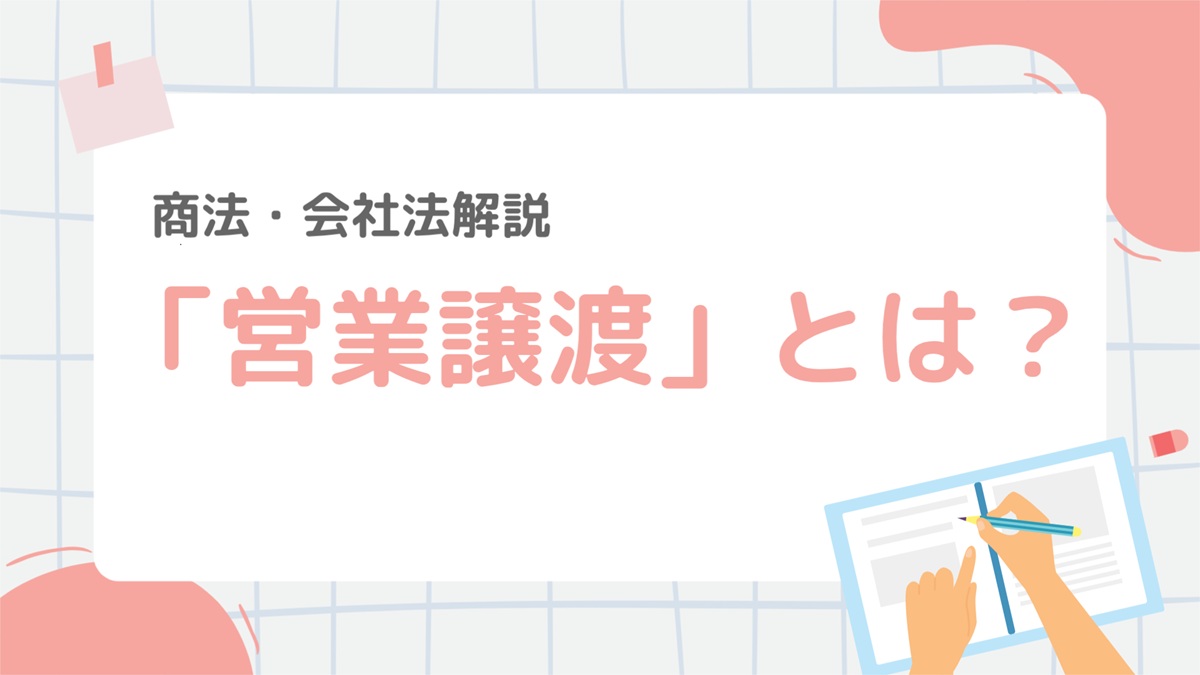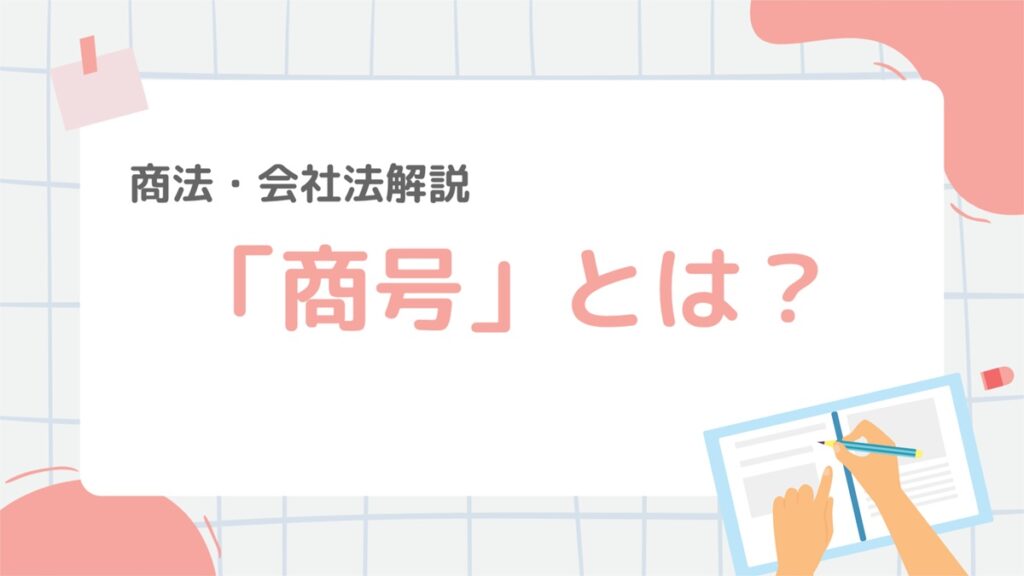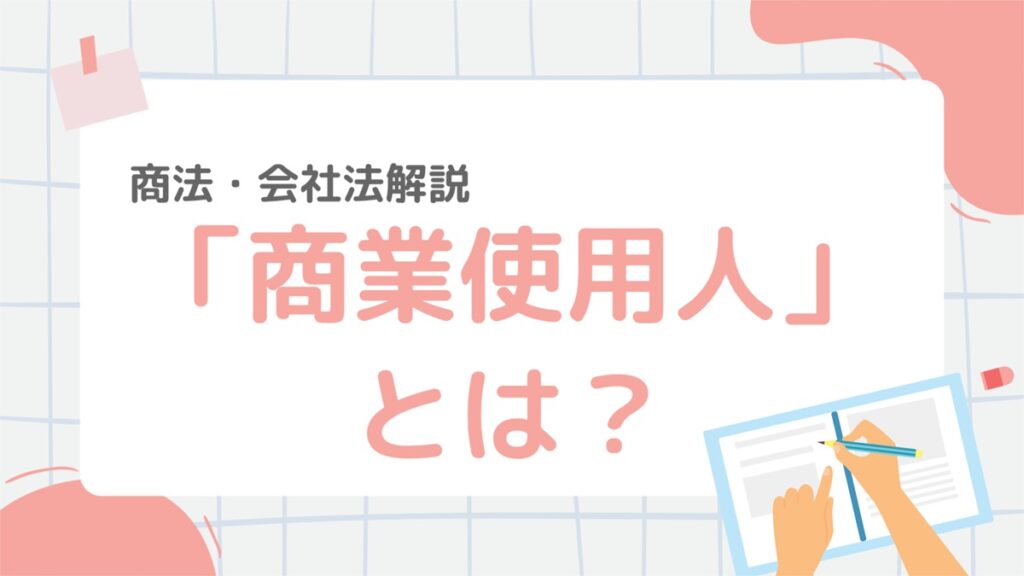- 「営業譲渡」とは何か、基本から丁寧に理解したい方
- 行政書士試験でよく出る”商法の営業譲渡の論点(競業避止義務・譲受人の責任)”を押さえたい方
- 判例・条文ベースの知識を整理しながら、効率よく学びたい方
営業譲渡とは?
「営業譲渡」とは、会社や個人が行っている一連の営業活動(顧客情報・ノウハウ・設備など含む)を、他人に引き継ぐことをいいます。単なる財産の売買とは異なり、営業としてのまとまり(有機的一体性)をもった財産の包括的な譲渡である点が特徴です。
判例(最大判昭40.9.22)では、営業譲渡を次のように定義しています:
一定の営業目的により組織化され、有機的一体として機能する財産の譲渡であって、
(1) 譲受人が営業活動を承継し、
(2) 譲渡人が法律上当然に競業避止義務1を負うもの
「有機的一体として機能する財産」とは?
ここでいう「有機的一体性」とは、単なる商品や設備などの物理的な財産にとどまらず、顧客情報や営業ノウハウ、信用など無形の要素も含まれるということです。つまり、営業の仕組み全体を丸ごと引き継ぐことが「営業譲渡」の本質です。
譲渡人に課せられる「競業避止義務」とは?
営業譲渡が成立すると、譲渡人には法律上当然に「競業避止義務」が課されます。これは、譲渡後に同じ地域・業種で営業を再開することを制限する義務です。
■競業避止義務の内容
- ①原則
-
譲渡人は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市区町村の区域内およびこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から20年間は、同一の営業を行ってはならない(16条1項)。
- ②特約がある場合
-
譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から30年の期間内に限り、その効力を有する(16条2項)。
- ③不正の競争の目的がある場合
-
譲渡人は、父性の競争の目的をもって同一の営業を行ってはならない(16条3項)。これは、地域・期間に関係なく禁止される。
譲受人の責任 ― 商号の続用がポイント!
営業譲渡では、「譲受人」が譲渡人の商号(屋号や社名)を使うかどうかで、譲渡人の債務(借金など)を引き継ぐかどうかが決まるため注意が必要です。
商号を続けて使う場合(商法17条)
譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合、譲受人は、原則として、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う(17条1項)。2
もっとも、譲受後、違いなく、譲受人がその本店の所在地において譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨の登記をした場合や、譲受人および譲渡人から第三者に対してその旨の通知をた場合には、責任を負わない(17条2項)。
なお、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する(17条4項)。
商号を続けない場合(商法18条)
商号を使わない場合、原則として譲受人に「譲渡人の営業によって生じた債務」の引き継ぎ義務はありません。
ただし、「譲渡人の債務を引き受ける」旨を広告した場合は、弁済責任が発生します18条1項)。3
詐害的な営業譲渡の場合はどうなる?
譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(残存債権者)を害することを知って営業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受人に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる(18条の2第1項)。
まとめ:営業譲渡のポイントはココ!
| 覚えるべきポイント | 内容 |
|---|---|
| 営業譲渡とは? | 有機的一体性をもった営業財産の包括的な譲渡 |
| 競業避止義務 | 原則20年・特約で30年・不正目的なら無制限禁止 |
| 譲受人の責任 | 商号を使うかどうかで債務引継ぎが決まる |
| 詐害営業譲渡 | 債権者から逃れるための譲渡は取消可能 |
👇あわせて確認 会社の事業を譲渡について