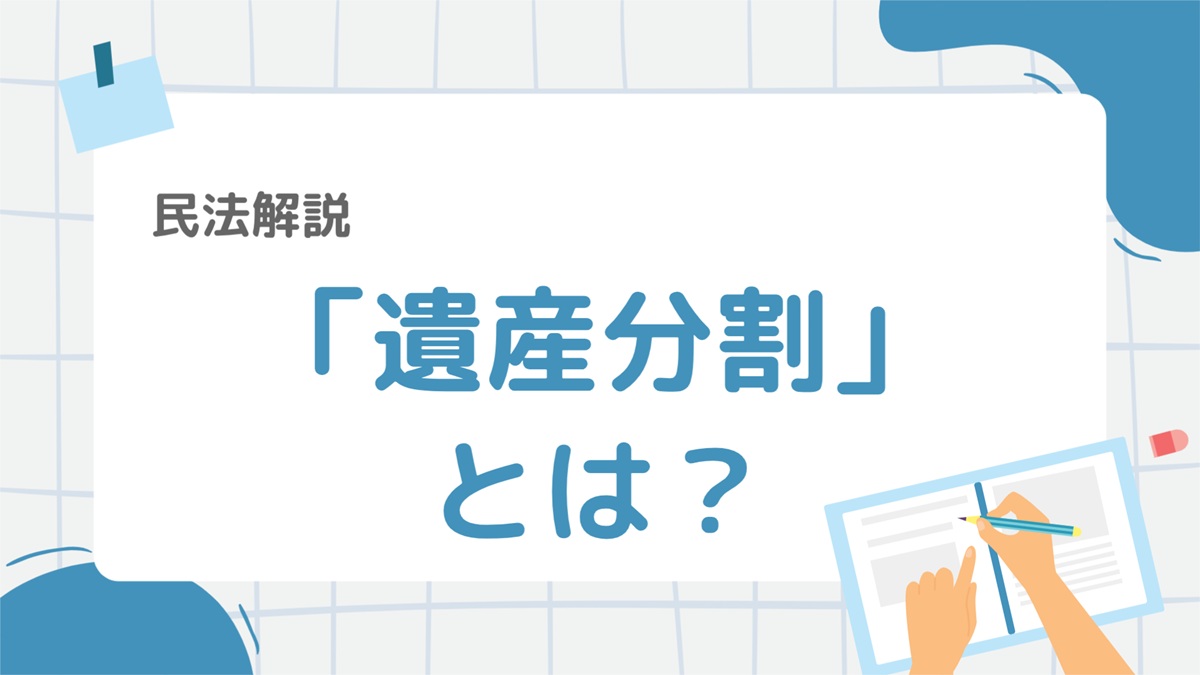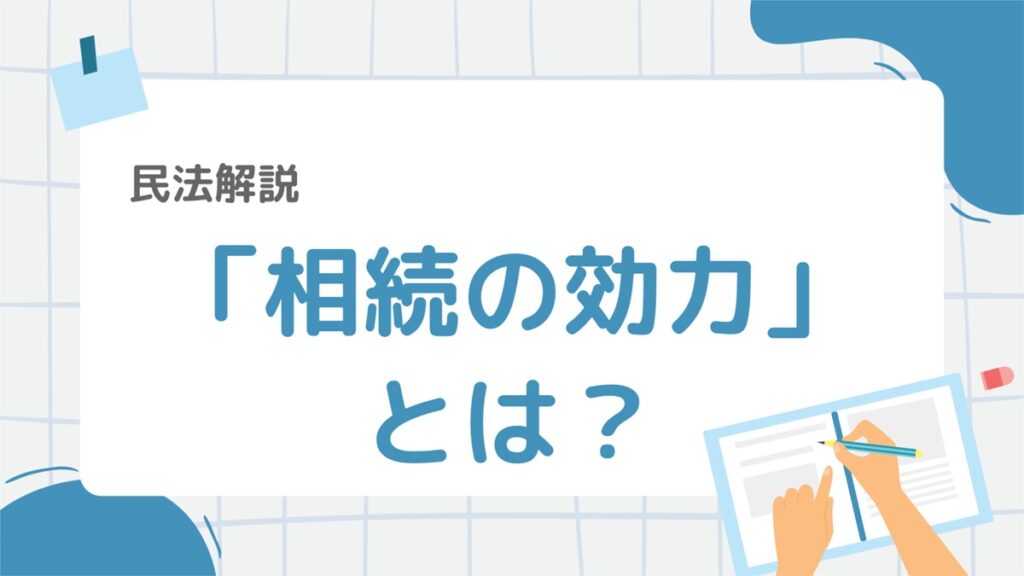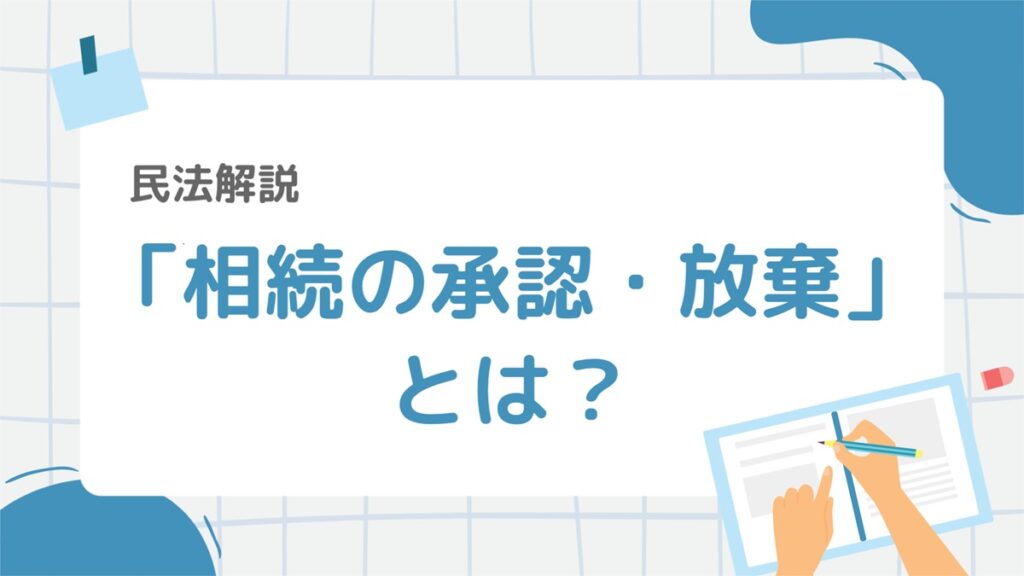- 行政書士試験で「相続」分野の得点力を上げたい方
- 「遺産分割」の種類や流れを理解したい方
- 「協議分割」と「審判分割」の違いがイマイチわからない方
- 試験対策と実務の両方に役立つ知識を効率よく整理したい方
遺産分割とは?【基本をおさえる】
遺産分割とは、亡くなった人(被相続人)の遺産を、法定相続人たちがそれぞれの相続分に応じて分け合い、それぞれの財産として確定させる手続きです。
この手続きによって、共同相続人が共有していた財産が、それぞれの個人の所有に移ります。1
遺産分割の3つの方法とその流れ
遺産分割には、以下の3つの方法があります。順を追って見ていきましょう。
①指定分割【まずは遺言を確認】
被相続人が遺言で「誰に何を相続させるか」を指定している場合、その内容に従って遺産を分けるのが「指定分割」です(民法908条)。
また、遺産の分け方を第三者に任せることもできます。2
②協議分割【話し合いで決める】
遺言で分割が禁じられていない、もしくは共同相続人が分割をしない旨の契約をした場合は、共同相続人は、いつでも、自由に話し合って(協議)分割方法を決めることができます(907条1項)。
この協議による分割では、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。3
注意ポイント
すべての相続人が参加していない協議は無効です。また、後から認知によって新たに相続人となった人が現れた場合、その人は「価額での支払い」を請求できます(910条)。
③審判分割【家庭裁判所にお願い】
遺産の分割について、共同相続人に協議がまとまらないときや協議をすることができないときは、各共同相続人は、分割を家庭裁判所に請求することができます(907条2項)。
この審判による分割は、協議による分割と異なり、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して判断されます(906条)。
遺産分割が「禁止」される場合もある?
一定の条件のもと、遺産分割を一時的に禁止することも可能です。
- 遺言による禁止
被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる(908条1項)。 - 契約による禁止
共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部または一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる(908条2項本文)。 - 審判による禁止
特別の事由があるときは、家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部または一部について、その分割を禁ずることができる(908条4項本文)。
遺産分割の「効力」と「法的効果」
- ①遺産分割の遡及効
-
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力が発生します。ただし、第三者の権利を害することはできません(909条)。
- ②共同相続人の担保責任
-
各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負います(911条)。
遺産分割前の「預貯金の払戻し」は可能?
以前は、相続人が単独で預貯金を引き出すことはできませんでした。
しかし、2019年の法改正により、以下の範囲で単独で払戻しが認められています(909条の2前段)。
- 各相続人は、被相続人の預貯金のうち3分の1に法定相続分を乗じた額の範囲で払戻し可能
- 金額の上限は法務省令で定められており、金融機関ごとに異なる
この制度により、葬儀費用や当面の生活費をまかなうことが可能となっています(909条の2前段)。
まとめ:行政書士試験ではここをチェック!
- 遺産分割の「種類」と「流れ」は確実に押さえる
- 協議・指定・審判それぞれの特徴を区別する
- 分割の禁止・効力・担保責任・預貯金の扱いも頻出ポイント
- 参考:遺産の分k夏前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる(906条の2第1項)。 ↩︎
- 重要判例:「甲土地をAに相続させる」趣旨の遺言は、遺産の分割の方法を定めたものであり、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時に直ちに甲土地が相続によりAに承継される(最判平3.4.19) ↩︎
- 重要判例:共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の1人が他の相続人に対して当該協議において負担した債務を履行しないときでも、他の相続人は541条、542条によって当該協議を解除することはできない(最判平1.2.9)
これに対して、共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部または一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることはできる(最判平2.9.27)。 ↩︎