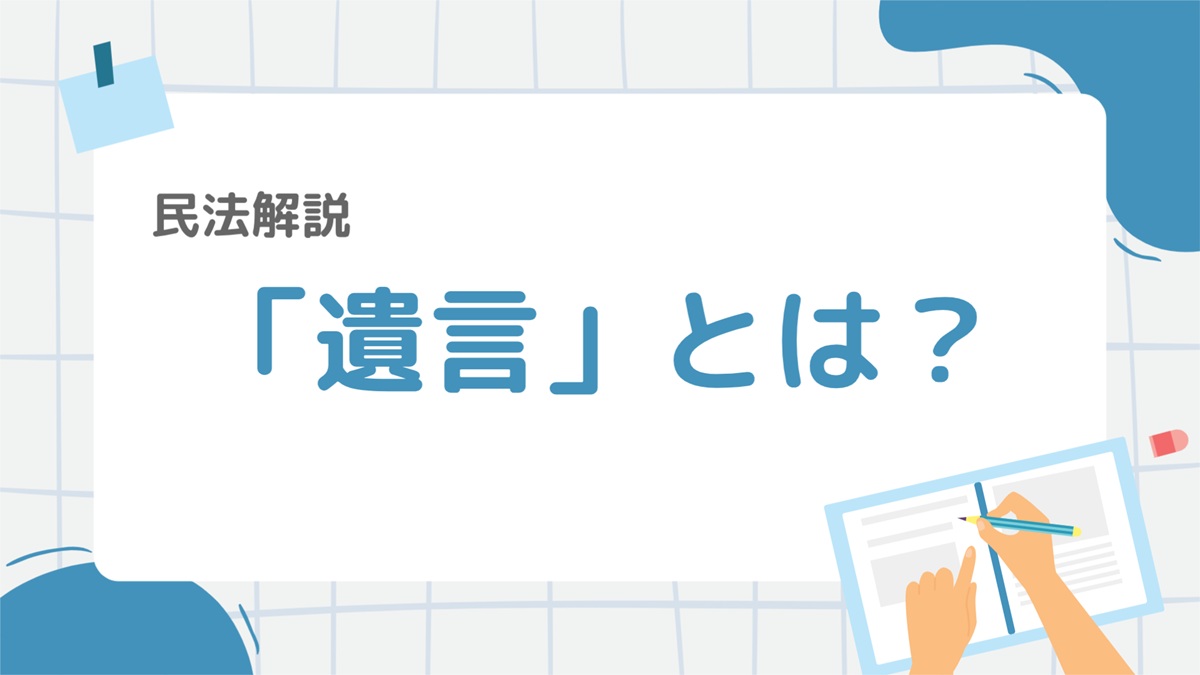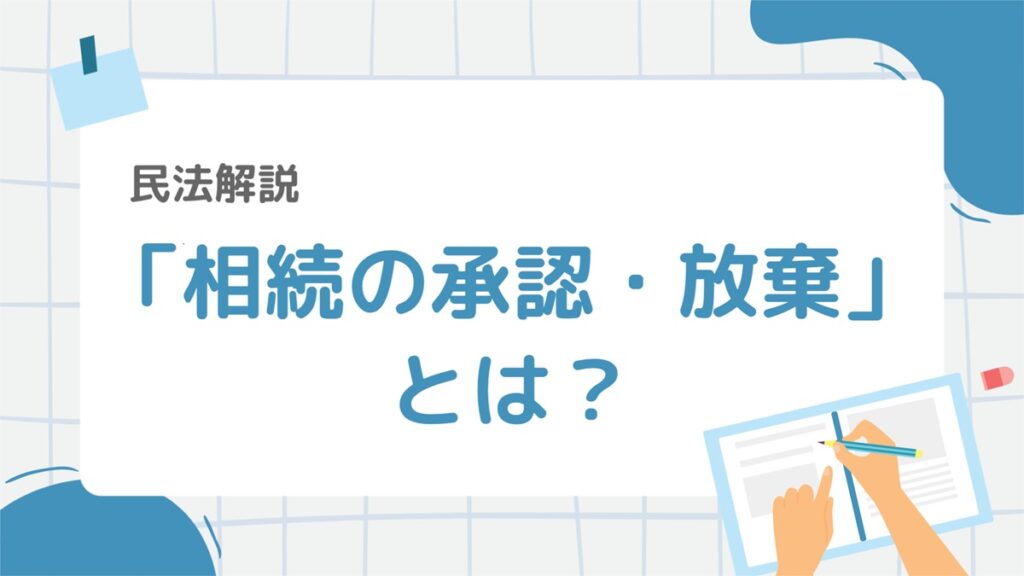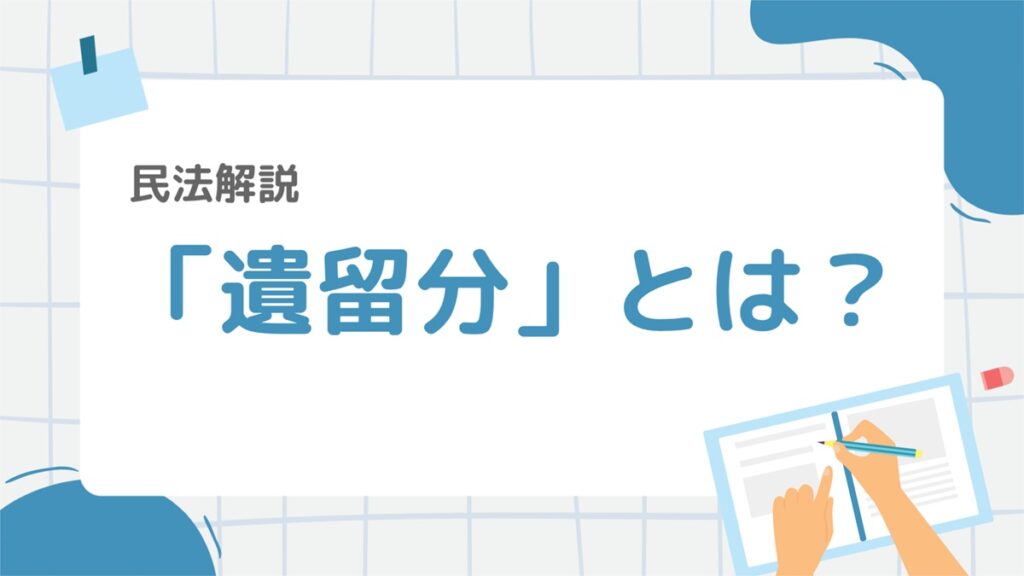- 行政書士試験の民法対策をしている方
- 「遺言書ってどうやって作るの?」「誰が書けるの?」と疑問を感じている方
- 親の遺言書が見つかったけど、どうすればいいのかわからない方
- 将来に備えて、遺言のルールを正しく理解しておきたい方
🖋遺言とは?まず押さえておきたい基本知識
遺言とは、自分の死後の財産の分け方などを生前に意思表示しておくための制度です。
遺言があれば、自分の想いを反映させた遺産の分配や、家族へのメッセージを残すことができます。
民法では、遺言について細かなルールが定められており、特に行政書士試験でも重要なテーマの一つです。
✅遺言できるのは誰?|遺言能力とは
遺言を書くには、「遺言能力」が必要です(963条)。ただし、これは通常の「契約などをするための行為能力」とは異なります。
遺言は本人の死後に効力が発生するため、行為能力の制限で保護する必要がないとされているからです(962条)。
| 属性 | 遺言できる? |
|---|---|
| 未成年者 | 15歳以上なら単独で可能(961条) |
| 成年被後見人 | 一時的に判断能力を回復しており、医師2人以上の立合いが必要(973条1項) |
| 被保佐人 | 制限なし(962条) |
| 被補助人 | 制限なし(962条) |
📄遺言の種類とそれぞれの特徴
遺言は、改ざん防止や意思の明確化のため、法律で決められた形式(方式)に従う必要があります。
大きく「普通方式」と「特別方式」に分かれます。
▶普通方式の3つ
普通方式は、本来の遺言の方式であり、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります(967条本文)。3それぞれの特徴は次の通りです。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
| メリット | 他人の関与無しで容易に作成可 費用がかからない | 遺言の存在と内容が明確 不備が生じにくい | 内容を秘密にできる |
| デメリット | 遺言書の偽造や滅失のおそれがある | 証人に遺言の内容を知られるため秘密を保持しにくい | 手続きが複雑 費用がかかる |
| 公証人 | 関与なし | 関与あり | 関与あり |
| 承認 | 不要 | 必要(969条1号) | 必要(970条3号) |
| 検認 | 必要(1004条1項) | 不要(1004条2項) | 必要(1004条1項) |
▶特別方式の4つ
死が差し迫り、普通方式に従った遺言をする余裕のない場合に用いられるもので、次の4種類があります。
遺言の全体像は次の通りです。
--- config: theme: neutral --- flowchart LR 遺言 --> 普通方式 普通方式 --> 自筆証書遺言 普通方式 --> 公正証書遺言 普通方式 --> 秘密証書遺言 遺言 --> 特別方式 特別方式 --> 死亡危急者遺言 特別方式 --> 伝染病隔離者遺言 特別方式 --> 在船者遺言 特別方式 --> 船舶遭難者遺言 style 自筆証書遺言 color:blue click 自筆証書遺言 "#自筆証書遺言の方式" style 公正証書遺言 color:blue click 公正証書遺言 "#公正証書遺言の方式" style 秘密証書遺言 color:blue click 秘密証書遺言 "#秘密証書遺言の方式"
🖊自筆証書遺言のルール
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文・日付・氏名を自筆し、これに印を押さなければならない(968条1項)。123
また、自筆証書の遺言を変更する場合には、変更の場所を指示し、変更内容を付記して署名し、かつ、変更の場所に押印しなければ効力を生じない(968条3項)。
・全文・日付・名前を自分で書くこと
・押印が必要
・修正したいときは、変更の場所を明示し、署名・押印しなければ無効
📜公正証書の作成方法
公正証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授しなければならない(969条2項)。4
📜秘密証書遺言の作成方法
秘密証書によって遺言をするには、遺言者が、
①証書に署名・押印した上、
②その証書を証書に用いた印章により封印し、
③公証人1人および証人2人以上の面前で、
当該封書が自己の遺言書である旨やその筆者の氏名・住所を申述する必要がある(970条1項1~3号)。5
遺言の証人・立会人
証人・立会人の要否については以下の通り。
🚫証人・立会人になれない人(974条)
- 未成年者
- 推定相続人および受遺者並びにこれらの配偶者および直系血族
- 公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・使用人
💡共同遺言は禁止
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない(975条)。
このため、夫婦であっても、同一の証書で遺言をすることはできない。67
⚙遺言の効力はいつから?
遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じます(985条1項)。
ただし、遺言に停止条件を付した場合、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生じます(985条2項)。
🏠遺贈とは?種類と違いを整理!
- ①遺贈とは?
-
「遺贈」とは、遺言によって財産を無償で他人に譲渡することです。
- ②遺贈の種類
-
遺贈には、次の2種類があります。
さらに、遺贈についての承認・放棄と撤回は下表のようになる
- ③遺贈の承認または放棄の催告
-
遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認または放棄をすべき旨の催告をすることができる(987条前段)。
- ③負担付遺贈
-
負担付遺贈とは、受遺者に一定の義務を課する内容を有する遺贈のこと。10
受遺者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う(1002条1項)。
⚖遺言の執行と検認
遺言の執行とは?
遺言の内容を実現するために、財産の登記の移転や物の引渡しを行うことです。
遺言執行者がいれば、相続人は勝手に財産処分できません(1013条)。
検認とは?
検認とは、遺言書の保存を確実にして後日の変造や隠匿を防ぐ証拠保全手続のことです。
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないとされています(1004条1項前段)。また、遺言書の保管者がない場合、相続人が遺言書を発見した後も同様の扱いです(1004条1項後段)。
ただし、公正証書遺言の場合は、偽造・変造のおそれがないので検認は不要です(1004条2項前段)。
遺言執行者
遺言執行者とは、遺言の執行のために特に選任された者のこと。
遺言執行者がいる場合、相続人は、遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません(1013条1項)。これに違反して相続人が遺贈の目的物についてした処分は無効となります(1013条2項本文)。
🔁遺言の撤回はいつでも可能
撤回自由の原則
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます(1022条)。11
そして、遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができません(1026条)。
撤回の擬制
以下の場合には、撤回があったものとみなされます。
- 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分(1023条1項)。
- 遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触するときは、その抵触する部分(1023条2項)。
- 遺言者が故意に遺言書・遺贈の目的物を破棄したときは、その破棄した部分(1024条)。
撤回の効果
撤回された遺言は、その撤回行為が、撤回され、取り消され、または効力が生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しません(1025条本文)。12
ただし、撤回行為が錯誤、詐欺または強迫による場合は、撤回された遺言が復活する(1025条但書)。
🎯まとめ:遺言の基本を押さえよう
- 遺言は15歳以上なら可能。方式に従って作成しないと無効になることも!
- 自筆・公正・秘密証書遺言にはそれぞれメリット・デメリットがある
- 遺言執行者がいれば、内容の実現もスムーズに
- 検認や撤回のルールも試験で問われやすい!
- 重要判例:カーボン紙を用いて複写の方式で記載したときでも、「自筆」の要件に欠けるところはなく、有効は遺言となる(最判平5.10.19) ↩︎
- 重要判例:「〇年〇月吉日」と記載されている場合は、暦上の特定の日を表示するものではなく、「日付」の記載を欠くものとして、無効な遺言となる(最判昭54.5.31) ↩︎
- 参考:自筆証書の遺言に相続財産の目録を添付する場合には、その目録については自書を要しない(968条2項前段)。 ↩︎
- 口がきけない者が公正証書によって遺言する場合には、遺言者は、公証人・証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、口授にかえなければならない(969条の2第1項前段)。 ↩︎
- 重要判例:証書は自書によらず、ワープロ等の機械により作成されたものでもよい(最判平14.9.24) ↩︎
- 重要判例:同一の証書に2人の遺言が記載されている場合、そのうちの一方につき氏名を自書しない方式の違背があるときでも、共同遺言に当たり、他方の遺言も含めて遺言全部が無効となる(最判昭56.9.11) ↩︎
- 重要判例:一通の証書に2人の遺言が記載されている場合であっても、その証書が各人の遺言書の用紙をつづり合わせたもので、両者が容易に切り離すことができるときは、当該遺言は共同遺言に当たらない(最判平5.10.19) ↩︎
- 包括遺贈の例:包括遺贈の例としては、遺産の3分の1を遺贈する場合など ↩︎
- 特定遺贈の例:遺産である甲土地を遺贈する場合など ↩︎
- 具体例:遺言者が自己所有の土地を遺贈する代わりに、受遺者に対して自己の介護を義務付ける場合など ↩︎
- 参考:「撤回する遺言」と「撤回される遺言」は同一の方式でなくてもよい。 ↩︎
- 重要判例:遺言者が「遺言を撤回する遺言」をさらに別の遺言をもって撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が当初の遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、当初の遺言の効力が復活する(最判平9.11.13) ↩︎