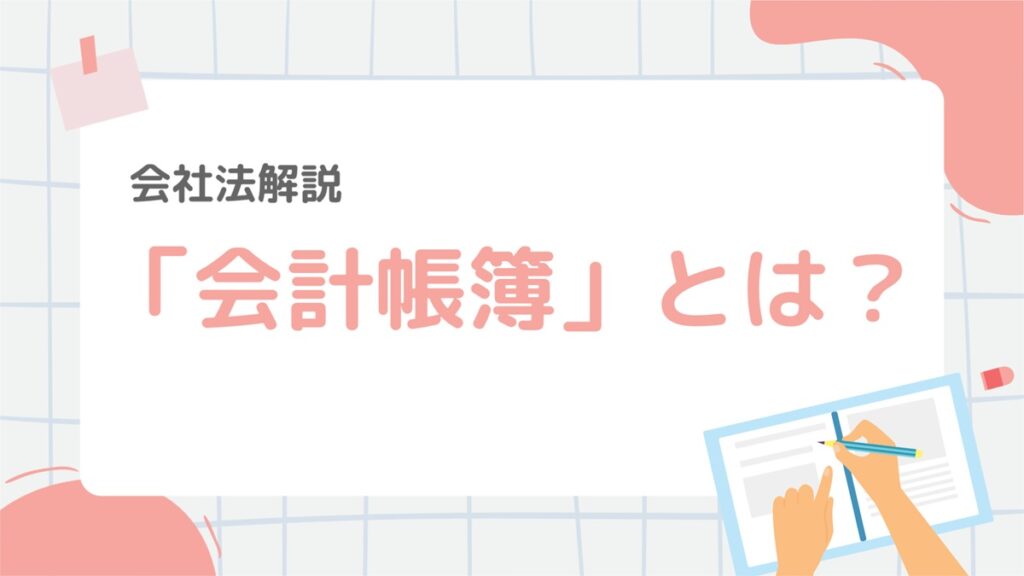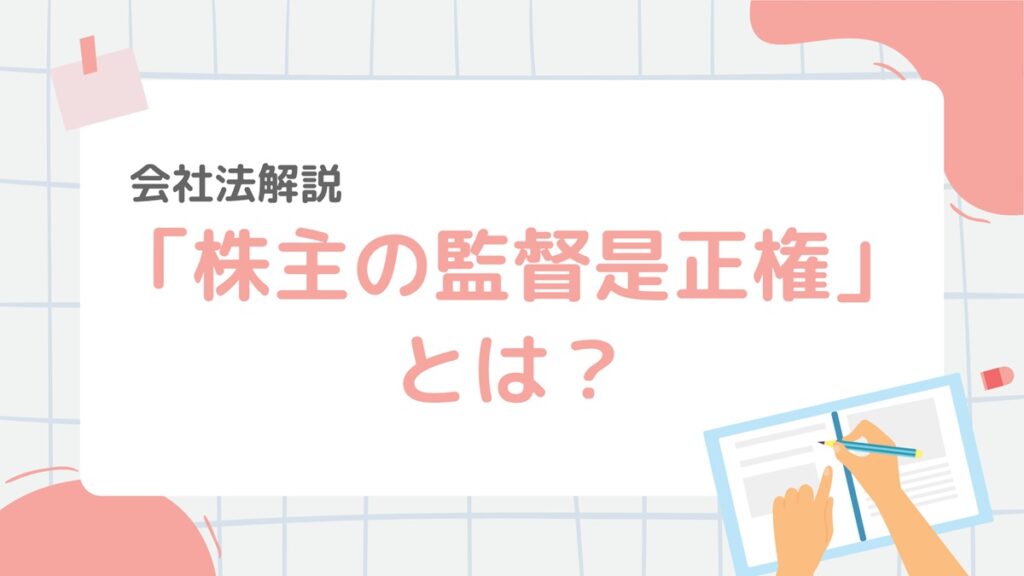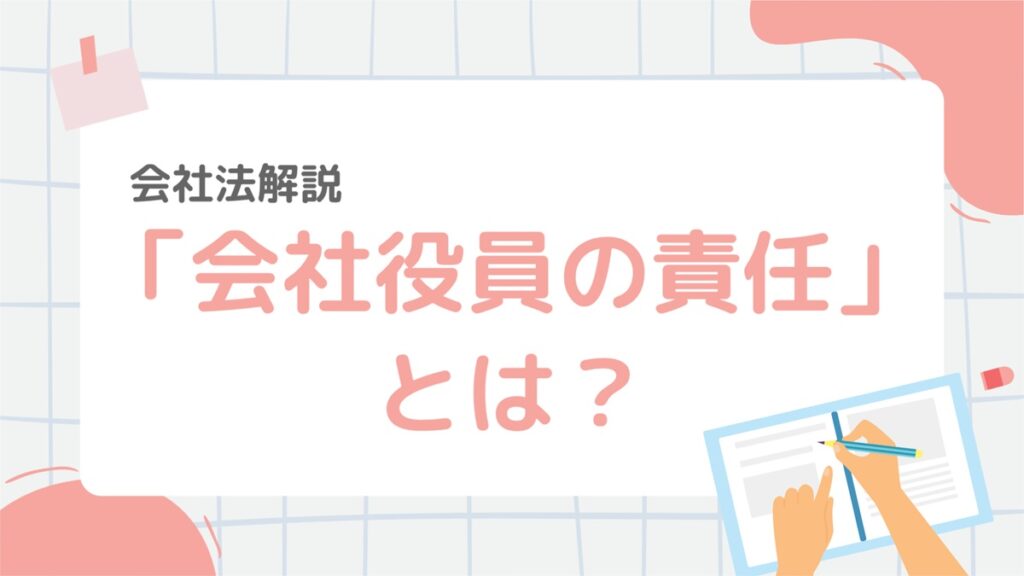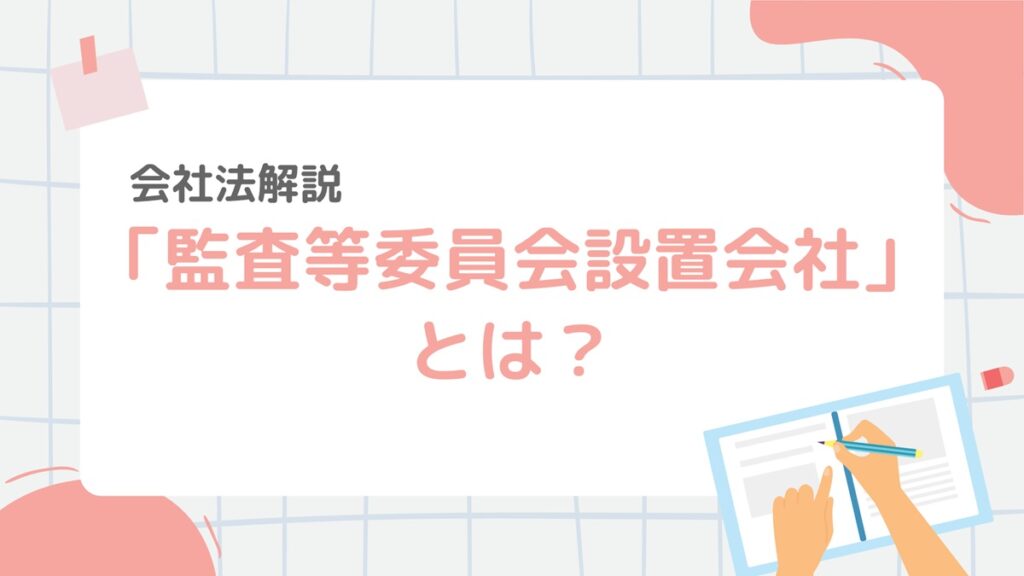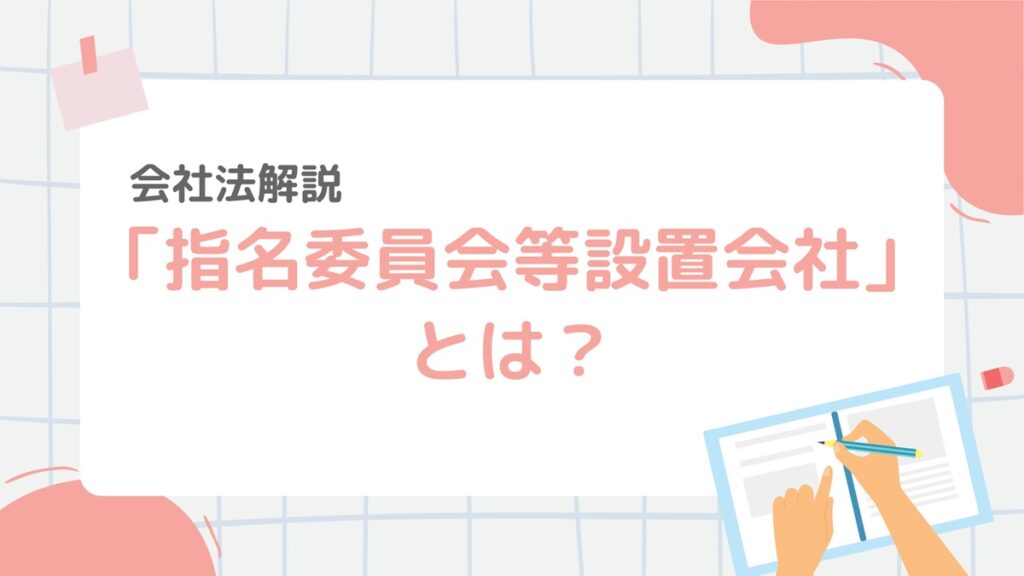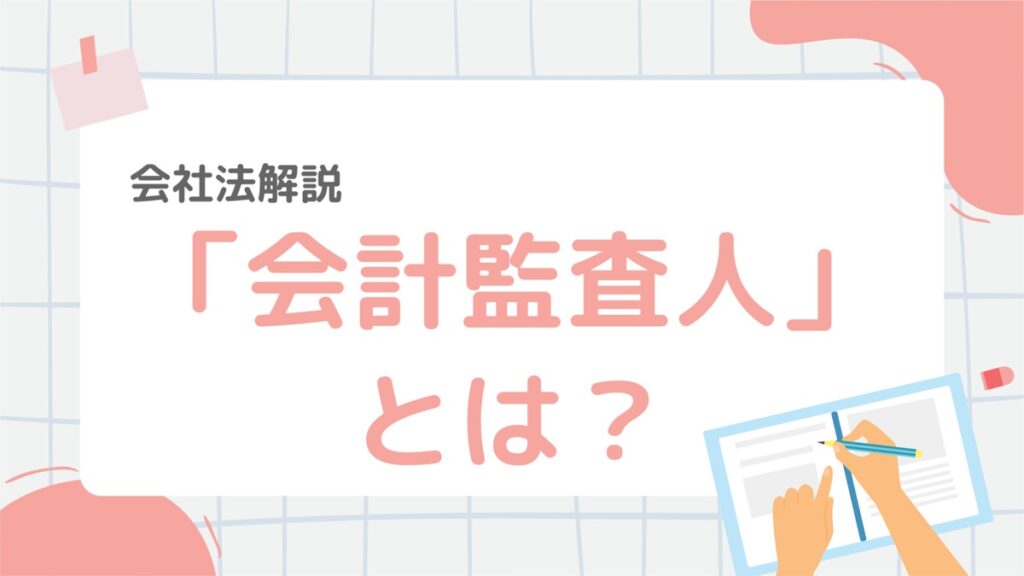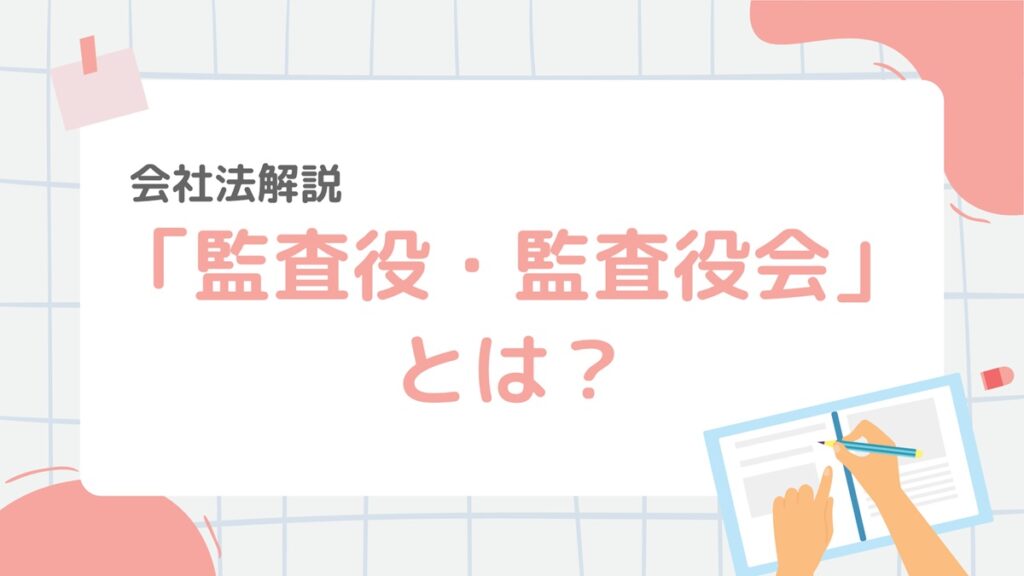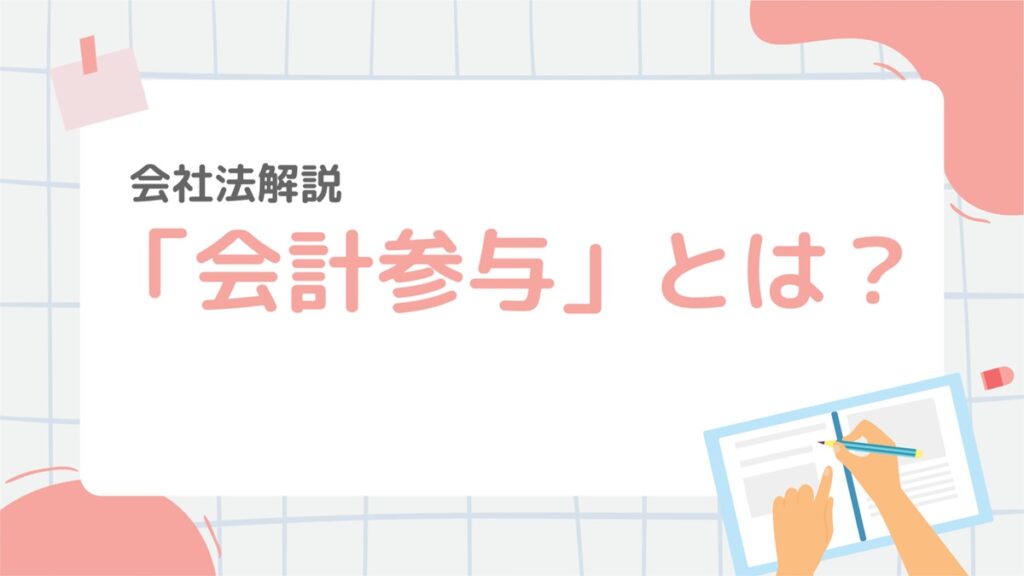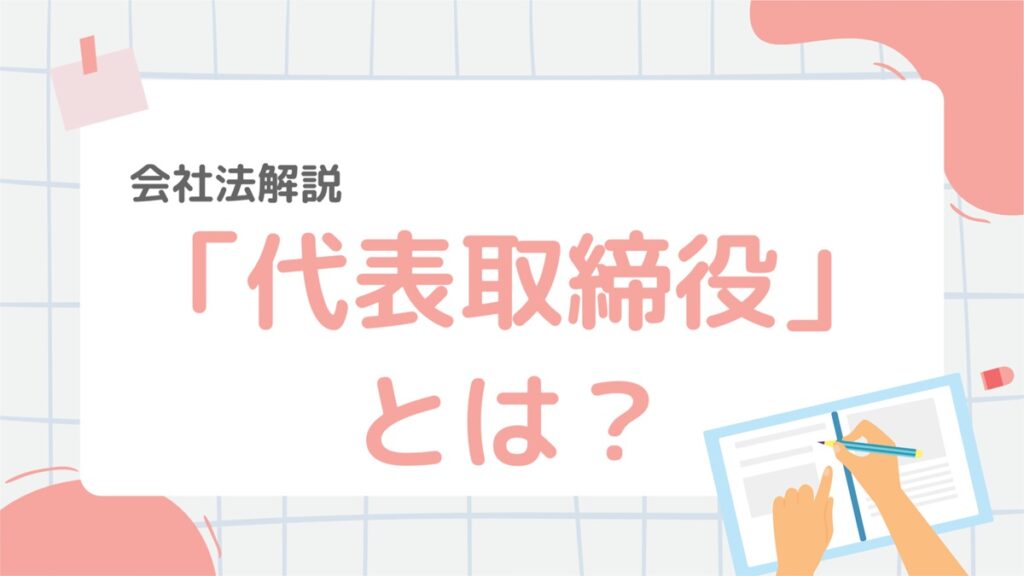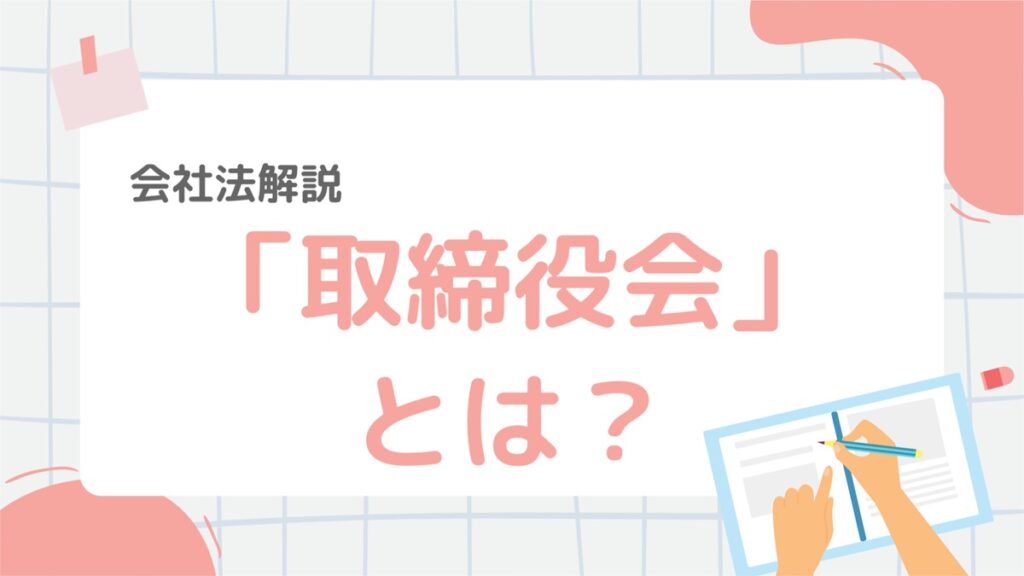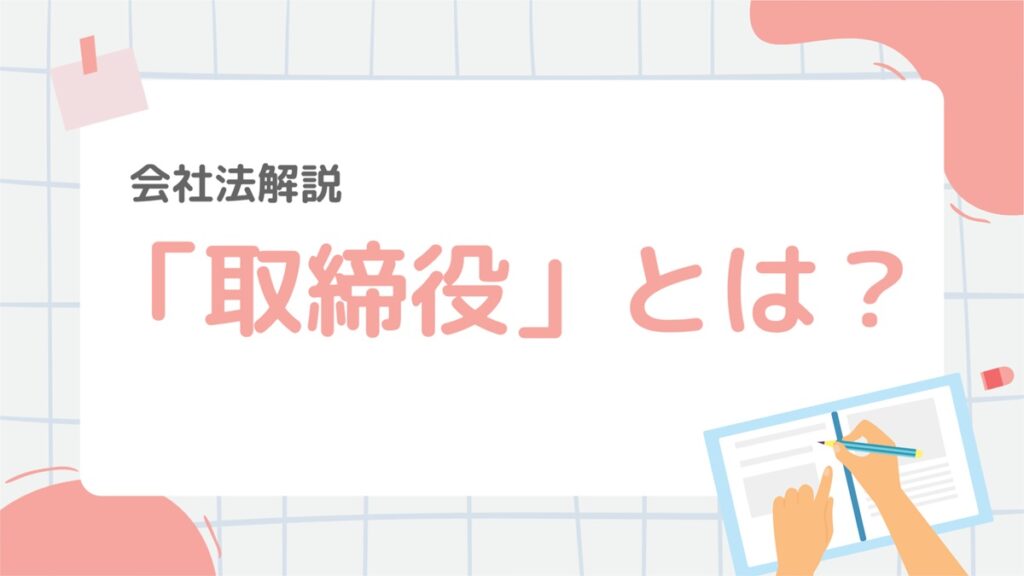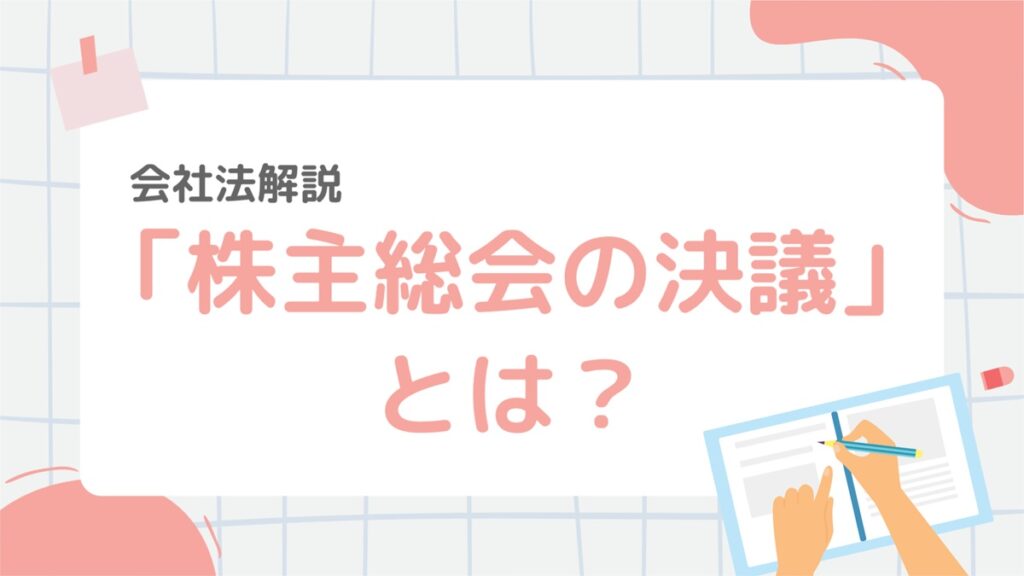会社法解説– tag –
-

会社法5-1:「会計帳簿」とは?作成・保存義務や閲覧請求のルールをやさしく解説
🔰この記事はこんな人におすすめ! 「会計帳簿って何?」という初学者の方 株式会社の帳簿に関する会社法のルールを理解したい方 少数株主の権利(閲覧・謄写請求)について知りたい方 行政書士試験の会社法対策を進めたい方 会計帳簿とは?意味をわかりや... -

会社法4-15:「株主の監督是正権」とは?少数株主が会社を守るための3つの方法
この記事はこんな人におすすめ! 「株主の監督是正権って何?」と疑問に思っている方 行政書士試験で会社法を学習中の方 少数株主がどのように会社の不正をただせるのか知りたい方 試験に出やすい条文(会社法360条・847条など)を押さえたい方 株主の監督... -

会社法4-14:「会社役員の責任」とは?損害賠償や免除・制限、第三者への責任までわかりやすく解説!
この記事はこんな人におすすめ! 行政書士試験で「会社法」を学んでいる方 取締役や役員の責任範囲について理解を深めたい方 会社法423条・429条などの条文をイメージで覚えたい方 会社役員が負う損害賠償責任の種類を整理したい方 役員が負う「会社に対す... -

会社法4-13:「監査等委員会設置会社」とは?わかりやすく解説!
この記事はこんな人におすすめ 「監査等委員会設置会社って何?」と基本から知りたい方 「他の会社形態(監査役会設置会社・指名委員会等設置会社)との違いがよくわからない」という方 行政書士試験で会社法を勉強中の方 監査等委員会設置会社とは? 監査... -

会社法4-12:「指名委員会等設置会社」とは?わかりやすく解説!
この記事はこんな人におすすめ 「指名委員会等設置会社」が何かよくわからない方 株式会社の組織形態について学びたい方 行政書士試験で会社法の出題対策をしたい方 「執行役」って誰?と疑問に思っている方 指名委員会等設置会社とは?やさしく解説! 指... -

会社法4-11:「会計監査人」とは?役割・監査役との違い・設置要件をわかりやすく解説!
この記事はこんな人におすすめ! 行政書士試験で「会社法」の分野が苦手な方 「会計監査人」と「監査役」の違いがよくわからない方 会計監査人に必要な資格や設置基準を知りたい方 試験に出るポイントだけを効率よくおさえたい方 会計監査人とは?簡単に言... -

会社法4-10:監査役・監査役会とは?役割・資格・権限までやさしく解説!
🎯この記事はこんな人におすすめ! 「監査役って何をする人なの?」と疑問に思っている方 行政書士試験の商法(会社法)対策をしている方 監査役と監査役会の違いや役割をスッキリ整理したい方 出題されやすい条文やポイントを押さえておきたい方 監査役と... -

会社法4-9:「会計参与」とは?意味・役割・要件をわかりやすく解説!
この記事はこんな人におすすめ 「会計参与ってなに?」と基本から理解したい方 行政書士試験で「会社法」の出題に備えたい方 会計参与に就任できる資格や役割を確認したい方 会計参与とは?会社の「数字の信頼性」を高める専門家! 会計参与とは、会社が作... -

会社法4-8:「代表取締役」とは?選び方・権限・表見代表取締役までわかりやすく解説!
✅この記事はこんな人におすすめ 「代表取締役」と「取締役」の違いがよくわからない 会社法で出てくる「取締役会設置会社」や「表見代表取締役」って何?と思っている 行政書士試験で出題されやすい代表取締役の選定・権限・責任を整理したい 代表取締役と... -

会社法4-7:「取締役会」とは?役割・決議・手続きまでわかりやすく解説
🎯この記事はこんな人におすすめ 取締役会の役割や手続きをわかりやすく把握したい方 行政書士試験の「会社法」の理解を深めたい方 決議や議事録に関するルールを整理して覚えたい方 取締役会とは?どんな役割があるのか 取締役会は、株式会社のすべての取... -

会社法4-6:「取締役」とは?役割・資格・権限をやさしく解説
🎯この記事はこんな人におすすめ! 「取締役って、社長のこと?それとも誰?」と疑問に思っている方 会社法の取締役に関する論点を効率よく学びたい行政書士受験生 難解な条文の意味をやさしい言葉で理解したい方 📌取締役とは?〜取締役の基本的な役割〜 株... -

会社法4-5:「株主総会の決議」とは?普通決議・特別決議の違いを簡単解説
株主総会の権限 株主総会の招集 株主総会の議事 株主総会の決議 🧭この記事はこんな人におすすめ! 行政書士試験で「会社法」を重点的に勉強している方 株主総会の決議の種類(普通決議・特別決議など)の違いがよくわからない方 決議に瑕疵があった場合の...