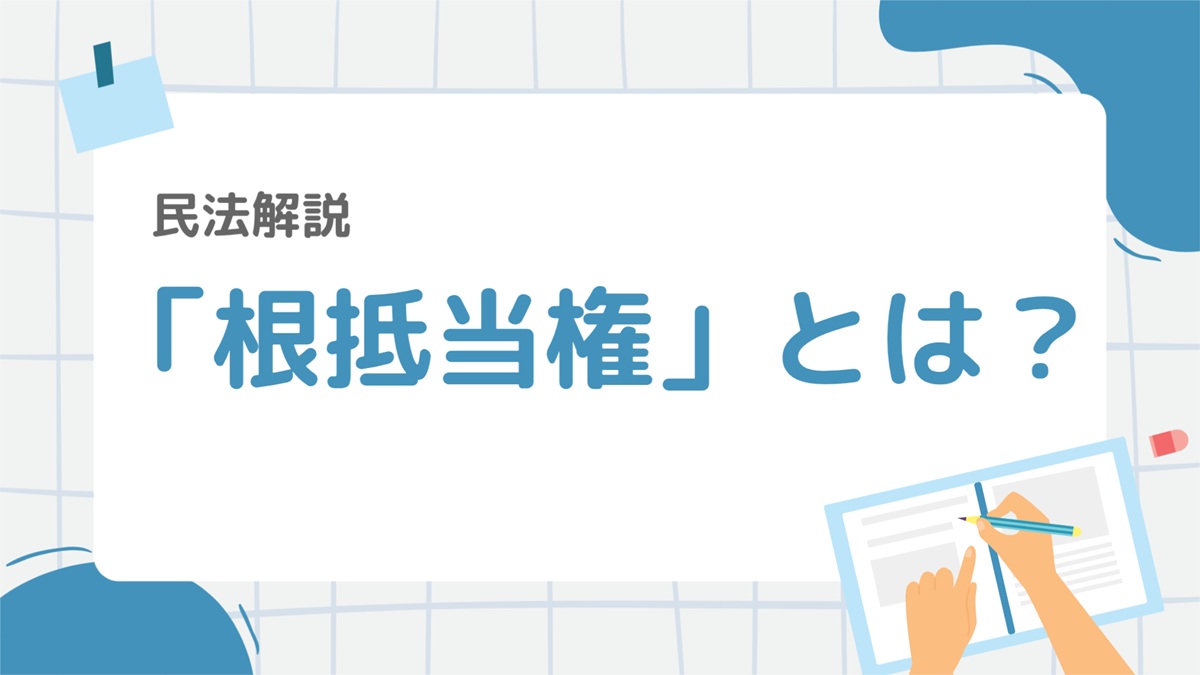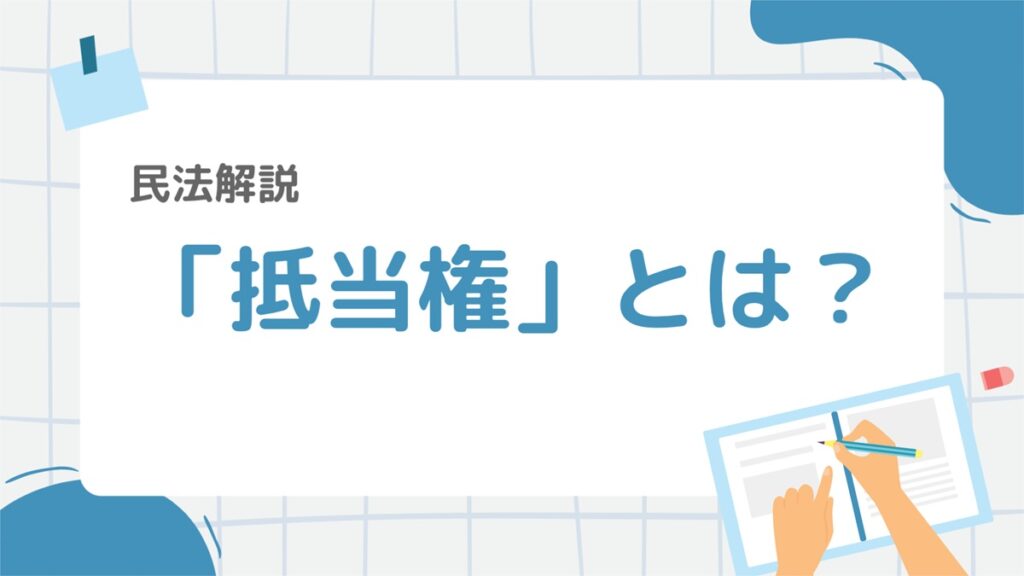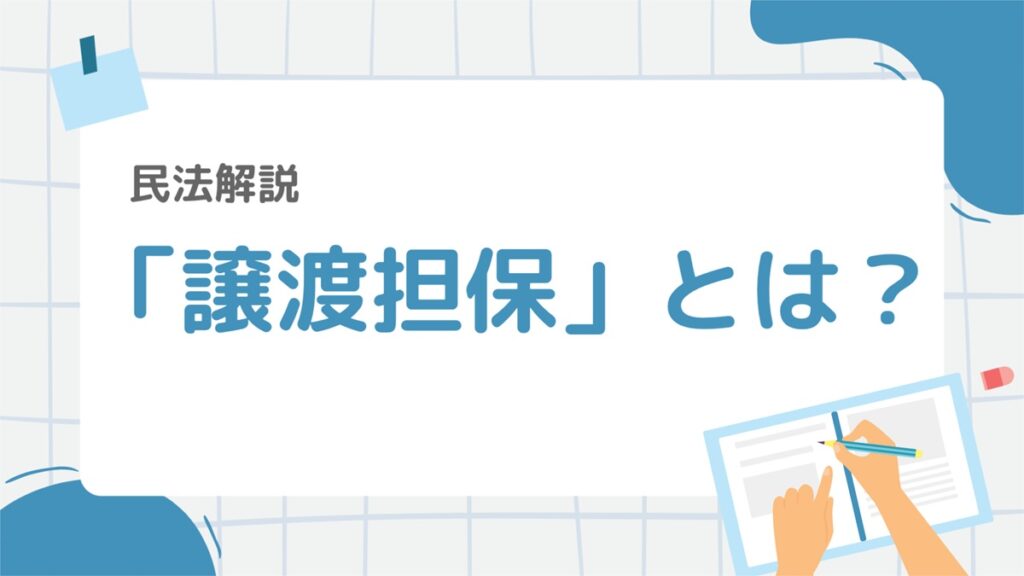根抵当権
根抵当権とは?
sequenceDiagram autonumber participant A所有の土地 actor A_債務者_根抵当権設定者 actor B_債権者_抵当権者 B_債権者_抵当権者 ->> A_債務者_根抵当権設定者:貸金債権(1000万円の限度) B_債権者_抵当権者 ->> A所有の土地:根抵当権
小売業を営むAは、商品の仕入先である問屋Bから継続的に商品を仕入れていました。Aは、その商品代金の支払い債務を最大1,000万円まで担保する目的で、自分が所有する土地に抵当権を設定しました。
事例のように、一定の範囲に属する不特定の債権を、あらかじめ定めた限度額(極度額)まで担保するために設定される抵当権を「根抵当権」といいます(398条の2第1項)。
また、根抵当権によって担保される債権のことを元本といいます。1
被担保債権の範囲
根抵当権者は、確定した元本・利息・その他の定期金、および債務不履行によって生じた損害の全部について、極度額を限度として根抵当権を行使することができます(398条の3第1項)。
内容の変更
根抵当権は、継続的な取引から生ずる債権を担保するため、1つの債権が弁済されても消滅せず、長期間にわたって存続します。その結果、途中で根抵当権に関わるさまざまな要素が変わる可能性があります。
そのため、このような状況の変化に対応するための規定が設けられています。
被担保債権の譲渡
元本確定前に、根抵当権者から被担保債権を譲り受けた者は、その債権について根抵当権を行使することはできません(398条の7第1項前段)。
また、元本確定前に被担保債務の債務引受があった場合には、根抵当権者は、引受人の債務について、根抵当権を行使することができません(398条の7第2項)。
確定
確定とは、根抵当権によって担保される元本債権が特定されることを指します。これにより、それまでに発生した債権が被担保債権となり、それ以降に発生する元本債権は担保の対象外となるため、根抵当権は通常の抵当権とほぼ同じ扱いになります。
これにより、債務者は確定した債務を弁済することで、根抵当権を消滅させることができます。また、債権者は、確定後の債権を根抵当権付きで譲渡することが可能です。
極度額の減額請求
元本確定後、根抵当権設定者は、根抵当権の極度額を、「現存する債務の額」と「今後2年間に発生する利息その他の定期金および債務不履行による損害賠償額」を合算した額まで減額するよう請求することができます(398条の21第1項)。
この規定は、元本確定時に被担保債権の額が極度額に達していない場合に、残存する担保価値を根抵当権設定者(債務者)が有効に活用できるようにするため、極度額の減額請求を認めたものです。