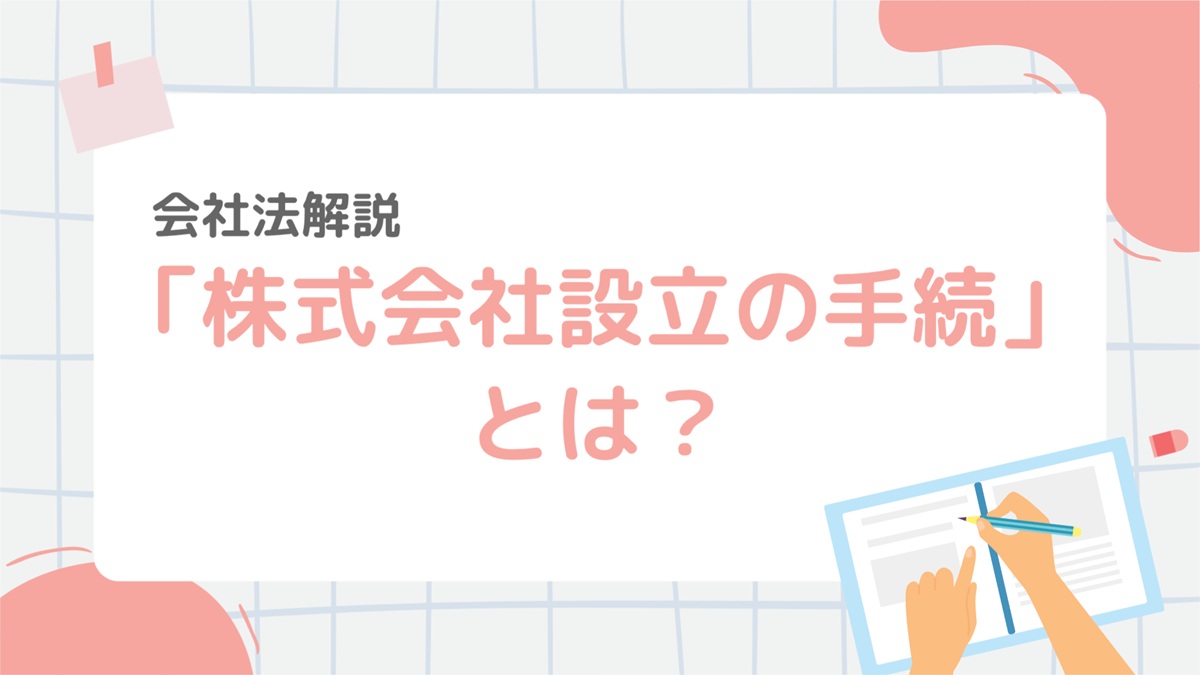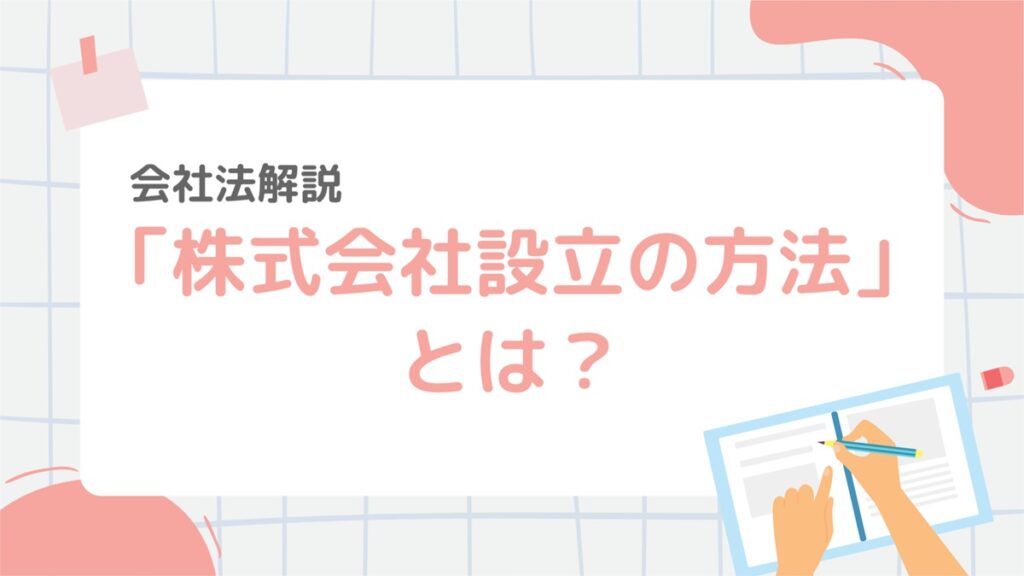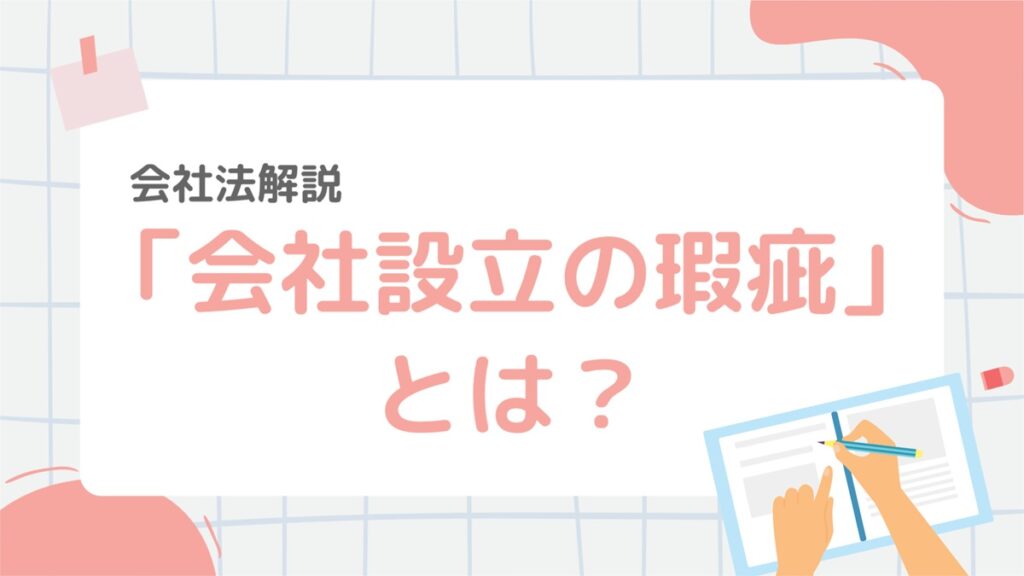- 株式会社設立の流れを図解や具体例で理解したい人
- 「定款って何?」という初学者〜中級者の方
- 難解な条文に疲れたけど、試験に出るところだけ効率的に学びたい人
株式会社設立の手続きはこの5ステップ!
株式会社は、以下の5つのステップを経て誕生します。
以下、それぞれのステップを行政書士試験対策として要点を絞って解説します!
①定款の作成 〜まずは会社の設計図をつくる〜
会社設立の最初の一歩は「定款(ていかん)」づくりです。これは会社の基本ルールをまとめたもの(26条)。ここで作成される定款を原始定款といいます。
発起人が作成し、公証人の認証を受けて初めて効力が発生します(30条1項)。
定款に記載する事項
定款に記載する事項は、①絶対的記載事項、②相対的記載事項、③任意的記載事項の3つに分類されます。
- 絶対的記載事項
-
- 意味:
必ず定款に定めなければならない事項であって、定めておかないと定款自体が無効となるもの。 - 具体例:
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名・名称・住所
- 発行可能株式総数1
- 意味:
- 相対的記載事項
- 任意的記載事項
-
- 意味:
強行法規・公序良俗に反しなければ自由に定めることができる事項 - 具体例:
- 取締役の員数
- 定時株主総会の開催時期
- 意味:
変態設立事項とは?
変態設立事項とは、会社の財産面でリスクが高い「特別な取決め」のこと。28条に4つの事項があります。2
- 現物出資:金銭以外の財産による出資のこと(不動産・動産・特許権など)
- 財産引受:発起人が会社の成立を条件として成立後の会社のために一定の営業用の財産を譲り受ける契約のこと
- 発起人の報酬や特別利益:発起人の労務に対して与えられる財産上の利益のこと
- 設立費用:会社の負担する設立に関する費用のこと(設立事務所の賃借料や、設立事務をする事務員の給与など)
👉 これらは 原始定款に記載し(28条)、さらに 裁判所が選任する検査役の調査が必要(33条1項)。
ただし、現物出資と財産引受については、以下の場合に、検査役の調査が不要とされる(33条10項)。
👇検査役の調査が不要とされる場合
- 定款に記載・記録された価額の総額が500万円を超えない場合
- 市場価格のある有価証券について定款に記載・記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合
- 定款に記載・記録された価額が相当であることについて弁護士等の証明を受けた場合(現物出資財産等が不動産である場合、不動産鑑定士の鑑定評価も必要)
②株主の確定(=株式の割当て)
発起人は、誰にどれだけ株を与えるかを決める「株式の割当て」を行います。
定款で定めが必要な部分と、発起人の多数決で決められる部分があります。
株式発行事項の決定
設立時発行株式に関する事項のうち、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額は、定款で定める必要がありますが(27条4号)、その他の事項は定款で定める必要はなく、原則として、発起人の多数決で決定することができる。3
ただし、
①発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数、
② ①の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額、
③成立後の株式会社の資本金および資本準備金の額に関する事項
については、定款で定めていないときには、発起人の全員の同意を得て定めなければなりません(32条1項、58条1項・2項)。
③出資の履行(お金や現物を実際に会社に渡す)
会社設立には「出資の履行(しゅっしのりこう)」が必要です。
つまり、決めた通りに お金や現物を会社に払う(渡す)ことです。
全額払込主義
発起人は、設立時発行株式の引受後遅滞なく、募集設立における募集株式の引受人は、発起人が定めた払込期日または払込期間中に、引き受けた株式につき全額の払込みまたは全部の給付(これを出資の履行4という)をしなければなりません(34条1項本文、63条1項)。56
※参考
出資しない人に対する「失権手続」
発起人のうち出資を履行しない者がいる場合、発起人は、失権予告付で払込を催告し、払込みがなければ失権します(36条1項・3項)。発起人以外の引受人の不履行の場合は、当然に失権します。
払込取扱場所・払込取扱機関による保管証明
発起人が不正(横領・搾取など)にお金を使わないよう、銀行や信託会社(払込取扱機関の払込取扱場所)を通して払込を行い、募集設立の場合には、必要に応じて払込取扱機関に対して「保管証明書」の交付を請求することができます(34条2項)。
これに対して、発起設立の場合、保管証明制度は廃止されています。7
創立総会とは?|設立中の会社が最初に行う“株主の会議”
創立総会とは、設立時株主(=設立時に株式を引き受けた人たち)で構成される会議で、会社設立の最終段階で重要な意思決定を行う場です。
募集設立の場合、発起人は、設立時募集株式の払込期日または払込期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、創立総会を招集しなければなりません(65条1項)。
創立総会は、会社設立後の株主総会に相当するものであり、手続についても株主総会とほぼ同様。
ただし、創立総会の決議要件は、株主総会の決議要件とは異なり、原則として、議決権を行使できる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した設立時株主の議決権の3分の2以上(73条1項)。8
④設立時役員等の選任
誰がどうやって決めるの?
設立時役員等9の選任10方法は、発起設立と募集設立で異なります。
| 設立の形態 | 発起設立 | 補修設立 |
|---|---|---|
| 誰が? | 発起人 | 創立総会 |
| 方法 | 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時役員等を選任しなければならず(38条1項・3項)、発起人が1株につき1個の議決権を有し、その議決権の過半数で選任する(40条1項・2項本文)。1112 | 創立総会の決議によって選任する(88条1項) |
選ばれた「設立時取締役」は、会社がちゃんと設立されているかチェックを行います。
問題があれば、発起人や創立総会に報告しなければなりません。
設立時取締役の職務・権限等
設立時取締役13が選任された後でも、設立事務を行うのは発起人です。
設立時取締役は、設立事項(現物出資等について定款記載価額が相当であるか、出資の履行が完了しているか、設立手続に法令・定款違反がないか等)の調査を行う権限のみを有します(46条1項、93条1項)。
そして、調査の結果、法令・定款違反等があれば、発起設立の場合は各発起人に通知し(46条2項)、募集設立の場合は創立総会へ報告しなければなりません(93条2項)。
設立時役員等の解任
設立時役員等は、会社が成立するまでの間、解任することができます。設立時役員等の解任方法は、発起設立と募集設立で異なります。
| 発起設立 | 補修設立 |
|---|---|
| 発起人の議決権の過半数(設立時監査等委員である設立時取締役または設立時監査役を解任する場合は、3分の2以上の多数)によって解任する(43条1項) | 創立総会の決議によって解任する(91条) |
⑤設立の登記(=ここで会社が正式に成立!)
最後に、「設立の登記」を法務局で行います。
これにより、株式会社として法律上正式に誕生します(49条)。
まとめ:行政書士試験でよく出るチェックポイント!
✅ 定款には絶対的記載事項を忘れずに!
✅ 変態設立事項の4つは丸暗記&検査役要件もセットで!
✅ 出資の履行と失権の流れを整理!
✅ 発起設立と募集設立での手続の違いに注意!
✅ 登記して初めて会社が成立する!
- 参考:発起設立・募集設立のいずれの場合でも、発行可能株式総数を原始定款で定めていないときは、会社設立時までに定款を変更して定めなければならない(37条1項、98条) ↩︎
- 参考:会社の設立に際して現物出資を行うことができるのは発起人のみであるが(34条1項、63条1項)、財産引受については、発起人以外の者もその相手方となることができる。 ↩︎
- 参考:公開会社においては、会社設立時に発行する株式の数は、発行可能株式総数の4分の1を下回ることができない(37条3項)。 ↩︎
- 参考:発起人が出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、設立後の株式会社に対抗することができない(35条)。 ↩︎
- 参考:発起人全員の同意があるときは、登記・登録その他の権利の設定・移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができる(34条1項但書)。 ↩︎
- 参考:設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、心裡留保(民法93条1項但書)と虚偽表示(民法94条1項)の規定は適用されない(51条1項)。また、株式会社の成立後は、錯誤(民法95条1項)・詐欺・強迫(民法96条1項)を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることもできない(51条2項)。 ↩︎
- 参考:保管証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること、または当該金銭の返還に関して制限があることをもって、成立後の株式会社に対抗できな(64条2項)。 ↩︎
- 参考:創立総会においても、株主総会と同様、書面による議決権行使や電磁的方法による議決権行使が認められている(75条、76条)。 ↩︎
- 設立時役員等:会社の設立に際して、取締役、会計参与、監査役、会計監査人となる者のこと。 ↩︎
- 参考:欠格事由に該当しない限り、発起人が設立時役員等に就任することは妨げられない。 ↩︎
- 参考:定款で設立時役員等として定められた者は、出資の履行が完了した時に、設立時役員等に選任されたものとみなされる(38条4項)。 ↩︎
- 参考:設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は3人以上でなければならない(39条3項)。 ↩︎
- 設立時取締役:株式会社の設立に際して取締役となる者のこと(38条1項)。 ↩︎