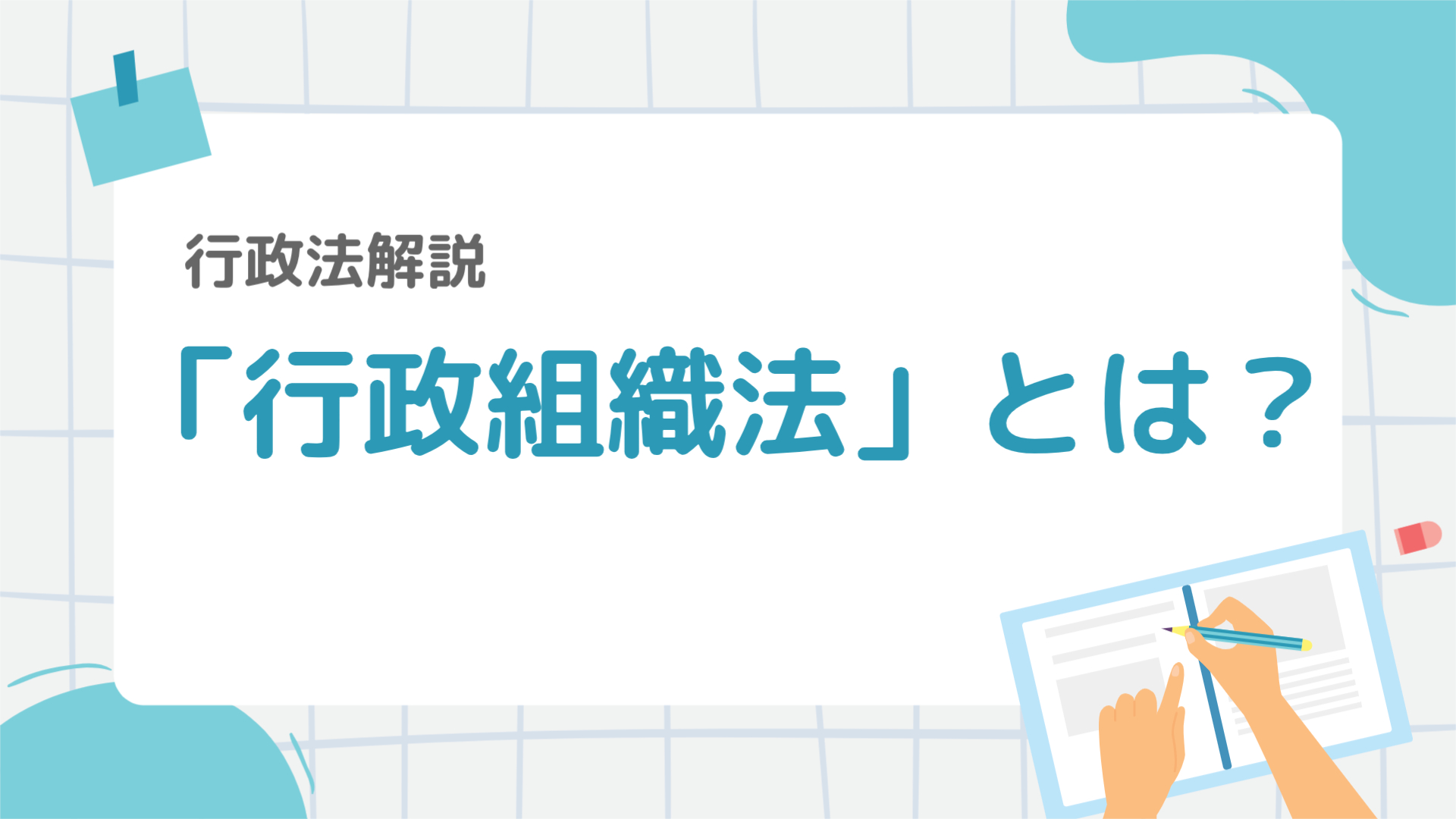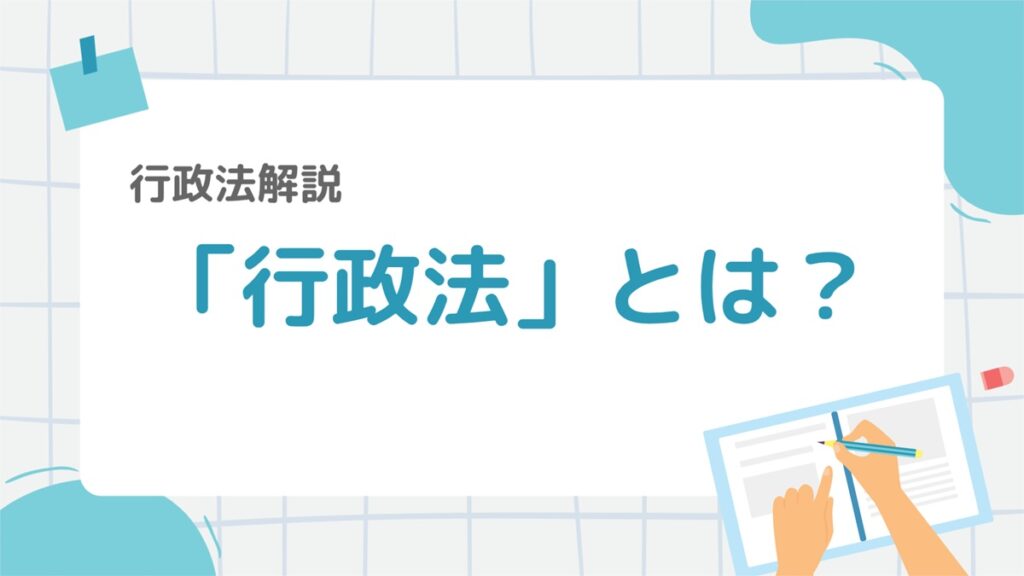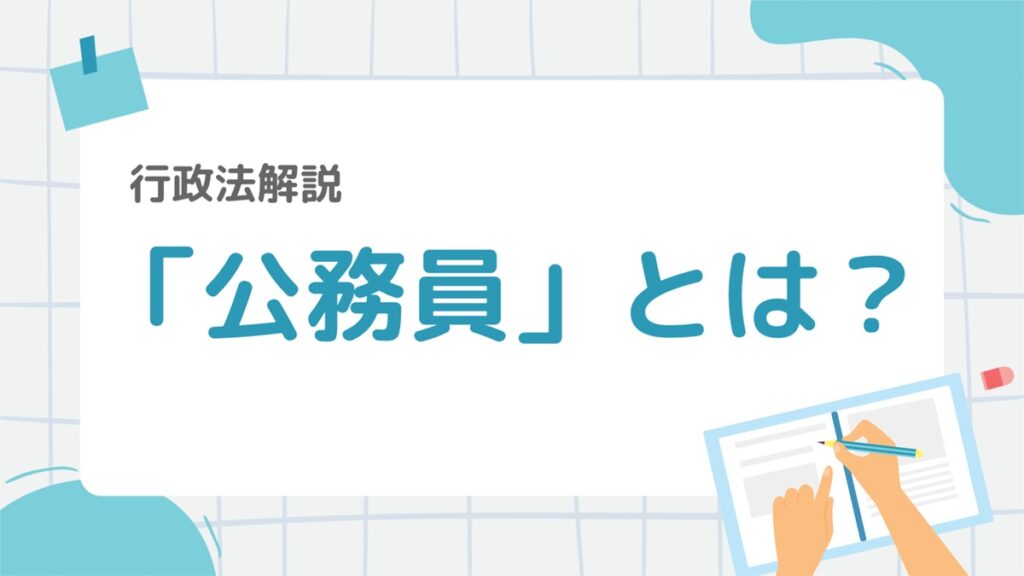- 行政書士試験で行政組織法の理解を深めたい方
- 行政主体と行政機関の違いを明確にしたい方
- 試験対策として、行政機関の分類や権限について整理したい方
行政主体と行政機関
行政主体とは?
行政主体は法人であり、実際に行政活動を行うことはできません。そこで、行政主体に代わって実際に業務を遂行する機関が必要となります。これが「行政機関」です。
行政主体には、国や地方公共団体(統治団体)と、それ以外の行政主体の二つの種類があります。
統治団体以外の行政主体には、以下の3種類があります。
- 公共組合
構成員が強制的に法人への加入や経費の支払いを義務付けられている法人です。設立や解散には国の意思が介在し、国の監督の下で公権力の行使が認められています。1 - 独立行政法人
公共の観点から確実に実施されることが求められる事務であり、国が直接実施する必要はないものの、民間にゆだねた場合には必ずしも実施されない可能性がある業務を、効率的かつ効果的に行わせることを目的として設立される法人です。2 - 特殊法人
法律に基づいて設立される法人、または特別な法律により設立行為をもって設立される法人のことを指します。新設や廃止に関する審査は総務省によって行われます。3
行政主体の体型をまとめると以下の通り。
--- config: theme: neutral --- flowchart LR 行政主体-->統治団体 統治団体-->国 統治団体-->地方公共団体 行政主体-->統治団体以外の行政主体 統治団体以外の行政主体-->公共組合 統治団体以外の行政主体-->独立行政法人 統治団体以外の行政主体-->特殊法人
行政機関とは?
行政主体は法人であり、実際に行政活動を行うことはできません。そこで、行政主体に代わって実際に業務を遂行する機関が必要となります。これが「行政機関」です。
行政機関は、以下の6つに分類されます。4
- ①行政庁
-
行政主体の意思を決定し、外部に表示する機関。
迅速な行政を実現し、責任の所在を明確にするため、原則として1人の人間が担当する「独任制」を採用しています。5中立性や慎重な判断が求められる場合は、複数人で構成される「合議制」が用いられることもあります。6 - ②諮問機関(しもんきかん)
-
行政庁から諮問7を受け、意見を述べる機関。8
あくまでも助言を行う立場であるため、行政庁はその意見に必ずしも従う必要はありません。9 - ③参与機関
-
行政庁の意思を拘束する議決を行う機関。10
諮問機関と異なり、行政庁は参与機関の議決に従わなければならず、違反した場合、その行為は無効とされます。 - ④監査機関
-
行政庁の事務や会計の処理が適正に行われているかを監査する機関。
代表的なものに、会計検査院や地方公共団体の監査委員があります。 - ⑤執行機関
-
行政目的を実現するために実力を行使する機関。
警察官、消防職員、自衛官、海上保安官などが該当します。 - ⑥補助機関
-
行政庁やその他の行政機関の職務を補助するため、日常的な事務を遂行する機関。
事務次官、局長、課長、一般職員などがこれに該当します。
行政機関の権限
指揮監督権
行政活動が統一した意思のもとで行われないと、国民の混乱を招くおそれがあります。そのため、行政機関は互いに他の行政機関の行政活動を尊重し、矛盾する行為をすることは許されないのが原則とされています。
そのため、行政組織は意思の統一を図るため、大臣などをトップとする階層構造を採用しています。これにより、上級行政機関は下級行政機関に対し、指揮監督権を行使することができます。
上級行政機関は指揮監督権に基づき、法律の特別の根拠がなくても、以下のような権限を行使できます。11
- 訓令権:下級行政機関の活動内容を指示すること
- 取消権:下級行政機関の行った違法な行政活動の取消しを要求すること
- 監視権:下級行政機関の事務の実行を調査すること
権限の代行
行政機関の権限は法律で定められているため、行政機関は原則としてその範囲内で活動しなければなりません。しかし、行政機関も人間である以上、病気や事故などで職務を遂行できなくなる可能性があります。そのような場合に備えて、他の行政機関が代わって権限を行使できる制度が権限の代行です。
権限の代行には、以下の3つの類型があります。
- ①権限の委任
-
権限の委任とは、ある行政機関の権限の一部を、別の行政機関に移動して行使させることです。1213
権限の委任は、法律で定められた権限が移動するため、法律の根拠が必要です。
権限の委任が行われると、委任元の行政機関(委任機関)はその権限を失い、委任を受けた行政機関(受任機関)が自己の名と責任で行使します。14
- ②権限の代理
-
権限の代理とは、ある行政機関の権限を、別の行政機関がその代理人として行使することです。
権限の代理がなされた場合、権限を代理する機関(代理機関)は、代理される機関(被代理機関)に代わってその権限を行使するだけであり、権限そのものが移動するわけではありません。
権限の代理は、本来の権限を有する行政機関が他の行政機関に対して代理権を授与することによって、代理関係が生じる授権代理と、法律で定められた一定の事由が生じた場合に当然に代理関係が生じる法定代理があります。
法定代理には、さらに本来の行政庁があらかじめ指定しておいた機関が代理権を持つ指定代理15と、法律の定める機関が代理権を当然にもつこととなる狭義の法定代理16の2つに分類されます。
授権代理は、法律の根拠は不要とされているのに対し、法定代理は、性質上、当然に法律の根拠が必要とされています。
権限の委任と代理の違いは次の通りです。
権限の委任 権限の代理 授権代理 法定代理 権限の移転 〇あり ×なし ×なし 権限の範囲 一部 一部 全部 法律の根拠 必要 不要 不要 - ③専決(せんけつ)・代決(だいけつ)
-
専決とは、法律によって権限を与えられた行政機関が、補助機関に対してその権限に関する事務の処理を委ねること。
代決とは、専決する人が不在の場合に、他の人が臨時にその権限に関する事務を処理すること。
これらは行政機関内部の問題であり、外部に対しては権限をもっている本来の行政機関の名で表示されます。17
なお、専決・代決がなされても、外部に対しては権限をもっている本来の行政機関の名で表示される以上、本来の行政機関が責任を負うことになるため、法律の根拠は不要とされています。
【権限の代行まとめ】
--- config: theme: neutral --- flowchart LR 権限の代行-->権限の委任 権限の代行-->権限の代理 権限の代理-->授権代理 権限の代理-->法定代理 法定代理-->指定代理 法定代理-->狭義の法定代理 権限の代行-->専決_代決
国の行政機関

国の行政組織については、国家行政組織法が規定しています。
国家行政組織法の目的は、内閣の統轄18の下における行政機関のうち、内閣府およびデジタル庁以外のの組織の基準を定めることです。これにより、国の行政事務を効率的に遂行するために必要な国家行政組織を整えることを目的としています(国家行政組織法1条)。
---
config:
theme: neutral
---
graph TB
内閣-->内閣府("内閣府")
内閣府-->庁_委員会("庁<br>委員会")
内閣-->省1("省")
省1-->庁_委員会1("庁<br>委員会")
内閣-->省2("省")
省2-->庁_委員会2("庁<br>委員会")
内閣-->省3("省")
省3-->庁_委員会3("庁<br>委員会")
内閣-->省4("省")
省4-->庁_委員会4("庁<br>委員会")
内閣-->省5("省")
省5-->庁_委員会5("庁<br>委員会")内閣
内閣は、首長である内閣総理大臣と14人以内の国務大臣(臨時的に増やすことも可能)で構成される合議制の機関です(内閣法2条1項・2項)。1920
行政権は内閣に属するとされています(憲法65条)。そのため、内閣がすべての行政権を行使しなければならないように思えますが、内閣の構成員は十数名しかいません。そのため、実際には内閣の統轄の下にある行政機関が行政権を行使しています。
内閣の統轄の下における行政機関
- ①内閣府
-
内閣府は、内閣の統轄の下にある行政機関ですが、国家行政組織法には規定されておらず、内閣府設置法によって定められています。
内閣府は、内閣に設置され(内閣府設置法2条)、内閣の重要な政策に関する内閣の事務を保佐することを任務としています(内閣府設置法3条1項)。21
- ②復興庁
-
復興庁は、復興庁設置法に基づいて設置された行政機関です。
復興庁は、内閣に置かれ(復興庁設置法2条)、
- 東日本大震災からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること
- 主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ること
を任務としています(復興庁設置法3条)。
- ③デジタル庁
-
デジタル庁は、令和3年9月1日施行のデジタル庁設置法に基づいて新たに設置された行政機関です。
デジタル庁は内閣に置かれ(デジタル庁設置法2条)、
- デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること
- デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ること
を任務としています(デジタル庁設置法3条)。
- ④その他の行政機関
-
内閣の統轄の下にある行政機関として、財務省・厚生労働省などの省が設置されています。22
各省の大臣は、国務大臣の中から内閣総理大臣が任命しますが、内閣総理大臣自らが各省大臣に当たることも可能です(国家行政組織法5条3項)。2324
省には、専門的な知見が求められる事務や、大量に処理する必要がある事務を担当するために「庁」が置かれることがあります。また、政治的な中立性を確保する必要がある事務を担当するために「委員会」が設置されることもあります。
このように、省の特殊な事務を処理するために設置される庁や委員会を総称して「外局(がいきょく)」といいます。なお、内閣府にも外局を設置することができます。
■内閣府の外局(内閣府設置法64条)
委員会・庁 根拠法 公正取引委員会(公式HP) 独占禁止法 国家公安委員会(公式HP) 警察法 個人情報保護委員会(公式HP) 個人情報の保護に関する法律 カジノ管理委員会(公式HP) 特定複合観光施設区域整備法 金融庁(公式HP) 金融庁設置法 消費者庁(公式HP) 消費者庁及び消費者委員会設置法 こども家庭庁(公式HP) こども家庭庁設置法 ■各省の外局(国家行政組織法別表第一)
- 具体例:土地区画整理組合、健康保険組合など ↩︎
- 具体例:国立科学博物館・国立公文書館・造幣局など ↩︎
- 具体例:日本放送協会(NHK)など ↩︎
- 行政組織法上の基礎概念である行政機関には、①行政主体とその外部との関係を基準として取られる作用法的行政機関概念と、②各々の行政機関が担当する事務を単位として捉える事務配分的行政機関概念がある。この6分類は①の概念に基づくもの。 ↩︎
- 具体例:各省の大臣・都道府県知事・市町村長など ↩︎
- 具体例:公正取引委員会・教育委員会など ↩︎
- 用語:所定の事項を示して意見をもとめること ↩︎
- 具体例:法制審議会等のような各種審議会 ↩︎
- 法令上、諮問機関への諮問が義務付けられている場合、諮問を経ないで行った行政庁の行為も、常に無効となるわけではない ↩︎
- 具体例:電波監理審議会など ↩︎
- 参考:下級行政機関の権限を当該下級行政機関に代わって上級行政機関自らが行使すること(代執行)は、法律の特別の根拠がなければすることができない。 ↩︎
- 具体例:「前三項の規定により保護を行うべき者は、保護の決定及び実施に関する事務の全部または一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。」とする生活保護法19条4項など ↩︎
- 参考:権限の委任は、通常、行政処分を行う行政庁がその権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任して行う ↩︎
- 参考:権限の委任が上級行政機関から下級行政機関に対して行われた場合、委任をした上級行政機関の指揮監督権まで失われるわけではない ↩︎
- 具体例:指定代理の例として「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。」とする内閣法9条など ↩︎
- 具体例:狭義の法定代理としては、「人事院総裁に事故のあるとき、又は人事院総裁が欠けたときは、先任の人事官が、その職務を代行する。」とする国家公務員法11条3項など ↩︎
- 具体例:市役所の職員が、市長の印を押して、戸籍謄本を発行する場合など ↩︎
- 用語:上級行政機関が下級行政機関を統率すること ↩︎
- 参考:各大臣は、主任の大臣として行政事務を分担管理するのが原則であるが、行政事務を分担管理しない大臣(無任所大臣)を設けることもできる(内閣法3条1項・2項) ↩︎
- 参考:内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて、行政各部を指揮監督する(内閣法6条) ↩︎
- 内閣府の長は、内閣総理大臣である(内閣府設置法6条1項) ↩︎
- 各省および内閣府には、必置の機関として副大臣・事務次官が置かれる(国家行政組織法16条1項・18条1項・内閣府設置法13条1項・15条1項) ↩︎
- 参考:各省大臣は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統括する(国家行政組織法10条)。
また、各省大臣は、その機関の掌握事務について、公示を必要とする場合には告示を発することができ、命令・示達をするため訓令・通達を発することもできる(国家行政組織法14条1項・2項) ↩︎ - 参考:各省大臣は、主任の行政事務について、法律または政令の制定、改正または廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない(国家行政組織法11条) ↩︎