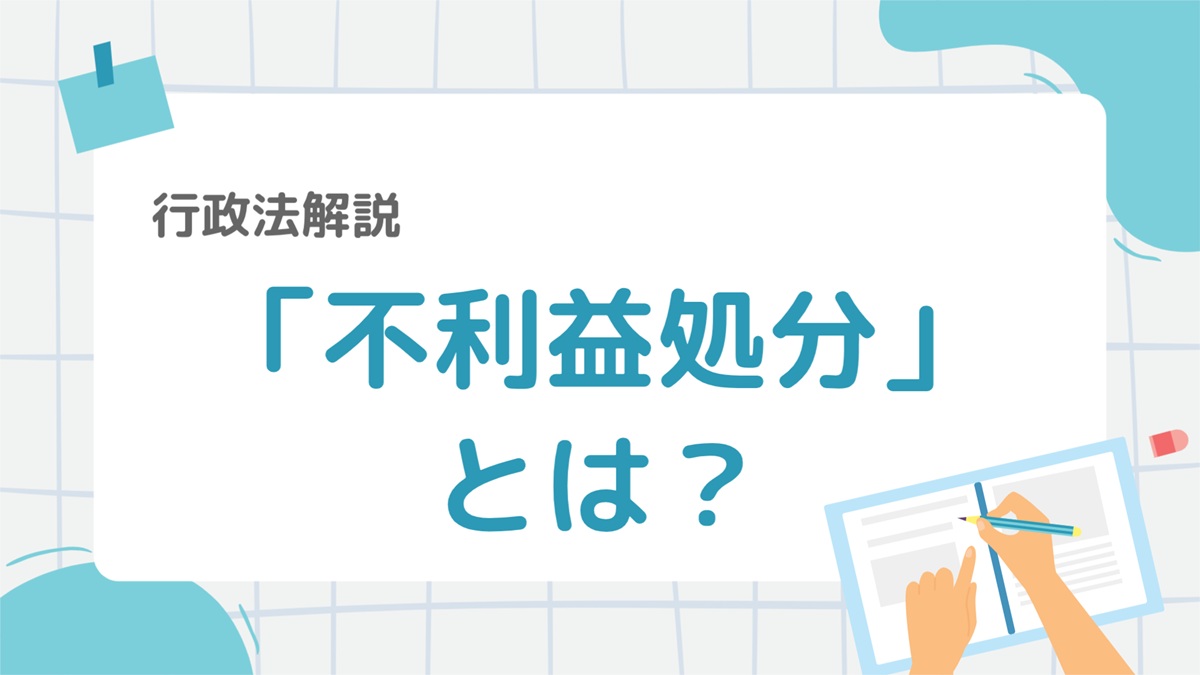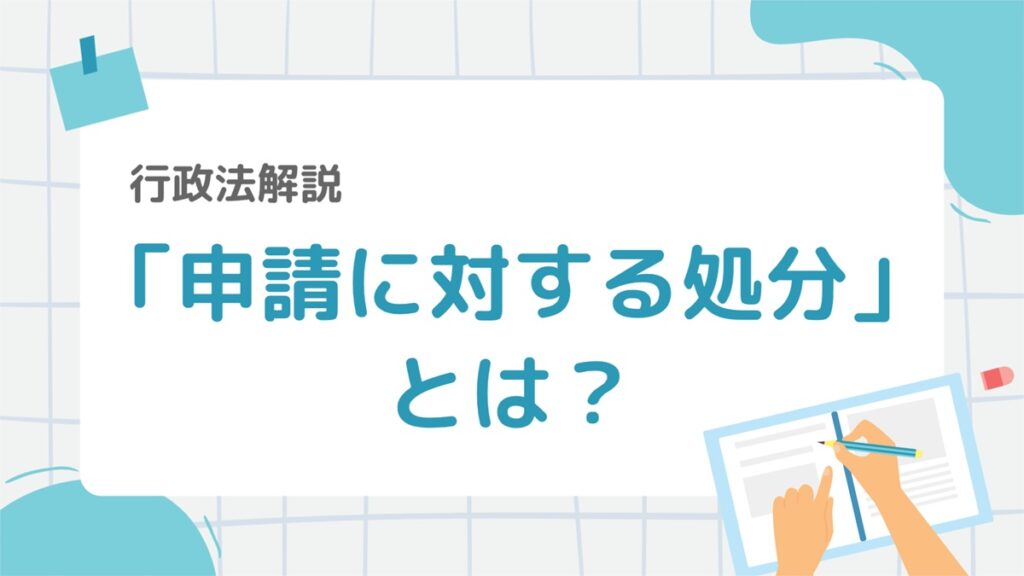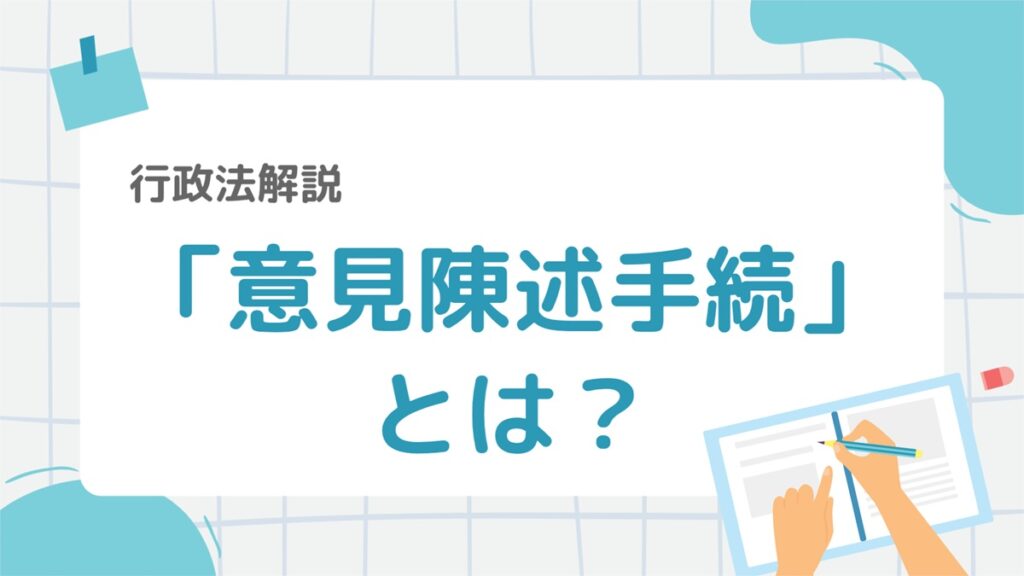- 「不利益処分って何?」と基本から知りたい方
- 行政法の「処分基準」や「理由の提示」が試験にどう出るか押さえたい方
- 行政書士試験の記述対策として重要用語を整理したい方
不利益処分とは?
不利益処分の定義とは?
不利益処分とは、行政庁が法令に基づいて、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、またはその権利を制限する処分のことをいいます(2条4号)。1
例えば、営業停止処分や許可の取消しなどが典型例です。「処分」という言葉がついていますが、すべての処分が不利益処分というわけではありません。
「申請拒否処分」は不利益処分に含まれない?
ちょっとややこしいですが、申請により求められた許認可等を拒否する処分(申請拒否処分)は、たとえ申請者の権利を制限する結果になっても、不利益処分には当たりません(2条4号ロ)。
なぜなら、申請拒否は「申請に対する処分」として、別の規定で扱われているからです。ここは試験でもよく狙われるポイントなので、しっかり押さえておきましょう。2

処分基準とは?処分のルールを事前に決めておく考え方
不利益処分を行う際に行政庁が使うルール、それが処分基準です(2条8号ハ)。
処分基準は、「①不利益処分をするかどうか、②どのような内容にするか、を判断する際の基準」のことです。
この基準がないと、同じ処分でも行政庁によって対応がバラバラになるおそれがあります。そうすると不公平ですよね。だから、処分の基準をあらかじめ定めておくことが大切なのです。
処分基準は「努力義務」
とはいえ、処分基準を公表することにはリスクもあります。
たとえば、どの程度の違反なら処分されないかまで明らかになってしまうと、「ギリギリセーフなら大丈夫」と考える人が増え、かえって違反を助長する可能性があるのです。
そのため、行政庁は「処分基準を定め、かつ、公にするよう努める」ことが求められています(12条1項)。つまり、これは「努力義務」にとどまります。(※この点、審査基準と異なるので注意)
なお、行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければなりません(12条2項)。
■基準の設定・公開の義務の種別
理由の提示|処分を受ける人に理由を示すのは当然?
行政庁が不利益処分をする場合は、同時に、当該処分の理由を示さなければなりません(14条1項本文)。
これは、
- 行政庁の判断を慎重にさせる
- 不利益処分の名あて人が後にその不利益処分を不服として争う場合の情報を提供するため
という重要な意味を持ちます。
理由を示さない例外もある?
例外として、以下のようなケースでは処分の際に理由を示さなくてもよいとされています。
- 差し迫った必要がある場合
- 当該名あて人の所在が判明しなくなったとき
- その他処分後において理由を示すことが困難な事情があるとき
それ以外の場合は、処分後相当の期間内に、理由を示さなければなりませんい(14条1項但書・2項)。
なお、不利益処分を書面でするときは、理由も書面により示さなければなりません(14条3項)。
まとめ|不利益処分の理解は、行政法の得点源!
不利益処分・処分基準・理由の提示は、行政法の中でも非常に頻出で、理解しておけば確実に得点につながる分野です。
ポイントは次の3つ:
- 「不利益処分」と「申請に対する処分」の違い
- 処分基準は「努力義務」、でも具体的に定める必要あり
- 理由提示は原則義務、ただし例外あり
条文と実例をしっかりリンクさせて理解しておくことで、記述式にも対応できる実力がつきますよ!