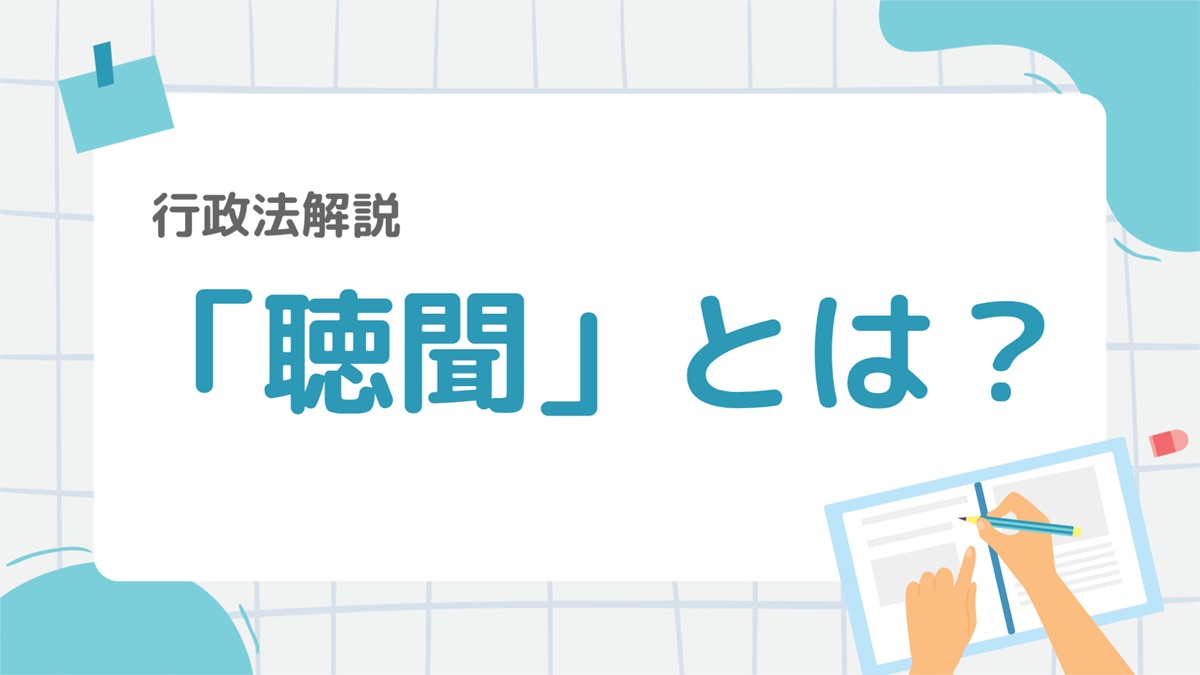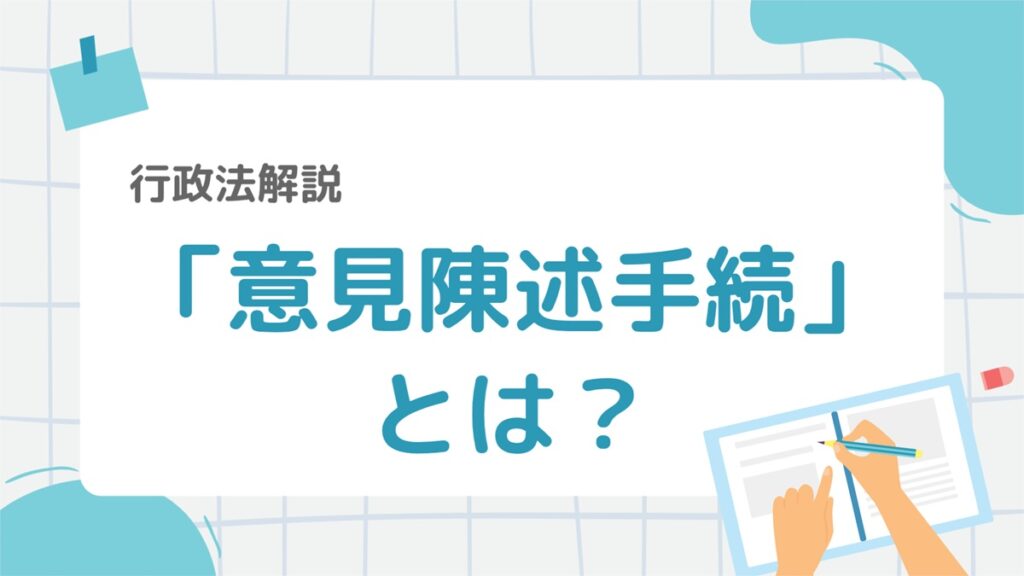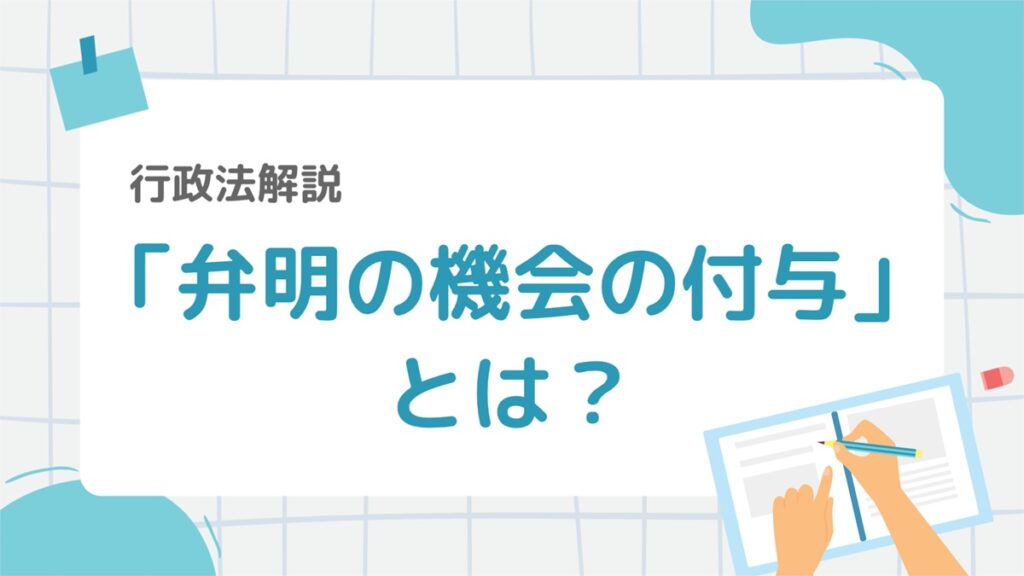- 「聴聞」って具体的に何をする手続きなのかイメージできない
- 行政法の不利益処分に関する出題対策を強化したい
- 聴聞手続の流れや関係者の権利を、体系的に整理したい
- 記述式や多肢選択式対策として、条文ベースの理解を深めたい
「聴聞」とは? ─ 不利益処分の前に行われる重要な防御手続
行政庁がある人に不利益処分(例:営業停止命令など)をする際に、その人に意見を述べる機会を与える手続きの一つが「聴聞(ちょうもん)」です。これは、処分される側にきちんと反論のチャンスを与えるための“防御の機会”の一環であり、行政の公平性を保つために重要なステップとされています。
聴聞の手続きは、以下のような流れで進んでいきます。
① 聴聞の開始:行政庁からの通知
行政庁が聴聞を行うときは、処分の相手(名あて人)に対して、予定されている不利益処分の内容・根拠となる法律の条項・事実関係などを書面により通知します(15条1項)。1
これは、名あて人がしっかり準備して期日に出頭して、意見を述べられるようにするための通知です。
この通知を受け取った人を「当事者」と呼び、代理人を立てることも可能です(16条1項)。
また、当事者ではないけれど、処分に利害関係がある人を「関係人」といい、主宰者の許可を得て「参加人」として手続きに関与することができます(17条1項)。
② 主宰者のもとで行われる審理
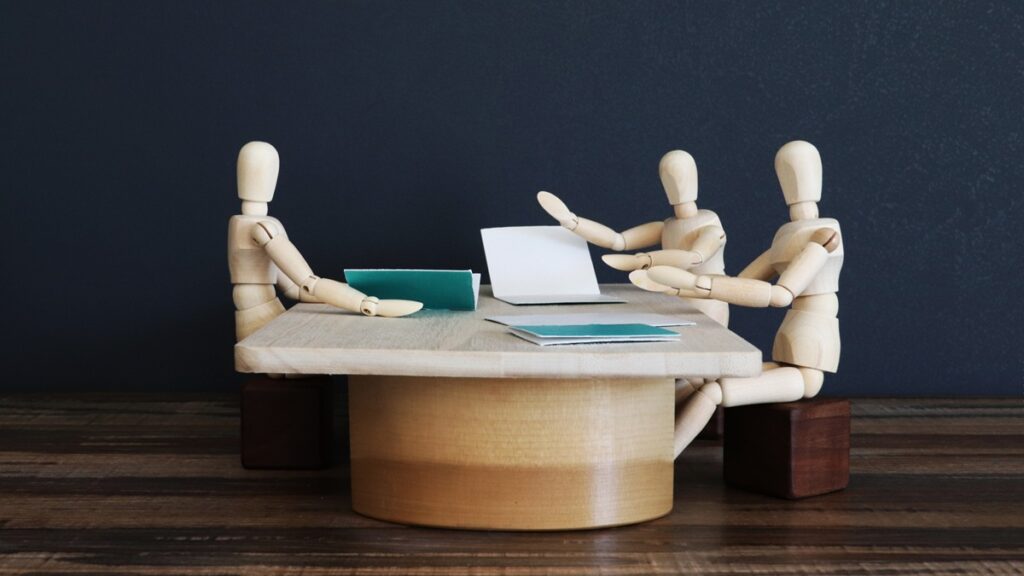
聴聞は、行政庁が指名した職員その他政令で定める者が「主宰者」として進行役を務めます。(19条1項)。
通知を受けた名あて人は、指定された日時・場所に出向き主宰者の下で自分の意見を述べたり、証拠書類を出したりすることができます。
ただし、公平性を確保するために、聴聞の当事者や参加人やこれらの配偶者・4親等内の親族・同居の親族などは、聴聞の主宰者にはなれません(19条2項)。
※参考:行政庁の職員のうち、当該不利益処分に係る事案の処理に直接関与した者であっても、主宰者となることはできる。
聴聞手続は、口頭審理主義となっており、裁判と同様に、主宰者が行政庁と名あて人の意見を聞きながら、不利益処分が適法かどうかを判断します。
なお、プライバシーや企業秘密の保護、行政庁の事務負担を考慮して、審理は原則非公開ですが、行政庁が必要と認めた場合は公開されることもあります(20条6項)。
③ 聴聞中の当事者等の権利(防御権)
当事者や参加人には、次のような権利が保障されています。
- ● 文書等の閲覧請求権(18条1項)
-
聴聞の通知を受けてから聴聞が終結するまでの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができます。行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができません(18条1項)
- ● 聴聞期日における権利(20条2~3項)
- ● 書面による提出もOK
-
聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書および証拠書類等を提出することができます(21条1項)2
④ 聴聞調書・報告書の作成と提出
審理が終わると、主宰者は以下の2つの書類を作成し、行政庁に提出しなければなりません(24条1項・3項)。
- 聴聞調書:聴聞の経過をまとめた記録
- 報告書:不利益処分に関する当事者の主張が妥当かどうかについての意見
当事者または参加人は、これらの書類の閲覧を求めることができます(24条4項)。
⑤ 行政庁による不利益処分の決定
行政庁は、主宰者から提出された聴聞調書や報告書の内容を十分に参酌したうえで、不利益処分を行うかどうかを決定します(26条)。3
ただし、主宰者の意見に必ず従う義務があるわけではありません。
審査請求の制限
聴聞手続における処分または不作為については、審査請求することができません(27条)。45
まとめ:聴聞手続きは「防御の機会」を保障する制度
行政法で頻出の「不利益処分」と深く関係する「聴聞」手続は、受験生が避けて通れない重要テーマです。
特に、手続の流れ・当事者や参加人の権利・主宰者の役割など、条文をおさえながらポイントを整理することが得点アップのカギになります。
- 不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合には、行政庁は、公示送達(掲示)の方法により聴聞の通知をすることができるが、聴聞の通知を省略することはできない(15条3項) ↩︎
- 参考:主催者は、当事者の全部または一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書または証拠書類等を提出しない場合、これらの者に対し改めて意見を述べ、および証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる(23条1項) ↩︎
- 。 ↩︎
- 聴聞手続きを経てなされた不利益処分については、審査請求をすることができる ↩︎
- 具体例:行政庁がなした文書閲覧不許可処分(18条1項)や、主宰者がなした関係人の参加の不許可処分(17条1項)など ↩︎