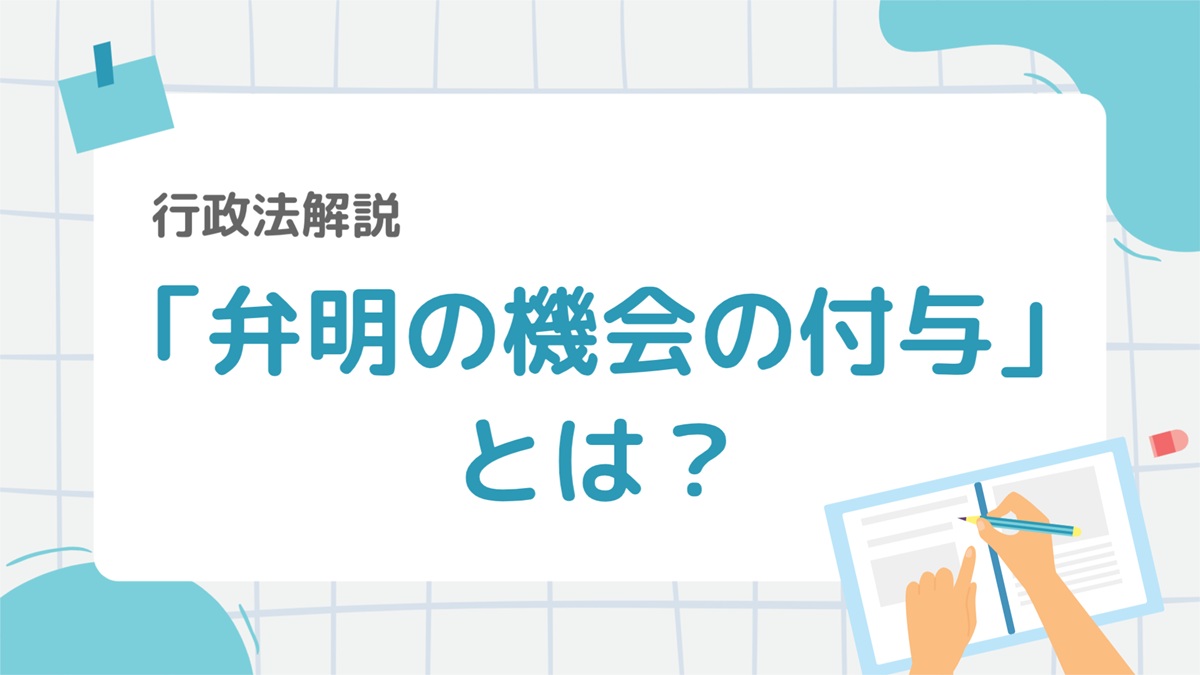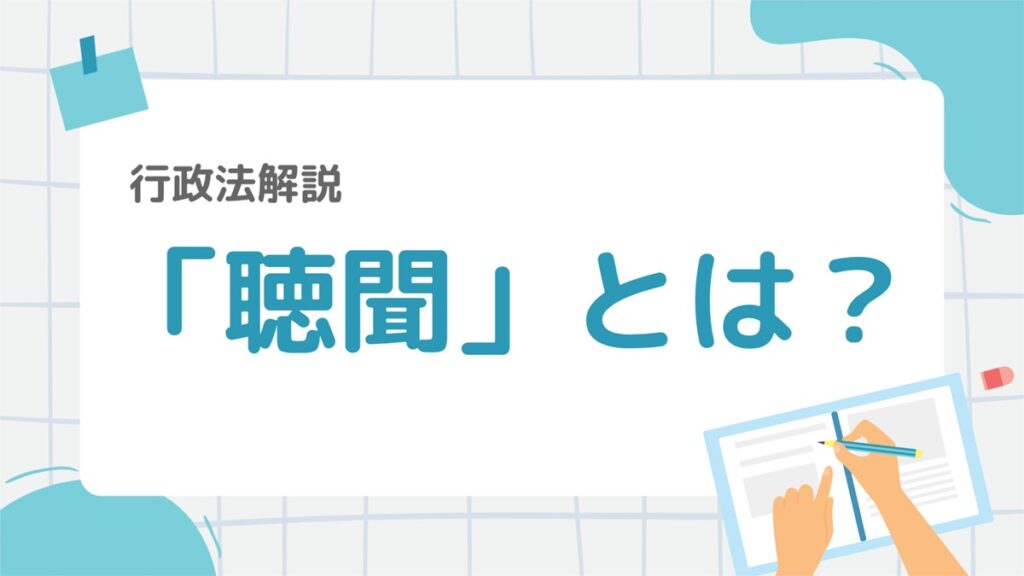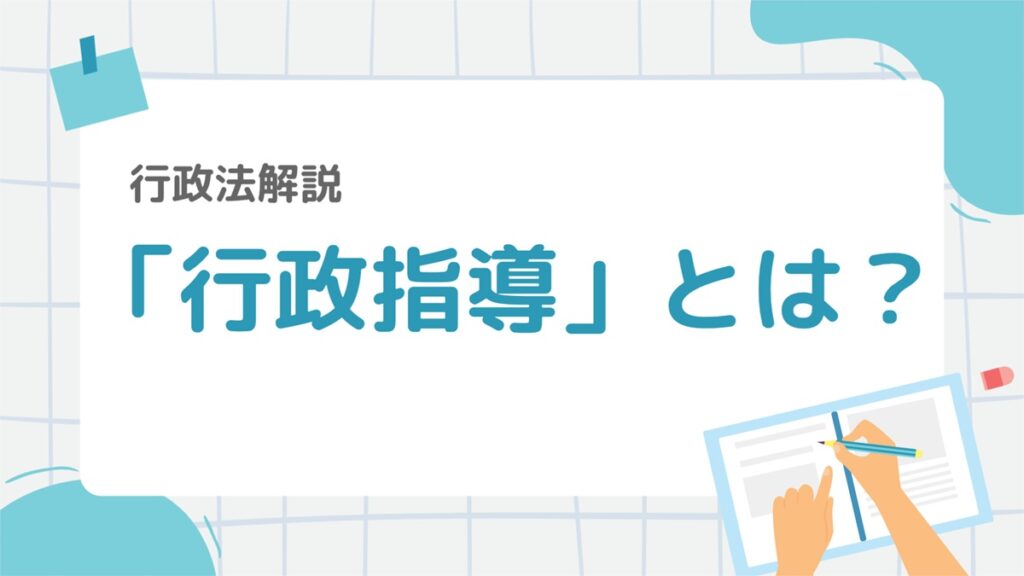この記事はこんな人におすすめ
- 「聴聞」と「弁明の機会」の違いがよく分からない方
- 行政書士試験の行政法を効率よく学びたい方
目次
弁明の機会の付与とは?不利益処分をする前に必要な手続き
行政庁が不利益処分をしようとする場合、その対象者に対してあらかじめ意見を述べるチャンスを与える手続きがあります。比較的重い処分に適用される「聴聞」と並び、比較的軽い場合に行われる手続が「弁明の機会の付与」です。
行政庁による通知
行政庁は、弁明の機会を与える際に聴聞と同じく、予定される不利益処分の内容や理由などを記載し、その処分の名あて人に書面で通知する必要があります(30条)。
この通知により、処分を受ける側(名あて人)は、自分の言い分を準備することができます。
弁明の方法は「書面」が原則
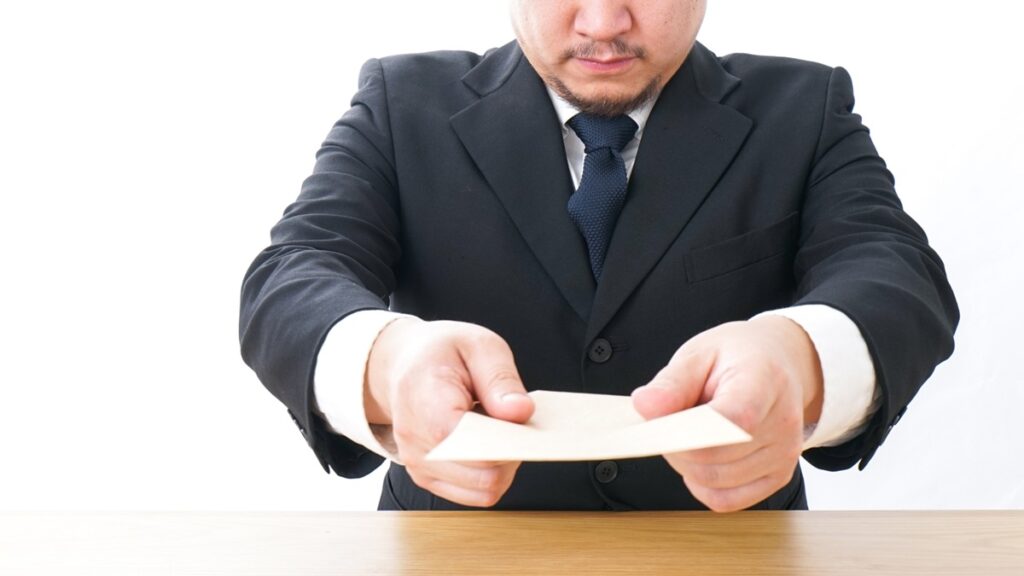
原則として、弁明は弁明を記載した書面(弁明書)と呼ばれる書面を提出して行います。
ただし、行政庁が認めた場合は、口頭での弁明も可能です。(29条1項)
提出された弁明書は、行政庁が最終的な判断を下す際の参考資料として扱われ、不利益処分をするかどうかの決定を行います。
「聴聞」と「弁明の機会」の違いを簡単に整理!
✅ポイント
「聴聞」は、より手続き的に厳格で、第三者の関与も可能な場面。一方で「弁明の機会」は、より簡略化された手続きであり、書面中心で行われることが特徴です。
弁明の機会の付与にも「聴聞のルール」が一部適用される
弁明の機会の手続きにも、「聴聞」に関する規定が準用される部分があります。
つまり、完全に別物ではなく、弁明の機会の付与にも聴聞のルールが部分的に使われるというイメージです。
「弁明の機会の付与」について、聴聞の規定が準用される規定
①公示送達による通知(15条3項)
②代理人(16条)
の2つだけです。
まとめ|試験対策のポイント
- 弁明の機会の付与は、行政庁が不利益処分を行う前に、対象者の意見を聞く手続き
- 原則として、書面(弁明書)で意見を述べる
- 「聴聞」との違いをしっかり押さえる(表形式で理解)