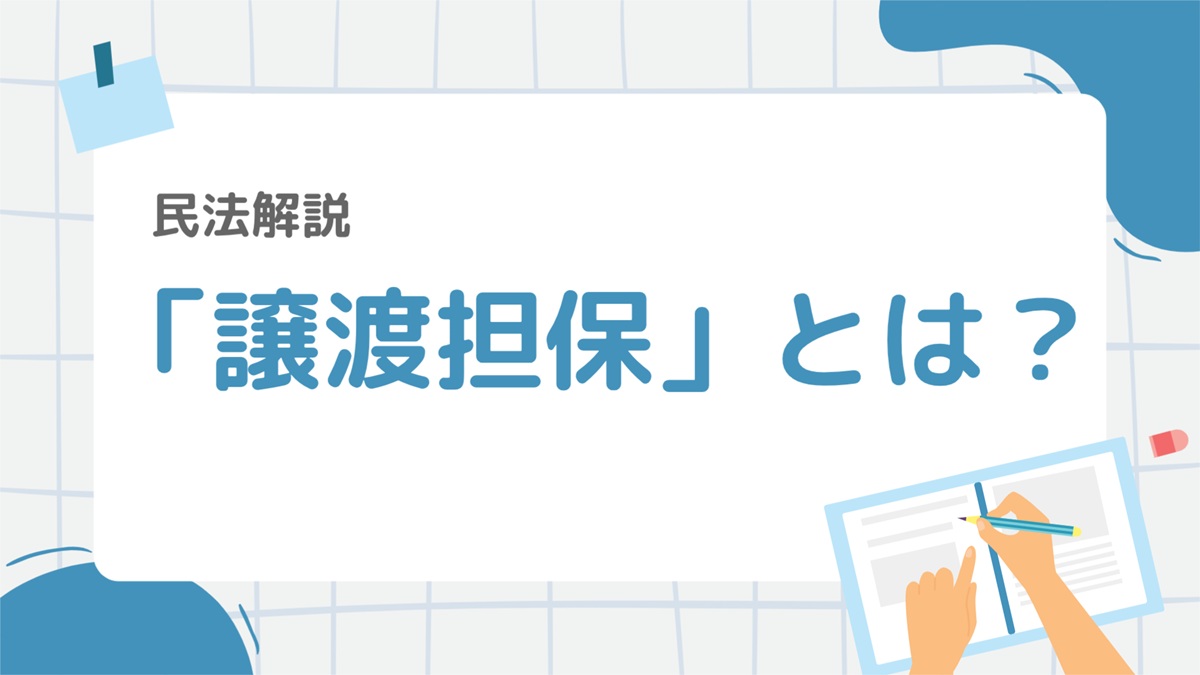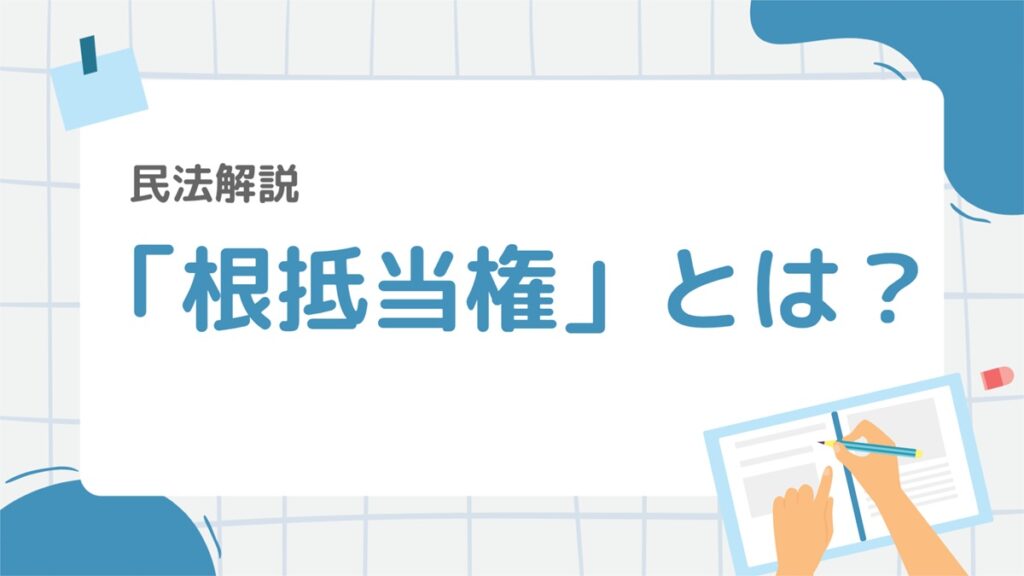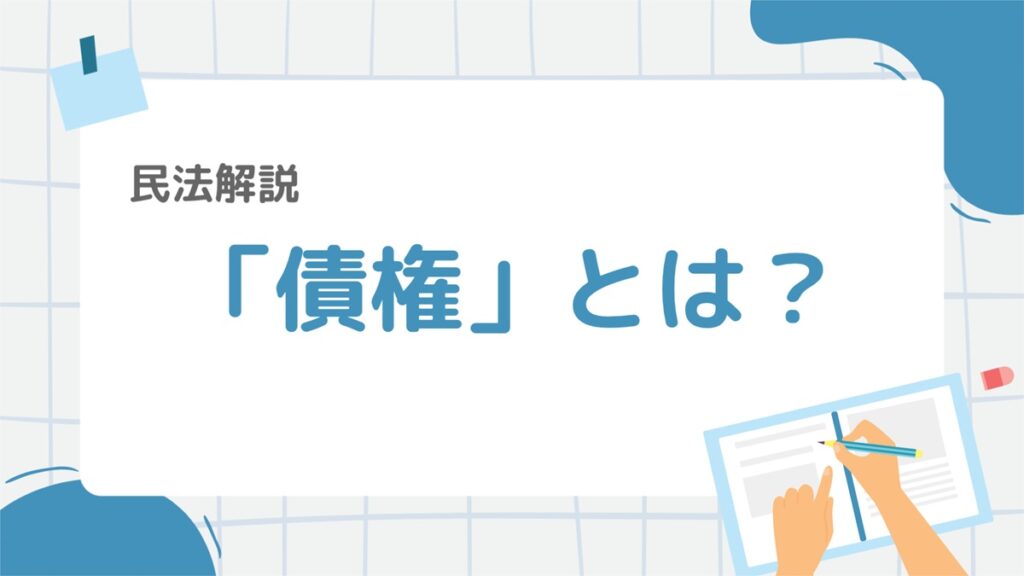譲渡担保とは?
sequenceDiagram autonumber participant A所有の機械 actor A_債務者_譲渡担保権設定者 actor B_債権者_譲渡担保権者 B_債権者_譲渡担保権者 ->> A_債務者_譲渡担保権設定者:貸金債権 A_債務者_譲渡担保権設定者 ->> B_債権者_譲渡担保権者:所有権の譲渡 B_債権者_譲渡担保権者 ->> A所有の機械:譲渡担保権
工場を経営しているAは、Bから資金を借りるにあたり、その貸付金債権の担保として、自分が所有している機械の所有権をBに譲渡しました。ただし、譲渡後もAはそのままこの機械を使い続けています。
譲渡担保とは、債権を担保するために、目的物の所有権などを債権者へ譲渡し、一定期間内に債務を弁済すれば、再び債務者に所有権が戻る仕組みの担保です。いわば「動産の抵当権」といえます。
事例のケースでは、Aが所有する財産が機械しかない場合、動産には抵当権を設定できないため(369条1項)、機械を担保にしてお金を借りることはできません。また、機械に質権を設定すると、担保として債権者に引き渡さなければならず、工場で機械を使用できなくなってしまいます。
そこで、Aが引き続き機械を使用しながら担保を設定する方法として、実務上よく利用されているのが「譲渡担保」です。
Aが機械に譲渡担保権を設定すると、所有権はいったん債務者Bに移ります。その後、Aが貸金債務を弁済すれば、機械の所有権はAに戻ります。しかし、弁済しなかった場合は、機械の所有権は確定的にBに帰属することになります。
譲渡担保権の及ぶ範囲
借地権
土地の賃借人が土地上が、その土地の上に所有する建物について、譲渡担保権を設定した場合、原則として譲渡担保権の効力は当該土地の賃借権にも及びます(最判昭51.9.21)。この点については、抵当権の場合と同様です。
物上代位
譲渡担保の目的物を債務者が第三者に売却した場合、譲渡担保権者は、債務者の第三者に対して有する売買代金債権についても、物上代位により譲渡担保権を行使することができます(最決平11.5.17)。
譲渡担保権の実行
実行方法
債務者が債務を弁済しなかった場合の実行方法には、以下の2種類がある。
- 処分清算型
債務者が目的物を第三者に譲渡し、その売買代金を被担保債権の弁済に充て、その残額(清算金)を債務者に返還する方法 - 帰属清算型
債権者が目的物の価値を適正に評価して、評価額と被担保債権の差額(清算金)を債務者に返還し、目的物の所有権を債権者に帰属させる方法
受戻権
受戻権とは、譲渡担保権者が譲渡担保権の実行を完了するまでの間に、債務者が債務を弁済することで目的物の所有権を回復できる権利です。この受戻権は以下の時点で消滅します。
- 処分清算型の場合
債権者が目的物を第三者に譲渡した時(最判昭57.1.22)1 - 帰属清算型の場合
債権者が債務者に対して清算金の支払いをした時、または、目的物の評価額が被担保債権額を上回らない旨を通知した時(最判昭62.2.12)
集合動産譲渡担保
集合動産譲渡担保とは?
集合動産譲渡担保とは、動産の集合体を対象として譲渡担保を設定することをいいます。2
構成部分が変動する集合動産であっても、種類・所在場所・量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定されている場合には、1つの集合物として譲渡担保の目的となります(最判昭54.2.15)。
対抗要件
集合動産譲渡担保の対抗要件は、引渡しによって具備されます(178条)。これは、一般的な動産物権変動の場合と同様に、占有改定による引渡しが認められています。3
また、債権者が譲渡担保の設定する際に占有改定の方法を用いて、現存する動産の占有を取得した場合、その対抗要件具備の効力は、その後に構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たに構成部分となった動産にも及びます(最判昭62.11.10)。
設定者の処分権
集合動産譲渡担保では、譲渡担保設定者の営業活動を通じて集合物の内容が当然に変動することが予定されています。そのため、譲渡担保設定者には、通常の営業の範囲内で譲渡担保の目的となっている動産を処分する権限が与えられています(最判平18.7.20)。
ただし、設定者が通常の営業の範囲を超える処分をした場合、目的物が集合物から離脱したと認められない限り、処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできません(同判例)。
集合債権譲渡担保
集合債権譲渡担保とは?
集合債券譲渡担保とは、複数の債権をまとめた集合体を対象として譲渡担保を設定することをいいます。4
この場合、契約締結時において目的債権が他の債権から識別できる程度に特定されていれば有効と認められます。将来発生する債権について、その発生が確実であることまでは要件とされません(最判平12.4.21)。
対抗要件
集合債権譲渡担保の第三債務者に対する対抗要件は、設定者が第三債務者に通知を行うか、第三債務者が承諾5することによって具備されます。
また、第三者に対する対抗要件については、その通知または承諾が確定日付のある証書によって行われる必要があります。
- 重要判例:不動産の譲渡担保において、清算金が支払われる前に目的不動産が債権者から第三者に譲渡された場合、原則として、債務者はもはや残債務を弁済して目的物を受け戻すことはできず、このことは譲受人が背信的悪意者に当たる場合であっても異ならない(最判平6.2.22) ↩︎
- 具体例:小売店を経営する債務者が、貸金債務を担保するため、在庫商品の所有権を一括して譲渡する場合など ↩︎
- 重要判例:継続的な売買契約において、目的物の所有権が売買代金の完済まで売主に留保される旨が定められていた場合、譲渡担保権者が占有改定の方法により現に存する動産の占有を取得したとしても、売買代金が完済されていない動産については、売主に対して譲渡担保権を主張することができない(最判平30.12.7)判例:継続的な売買契約において、目的物の所有権が売買代金の完済まで売主に留保される旨が定められていた場合、譲渡担保権者が占有改定の方法により現に存する動産の占有を取得したとしても、売買代金が完済されていない動産については、売主に対して譲渡担保権を主張することができない(最判平30.12.7) ↩︎
- 具体例:特定の債権者・債務者間で継続的に発生する債権を一括して譲渡する場合や、多数の債務者の小口債権を一括で譲渡する場合など ↩︎
- 重要判例:既に生じ、または将来生ずべき債権を譲渡担保権者に譲渡する集合債権譲渡担保について、第三者対抗要件を具備するためには、債権譲渡の対抗要件の方法によることができる(最判平13.11.22) ↩︎