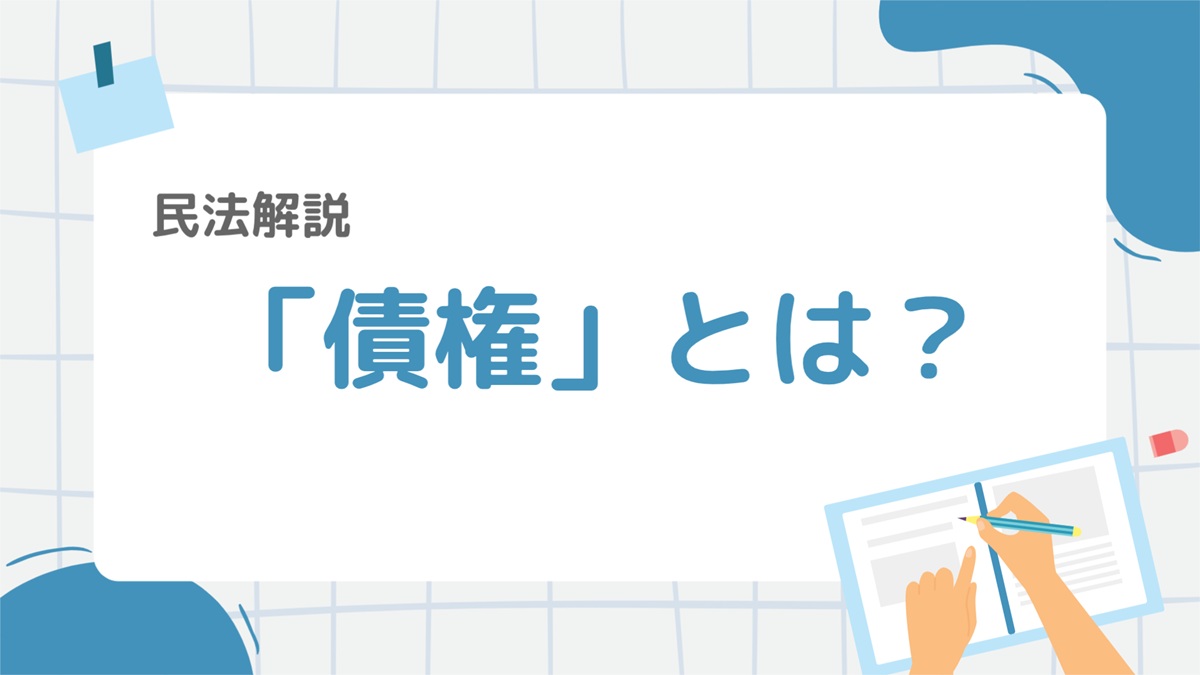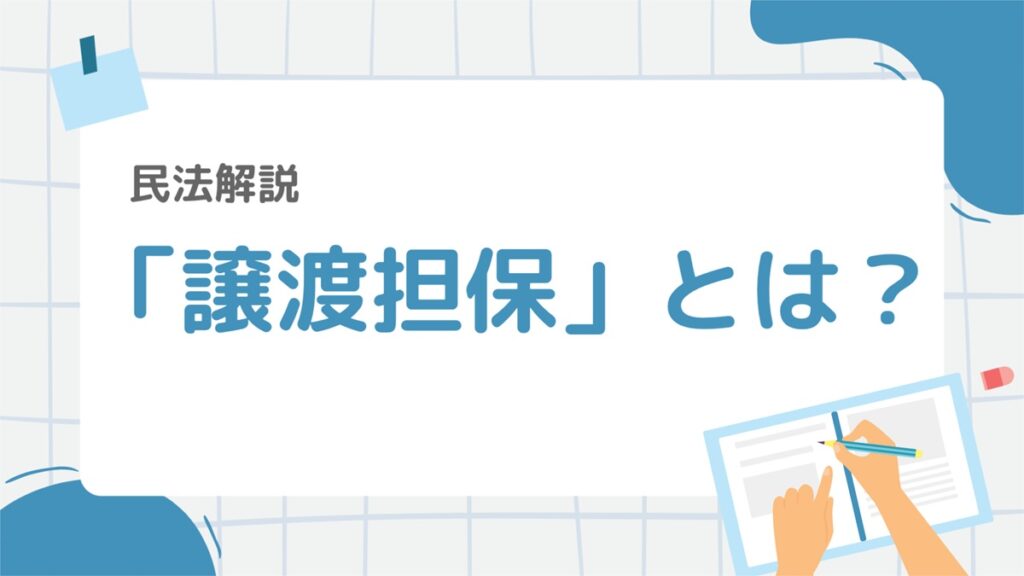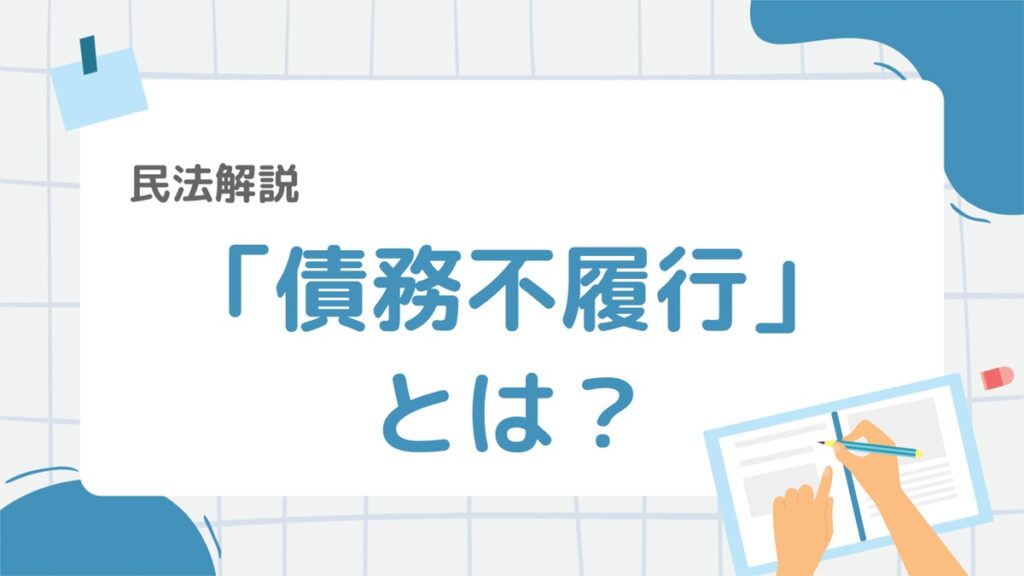債権とは?
債権とは、特定の人が別の特定の人に対して一定の行為を請求できる権利のことをいいます。例えばAさんがBさんにお金を貸した場合、AさんがBさんに対して返済を請求する権利を持ちます。12逆に、お金を借りたBさんは、Aさんに対して返済をする義務を負います。このような義務を債務といいます。
このように、債権と債務は表裏一体の関係にあります。債権を持つ人を債権者、債務を負う人を債務者といいます。
---
config:
theme: neutral
---
flowchart LR
A("A<br>貸主<br>(債権者)")----->|AがBに対する債権|B("B<br>借主<br>(債無者)")
B("B<br>借主<br>(債無者)")----->|BがAに対する債務|A("A<br>貸主<br>(債権者)")
特定物債権と種類債権
特定物債権とは?
特定物とは、その物の個性に着目して引渡しの対象とされた物のことをいいます。そして、特定物債権とは、この特定物の引渡しを目的とする債権を指します。3
債権の目的が特定物の引渡しである場合、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって、その物を保管しなければなりません(400条)。
種類債権とは?
- ①種類債権とは?
-
種類債権とは、同じ種類の物の一定数量の引渡しが目的とされる債権をいいます。その目的物を種類物といいます。
種類債権の場合、法律行為の性質または当事者の意思によってその品質を定めることが出来ないときは、債務者は、中等の品質を有する者を給付しなければなりません(401条1項)。
- ②種類債権の特定
-
種類債権の場合、その種類物が市場に存在する限り、債務者の調達義務は存続します。
しかし、このままでは債務者の責任が過度に重くなってしまうため、種類物の売買においても、ある段階に達すると、売主が引き渡すべき目的物を特定することになります。例えば、「このオレンジ」といった形で対象を限定することを種類債権の特定といいます。
種類債権の特定が生じるためには、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了するか、または債権者の同意を得てその給付すべき物を指定することが必要です(402条2項)。
- ③特定の効果
-
種類債権の特定が行われると、債務者は特定した物を引き渡す義務を負います。その場合、以下のような効果が生じます。
制限種類債権とは?
制限種類債権とは、種類物について一定の制限を加えて目的物を限定した債権のこと。4
種類債権は、他から入手可能である限り履行不能とはならないが、制限種類債権は、制限の範囲内の物がすべて滅失すれば履行不能となる。
選択債権
選択債権とは?
選択債権とは、複数あるうちから、特定の物を選択して給付することを内容とする債権をいいます。
選択権とは?
- ①選択権者
-
選択債権において、誰が選択権を持つかは、原則は当事者の合意によって決められます。選択権の所在が不明な場合、選択権は債務者に属します(406条)。
ただし、債権が弁済期にある場合、相手方から相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、選択権を持つ者がその期間内に選択を行わなかったときは、選択権が相手方に移転します(408条)。これは、選択権者が選択を放置すると、給付内容が特定されないままとなり、債務の履行に支障をきたすためです。
また、民法では、第三者が選択権を持つ場合も想定されています。この場合、第三者が選択を行えない、または選択をする意思がないときは、選択権は債務者に移転します(409条2項)。
- ②選択権の行使
-
債権者または債務者が選択権を持つ場合、選択権の行使は、相手方に対する意思表示によって行います(407条1項)。一方、第三者が選択権を持つ場合、その選択は、債権者または債務者に対する意思表示によって行います(409条1項)。
なお、選択の意思表示は、相手方の承諾を得ない限り、撤回することができません(407条2項)。これは、一度選択されると、債権の目的物が特定されるため、相手方がそれを信頼し、後から変更されると不測の損害を被る可能性があるためです。
- ③選択の効果
- ④不能による選択債権の特定
-
債権の目的となる給付の中に履行不能の物が含まれる場合、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、残存するものについて存続するものとされ(410条)、選択債権が特定されることになります。