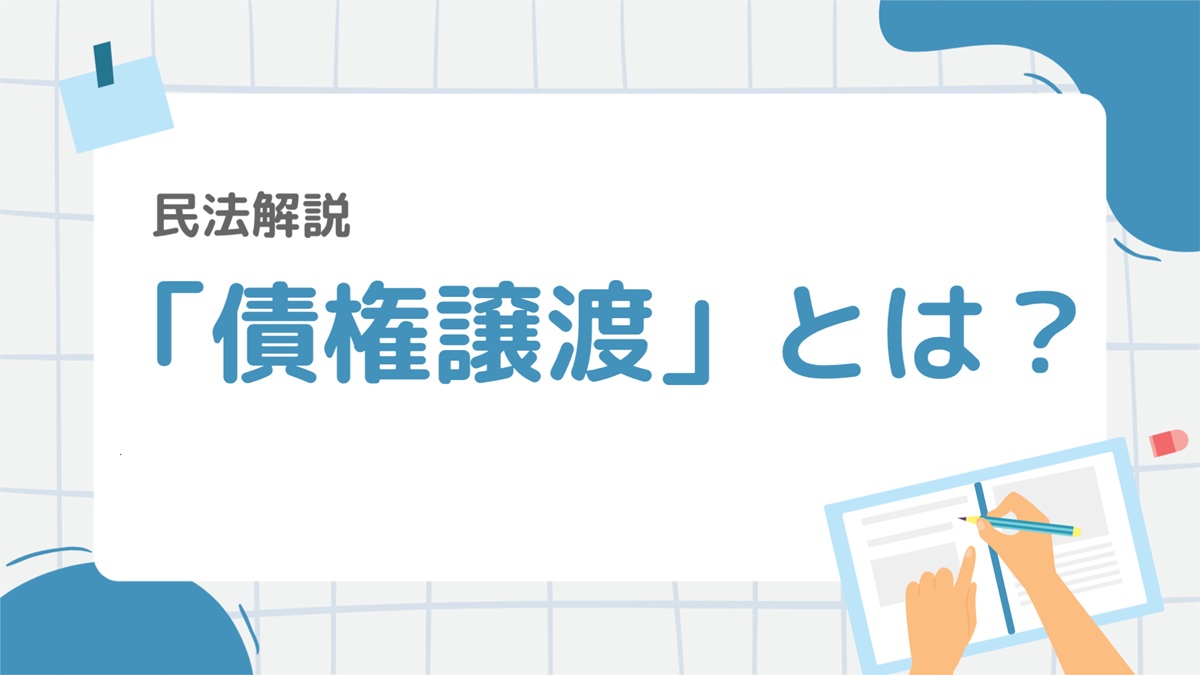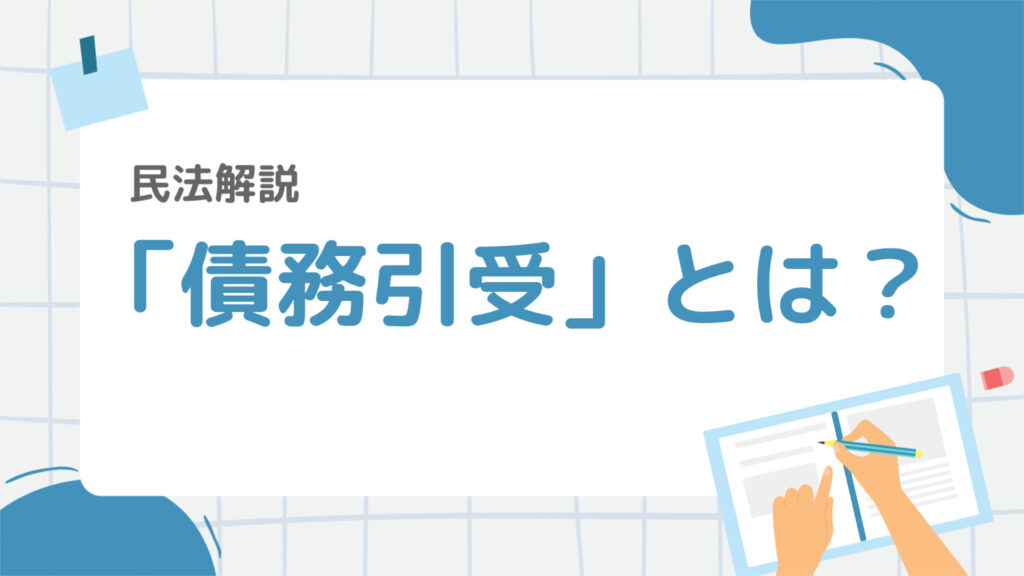- 「債権譲渡って何?」という基本から学びたい初学者の方
- 行政書士試験で民法を勉強中の方
- 対抗要件や譲渡制限などの論点をわかりやすく整理したい方
- 具体例や図解を交えて理解したい方
債権譲渡とは?
債権譲渡とは、ある人(債権者)が持っている「お金を返してもらう権利」などの債権を、別の人に移すことをいいます。ポイントは、「債権の内容はそのまま」にして、権利だけが移るという点です。
--- config: theme: neutral --- sequenceDiagram autonumber actor A(譲渡人) actor B(債務者) actor C(譲受人) A(譲渡人) ->> B(債務者):100万円 A(譲渡人) -->> C(譲受人):貸金債権を譲渡 C(譲受人) ->> B(債務者):100万円
Aは、Bに対して100万円を貸しており、その返済を受ける権利(貸金債権)を持っていました。Aはこの権利をCに譲渡しました。
👉この場合、CはBに対して100万円を請求できるようになります。
例えば、事例1の場合、、CはBに対して100万円を請求できるようになります。
債権は、原則として自由に譲渡することができます(466条1項本文)。
債権譲渡に関する3つの制限
債権は自由に譲渡できますが、以下のような場合には制限されます。
①債権の性質による制限
債権の性質が、特定の人でなければ意味がない場合には譲渡できません(466条1項但書)。
例:有名建築家に設計を依頼する権利など。
👉債権者が変わると意味がなくなる場合はNGです。
②法律上の譲渡制限
法律で「この権利は譲渡できません」と決められている場合があります。
例:生活保障の観点から、扶養を受ける権利は譲渡できません(881条)。
③譲渡制限特約(契約での制限)
債権者と債務者の間で、「この債権は譲渡しない(譲渡制限特約)」と約束していても、譲渡の効力自体は無効になりません(466条2項)。ただし、譲渡を受けた第三者がその約束を知っていた(悪意)または重過失で知らなかった場合は、債務者がそれを理由に対抗することができます(466条3項)。1
債権譲渡の対抗要件とは?
「債権譲渡が有効になる条件」は満たしていても、それだけでは債務者や他の第三者に対して効力を主張(=対抗)することはできません。
対抗するには、次のいずれかの方法が必要です(467条1項)。
- 譲渡人が債務者に通知をする
- 債務者が承諾する
①AがBに対して持っていた100万円の債権をCに譲渡。CがBに請求する。
--- config: theme: neutral --- sequenceDiagram autonumber actor A(譲渡人) actor B(債務者) actor C(譲受人) A(譲渡人) ->> B(債務者):100万円 A(譲渡人) -->> C(譲受人):貸金債権を譲渡 C(譲受人) ->> B(債務者):100万円
②Aが同じ債権をCに譲渡した後、さらにDにも譲渡。CとDのどちらが正当な権利者かが争点に。
--- config: theme: neutral --- sequenceDiagram autonumber actor A(譲渡人) actor B(債務者) actor C(譲受人1) actor D(譲受人2) A(譲渡人) ->> B(債務者):100万円 A(譲渡人) -->> C(譲受人1):貸金債権を譲渡 A(譲渡人) -->> D(譲受人2):貸金債権を譲渡 C(譲受人1) ->> B(債務者):100万円
例えば、事例2の①の場合、CはAからの通知やBの承諾がなければ、Bに対して100万円の支払いを請求することができません。
さらに、Aの通知やBの承諾は、確定日付のある証書2によって行わなければ、債務者以外の第三者に対抗することができません(467条2項)。したがって、事例2の②の場合、Cは、確定日付のある証書によるAの通知またはBの承諾がなければ、Dに対して貸金債権の取得を主張することができません。
対抗要件の構成要素
債権譲渡の対抗要件の通知または承諾は、次のルールに従ってなされなければなりません。
| 通知 | 承諾 | ||
| 主体 | 譲渡人3 | 債務者 | |
| 客体 | 債務者 | 譲渡人でも譲受人でもよい (大判大6.10.2) | |
| 時期 | 譲渡前 | ×不可 | 譲受人が特定されていれば可能 (最判昭28.5.29) |
| 譲渡後 | 〇可能 | ||
複数の譲渡があった場合の優先順位
債権が二重に譲渡されてしまった場合、どちらの譲受人が優先されるかは「確定日付のある通知が債務者に到達した日時、または確定日付のある債務者の承諾がされた日時」の先後によって決まります(最判昭49.3.7)。
同時に通知が届いたら?
→ それぞれの譲受人は、B(債務者)に全額請求できます。
→ ただし、Bが一方に弁済すれば、もう一方からの請求は拒めます。
→ 支払いを受けられなかった方は、受け取った方に対して、不当利得として按分請求できます(最判昭55.1.11)。
確定日付のある通知が同時に到達した場合、それぞれの譲受人は、債務者に対し自らの譲受債権について全額を請求することができます。債務者は、単に同順位の譲受人が他に存在するからといって弁済の責任を免れることはできません(最判昭55.1.11)。
債権譲渡の効果とは?
債権譲渡が成立すると、元の債権と同じ内容で新しい債権者に移転します。これにより、以下のような効果があります。
まとめ:債権譲渡のポイントをおさらい
✅ 債権は原則自由に譲渡可能
✅ 性質・法律・契約上の制限に注意
✅ 債務者や第三者に主張するには「通知 or 承諾」+「確定日付」がカギ
✅ 複数譲渡の優先順位は「通知が届いた日時」で決まる
✅ 債務者は譲受人に対しても一定の抗弁を主張できる