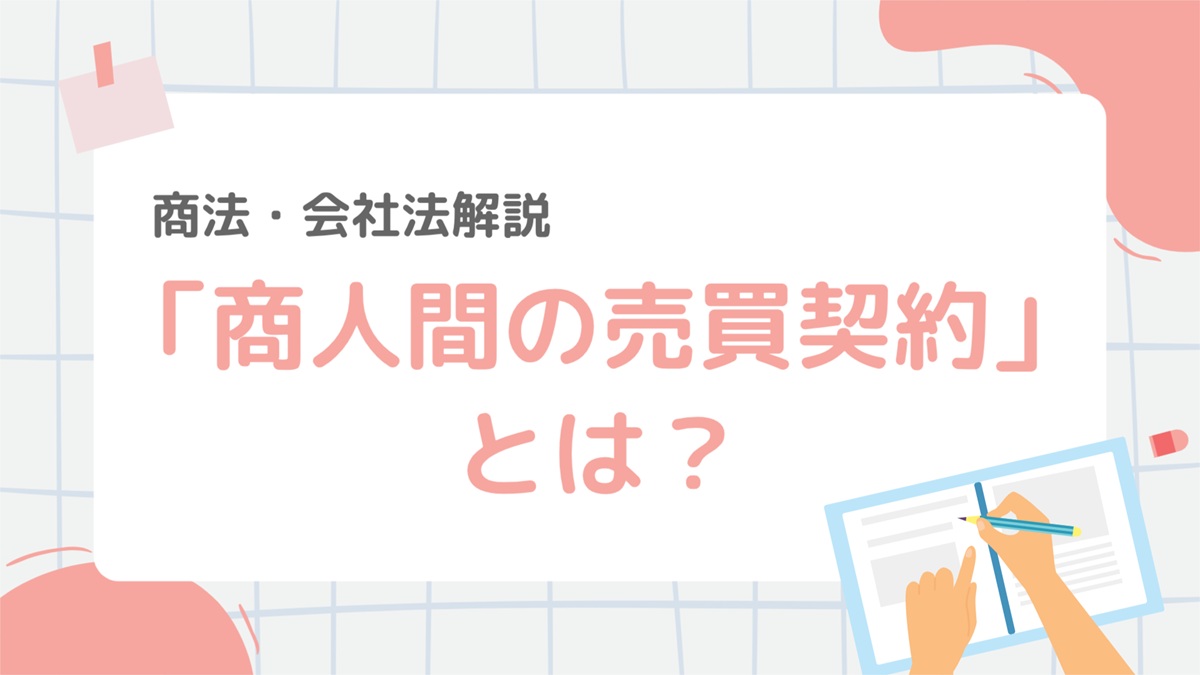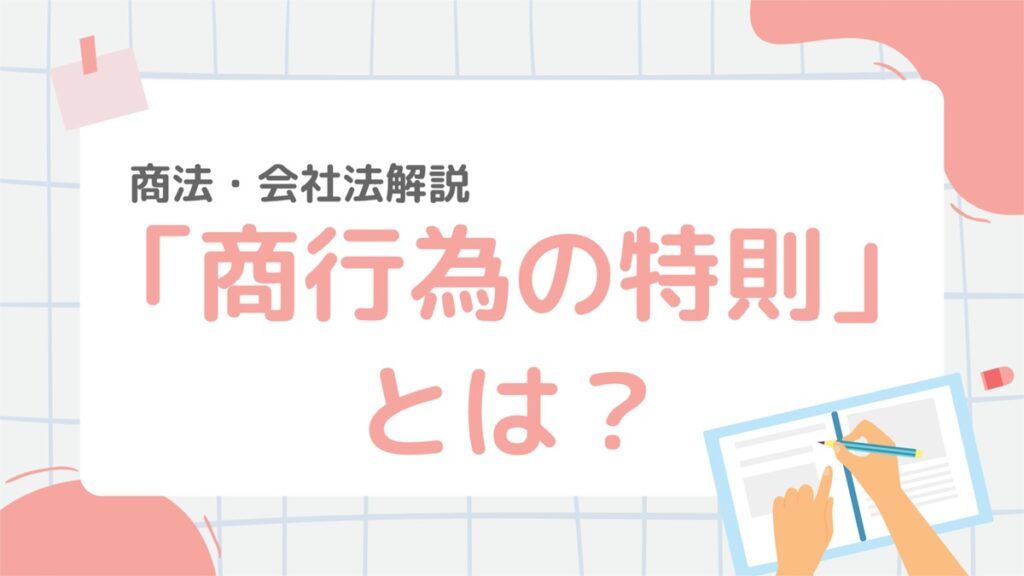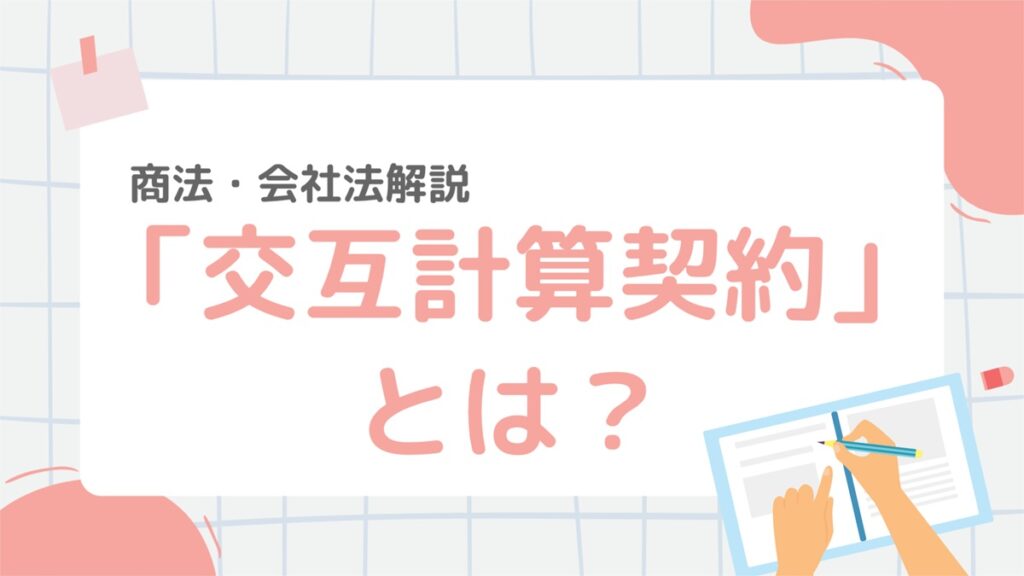- 商法の「商人間の売買契約」の特則を簡潔に理解したい
- 民法との違いを整理して覚えたい
- 行政書士試験で出題されるポイントを効率よく押さえたい
商人間の売買契約とは?
商人同士の売買契約では、迅速で円滑な取引が求められます。そのため、民法の売買契約のルールとは異なる、商法独自の特則が設けられています。
ここでは、「売主による供託・競売」「定期売買の解除」「契約内容不適合と通知」「買主の保管義務」など、試験に出やすいポイントを中心に解説します。
売主による供託・競売(商法第524条)
民法では、買主が商品を引き取らない場合、売主は目的物を「供託」したり、供託に適さない場合は裁判所の許可を得て「競売」にかけることができます(民法494条1項1号・民法497条)。
しかし、裁判所の手続きを待っていては時間がかかるため、売主にとって不利となります。そこで商人間の売買では供託だけでなく競売もすることができるものとされ、競売の際に相当の期間を定めて催告をすれば、裁判所の許可なく可能です(524条1項前段)。
そして、売買の目的物を競売に付した時は、売主は、その代価を供託しなければなりませんが、その代価の全部または一部を代金に充当可能です(524条3項)。
✅ポイント:
- 相当な期間を定めて買主に催告すれば、裁判所の許可なしで競売OK
- 競売の代金は供託しなければならないが、代金債権に充当可能
定期売買の履行遅滞による解除(商法第525条)
民法では、契約を解除するには明確な意思表示が必要です(民法540条1項、542条1項4号)。
しかし、商人間の「定期売買」では、納期が過ぎた時点で相手が直ちに履行の請求をしない限り、当然に契約の解除したとみなされ、解除の意思表示は不要です(525条)。
✅ポイント:
- 明示的な解除の意思表示 不要
- 納期遵守が前提の取引の安定性を保つための特則です
買主による目的物の検査と通知(商法第526条)
民法では、引き渡された商品が契約内容と違っていた場合、買主は売主に対して「契約内容不適合責任」を追及できます(民法562条1項)。
しかし商法では、買主が遅滞なく検査して、契約不適合を見つけたら直ちに売主に対して通知しなければ、売主の担保責任を追及することができません(526条1項、2項前段)。
これは、売主が不安定な立場に置かれることを防止して、売主を保護するための規定です。1
民法上の売買契約においては、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合(契約内容不適合)、買主は、売主の担保責任を追及することができる(民法562条1項)。
✅ポイント:
- 「遅滞なく検査」+「ただちに通知」しないと責任追及できない
- 売主保護が目的
→ 売主が不安定な立場に置かれるのを防ぐためです
買主による目的物の保管・供託(商法第527条・528条)
民法では、契約を解除しても買主は単に目的物を返せばよく(民法545条1項本文)、保管・供託義務はありません。
しかし、商人間の取引では、売主が再販売する機会を失わないように、買主が商品を保管・供託する義務があります。
主なルール:
- 目的物に契約内容不適合があり売買契約が解除された場合、売主の費用で目的物を保管・供託(527条)
- 品違いや数量超過分にも適用(528条)
- ただし、売主・買主が同一の市町村にある場合はこの義務はなし(527条4項)。
まとめ:商人間売買の特則は「スピード」と「売主保護」がカギ
商人間の売買契約では、民法と異なる特則が数多く設けられています。これらのルールは、商取引の迅速性と売主の立場を守るためのものです。行政書士試験でも頻出の分野なので、民法との違いを整理して覚えることが得点アップのポイントです。