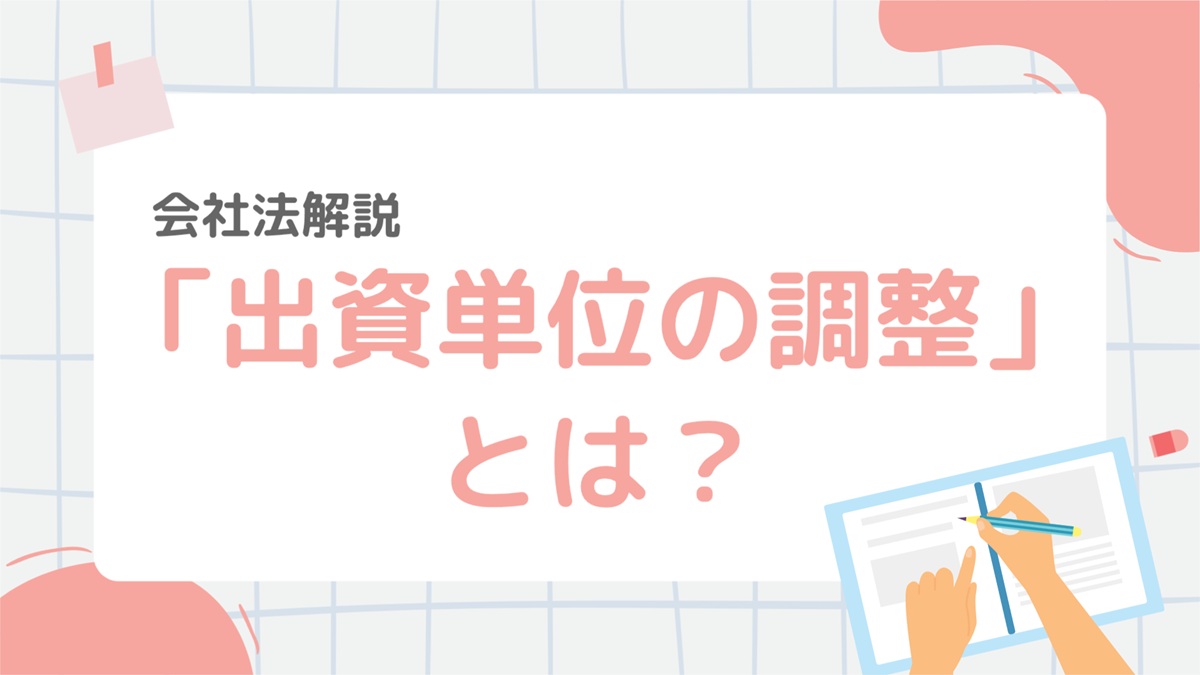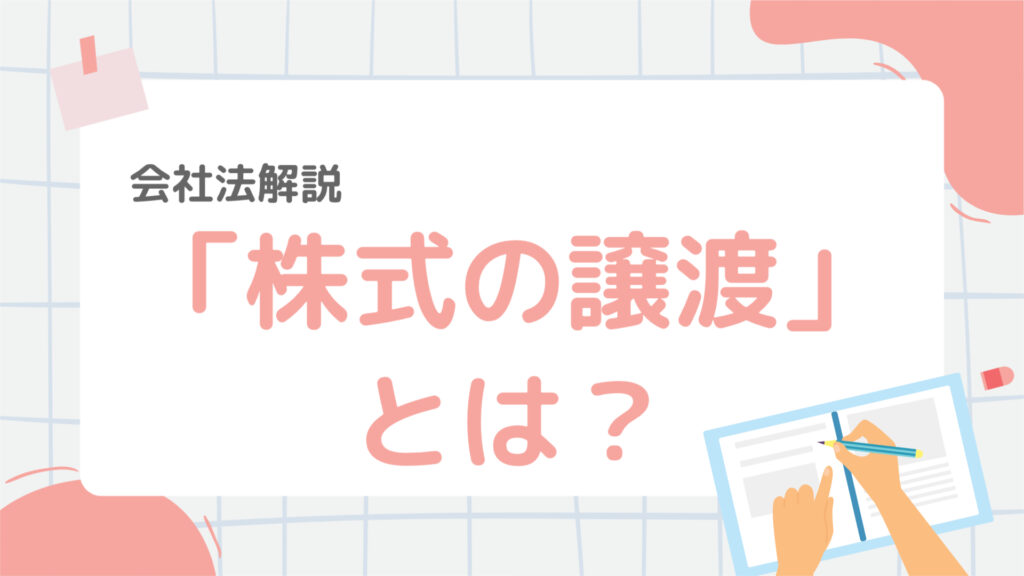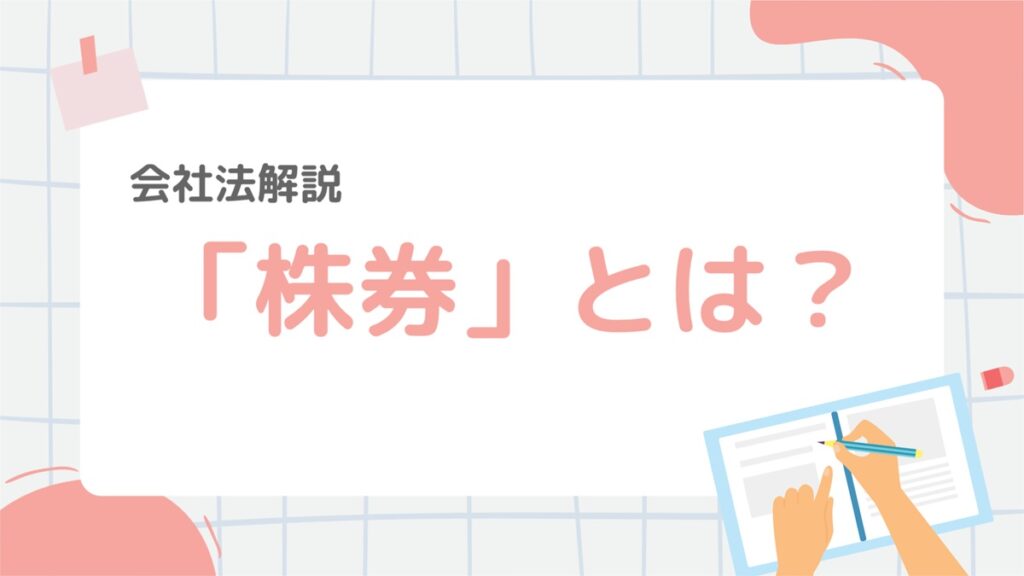- 「出資単位の調整」がどういう意味か分からない方
- 株式の分割や併合の違いをスッキリ理解したい方
- 単元株制度や株式無償割当てについて、試験に出るポイントを押さえたい方
- 行政書士試験で会社法の得点力を高めたい方
💡出資単位の調整とは?
株式の「1株の価格(出資単位)」が高すぎると、個人投資家にとっては手が出しにくくなります。反対に、価格が低すぎると株主が増えすぎて、会社の事務処理が大変になります。
そこで、会社は適切な出資単位を調整することで、投資のしやすさと管理のしやすさのバランスを取っています。
この調整方法には、次の4つの手段があります:
①株式の併合とは?
株式の併合とは、複数の株式を1つにまとめて、株式数を減らす方法です(180条1項)。
これにより、1株あたりの価格が上がり、株価をつり上げるすることができます。1
✅ 例:2株を1株に併合すれば、株数は半分に、株価は約2倍になります。
🔒必要な手続き:
株式併合は、株主に不利益を与える可能性がある(特に少数株主)ため、株主総会の特別決議が必要です(180条2項、309条2項4号)。
このように厳格な手続が必要とされている理由は、例えば2株を1株にした場合に、もともと1株しか持っていない者は端数だけの株主となり、不利益を生じさせることになるためです。
②株式の分割とは?
株式の分割は、1株を複数の株式に分けて、株式数を増やす方法です(183条1項)。
これにより、1株の価格が下がり、投資しやすくなります(流通性が高まる)。
✅ 例:1株を2株に分割すれば、株価はおよそ半分になります。
🔓必要な手続き:
株主に不利益がないため、株主総会の普通決議や取締役会会議(取締役会設置会社)で行えます(183条2項)。2
③株式無償割当てとは?
株式無償割当てとは、株主に対して無償(新たに払い込みをさせない)で新株や自己株式を配布する制度です。
実質的には株式の分割と似た効果があり、株主数の増加や市場での流通性を高められます。3
🔓必要な手続き:
こちらも、株主総会の普通決議(取締役会設置会社の場合は取締役会会議)でOKです(183条3項)。
④単元株制度とは?
単元株制度は、一定数の株式を1つの「単元」としてまとめ、その1単元に1つの議決権を与える制度です(188条1項)。
✅ 例:100株=1単元として、その単元に対して1票の議決権を認める。
この制度により、株主数が増えても管理コストを抑えられるメリットがあります。
🔧導入方法:
会社は定款に「単元株制度を採用する」ことを明記する必要があります(188条1項)。
単元未満株主の扱いは?
単元株に満たない株式(単元未満株)を持っている株主には、議決権がありません。そのため、株主提案権(303条)などの議決権に基づく権利も行使できません。
ただし、以下のような自益権は認められています(189条2項)。4
- 剰余金配当請求権(剰余金の配当を受け取る権利)
- 余財産分配請求権(残余財産の分配を受ける権利)
単元株制度の採用・廃止の手続
1単元の株式の数を増加する場合には、株主総会の特別決議による定款変更が必要です(466条、309条2項11号)。
一方、1単元の株式の数を減少する場合や、単元株制度を廃止する場合には、取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会決議)により行うことができる(195条1項)。
🎓まとめ
株式の併合・分割・無償割当て・単元株制度は、すべて会社の出資単位を調整するための制度です。これらを理解することで、会社法の「会社と株主の関係」や「資本の構造」を深く押さえることができます。
| 取締役会設置会社 | 取締役会非設置会社 | |
|---|---|---|
| 株式併合 | 株主総会の特別決議 (180条2項、309条2項4号) | |
| 株式分割 | 取締役会決議 (183条2項) | 株主総会の普通決議 (183条2項) |
| 株式無償割当て | 取締役会決議 (186条3項) | 株主総会の普通決議 (186条3項) |
| 単元株:採用・増加 | 株主総会の特別決議による定款の変更が必要 (466条、309条2項11号) | |
| 単元株:廃止・現象 | 取締役会決議 (195条1項) | 取締役の決定 (195条1項) |