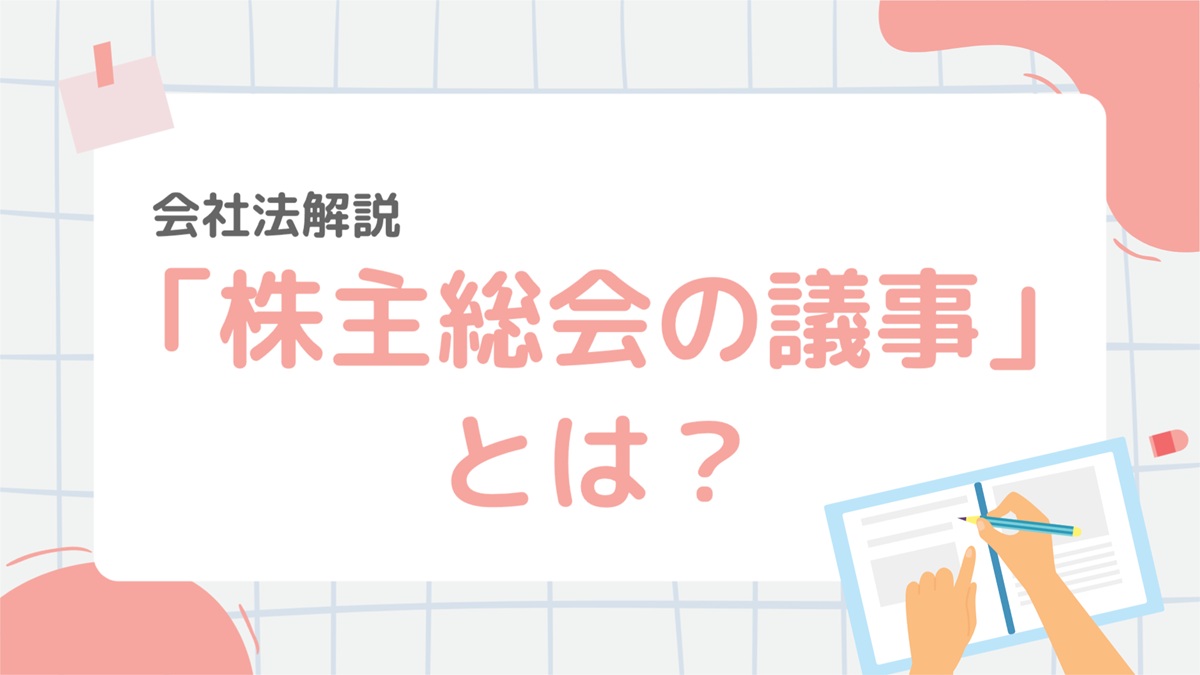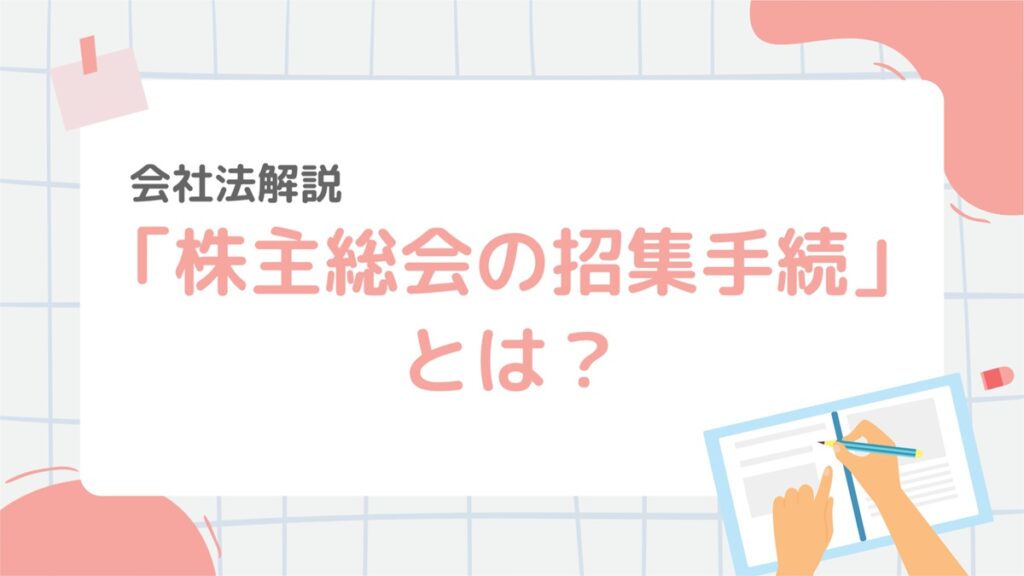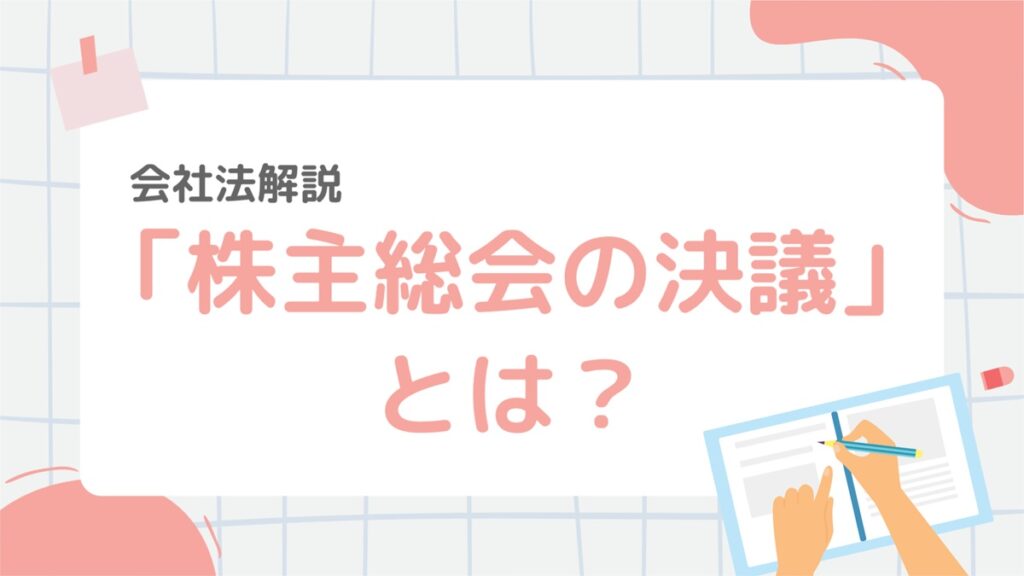- 株主総会の仕組みや流れを知りたい方
- 「株主提案権」や「議決権の制限」などの違いがよくわからない方
- 行政書士試験で会社法(商法)の得点アップを目指している方
株主総会の「議事」とは?
株主総会では、会社の重要事項を株主が決定します。この話し合いの内容を「議事(ぎじ)」と呼びます。ここでは、株主がどのような権利を持っているのか、取締役の説明義務や議事録の取り扱いなど、試験によく出るポイントをまとめて解説します。
🔸株主提案権:株主が議題や議案を提案できる権利
株主は、株主総会に対して一定の条件のもとで提案を行うことができます。これを「株主提案権」といいます。主に以下の3つの権利からなります。
- 議題提案権
一定の事項を議題とするよう会社に請求できる権利(303条1項)。 - 議題提出権
株主総会の会日に、株主総会の目的に沿った事項について議案を提出することができる権利(304条)。 - 議案の要領の通知請求権
あらかじめ取締役に対して議案を提案して、それを招集通知に記載するよう請求できる権利(305条1項)。
🔸取締役等の説明義務(会社法314条)
株主からの質問に対して、取締役などは必要な説明を行わなければなりません(314条本文)。
ただし、以下の場合には説明を拒むことができます。
- 質問が株主総会の事項(議題)と関係ない内容の場合
- その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合
(例:説明により企業秘密が外部に漏れる場合など) - 正当な理由がある場合として法務省令で定める場合
(説明するのに調査が必要で、その場で回答するのが困難な場合等)
🔸総会検査役(会社法306条)
株主総会の運営が適正に行われているかを調査させるため、株式会社または総株主の100分の1以上の議決権を持つ株主は、株主総会に先立ち、裁判所に「総会検査役」の選任を申立てることができます(306条1項)。
🔸議事録の作成と閲覧(会社法318条)
株主総会終了後には、議事録の作成が義務です(318条1項)。1
また以下のように、関係者が閲覧する権利も認められています。
🔸決議の省略(会社法319条)
ある提案について、議決権を行使できるすべての株主が書面または電磁的記録で同意した場合には、株主総会を開かずに提案を可決する決議がされたとみなされます(319条1項)。
このとき、同意の記録を決議があったとみなされた日から10年間本店で保管し、閲覧できるようにしておく必要があります(319条2項~4項)。
🔸議決権の基本と例外
1株1議決権の原則(会社法308条など)
● 原則:「1株=1議決権」
各株主は、原則として、その有する1株について1個の議決権を持つ(308条1項本文)。これを1株1議決権の原則といいます。(※1株に複数の議決権を有する種類株式は発行できない)
ただし、以下のような場合は議決権が制限・無効となります。
- 単元未満株式
単元株制度が採用されている場合、単元未満株式については議決権なし(308条1項但書) - 議決権制限株式
議決権制限株式を有する株主は、制限された事項について議決権なし(108条1項3号) - 自己株式
会社が保有する自己株式には、議決権なし(308条2項) - 子会社の保有する親会社株式
子会社が親会社株式を保有する場合、原則として議決権なし(308条1項本文かっこ書) - 相互保有株式
総株主の議決権の4分の1以上の議決権を保有されている会社(被支配会社)は、支配会社の株式について議決権なし(308条1項本文かっこ書)
代理人による議決権行使(会社法310条)
株主は、他人(代理人)に議決権の行使を任せることができます(310条1項前段)。2
ただし、代理権は株主総会ごとに設定しなければなりません(310条2項)。
議決権の不統一行使(会社法313条)
株主は、すべての株に同じ意思で投票する必要はありません(統一しないで行使可)(313条1項)。3
👉例:信託会社が複数の委託者の株式を保有しており、議決権の行使について、各委託者から個別に賛成や反対の指示を受けた場合など。
ただし、「他人のために株式を保有している者」に限定される制度であり、会社は要件を満たさない者の不統一行使を拒否できます(313条3項)。
書面投票・電子投票制度(会社法311条・312条)
会社は、株主総会の前に書面や電子データで議決権を行使できる制度を導入することができます。
会社側から、株主総会の招集通知に株主総会参考書類と議決権行使書面を添付して株主へ送付し、株主が議決権行使書面に必要な事項を記載し、総会直前の営業時間終了時までに会社に提出した場合には、議決権を行使したものと扱うことができます(311条1項)。これを書面投票制度といいます。4
また、この投票方式を電磁的方法によって行う場合のことを、電子投票制度といいます(312条)。
✅まとめ|試験でも実務でも重要な「議事」の知識
株主総会の議事は、会社の運営に大きな影響を与える重要なプロセスです。特に、株主の提案権・取締役の説明義務・議決権の扱いなどは行政書士試験でもよく問われますので、条文とセットで覚えておきましょう。
- 参考:議事録は株主総会の日から本店に10年間、写しを支店に5年間備え置かなければならない(318条2項・3項本文)。 ↩︎
- 重要判例:株主総会において議決権を行使する代理人を株主に限る旨の定款の規定は、株主総会が第三者により撹乱されることを防止して、会社の利益を保護する趣旨に出た合理的理由による相当程度の制限であるから、有効である(最判昭43.11.1) ↩︎
- 具体例:信託会社が複数の委託者のために株式を保有しており、議決権の行使について、各委託者から個別に賛成や反対の指示を受けた場合など。 ↩︎
- 参考:株主が議決権行使書面を送付したあとで、当該株主が株主総会に出席して議決権を行使したときには、書面による議決権行使の効力は失われる。 ↩︎