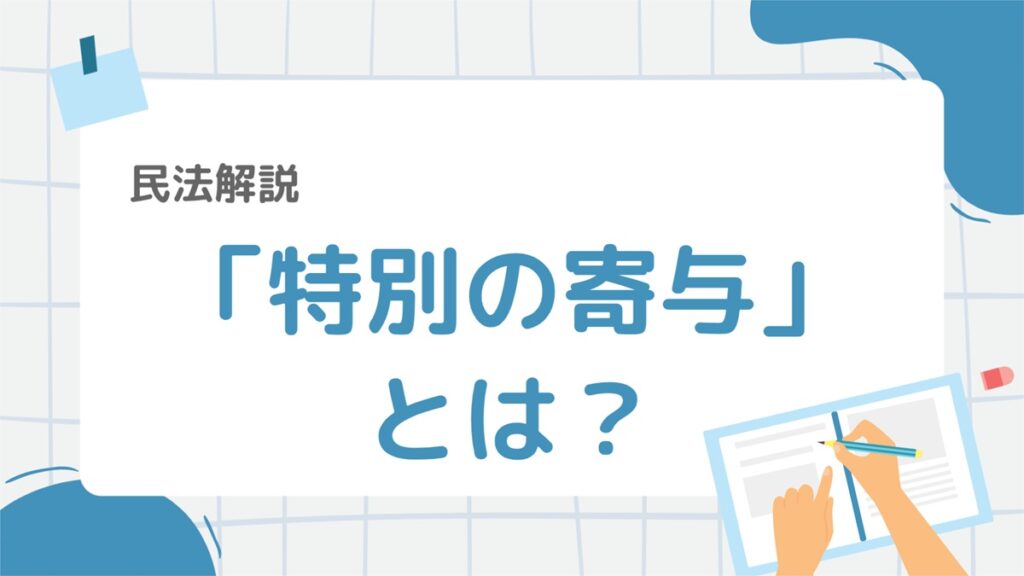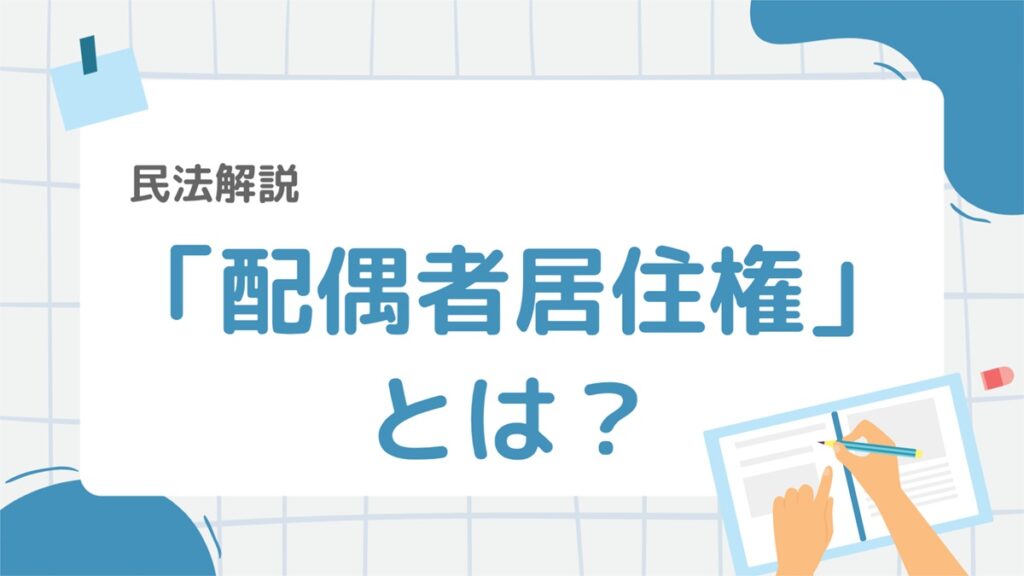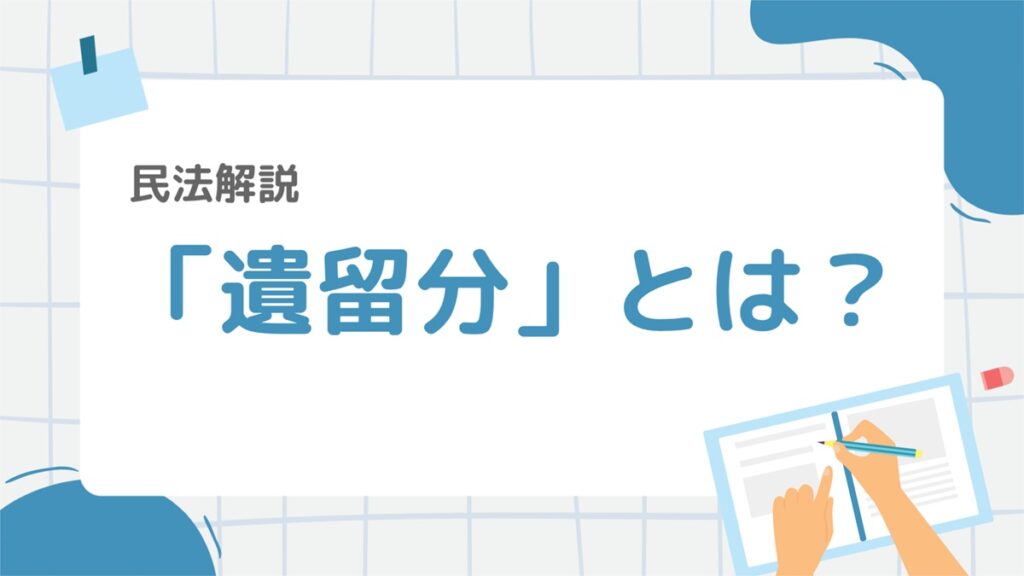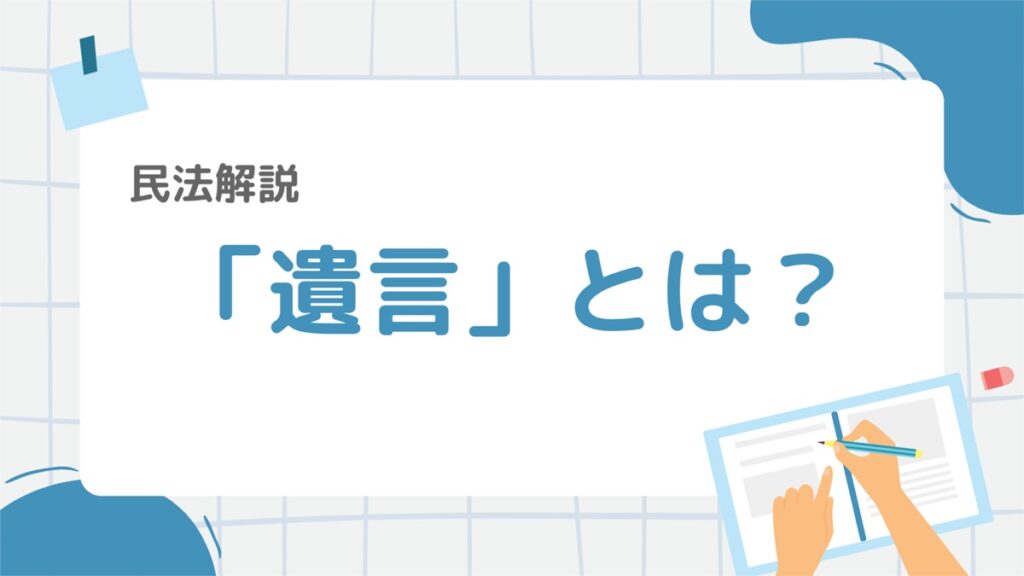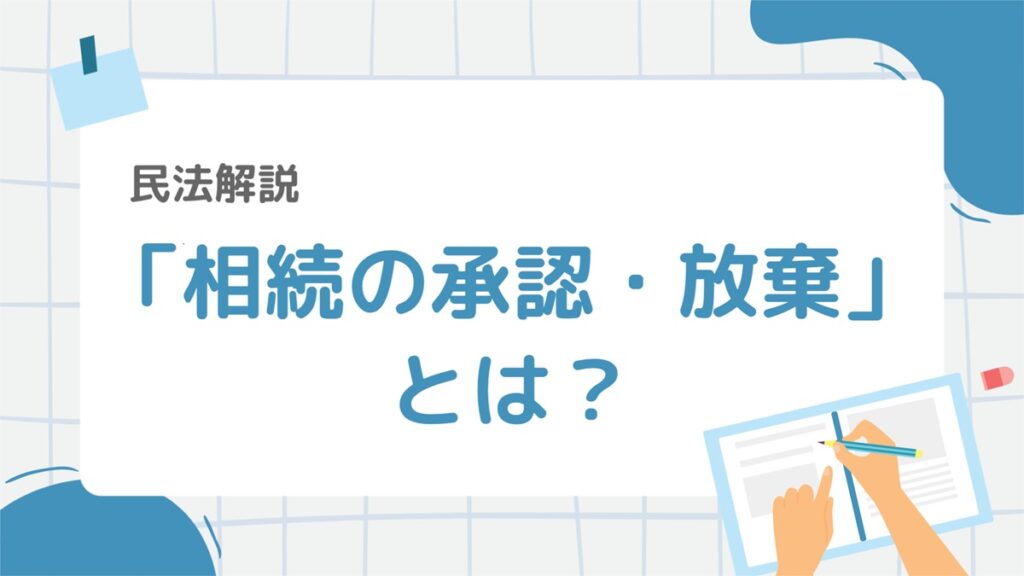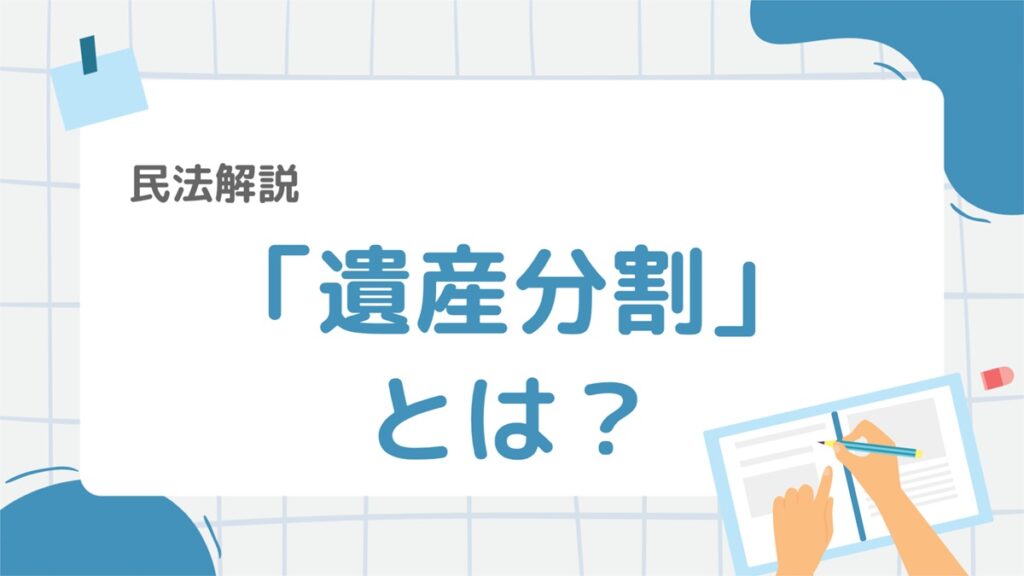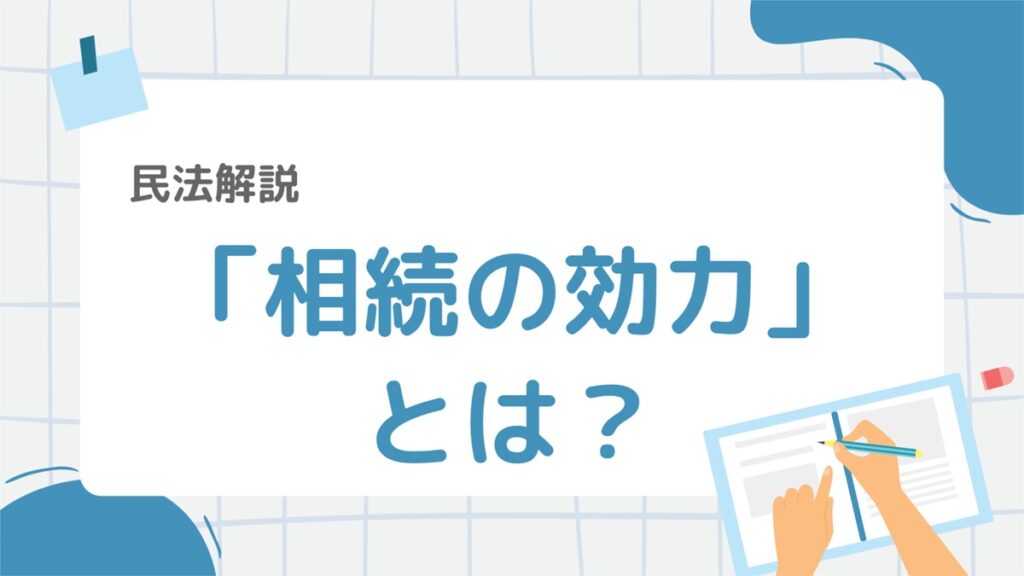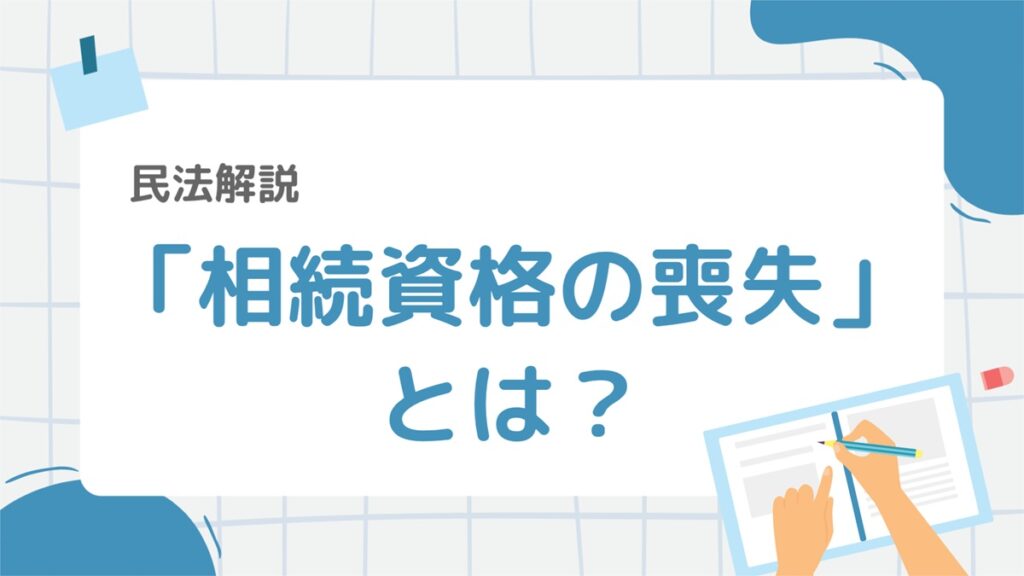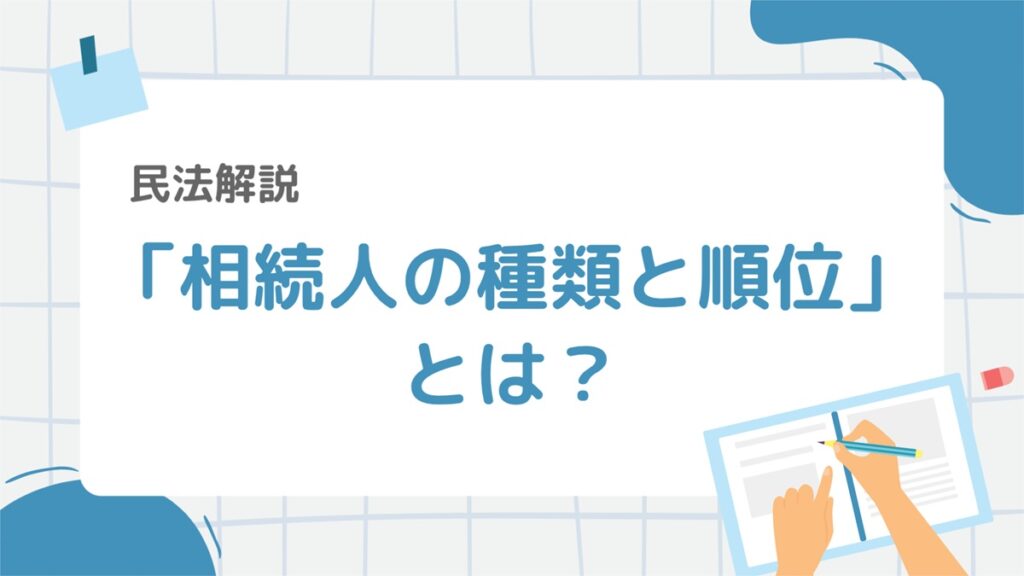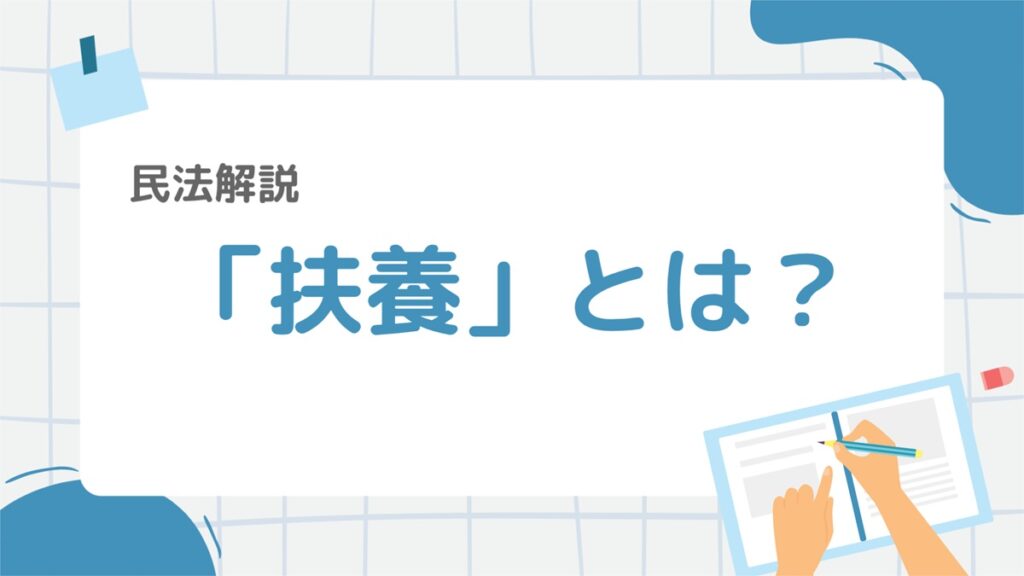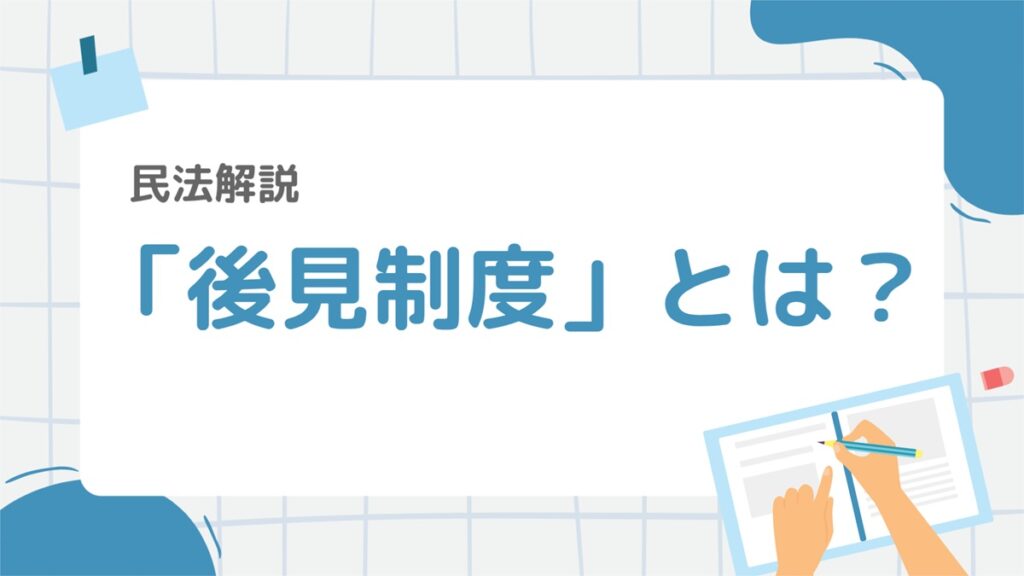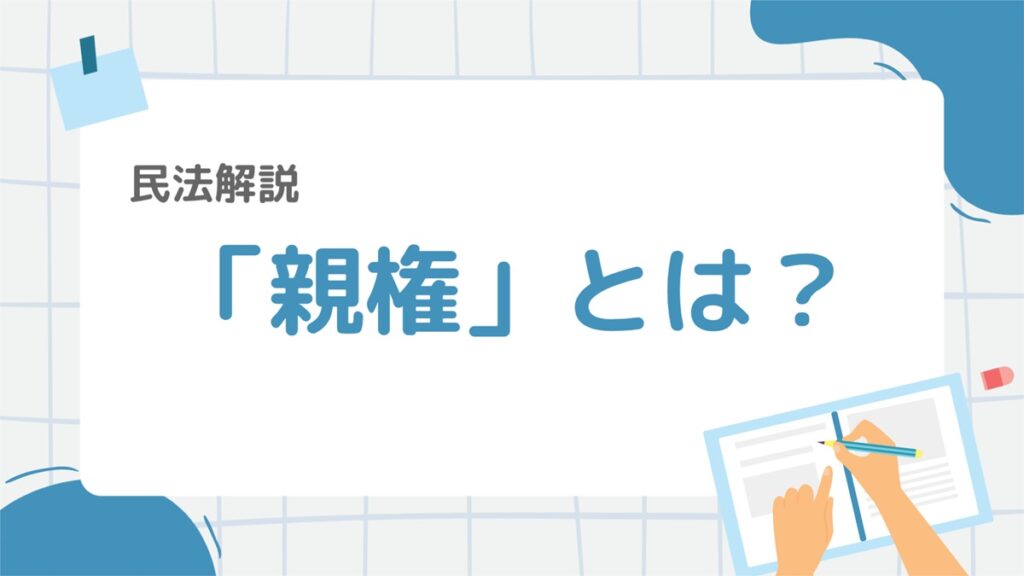民法– category –
-

民法30-2:特別の寄与とは?相続人以外の親族も請求できる“特別寄与料”をわかりやすく解説
✅この記事はこんな人におすすめ! 相続人ではないけれど、長年介護や世話をしてきた親族がいるケースを知りたい方 行政書士試験で民法の“相続分野”をしっかり得点源にしたい方 💡特別の寄与とは?相続人以外の親族にも認められる寄与分制度 これまでの相続... -

民法30-1:「配偶者居住権」とは?相続後も住み慣れた家に住み続けられる仕組みをわかりやすく解説
✅この記事はこんな人におすすめ 配偶者が亡くなった後も、今の家に住み続けたいと考えている方 相続で「家はもらったけど生活費が足りない」とならないようにしたい方 配偶者居住権や短期居住権が行政書士試験にどう出題されるか気になる受験生の方 配偶者... -

民法29-2:「遺留分」とは?誰がどれだけ遺産をもらえるかをスッキリ解説
🔶この記事はこんな人におすすめ 相続に関する基礎知識を知りたい方 「遺留分」って何?と感じている相続初心者の方 行政書士試験の民法対策をしている方 相続トラブルを未然に防ぎたい方 🔷遺留分とは?|法定相続人に保障された“最低限の取り分” 遺留分(... -

民法29-1:「遺言」とは?作成方法・有効要件・撤回のルールまでわかりやすく解説
✅この記事はこんな人におすすめ! 行政書士試験の民法対策をしている方 「遺言書ってどうやって作るの?」「誰が書けるの?」と疑問を感じている方 親の遺言書が見つかったけど、どうすればいいのかわからない方 将来に備えて、遺言のルールを正しく理解し... -

民法28:相続の承認・放棄とは?単純承認・限定承認・相続放棄と熟慮期間をわかりやすく解説
🧭この記事はこんな人におすすめ 行政書士試験の民法対策として「相続の承認・放棄」について学びたい方 「熟慮期間」や「限定承認」「相続放棄」などの用語の違いに混乱している方 試験によく出る条文の趣旨や適用例を理解したい方 相続の承認・放棄とは?... -

民法27-2:遺産分割とは?種類・流れ・効力までわかりやすく解説!
この記事はこんな人におすすめ! 行政書士試験で「相続」分野の得点力を上げたい方 「遺産分割」の種類や流れを理解したい方 「協議分割」と「審判分割」の違いがイマイチわからない方 試験対策と実務の両方に役立つ知識を効率よく整理したい方 遺産分割と... -

民法27-1:相続の効力とは?被相続人の権利義務はどうなる?一身専属と共同相続の基本をやさしく解説!
この記事はこんな人におすすめ! 相続の基本的なルールをわかりやすく理解したい方 一身専属の権利義務とは何か、判例とあわせて整理したい方 行政書士試験で「相続の効力」に関する出題に備えたい方 相続の効力とは?~死亡した人の財産や義務はどうなる... -

民法26-2:「相続資格の喪失」相続できない人とは?相続欠格・廃除の違いと要件をわかりやすく解説!
この記事はこんな人におすすめ ✅ 相続人になれない場合ってどんなケース?✅ 「相続欠格」と「相続人の廃除」の違いをサクッと知りたい✅ 行政書士試験で民法(相続)を攻略したい! 相続資格の喪失とは? 民法では、本来なら相続人となるはずの人が、「ある... -

民法26-1:相続人の種類と順位|配偶者・血族・代襲相続・胎児・同時死亡まで完全整理!
📝この記事はこんな人におすすめ 「相続人って誰がなるの?順位ってあるの?」と疑問を持っている方 配偶者と子どもの相続分がどう違うのかを知りたい方 代襲相続や胎児の相続権、同時死亡のルールまで一気に整理したい方 行政書士試験で出題される「相続人... -

民法24-5:「扶養」とは?誰にどこまでの義務があるのかをわかりやすく解説
✅この記事はこんな人におすすめ! 「扶養って法律的にはどういう意味?」と疑問に思っている方 行政書士試験で民法の扶養に関する知識を整理したい方 扶養義務の範囲や優先順位をわかりやすく理解したい方 扶養とは? 「扶養」とは、自分一人では生活でき... -

民法24-4:後見制度を完全攻略!未成年後見・成年後見・後見人の選任や注意義務までわかりやすく解説
🧭この記事はこんな人におすすめ 行政書士試験の民法対策として「後見制度」の理解を深めたい方 「未成年後見」と「成年後見」の違いがよくわからない方 後見人の選任や資格、辞任の要件について整理したい方 後見制度に関する重要条文を効率よく学びたい方... -

民法24-3:「親権」とは?基本から親権喪失・利益相反までわかりやすく解説!
この記事はこんな人におすすめ! 行政書士試験で「親権」のポイントをしっかり押さえたい方 民法の中でも親子関係の法律を整理して覚えたい方 親権に関する判例や利益相反の具体例を知っておきたい方 親権とは? 親権とは、未成年の子どもを育て(監護)、...