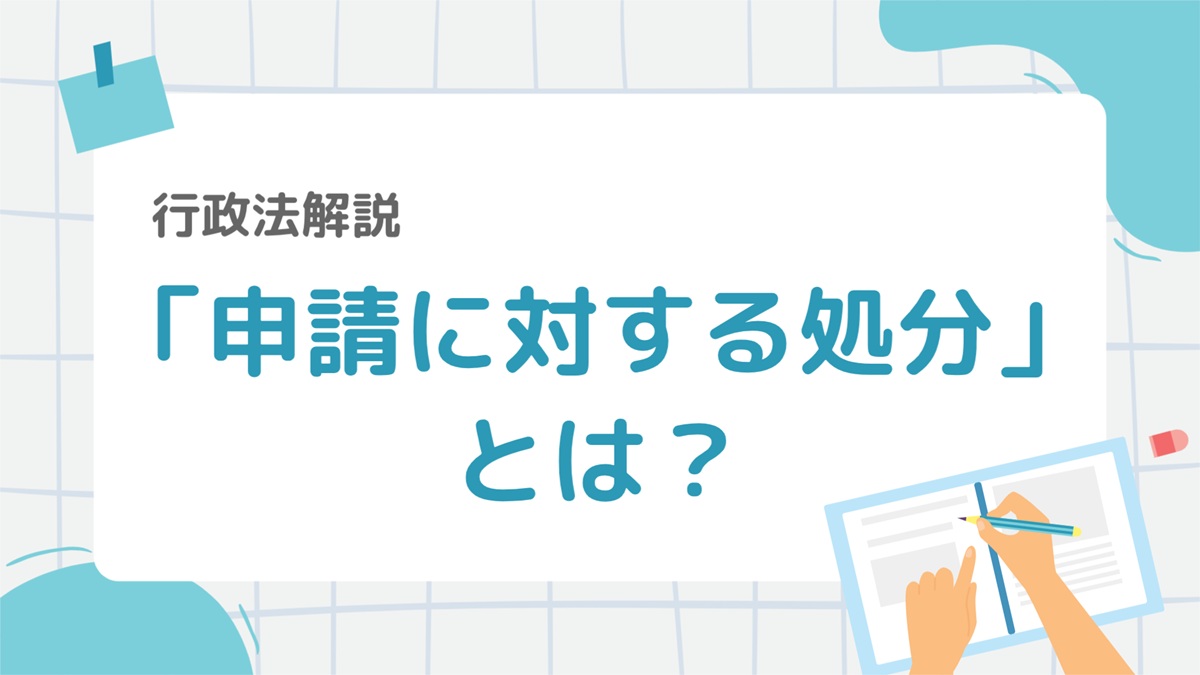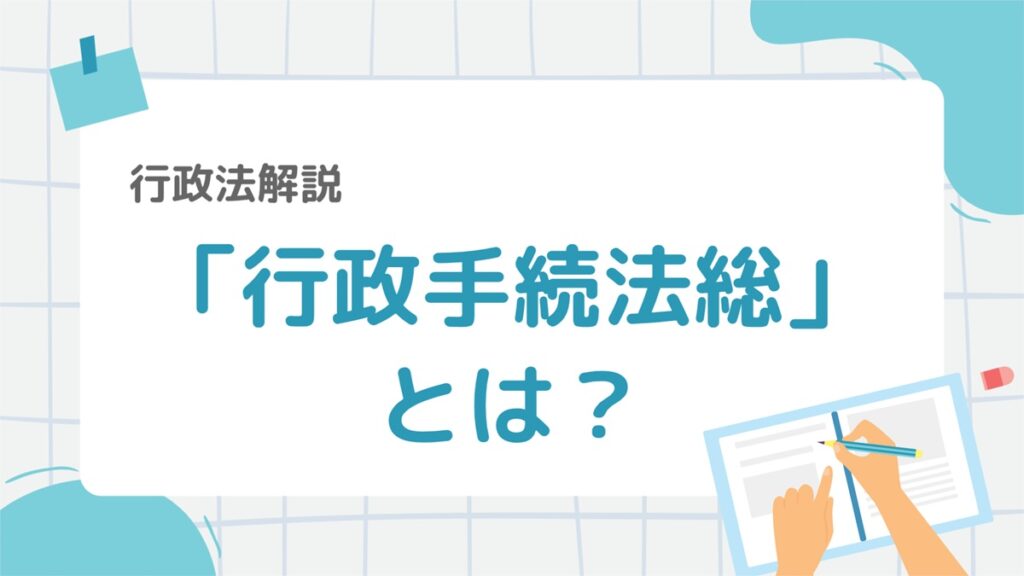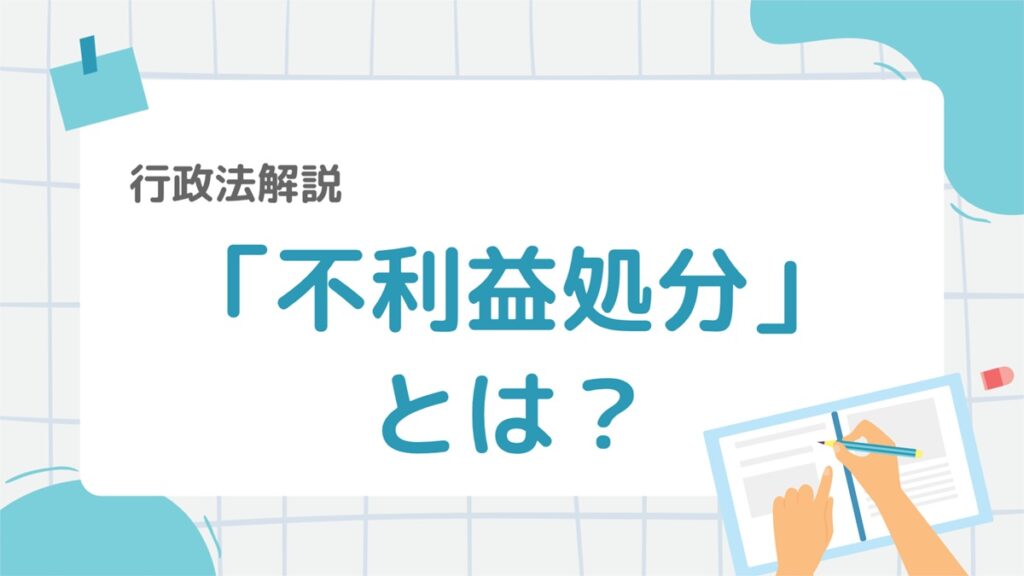- 試験で「申請に対する処分」を確実に押さえたい方
- 審査基準や処理期間、拒否理由のルールを整理したい方
申請に対する処分とは?
行政手続法における「申請に対する処分」とは、私たちが行政機関に対して許可や認可などの申請を行った際に、行政機関がその申請に「許可するかどうか」を判断して行う処分のことをいいます。
この記事では、「申請に対する処分」に関する重要なポイントを、行政書士試験にも役立つようにやさしく整理して解説します。
✅「申請」ってそもそも何?
申請とは、法令に基づいて、行政庁に対して何らかの利益(許可・認可・免許など)を求める行為のことです。
この申請に対し、行政機関が「許可するか・しないか(行政庁が諾否の応答)」を判断して出すのが「申請に対する処分」です。(2条3号)1。
申請をめぐる行政庁の義務とは?
行政手続法は、申請を法に従って公正かつ迅速に処理するため、以下のような行政庁の手続上の義務を規定しています。
| 法的義務2 | 努力義務3 |
| 審査基準の設定・公開(5条1項・3項) 標準処理期間を定めたときの公開(6条) 申請の到達後の遅滞なき審査の開始(7条) 申請拒否処分をする場合の理由の提示(8条) 複数の行政庁が関与する処分の遅延の禁止(11条1項) | 標準処理期間の設定(6条) 申請に係る審査の進行状況および当該申請に対する処分の時期の見通しの提供(9条1項) 申請に必要な情報の提供 公聴会の開催等により申請者以外の者の意見を聴く機会を設けること(10条) 複数の行政庁が関与する処分の審査の促進(11条2項) |
審査基準の設定
審査基準とは?
申請に対して許可するかどうかを判断するためのルールです(2条8号ロ)。行政機関が自由に判断してしまうと、不公平になるおそれがあるため、審査基準は必ず定めなければなりません(5条1項)。
(※設定した審査基準を変更することも可能)
標準処理期間の設定(努力義務)
申請に対して、いつ処分が出るのかが分からないと、申請者は不安ですよね。
そこで行政機関は、申請から処分までに通常かかる期間=「標準処理期間」を定めるよう努力し、定めた場合は公にしておかなければなりません(6条)。5
■基準の設定・公開の義務の種別
申請に対する審査・応答
行政機関は、申請が到達したときは、遅滞なく審査を開始しなければなりません(7条)。
また、もし申請に形式的な不備があった場合でも、放置してはいけません。その場合は速やかに以下の行為をしなければなりません(7条)。
- 不備がある場合は、補正(修正)を求める
- または、許認可等を拒否をしなければならない
申請を拒否する場合の理由の提示
行政機関が申請を拒否(申請拒否処分)する場合には、申請者に対して、同時に理由をしめさなければなりません(8条1項本文)。これは、行政庁の判断を慎重にさせることと、申請者が納得したり、不服申立てをする際の情報を提供するためです。▶判例① ▶判例②
ただし、客観的な基準(数値など)で明確にNGと分かる場合は、申請者の求めたときにその基準を示すだけでもOKです(8条1項但書)。また、書面で拒否処分をする場合は、理由も書面で示す必要があります(8条2項)。
その他の関連ポイント
情報の提供
行政庁は、申請者から求めがあれば、申請の進行状況や処分の時期の見通しについて、示すよう努めなければなりません(9条1項)。
さらに、申請方法や必要書類についても、申請予定者に対して情報の提供に努めなければなりません(9条2項)。
公聴会などの開催
申請に対する処分が、申請者以外の者の利害を考慮することが許認可の要件とされている場合は、必要に応じて公聴会6の開催やその他適当な方法で、申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければなりません(10条)。
すべての案件に公聴会の開催を義務付けるのは合理的でもないし、行政庁の負担も大きくなることから、努力義務にとどまっています。
複数の行政庁が関与する処分
複数の行政庁が関与する処分については、行政庁の間で申請がたらい回しにされ、無駄に時間がかかる可能性があります。そこで、行政手続法は、複数の行政庁が関与する処分の遅延の禁止(11条1項)や、行政庁間の協力による審査の促進の努力義務(11条2項)を規定しています。
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 申請とは | 許可や認可などを行政に求めること |
| 処分とは | 申請に対して許可・不許可を決めること |
| 審査基準 | 公平な判断のために定めるべきルール |
| 標準処理期間 | 申請から処分までの目安となる期間 |
| 拒否理由の提示 | 拒否されたときは理由を申請者に通知 |
| 情報提供 | 処分の見通しや書類の案内などに努める義務あり |
- 具体例:例えば福祉施設を開業したいと思っている人が、都道府県知事に対して営業許可を求める場合。 ↩︎
- 法的義務:「~しなければならない」と規定されており、守らなければ違法となる義務 ↩︎
- 努力義務:「~するよう努めなければならない」と規定されており、守らなかったとしても必ずしも違法となるわけではない義務 ↩︎
- 参考:「公にしておかなければならない」とは、秘密扱いをしないということであり、「公表」のように積極的に周知することまでは求められていない ↩︎
- 参考:申請の処理が標準処理期間を徒過した場合に、徒過した理由を通知しなければならないとする規定は存在しない。 ↩︎
- 公聴会:国または地方公共団体の機関が、その権限に属する一定の事項を決定するに当たり、広く利害関係人や学識経験者等の意見を聴く制度のこと ↩︎