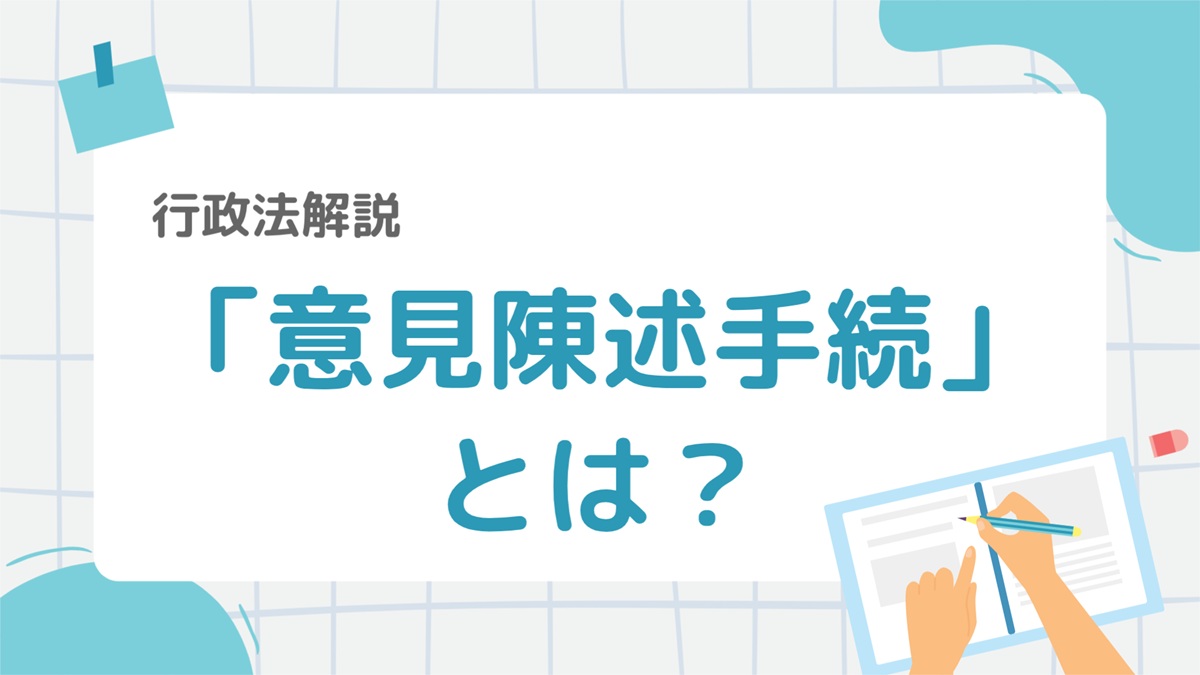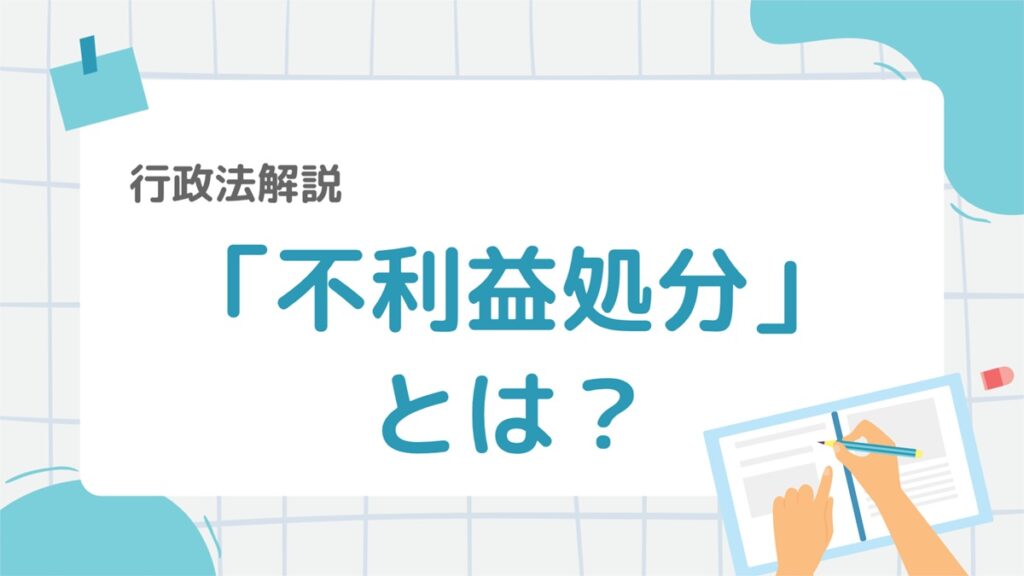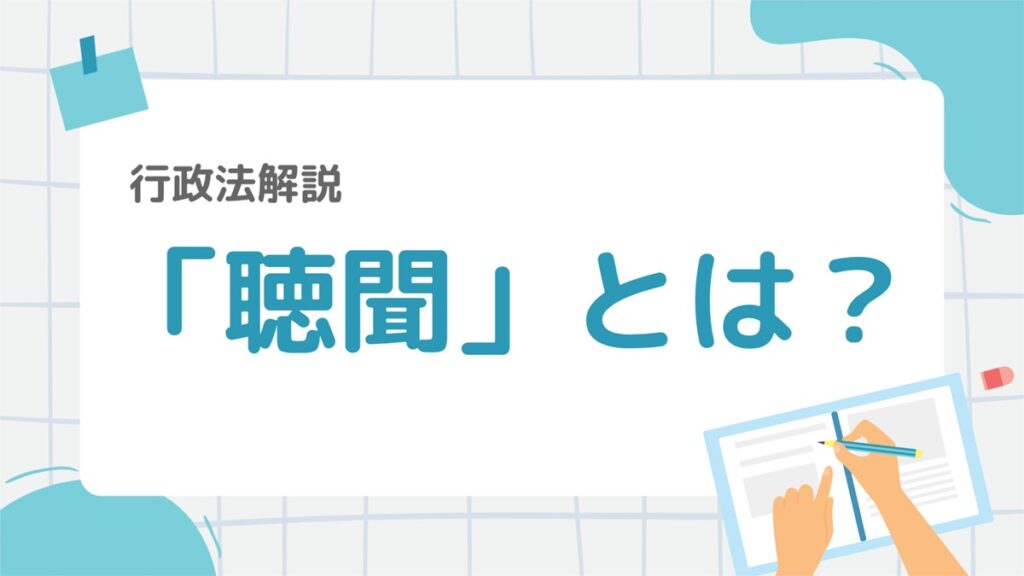この記事はこんな人におすすめ!
- 「聴聞」と「弁明の機会」の違いがよくわからない方
- 意見陳述手続がいつ必要になるのか整理したい方
- 行政書士試験の行政法を勉強している方
目次
意見陳述手続とは?わかりやすく解説!
行政庁が国民に不利益処分を行う際、処分の対象者(名あて人)にとっては、生活や仕事に大きな影響を与える場合があります。そのため、処分を受ける本人にあらかじめ言い分を述べる機会を与えることが大切です。これが「意見陳述手続」と呼ばれる制度です。
なぜ意見陳述手続が必要なの?
たとえば「許可しません」という申請拒否処分は、本人にとって残念ではありますが、「現状のままにとどまる」だけです。しかし、許可の取消や業務停止命令のような不利益処分は、すでに得ている地位や利益を奪うため、より重大な影響を及ぼします。
このような場合には、処分の前に本人の主張を聞き、防御の機会を保障することが重要です。
そのため、行政手続法13条1項では、不利益処分を行う際に、名あて人に対して意見陳述のための手続を行うことが義務付けられています。1
意見陳述手続は2種類ある!
意見陳述手続には、処分によって生じる不利益の重さに応じて、「聴聞」と「弁明の機会の付与」という2つの方法があります。
聴聞
👉 重い不利益がある場合に適用される「正式な手続」です。
👉 本人(名あて人)に期日に出頭してもらい、口頭で意見を述べる場が設けられます。
▼聴聞が必要となる主なケース(13条1項1号)
- 許認可等を取り消す不利益処分2
- 名あて人の資格・地位を直接にはく奪する不利益処分
- 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、
名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分または
名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分 - 行政庁が相当と認める不利益処分
弁明の機会の付与
👉比較的軽い不利益処分の場合に行われる、簡易な手続です。
👉本人に対して「書面で意見を提出してください」と案内し、行政庁がその意見を考慮して処分を決定します。
▼弁明の機会が与えられるケース(13条1項2号)
- 上記以外の不利益処分3
※聴聞を要するほど重大ではない不利益処分
「聴聞」「弁明の機会の付与」の解説記事はこちら👇